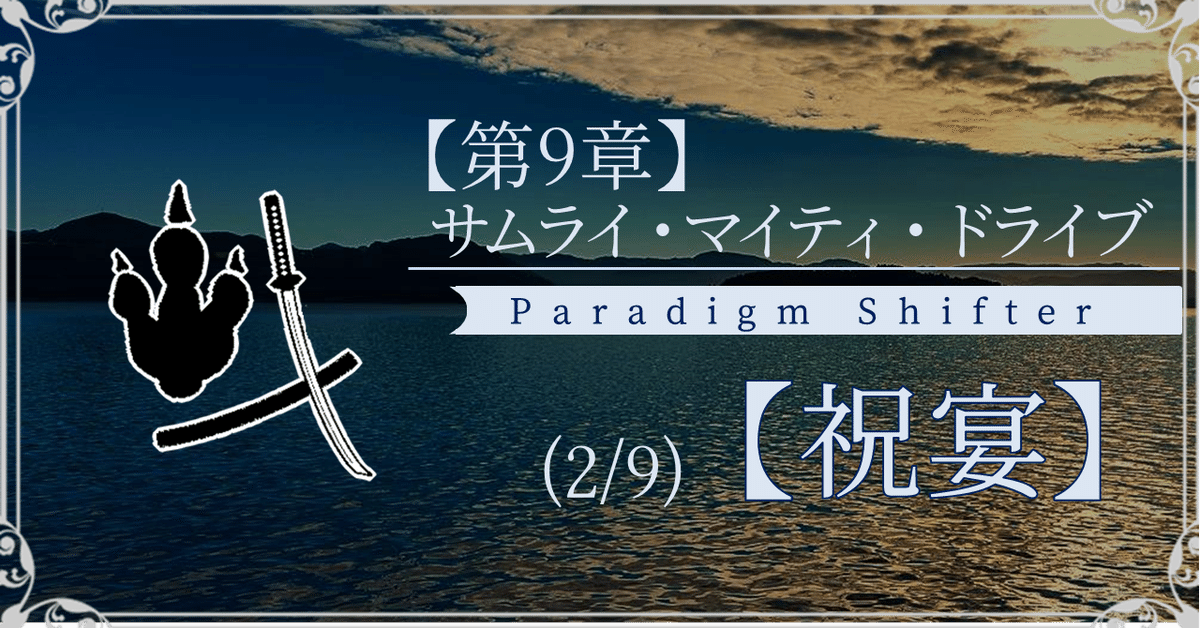
【第9章】サムライ・マイティ・ドライブ (2/9)【祝宴】
【合戦】←
「バッド。わずらわしいにも、ほどがあるだろ……」
騒がしいばかりの武将たちの祝宴に義理で同席した翌日、ナオミは早々に自分の領地へ向けて出立する。
昨晩の酒が残っているのか、軽く頭痛がする。朝餉も、箸が進まなかった。女武者は、鞍のうえで自分の額を抑える。
首を傾げた『薙鳥<ちどり>』が、心配するようにのどを鳴らす。
「ああ、だいじょうぶだ。テメェが気にするようなことじゃない、だろ?」
己の騎竜の頭をなでると、ナオミは手綱を操り、軽快に道を走らせる。『薙鳥<ちどり>』のほかに、供のものはいない。女だてらの、一人旅だ。
サムライたちのなかで、随伴の足軽はおろか、小間使いも連れていないのはナオミくらいのものだったが、赤毛の女武者にとっては、そのほうが気軽だった。
道中の大半は、野宿。落ち武者や山賊に襲われたことも、一度や二度では済まないが、すべて返り討ちにしてきた。
迅脚竜の歩みで、三日ほど。渓谷を縫うように道を進むと、巨大な湖のほとりに出る。対岸が見えないほどの大規模な水域だ。
湖畔の道をさらに半日ほど進むと、大御所からナオミに与えられた領土に入る。盆地と森に囲まれた土地を中心に、湖周辺の一帯だ。
見慣れた風景のなかに踏みこみ、赤毛の女武者は少しばかりの安堵を覚える。
「あー、ナオミさまだー!」
「ナオミさまが帰ってきたよー!」
野良仕事の手伝いを抜けて遊んでいた童たちが、真っ先に領主の帰還に気がつく。つづいて、田畑で鍬を振るっていた大人たちが駆け寄ってくる。
「お帰りなさいませだ、御前さま」
「領主さま、ご無事でなによりですだ」
自分よりも年長の領民たちから歓迎の声を投げかけられ、赤毛の女武者は、気恥ずかしそうに手を振って応える。『薙鳥<ちどり>』もどこか、誇らしげだ。
やがて、ナオミと騎竜は畦道を通り抜け、領地の中心にある砦へと向かう。盛り土の台地のうえに築かれた丸太の城門が、主の到着に応じて開かれる。
「無事だったかい、ナオミさま!」
砦のなかに入った女武者を出迎えたのは、手ぬぐいを頭に巻いた女たちだった。頭目格の女が、帰還した領主に声をかける。
ナオミは鞍から降りると、騎竜の手綱を女の一人に預ける。
「留守中、みんな、ごくろうさま」
「ナオミさまこそ! 飛脚で、連絡のひとつでもよこしてくれれば良かったのに」
「ウチが、そういうの苦手だってのは知ってるだろ」
「ああ、そうだった、そうだった!」
ナオミの返答に、女たちは一斉に笑い声をあげる。砦を警護する兵は男だが、なかで働いている大多数は女、ついで子供たちだ。
人の背丈ほどもある卵を、布で何重にも巻き、台車に乗せて、女たちが押していく。子供たちは、小魚が満載された桶を足しげく運んでいく。
「グッド。滞りなくまわっているようで、なにより。ウチがいないほうが、調子はいいんじゃないか?」
「ナオミさま、冗談はよしておくれよぉ!」
赤毛の女武者が大御所から預けられた領土は、恐竜の孵化と養育場として使われる貴重な土地だ。
湖畔には、野生の恐竜の産卵地帯があり、そこから卵をちょろまかす。無事に孵化して、成長すれば、大御所傘下の武将たちのもとへ騎竜として供給される。
ほかのサムライたちが治める土地に比べれば面積は狭いが、戦略的な価値は高い。ナオミの身勝手な振る舞いが許されるのも、ひとえにこの土地の重要性は大きい。
砦が女ばかりになったのも、ナオミの独断によるものだ。行き場を失った未亡人や戦災孤児を受け入れているうちに、こんな有様となった。
赤毛の女武者は、頭目格の女に案内されながら、留守中の砦の出来事の報告を受ける。竜たちの繁殖期が過ぎ、続々と孵化のときを迎えている。
「大御所さまからもらった恩賞で、餌代はまかなえそうだな。なんだったら、竜舎の増築だってできるだろ」
「あたしらは、ありがたいけどねえ。ナオミさま。少しは、自分のためにカネを使おうとは思わないのかい?」
「ウチは、そういうのは性にあわないんだ。知っているだろ」
領主を取り巻く女たちがふたたび、どっ、と笑い声をあげる。無愛想なナオミも、つられて、少しばかり噴き出す。
「領主さまぁ! お風呂が沸いたよぉ!!」
遠くから、子供の声が聞こえてくる。
「湯を浴びて、汗を流してきな。そのあいだに、あたしらは祝宴の準備だよ!」
頭目格の女が、ナオミの背を押し、他の女たちに号令をかけた。
───────────────
「あー、染みるぜ……」
赤毛の女武者は、木製の風呂桶を満たす湯のなかに裸体を沈める。腕と背筋を伸ばせば、気が張って忘れていた身の強ばりを思い出す。
「大御所さまんところの荒武者どもは、まあ、ともかくとしても……ここの女たちは皆、いいやつらなんだけどなあ……」
肩まで湯に浸かったナオミは、あごの先を水面に触れさせながら、小声でつぶやく。知らぬ間に戦場で蓄積していた疲れが、湯に染み出していく。
それでも、心の奥に染みついたわずかな違和感だけはぬぐえない。
物心ついたときから抱き続けている「ここにいるべきではない」という感覚だけは、いまでも胸の内に残り続けていた。
───────────────
「ナオミさまの、勝利と帰還を祝って!」
濁り酒を満たした杯を、車座に座った女たちが掲げる。女たち主催の祝宴は、陽が沈んですぐに始まりを告げる。
人の輪の中心には、湖から水揚げされた海老や貝を炊きこみ、しいたけや錦糸卵も混ぜこんだちらし寿司が山盛りになっている。
その周辺には、里芋の煮っ転がしや、川魚の塩焼き、熊や猪の肉に、とれたての果物まで並んでいる。
「グッド。こいつは、豪勢だ」
「ナオミさまが帰ってきたと聞いて、領民がこぞって持ってきてくれたんだよ」
女たちのあいだからは、子供たちが顔を出し、馳走の相伴に預かろうと食べ物に手を伸ばしている。戦で夫を亡くした女の連れ子が、ほとんどだ。
「こらこら! 勝手に、それも手づかみで食べるんじゃないよ!」
「いいだろ。子供たちにも、少しは分けてやってくれ」
「わぁーい! 領主さま、ふとっぱらー!!」
「まったく……ナオミさま、ちょっと子供たちに甘過ぎないかい?」
「ま、あたしらが窮屈な想いをしなくて済むのも、甘くて優しいナオミさまのおかげなんだけどねえ」
「違いない。ナオミさまがいなけりゃ、ここにいる女子供全員、野垂れ死にさ!」
女たちは、顔をあわせて笑いあう。ナオミもつられて、表情をほころばせる。それでも、わずかに覚える疎外感はぬぐえない。
「一応、昼間に見て歩いたが、孵化場の仕事でなにか変わったことはないか?」
赤毛の領主は、箸を進めながら尋ねる。
「ナオミさまぁ、祝宴でまでお勤めの話をすることはないよ!」
女たちは、また笑い声をあげる。冗談を交えながらも、領主の留守中の出来事を口々に報告し始める。
卵の採取でけが人は出ていないか、賊のたぐいが現れてはいないか、幼竜の餌は滞りなく調達できているか……
ナオミは、濁り酒をすすりながら、注意深く耳をそばだてる。自分の性にあわないと思いながらも、任された務めである以上、おろそかにもできない。
「ねえねえ、そんなつまらない話よりも、領主さまのぶゆーだん、聞かせてよ!」
日常の報告が一通り終わると、事務的な話に飽き始めた子供たちが、頬に飯粒をつけながら戦場の武勇談をせがむ。
「なんだよ。ウチがそういう話をするのは、苦手だって知っているだろ」
「うん。でも聞きたい! 領主さまのぶゆーだん!!」
「ぶゆーだん! ぶゆーだん!!」
「いいねえ、武勇談。あたしらも聞きたいよ!」
童らの要求を、母親たちも調子に乗ってあおり始める。ナオミは、観念して、此度の戦場での活躍を語る。
単身で敵陣に斬りこんだこと、相棒である『薙鳥<ちどり>』の活躍、敵将をしとめて金星をあげたこと、大御所からのお褒めの言葉……
口下手の自覚があるナオミだったが、女も子供も身を乗り出して、自分たちの領主の活躍に耳をそばだてる。
「はあー、ナオミさま発案の革細工。最初に聞いたときは、なんに使うのかと思ったものだけど、大活躍だったんだねえ」
「サムライどものあいだで、流行するんじゃないかい? いまのうちにたぁんと作って、高値で売りさばいて、一山当てようか」
笑いあう女子供たちを見て、自分の話で楽しんでくれたようだと、ナオミはほっと胸をなでおろす。
「で、テメェらのほうはどうだったんだ? 砦のほうはいつも通りだったみたいだが、領内にも変わったことはないのかい?」
赤毛の領主が、そう言うと、女たちは笑い声を止めて、互いに視線を交わしあう。
「……じつは、漁民が湖畔で土左衛門を見つけてねえ。弱っちゃいたが、命はあったんで、砦で保護しているんだよ」
頭目格の女の報告に、ナオミは目を細める。
「溺れたふりをした、どこぞの間者じゃないだろうな?」
「かんじゃは、あんなめだつ格好しないと思うよー」
ちらし寿司を頬張りながら、子供が口を挟む。周囲の女たちも、うなずき返す。
「髷も結っていない、奇妙な風貌の男さ。服装も含めて、イクサヶ原の人間じゃあないみたいだった……どこか、ナオミさまのような……」
「へえ……?」
皆の報告に、赤毛の領主は少しばかり好奇心をくすぐられる。保護している土左衛門とやら、もしかしたらナオミと同じ『ハグレモノ』なのかもしれない。
→【朧月】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
