
日本特殊論、ついに否定できず:三浦環とアート・テイタム、それぞれのユーモレスクの当惑と久生十蘭
アート・テイタムの未聴の盤を聴いていたら、またしてもHumoresqueが出てきて、いったい、テイタムは何度この曲をやったんだと、Everythingで検索してしまった。

5ヴァージョンがリストアップされ、すべてFB2Kにドラッグしてたしかめたところ、ダブりがひとつあり、結局、4ヴァージョン持っていることがわかった。
◎久生十蘭の「ユモレスク」と「野萩」
テイタムのHumoresqueを聴いていて、久生十蘭の「ユモレスク」を思いだし、再読した(フランス語としては長音なしなので、十蘭の表記のほうがいい。ただし、じっさいの音は「ウモレスク」に聞こえる)。
これはかの「野萩」のヴァリアント、いや、発表順で云えば「ユモレスク」が先、それを改稿して完成したのが「野萩」なのだが、ほぼ同じ小説でありながら、結末の違いで、まったくの別物になっている。
「野萩」は、まだ三一書房版全集を買う以前、高校二年だったか、中井英夫の十蘭論を読んで関心を持った時に、たまたま近所の古書店で見つけた、新潮小説文庫なる新書版叢書の短篇集「母子像」に収録されていた。
「人生を左右した本」などというものがあるとしたら、この「母子像」だったと思う。十蘭の日本語は圧倒的だった。

収録作は「予言」「姦〔かしまし〕」「白雪姫」「手紙」「蝶の絵」「野萩」「西林図」「春雪」「母子像」。つまらない母子像を削除し、かわりに「黄泉から」を入れれば、『ザ・ベスト・オヴ・十蘭 戦後篇』である。すごいラインアップ。高校生の精神には圧倒的な力をふるった。
戦後の、十蘭がもっとも厳しい日本語を書いていた時期の精華集だから、いずれもすぐれた短篇だが、とりわけ「西林図」と「野萩」に深い感銘を受け、翌年の三が日、家族で東京に行った時、機嫌のよい父親を口説いて、三一書房版全集を買ってもらった。
「ユモレスク」はずっと後年、国書版全集ではじめて読んだのだと思う。原型はあんな形で終わっていたことに驚いたが、なぜタイトルがユモレスクなのか、その意味はわからず、そして、いまもって理由を突き止められずにいる。
ふと、子供のころ、ユモレスクの唄ヴァージョンを聴いたような気がしてきて、その歌詞に、十蘭の「ユモレスク」解決のヒントがありはしないかと思い、検索した。

短篇の上澄みを集めた巻だが、選者はたぶん巻末解題も書いている中井英夫だろう。
◎ユーモアレス・ユーモレスク
Humoresqueの唄ヴァージョンは存在した。歌詞は複数あったようだが、聴けたのは妹尾幸陽作詞の一種のみ。音源は二種あった。チューブにも上がっているが、音質は以下の国会図書館のもののほうがはるかにいい。
三浦環
https://dl.ndl.go.jp/pid/8267424/1/1
能子ベルトラメリ
https://dl.ndl.go.jp/pid/1316764
ボブ・ディランのBelle IsleやビーチボーイズのSanta Ana Windsでは、歌詞の聞き取りにえらく手間取ったが、この戦前のユーモレスクも、日本語だから楽なはずなのに、はじめは何を云っているのかさっぱり聞き取れず、唖然とした。

しかし、ヘッドフォンをかけて、何度も何度も繰り返し聴いているうちに、だんだん云わんとすることがわかってきて、結局、一時間ほどで、ブリッジはさておき、ヴァースはコピーできた。友人にも聴いてもらい、一部訂正して、結局、以下の通りになった。
月の吐息か、ほのかなしらべは闇をば流れ来る わびしいこの身に、もだえる心に、響け、しらべよ
ひそやかに慕い寄る慰めの唄 誰の心 人知れぬ 涙さそう唄よ
この世の憂いもしばしは忘れて聞き入るわが胸に 月の吐息か、ほのかなしらべはただ涙さそう
日本語の歌詞というのは漢字のおかげもあって、呆れるほど短い。上記三行、最初が第一ヴァース、二行目がブリッジ、三行目が第二ヴァースである(いや、ポップ・ソングの用語で呼ぶとお怒りになる向きがあるやもしれぬが、そのほうが話が早い、というか、ほかの呼び方を当方知らず!)。
二行目はよくわからない。「慕い寄る」は「忍び寄る」かもしれないし、「誰の心、人知れぬ」は当てずっぽう、妄想のたぐいである。

いや、細かな字句のことは、この際、どうでもいい。問題は大筋、要するに、これはどういう歌なのか、だ。
Humoresqueというのは、ユーモラスな曲、という意味の音楽用語である。したがって、いま問題にしているドヴォルジャークのものばかりでなく、たとえば、チャイコフスキー、ド・ファリャ、ラフマニノフ、シベリウスなどなど、さまざまHumoresqueが手元にはある。
しかし、この歌詞のどこがユーモラスなのだ?
◎アート・テイタム、メル・ブラント、リロイ・ホームズ
上述のように、テイタムのHumoresqueは四種所持しているが、もっとも古い1940年のものから、53年の録音に至るまで、アレンジはほぼ変わらず、すべてバンドなし、ピアノのみでやっている。

したがって、イーヴン・タイムではなく、テンポは自由に変化させている(クラシックのほうも当然ながらテンポ・チェンジ数回あり)が、一貫して、いつものテイタムのスピード、つまり速いのだ。

「年代順」という意味ならば、正しくはChronologicalなのだが、このシリーズのタイトルは一貫してChronogicalなので、いかんともしがたし!
つぎに古いのは、経歴不明、シカゴのピアノ・プレイヤーらしいピート・ハンディーの1957年のものだが、テイタムよりは遅いものの、Honky Tonky Pianoというタイトルのアルバムに入っているぐらいで、ミディアム・アップで軽く、陽気にやっている。

1959年リリース、メル・ブラントのアコーディオン盤は、2ビートのポルカ、したがって当然、高速かつ陽気も陽気、バカ陽気。陰気なポルカなんてものはノー・サッチ・シングなのだ!
(わが家のアコーディオン盤の多くがそうであるように、これもまたIAでもらったのだが、先週も書いたように、目下ダウン中で、現在もあるかどうかは不明。何か書くにも、IAが使えないのはひどい足枷、復旧が待たれる。)

主としてMGM映画で働いたジャズ出身の作曲家、リロイ・ホームズの1960年のラウンジ・アルバム、Sophisticated Strings収録のHumoresque(当然、MGMレコードのリリース!)は、いかにもハリウッドらしいスムーズなサウンドで、ドラムズはフィルインを入れられず、ただ裏拍を強調した8分を叩くだけ。それくらい高速、したがって当然、軽快で陽気。

◎1960年代のヴァージョンズ
60年代録音のHumoresqueはほとんど持っていない。
オーストリア生れでイギリスで活動したヴァイオリン・プレイヤー、作曲家、オーケストラ・リーダーのレイ・マーティンのDynamica収録ヴァージョンは、リロイ・ホームズ盤すら圧倒する超高速で、わが家にあるHumoresqueのなかの速度記録保持者、当然、ドラムズは何もできず、ヴァースはハイハットで8分を叩きつづけている。草臥れただらうなあと旧仮名で同情した。

録音年不明、60年代中期のリリースと思われる、スカイロケッツなる経歴不明泡沫バンドによるHumoresqueは、リヴァーブ&トレモロをバリバリきかせた、ごくふつうの60年代ギター・インスト、もちろん、速くて軽くてノーテンキ。

◎1970年代のヴァージョンズ
1974年リリースの、ヴァイオリンのジョー・ヴェヌーティーとギターのジョージ・バーンズの共演盤 Gems 収録のヴァージョンは、導入部のヴァイオリン・ソロに関しては、後述するクラシック・レンディションに近いが、本体は4ビート・アレンジ。高速ではないが、遅くもなく、ミディアム・アップで、軽くやっている。

先年聴いた、ジョージ・バーンズとカール・クレスの共演盤 Two Guitars は素晴らしく、以来、バーンズを蒐集中だが、そう簡単には集まらず。
アル・カイオラがお年を召してからのアルバム、Lover's Guitars収録のHumoresqueは2ビートのポルカ・アレンジで、当然、高速。いや、アル・カイオラの無数のアルバムの中でも、これは最底辺の出来だと思うが。
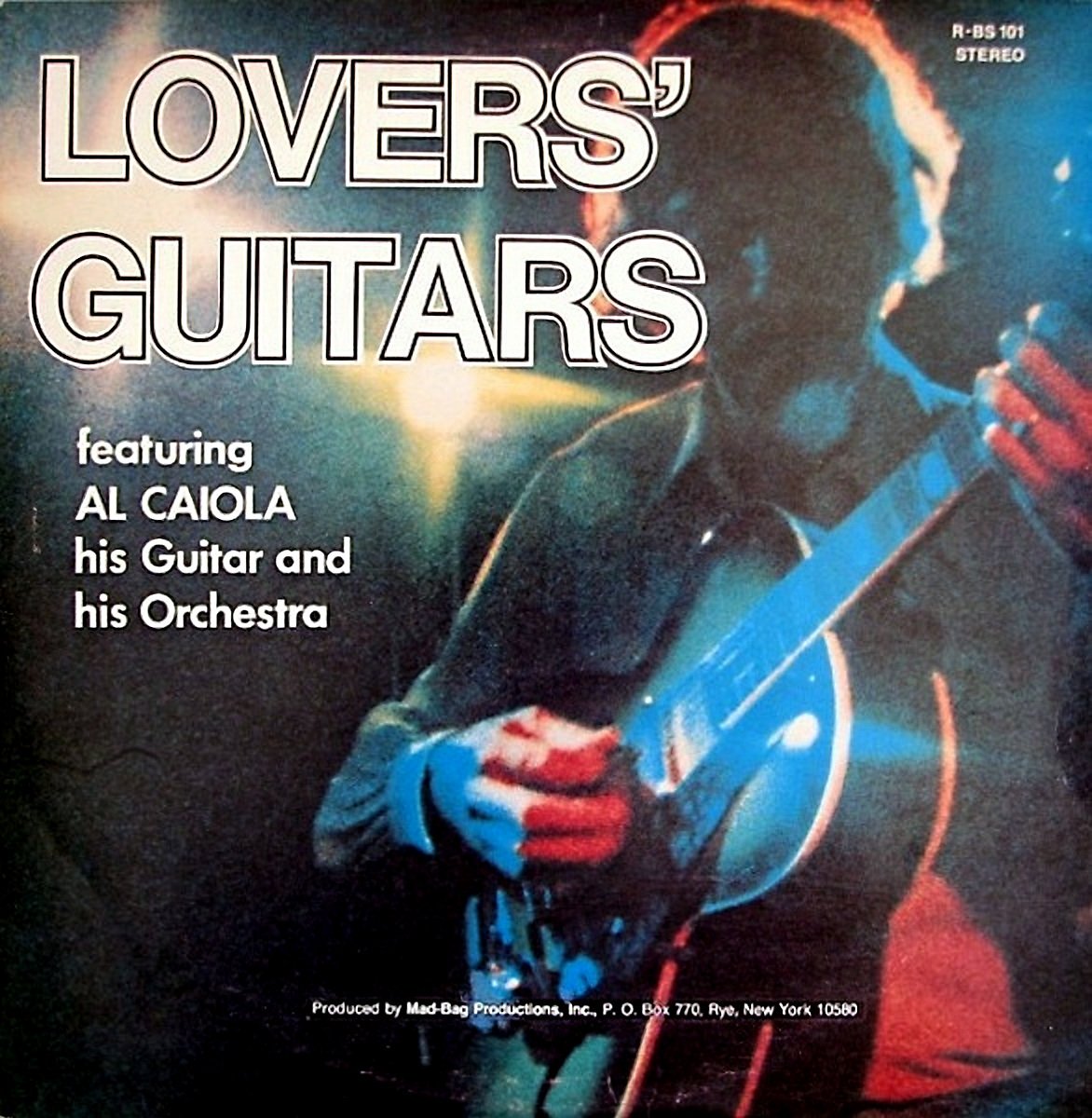
中身の出来もいまひとつだが、デザインはさらにひどい。どうしてこんなに駄目にできるのやら。
70年代にはもうひとつ。アート・テイタムと並んで、いや、おそらくテイタム以上に後年のピアノ・プレイヤーに影響を与えた、「バップ以降のピアノ・スタイルを創始した」ともいえる、アール・ハインズの晩年のプレイがある。

ヒットの反対語はミス。「懐かしむ」というmissのもうひとつの意味とかけたややこしいタイトル。アール・ハインズもなかなか盤が集まらない。思うに、テイタムはたしかにすごいのだが、あれは云ってみれば一代限りの芸、後進に継承されなかった。いっぽう、アール・〝おやじさん〟・ハインズは多数の後進に絶大な影響を与えた。
前半はゆったりやっているが、遅いわけではなく、テンポ・チェンジがあって、後半は高速になる。これがバンドといっしょなら、管はディクシー・アレンジになるだろうというスタイルで、当然、陽気なサウンドだ。
というしだいで、4ビートまで含む、ポップ系のカヴァーには、三浦環のような、悲しく陰鬱な解釈はゼロ。いずれも軽快、中速から高速、陽気なレンディションしかない。なんでこうなるんだ?
◎クラシックに戻って
Humoresqueはドヴォルジャークの作なので、当然、クラシックのプレイヤーのレンディションを聴かないといけないのだが、うちには一種しかなく、泥縄でさっき、ふたつ聴いてみた。合計で以下の三種。
まず、Arthur Grumiaux (発音サイトの音は、日本での一般的な表記である「グリュミオー」とはまったく異なり、「アルテュール・グルミヨー」)の Favorite Violin Encoresに収録されたもの。
ポップ系のカヴァーとは異なり、やはり古典のほうは速度はゆるめだし、ヴァイオリンのサウンド特性のせいで、マイナー・コードの入るブリッジはやや物悲しいニュアンスがある。

イ・サロニスティー(「サロン主人」という意味らしい)という、スイスのチェンバー・ミュージック・アンサンブルによるHumoresqueは、ヴァイオリン×2、チェロ、ベース、ピアノというクウィンテットによるもの。
リード楽器は2ヴァイオリンとチェロで、低い音が入る分、感傷的ニュアンスはグルミヨーにくらべて薄い。セカンド・ヴァースはチェロ単独なので、ブリッジのニュアンスは完全にキャンセルされている。音の重なりがある分、ピアノ伴奏のみのグルミヨー盤よりこちらのほうが好ましい。

なかなか面白い企画盤で、「タイタニック号で演奏された音楽」という副題が示す通り、かのThe Band on the Titanicがあの航海でプレイした楽曲を、弦楽クウィンテットで演奏したもの。
そもそも、このイ・サロニスティーというグループはジェイムズ・キャメロンのあの映画スコア録音のために生れたのだそうだ。いや、わたし自身はもっと古い、エリック・アンブラー脚本の『SOSタイタニック』のほうを子供の時に見て、あのバンドの運命に畏怖の念を感じたのだが。
もうひとつ、レオニダス・カヴァコスのVirtuoso収録のもの。これもグルミヨーに同じく、ピアノ伴奏のみ。ブリッジのスロウ・ダウンが強調されていて、グルミヨー同様、やや感傷的だ。

◎日本的な、あまりに日本的な
これで、だいたいわかった。戦前、三浦環が唄った時には、ブリッジのマイナーを強く響かせる解釈が当たり前だったのだろう。そして、それはヴァイオリンによるプレイを前提にしていたのだと想像する。
日本人の心性はマイナー・コードのほうに強く反応するらしい。昔、よくそういうことが云われたのだが、ロックンロール小僧としては、冗談じゃねーや、俺は違うぞ、といつも憤慨していた。
本邦戦前のHumoresqueのヴォーカル・ヴァージョンズは、ヴァースの軽快な、ブルーグラス・アレンジもオーケイなメイジャーの3コード進行のほうは無視して、ブリッジのマイナーに強く感応し、それをベースに歌詞をつくったのだと思う。そして、そこから逆算して、メイジャー・コードのヴァースまで、暗く唄うことになったのだろう。

これはまだ続きがあるのだが、下段がブリッジで、マイナー・コードがあるのがわかるだろう。このささやかなマイナーのために、日本語ヴァージョンは陰鬱になってしまったのだ。
それに対して、アメリカやイギリスのプレイヤーは、ブリッジのマイナー・ニュアンスを消す方向で解釈し、ユーモレスクという音楽形式に忠実に、明るく軽快にやったのだ。その典型として、以下の二種を聴かれたい。
リロイ・ホームズのHumoresque
https://youtu.be/F4ng_u3mJrw?si=aozQEwedDNYKhyMG
レイ・マーティンのHumoresque
https://youtu.be/4zjJbklsNcA?si=AegsDnYudLWUW029
クラシックではなく、ポップ分野のヴァージョンだからということもあるが、それにしても、マイナー・コードなんてどこにあるんだよ、というくらいにどこかに埋没されてしまった、ユーモレスクという看板を裏切らない明るさである。
考えてみると、ユーモレスクという言葉に、たとえば、「メヌエット=喜遊曲」とか「ノクターン=夜想曲」とか「ラプソディー=狂詩曲」といったような訳語をつくらなかったおかげで、あんな陰鬱歌詞、陰鬱解釈が成立したのだ。
たとえば、「ユーモレスク=諧謔曲」などという訳語があったら、あんな歌詞で、あんな唄い方をしたら、楽曲への冒瀆と嘲笑されたに違いない。

◎故郷の空のユモレスク
じつは、わたし自身、「ユーモレスク」という言葉を見ると、夕方の空を思い浮かべる。子供のころの、「ああ、うちに帰らなきゃ」と、空を見上げた時のさびしい感覚に結びついているのだ。
これはやはり、子供のころにラジオや音楽の授業で聴いたドヴォルジャークのユーモレスクが、そういうニュアンスで記憶されたということだろう。純粋培養ロックンロール小僧のはずだった人間も、実体はやはり、マイナー・コードに強く反応する「日本の子供」だったらしい。やれやれ。

それにしても、久生十蘭がなぜあの小説にユモレスクというタイトルを与えたのか、やはり疑問は解決できず。ま、そんなものだよ、life goes on。
