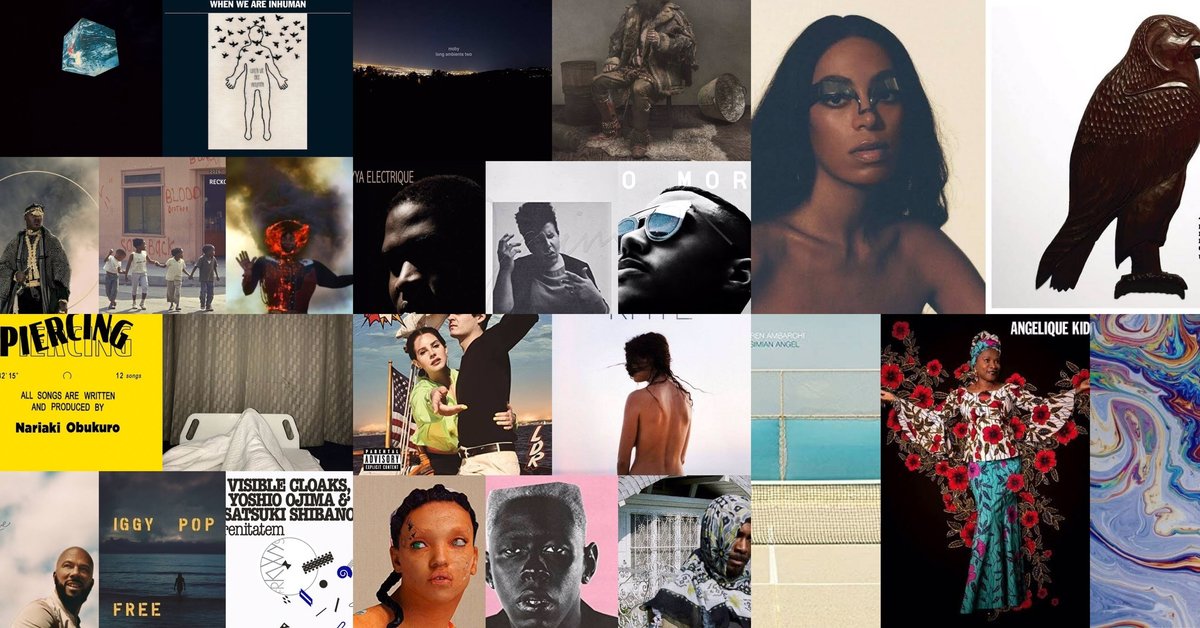
2019年ベストアルバム4: 25位〜1位
2019年ベストアルバム1: 100位〜76位
2019年ベストアルバム2: 75位〜51位
2019年ベストアルバム3: 50位〜26位
待っていただいた方本当に申し訳ありませんでした。
遅ればせながら2019年ベストアルバム、誰が全部読むのかわからんけど100枚です。後々になって振り返っても価値のある作品を選べたつもりです。長いけど全部に目を通してくれたら嬉しいな!
本稿公開現在、新型コロナウィルスが未だ治療法の確立されない中感染者が増える一方であり、各地で混乱と同時に公演のキャンセル等アート/エンターテイメント業界も大変な打撃を受けています。
とりあえず音楽に限って話をしても、主な収入源をライヴに置くアーティストと音源に置くアーティストがおりますが、まず前者を助ける策としては、一つでは無いと思いますがとりあえず簡単な一歩かつ実現したらもっとも効果的という事でふじもとさんのこのキャンペーンに共にご賛同頂けたらなと思います。
音源による収入の割合が大きいアーティストにとっても、公演中止は小さなダメージではありません。私自身がどちらかと言えばライヴハウスやクラブに足を運ぶよりもレコードにお金を使うタイプのリスナーなので、必然的にこのリストにも(収入割合としてはともかく)録音により意義を見出すアーティストの率が多くなっているかなと思います。
また現状は国内のニュースに目が行きがちで、こういう状況下にそうなってしまう事は決して悪い事とも思いませんが、ダメージは日本国内に留まりません。相次ぐ英語圏アーティストのアジアツアーの中止は、ファンやヴェニューのみならずアーティスト本人にも痛手であるわけです。
そんな様々な角度からダイレクトにダメージを受けたアーティスト、また…経済を回す事こそが至上の活動である、といった論調には率直に言ってあまり与したくないのですが、ある程度業界としてお金が回らないと文化的活動も立ち行かなくなるのが現実です。そういった状況下、普段YouTubeや定額制サブスクストリーミングをメインに音楽を聴いている方にも、サポートとしての意味も込め個別にお金を出して頂けたらな、という思いもあり、ストリーミング(Spotify)のほかアーティストを最もダイレクトに近い形でサポート出来るBandcamp、国内大手でのLPやCDといったフィジカル販売のリンクも(ある場合は)全ての作品に貼ってあります。
もちろんサポートとしてだけでなく、より高い音質で聴ける事や現在ではある種煩雑でさえあるフィジカルフォーマットであえて聴く体験、それらがシンプルにあなたにもたらすものも必ずあるはずです。
私が貼ったリンクから直接購入いただけることも嬉しいですが、外出自粛の波はアーティストを支えるもう一つのプラットフォーム、レコード店にも打撃を与えていると聞きます。このリストから気になった作品をピックアップし、実店舗であれオンラインであれ皆様それぞれの地元拠点のレコード店で購入していただければ、それもまた私としてもとても嬉しいですし、きっと現状に対する大きなサポートになると思います。
音楽を、文化を、どんな状況下でも絶やさぬように。その一助となれれば幸いです。
25. Christian Scott aTunde Adjuah - Ancestral Recall

トランペットを主とするジャズ畑のマルチ・インストゥルメンタリスト。
リリシストとしての評価も高くNine Inch NailsのTrent Reznorによるプロデュースでの作品も出しているシンガーSaul Williams、同年の名盤Common『Let Love』キーパーソンの一人Samoraの妹Elena Pinderhughesらが参加。
直近の3作を”ジャズ100周年三部作 (The Centennial Trilogy)”と銘打って歴史の総括を試みた彼は今作でより明確な未来志向へシフト。アフロ・フューチャリズムの最新型であると同時に、あらゆるジャンルを含めた音楽というフォーマットでの未来的ないしSci-Fi的表現の最新型である。アフリカ大陸における様々な地域での伝統的なパーカッションの乱舞と現代的なエレクトロニクスを結びつけているが、それは異化作用を狙ったものというより、異なる世界線もしくは異なる惑星でのポップ・ミュージックはこういった形が当たり前として育ったのだ、と言わんばかりに響く。プロダクションやアレンジメントの妙だけで無くソロイストとしての技量も大いに聴かせ、単純な音楽的類似点以上に、視線のその先にあるものが同じという点で所謂エレクトリック・マイルス期Miles Davisの正統的後継者はこの人物ではないか。
24. Tim Hecker - Konoyo / Anoyo


Konoyo: Spotify / Bandcamp / LP
Anoyo: Spotify / Bandcamp / LP
『Konoyo』は厳密には昨年作だが、他アーティストの年内に出た姉妹作を並べてランクインさせてる中ブランク1年以内は並べておいた方が座りが良いかなと…なにせ『Konoyo』と『Anoyo』だし。
そのタイトルから察しがつくように、ノイズ/ドローン/アンビエントといった範囲にカテゴライズされるエレクトロニカを作ってきたカナダ人プロデューサーの近作のテーマは日本の伝統音楽だ。なんだか安直なジャパネスクを危惧する向きもありそうだが、下手な邦人による純邦楽器を用いた現代的サウンドの作品よりもよっぽど雅楽や琵琶楽の形式に対する理解とリスペクトを感じる。
西洋的な拍節感覚と異なる日本的な”間(ま)”の概念と時間軸を融解させるアンビエントの親和性を活かして笙や篳篥をドローンに仕立て、ピークメーターのヘッドルームにこそ”何か”を忍ばせたような幽玄な音、ポスト・プロダクションによってその”現代性”を担保させた現代雅楽と言えるほどに雅楽の形式を強く残した音、エレクトロニクスと純邦楽器を暴力的にぶつけ合ってまだ見ぬ地平を開拓した音、とアプローチは様々。『Konoyo』=この世、と『Anoyo』=あの世、という言葉に対する日本人的な感覚が音に対して全く大げさでは無い、本当に涅槃が見えてくるような壮絶な音響絵巻。あらゆる観点からマイルストーンと認識されるべき歴史的連作。
23. Bonnie ‘Prince’ Billy, Bryce Dessner & Eighth Blackbird - When We Are Inhuman
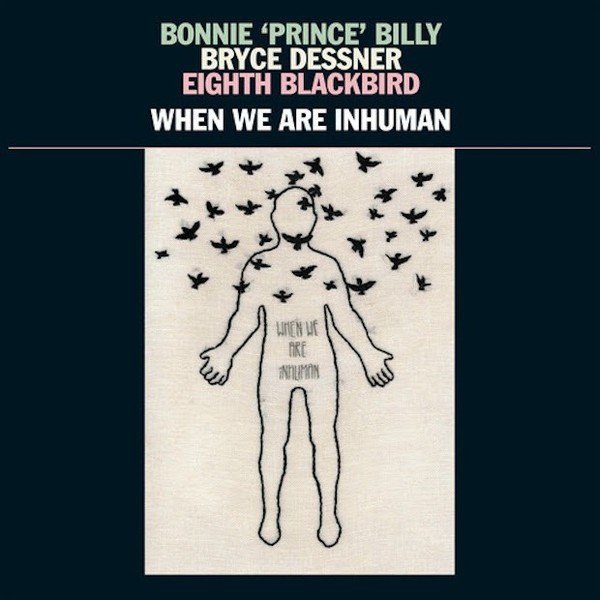
フォーク〜アメリカーナSSW Bonnie ‘Prince’ Billy、The Nationalの一員でポスト・クラシカル作曲家としても活動するBryce Dessner、現代音楽〜ポスト・クラシカルの領域で活動する室内楽団Eighth Blackbirdによる連名作品。
”繰り返す事”と”全く同じ繰り返しはありえない事”の同居というあらゆる事象の根源的な部分に迫るようなコンセプト。
2019年ベストアルバム補完ミドルレビュー集2: Kel Assouf, Kim Gordon, The National, Bonnie ‘Prince’ Billy & Bryce Dessner & Eighth Blackbird, Iggy Pop, Visible Cloaks & Yoshio Ojima & Satsuki Shibano, Uboa
22. Mourning [A] BLKstar - Reckoning

黒いスターを悼む”とのバンド名通り、アフロ・アメリカンを中心とした所謂”ブラック・カルチャー”を横断する事を志向した大所帯バンドの、ディストピアSci-Fiと今そこにある現代の厳しさを結びつけて歌ったコンセプト・アルバム。
70年代ソウルを基調としつつ現代的にアップデートする術はヒップホップへの接近に留まらず、2010年代の終りにディストピアを歌うことに相応しくVaporwave以降のサンプリング感覚を時に人力で時にポスト・プロダクションで持ち込んでいる。これはVektroidが現れた当初にVaporwaveが持っていた批評性の回復でもあり、そこでのサンプリング素材として多く使われたブラック・カルチャー側からの意趣返しであり批評返しでもあるのだろう。特に表題曲「Reckoning」におけるそれは鮮やかで、唐突な無音の挿入も楽曲展開の中に飲み込む手腕は舌を巻く。
何よりそういったVaporwaveを含む現代的なプロダクションと、最もプリミティヴな表現である肉声の歌唱による熱量が完璧に合致しているのが素晴らしい。リードヴォーカルは複数人で回しているが、特にJames LongsによるBobby Womackを彷彿とさせる歌唱の力は圧倒的なものがある。
21. Fear Gorta - Fear Gorta

2020年代裏の舵取り役筆頭候補にも挙げられる異才中の異才Jon Bapが絡んだ謎の集団のデビュー作。
「チルから暴力」(© @BLUEPANOPTICON)な流れもあった2019年の中でその両者の橋渡しとして最も相応しい作品ではないか。あざといほどに前衛を表明するサウンドで幕を開け、暴力とチル(≒メロウネス)が交互に現れ、徐々にそれが渾然一体となって、もはやチルと暴力という対極的でさえあるものの区別がつかなくなった先に謎の背徳的な快楽へ辿り着く。
非常にストレンジではあるものの、サブベース、現代ジャズ的なドラム・サウンドといった2019年的な音色をさらにカットアップ/コラージュする感覚もまた2019年的な音が並んだ果てに、サイケデリック・ロックを経由してAmon Duul IIとJohn ZornのNaked CityがPink Floydを素材にジャム・セッションを繰り広げたような長尺プロッグで幕を閉じるのが全く意味がわからないのだが、これでいいのだ。
20. Ifriqiyya Electrique - Laylet El Booree

チュニジアのヴォーカリストとフランスのギタリストを中心とした多国籍バンドの2nd。ヴィジュアルがそのままHUNTER X HUNTERに出せそうな手練の殺人集団の如しだが、音も凄まじく殺傷力が高い。
北アフリカ〜中東とイスラム圏の伝統的なスタイル(特に音楽ファンにはNusrat Fateh Ali Khanでも知られるスーフィー色が濃い)と、ハードなギターとドラムが引っ張るロックの見事な融合。そのロック要素は時にMinistryも真っ青なインダストリアルで、時にLed Zeppelin(そしてRobert Plantソロ作)が「Kashmir」や「Friends」といった曲で試みた実験のその先の地平で、時にJohn Frusciante加入初期のRed Hot Chili Peppersを思わすファンク寄りミクスチャーと引き出しが豊富。
同年作で言えばChristian Scott aTunde Adjuahにも似た異なる世界線の宗教音楽といった趣もあり、スピリチュアル・ジャズともデトロイト・テクノとも違ったアプローチでアフロ・フューチャリズムの地平を切り拓いている。
本編最終曲「Mabbrooka」は2019年最も暴力的なサウンドのひとつに数えられるであろう壮絶さ。ボーナストラックでは4つ打ちテクノも披露。
19. ドレスコーズ - ジャズ

バンド”毛皮のマリーズ”フロントマンとしてキャリアをスタートさせた志磨遼平のソロ・プロジェクト7作目。
マリーズ最終作『ティン・パン・アレイ』に垣間見えた豊富な音楽知識とカリスマ性に惹かれ注視していたが、作品ごとのコンセプト立ては非常に巧みながらもその表現方法に今一歩の物足りなさを感じていた。しかしその殻はとてつもない大傑作によって鮮やかに破られた。
風変わりな社会学系書籍の目次かというような固有名詞を並べた曲名と、アレンジのベースにロマやユダヤ系(クレズマー)といった"放浪の民"なイメージの伝統音楽を敷く…という虚飾に交えて、Bob Dylan『The Rolling Thunder Revue』やU2『The Joshua Tree』といったロック・レジェンド達のアメリカン・ルーツ探究の試みと日本の音楽の関係を紐解く。Beirutと久保田早紀を、Wilcoと桑田佳祐をシャッフルした先にアレハンドロ・ホドロフスキーの映画の如く現実と幻想、真実と偽史が入り混じる志磨遼平流音楽(偽)史解剖図。
終末へと向かう物語は、アルバムのど真ん中でありながらサウンドのコンセプトとしては完全に場違いなエレクトロニカ・トラップで"オリンピックがもうすぐくる"国を歌う「もろびとほろびて」によって異様な強度に補強されている。
18. Brittany Howard - Jaime

ロック/ソウル・バンドAlabama Shakesのギター/ヴォーカル、初のソロ作。
Alabama Shakes作品においても、音楽制作のエンジニアリング部分に関心が高くない層まで巻き込む程の評判を呼んだShawn Everettの録音やミックスは更に高みに辿り着いている。
シェイクスのSteve Johnsonも素晴らしいドラマーではあるが、Chris PotterやJose James、日本では黒田卓也との共演も知られるジャズ畑のベテランNate Smithのエヴェレット・サウンドとの相性は更に抜群だ。特に「13th Century Metal」でのJohn Bonhamを口寄せして現代的プレイを植え付けたパフォーマンスは筆舌に尽くし難く、鍵盤のRobert Glasperと共に凄まじいグルーヴを巻き起こしている。
もちろん主役ブリタニーのパフォーマンスも出色だ。前述「13th Century Metal」でのアジテーティヴなそれから、一転して自身でエレピも弾きつつ歌う「Georgia」での抑制されたトーン、Prince的な歌声を披露する「Tomorrow」と変幻自在。ギターもJack Whiteバリのハーモナイザー使いからストレンジなファンク・リフまで多種多様。”参加してる奴ら全員天才”案件。圧倒。
17. Moby - Long Ambients 2

ハウスやビッグビート等ダンサブルな領域でのプロデューサーやDJ業が高く評価されている人物のアンビエントシリーズ第2弾。
代表作は抑えていてもMobyがアンビエントを作るというイメージは無かったかもしれない。しかし最初期に既に『Ambients』という作品をリリースしており(ただこれはノンビートの曲が無いばかりか"アンビエント・テクノ"と呼ぶのも憚られるメインフロア向きトラックもあり少々散漫)、2005年には『HOTEL』の限定盤ボーナスディスクで全曲アンビエントミックスを加えていた。私的にはこの『HOTEL』リミックスにヤられて、時折ダンス路線は辞めてアンビエント専門になって欲しいと思う事さえあった程。
そして2016年、純然たるオリジナルのアンビエント作としては2009年『Wait For Me』以来7年ぶりの『Long Ambients 1: Calm, Sleep』という作品がフリーDLでドロップされた。穏やかながら極端に長い尺、変化に乏しい展開のそれはかしこまって耳を傾ける聴取姿勢を完全に拒んだもので、エリック・サティ云う所の"家具の音楽"を完璧に表現した作品だった。
話を2019年に戻す。"1”と冠しておきながら2が出ないのはもう本人も飽きたか忘れたか…と思っていたら再びフリーDLでこの『2』がドロップ。今回は副題を冠されていないが、機能性としては前作の"Calm, Sleep”とその単語の周縁的な言葉を思い浮かべれば期待は裏切られぬだろう。入眠用BGMとしてこれほどよく出来たものは無い。文字通りこれが”家具”ならば、10年経ってから「高かったけどあの時背伸びして買ってよかった」と思える究極の機能美を備えた家具だ。
16. Swindle - No More Normal

グライムの筆頭プロデューサーが生のストリングスやブラスを従えた作品。実質的に、その生音アレンジを手掛けたNeil Waters、それらとビートの融合を理想的な形で実現したミックスのJokerによる三頭体制と捉えたい。
ダンス・ミュージックとして重要な腰に来るグルーヴの官能性が増している一方、キックやスネア一つ一つの磨き上げとその上に積み重なるアレンジ、それらを整理するミックスが到達した練度の高さはまるで荘厳な建築物に対峙したような感動をもたらす。ある程度近い範囲で言えばDr. Dre『2001』や広く括ったダンス・ミュージックとしてRicardo Villalobos『Alcachofa』、構造的により離れた所で言えばMy Bloody Valentine『Loveless』のような高みだ。そう、リリースから1年足らずで幾年の風雪に耐え名盤と呼ばれる作品の風格がある。
生楽器奏者にはジャズ文脈の面々を多く起用しているが、それが異化作用というよりもグライムもまた伝統的なジャズから多くを受け継いでいるのだと示しているのが面白い。例えば「Drill Work」の脈打つベースは一聴するとドラムンベース〜グライム独特の、USヒップホップに比べ歴史的文脈の薄いある種奇妙なものに聴こえるが、そこにブラス・アンサンブルが同じラインを乗せる事で一気に伝統的なニューオーリンズ・ジャズからの歴史が浮かび上がる。温故知新、とはこのような作品を形容する上であまりにありきたりだが、しかしやはり歴史を辿る事にこそ新しい道があるのだという事を再認識させられる。
15. Iggy Pop - Free
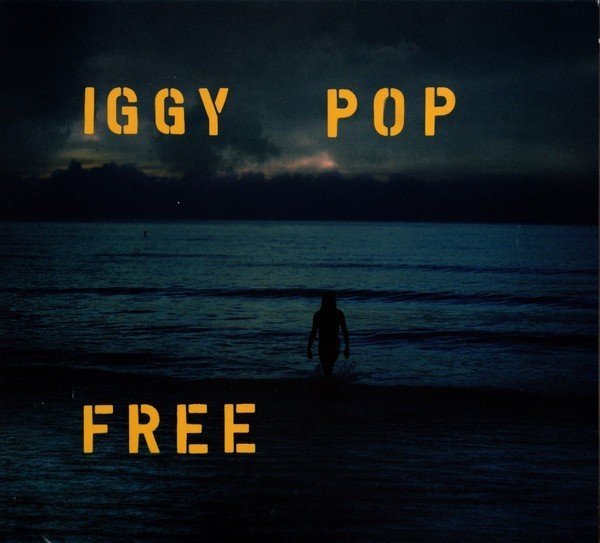
パンクのゴッド・ファーザーがジャズ・トランペッターLeron Thomasを招きジャズに接近した作品。
盟友David Bowieとの地球最後の旅路。
2019年ベストアルバム補完ミドルレビュー集2: Kel Assouf, Kim Gordon, The National, Bonnie ‘Prince’ Billy & Bryce Dessner & Eighth Blackbird, Iggy Pop, Visible Cloaks & Yoshio Ojima & Satsuki Shibano, Uboa
14. Visible Cloaks, Yoshio Ojima & Satsuki Shibano - FRKWYS Vol. 15: Serenitatem

ニューエイジ再評価/リバイバルとVaporwaveの交差点に立つポーランドのユニット、Visible Cloaks。日本の音楽からの影響と敬愛を公言してきた彼らがその先駆者たるシンセサイザー奏者の尾島由郎、アンビエントの原点=家具の音楽の提唱者エリック・サティの演奏で知られるピアニスト柴野さつきという二人の日本人と共演した作品。
2019年ベストアルバム補完ミドルレビュー集2: Kel Assouf, Kim Gordon, The National, Bonnie ‘Prince’ Billy & Bryce Dessner & Eighth Blackbird, Iggy Pop, Visible Cloaks & Yoshio Ojima & Satsuki Shibano, Uboa
13. 小袋成彬 - Piercing

宇多田ヒカルのプロデュースにてソロ・デビューから注目を集めていた男声SSW、1年半のスパンでの2作目。
小袋成彬 - Piercing にまつわる雑文だけどひょっとしたら正解を射抜いているかもしれない文
12. Uboa - The Origin Of My Depression

ダーク・アンビエント、インダストリアル、スラッジ・メタル…そういったエッジーなジャンルを網羅に近い形で横断するオーストラリアのアーティスト、Uboaの6作目。
2019年ベストアルバム補完ミドルレビュー集2: Kel Assouf, Kim Gordon, The National, Bonnie ‘Prince’ Billy & Bryce Dessner & Eighth Blackbird, Iggy Pop, Visible Cloaks & Yoshio Ojima & Satsuki Shibano, Uboa
11. Common - Let Love

俳優としても知られるコンシャス・ラッパーの筆頭たるベテラン。
ソロ名義前作『Black America Again』は現代ジャズを代表するピアニストRobert Glasperの全面的バックアップでタイトルが示すブラック・カルチャーへの高い意識を備えつつ非常に先進的な力作だった。それに手応えを得てか、ロバートと共にKarriem Rigginsを招いてAugust Greenというユニットまで結成しアルバムを出した。そして今回はそのAugust Greenを挟んだリレーと言えるカリームが全面バックアップ。
しかしカジュアルなジャケットとタイトルに現れたように、前作の黒人である事やアメリカ人である事への強い意識といった社会性は少々減退し、生活に寄り添う美しいポップが紡がれている。
カリームと共に今作のキーパーソンと言えるのがSamora Pinderhughes。これまでもコモン作品に参加した事はあったが、ここまで深く関わるのは初めての事。妹のElenaと共に音楽家であり、劇伴仕事等も手掛けていながら、未だ確たる評価を得ているとは言い難いサモラの才能を決定的に世界に紹介した作品としてもこのアルバムは記憶される事だろう。
そのサモラが美しいピアノを奏で、Jill Scottが儚くも身震いする名唱を添える「Show Me That You Love」は2019年の遍く音楽の中で最上位の輝きを放っている。
10. Lana Del Rey - NFR! Norman Fucking Rockwell

アメリカの影を戯画的に描く女声SSWの6作目。
Review coming soon
9. FKA Twigs - Magdalene

Arcaを従えミュータント・エレクトロのディーヴァとして華々しく登場も寡作気味でこれが5年ぶり2作目。
Review coming soon
8. Tyler, The Creator - IGOR

Frank OceanやThe InternetのSyd, The Kidらを10年代のキーパーソンを多数排出したクルーOFWGKTAの中心人物。
Review coming soon
7. JPEGMAFIA - All My Heroes Are Cornballs

ボルティモアのラッパー/プロデューサー、前作『Veteran』が喝采をもって受け入れられた中1年半と短めのスパンでリリースされた3作目。
古い表現で言えばTVのザッピング、あるいはTwitterのタイムラインのようなコラージュ…と一聴すると聴こえるが、実のところドラムビートが大胆に切り替わってもウワモノのどれかのトラックは継続して鳴っていたり、全体が変わってしまう場合は「Kenan Vs. Kel」における前半のメロウネスと後半の暴力性というのが象徴的だが対極的になって派手なコントラストを作るように計算されていたりする。タイトル曲などコラージュと呼ぶよりグラデーション的な変化と捉えたほうがしっくり来る。破天荒なようでいて、実はトラディショナルな意味での”作曲”を拡張する、第二次大戦後から60年代いっぱいにかけての現代音楽作家が行っていた試みのアップデートでもあるのかもしれない。
しかし旧来的なヴォキャブラリーのみで語るには謎めいているのも確かで、掴みきれない部分があるからこそ中毒的にリスナーを惹き付ける。Vaporwaveやトラップといった2010年代のトレンドを数多く散りばめつつ、遂に来た2020年代はおろか更にその先さえも見通したような未来的作品。
6. Rhye - Spirit

チルウェイヴの流れから登場したバンドがヴォーカルMike Miloshのソロ・プロジェクトとなっての2作目、通算3作目。
ポスト・クラシカル/インディ・クラシカル畑のピアニストOlafur Arnaldsを招聘しているが、そのジャンルらしさ…クラシカルへの接近と言うよりも、ピアノの比重を高めるに当たって白羽の矢が当たったのがオーラヴルだったという程度に考えた方が良い。そう、今回接近しているのはピアノを主とするSSW的な形だ。
セックスを描く事は必然的に生と死を描く事であるとばかりにR&Bの官能を内省へと置き換えてきたRhye。その内省をより深化させるため感情表現において更に奥へ踏み込むために取った音楽的手段が、しなやかなグルーヴを産んでいたドラムビートを控えめにして典型的なピアノSSWに接近する事だった、というのに一抹の寂しさはある。あくまでダンサブルなグルーヴを保ったまま内向的な感情を表現する事こそRhyeの真骨頂だったのではないか、と。
しかし結果的に発せられたこの音には抗えない。音楽は時として直接対話するよりも生々しい感情を伝えるのだ、という事を思い出させるヒリヒリした感触。あまりの赤裸々さに戸惑いすら覚える、真夜中のベッドで咽び泣く愛の音。
5. amamiaynu - amamiaynu
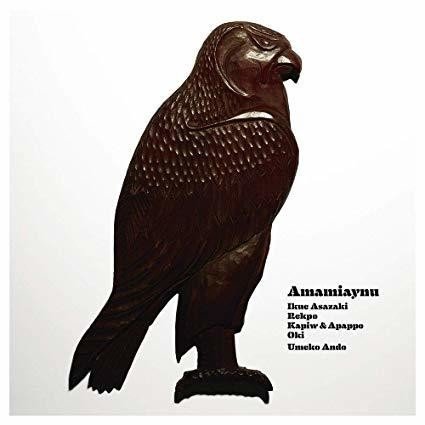
Marewrewの評にて触れたChikar Studioから、こちらもOKIのプロデュースにてマレウレウのRekpoやKapiwといった現役アイヌ音楽歌手、さらに故・安東ウメ子もサンプリングした中に奄美民謡のベテラン朝崎郁恵を迎えてアイヌ音楽と奄美音楽の融合を図った作品。
OKIの似たような試みは初めてでは無く、かつて琉球のベテラン大城美佐子と共に『北と南』というアルバムを作っている。そちらも非常に良質かつ興味深い作品ではあったが、ある程度ポップな企図を持った作品故に、ポップスのグローバルな伝播と共にアイヌや琉球に限らず各地の伝統音楽からスポイルされた部分は薄いままで提示された作品という側面も否めなかった。
翻って本作はプロダクションも実にミニマル。なんとなく、な心構えで聴いてしまうと、まるで太古の音楽を蘇らせたかに聴こえてしまう…アイヌ文化と奄美文化が交わった事など近代以前に無い(はず)にも関わらず、だ。
そうして作り上げた日本の北端と南端(にして倭人が侵略した土地)を結び付ける仮想のミッシング・リンクは、伝統音楽という言葉につきまとうイージーな”素朴で自然志向”といった形では無く、シャーマニズムに回帰した上で未来を見通す2020年代のサイケデリック・ミュージックとして結実した。これはAnimal Collectiveの商業的全盛期に見た夢の続きにして、TOOLが新作で試みたミニマリズムのその先の鏡像だ。そして伊福部昭とRas Gの白昼夢の交差点だ。James HoldenもShabaka Hutchingsも泣いて羨む呪術的サイケデリアの極値点。全音楽ファン必聴の大名盤。
4. Oren Ambarchi - Simian Angel

Sunn O)))やChristian Fennesz、Jim O’Rourkeらとの共演が知られるギターを中心としたオーストラリアのマルチ・インストゥルメンタリスト。
Oren Ambarchi - Simian Angel、とほか幾つかの作品と考える、”録音芸術” (年間ベストアルバム4位)
3. Angelique Kidjo - Celia

ベニンを代表する存在からアフリカ大陸全体を代表する存在にまで登り詰めたこのシンガーは、齢60を目前にして遂に全地球を代表する存在になった。
Talking Heads『Remain In Light』をまるまるカバーした前作に続いてのトリビュート・シリーズとも言える今作はサルサのレジェンドCelia Cruzのカバー。まさか前作がトーキング・ヘッズのカバーだと言う事で聴いておきながら「今回はサルサか、じゃあいいや」などとスルー出来るロックファンは居ないとは思うが、ついDavid Byrneを憐れんでしまった前作同様セリア・クルーズという巨星すらなんだか可哀想に思える圧巻の出来である。
前作から引き続きFela Kutiを支えたTony Allenをドラムに、そしてベースにはMeshell N’Degeocelloを招聘してアフリカ大陸及び地球最強のリズム隊を従えるだけでは飽き足らず、若き”King” Shabaka Hutchingsが前作でDev Hynesが聴かせた暴力的なギターソロに匹敵するブロウを聴かせる。「La Vida Es Un Carnaval」ではトニーが何故自らがレジェンドと呼ばれるのかを誇示し、「Toro Mata」でのミシェルのベースは人間を辞めている。主役の「Quimbara」におけるポリリズミックなヴォーカルにはもう言葉が出ない。
南米系が北米へと渡って築き上げられたサルサという音楽を、自らの故郷アフリカと結び付けるだけに留まらずユーラシア大陸へと足を伸ばして中東やインドも匂わす豊かなアレンジが、これ以上無い演奏のこれ以上無い素晴らしい録音によって聴ける。人類の歴史のひとつの到達点。
2. Floating Points - Crush

マンチェスター出身でDJ/テクノ〜ハウス・プロデューサーとして最も知られるが、ジャズやプログレッシヴ・ロックに接近した活動も並行して行っており、本作は両路線の集大成と言える。
Review coming soon
1. Solange - When I Get Home

Beyonceの妹…という枕詞ももう不要なR&Bシンガー。
Review coming soon
いいなと思ったら応援しよう!

