
2019年ベストアルバム3: 50位〜26位
2019年ベストアルバム1: 100位〜76位
2019年ベストアルバム2: 75位〜51位
待っていただいた方本当に申し訳ありませんでした。
遅ればせながら2019年ベストアルバム、誰が全部読むのかわからんけど100枚です。後々になって振り返っても価値のある作品を選べたつもりです。長いけど全部に目を通してくれたら嬉しいな!
本稿公開現在、新型コロナウィルスが未だ治療法の確立されない中感染者が増える一方であり、各地で混乱と同時に公演のキャンセル等アート/エンターテイメント業界も大変な打撃を受けています。
とりあえず音楽に限って話をしても、主な収入源をライヴに置くアーティストと音源に置くアーティストがおりますが、まず前者を助ける策としては、一つでは無いと思いますがとりあえず簡単な一歩かつ実現したらもっとも効果的という事でふじもとさんのこのキャンペーンに共にご賛同頂けたらなと思います。
音源による収入の割合が大きいアーティストにとっても、公演中止は小さなダメージではありません。私自身がどちらかと言えばライヴハウスやクラブに足を運ぶよりもレコードにお金を使うタイプのリスナーなので、必然的にこのリストにも(収入割合としてはともかく)録音により意義を見出すアーティストの率が多くなっているかなと思います。
また現状は国内のニュースに目が行きがちで、こういう状況下にそうなってしまう事は決して悪い事とも思いませんが、ダメージは日本国内に留まりません。相次ぐ英語圏アーティストのアジアツアーの中止は、ファンやヴェニューのみならずアーティスト本人にも痛手であるわけです。
そんな様々な角度からダイレクトにダメージを受けたアーティスト、また…経済を回す事こそが至上の活動である、といった論調には率直に言ってあまり与したくないのですが、ある程度業界としてお金が回らないと文化的活動も立ち行かなくなるのが現実です。そういった状況下、普段YouTubeや定額制サブスクストリーミングをメインに音楽を聴いている方にも、サポートとしての意味も込め個別にお金を出して頂けたらな、という思いもあり、ストリーミング(Spotify)のほかアーティストを最もダイレクトに近い形でサポート出来るBandcamp、国内大手でのLPやCDといったフィジカル販売のリンクも(ある場合は)全ての作品に貼ってあります。
もちろんサポートとしてだけでなく、より高い音質で聴ける事や現在ではある種煩雑でさえあるフィジカルフォーマットであえて聴く体験、それらがシンプルにあなたにもたらすものも必ずあるはずです。
私が貼ったリンクから直接購入いただけることも嬉しいですが、外出自粛の波はアーティストを支えるもう一つのプラットフォーム、レコード店にも打撃を与えていると聞きます。このリストから気になった作品をピックアップし、実店舗であれオンラインであれ皆様それぞれの地元拠点のレコード店で購入していただければ、それもまた私としてもとても嬉しいですし、きっと現状に対する大きなサポートになると思います。
音楽を、文化を、どんな状況下でも絶やさぬように。その一助となれれば幸いです。
50. Kindness - Something Like A War

Adam Bainbridgeのソロ・プロジェクト、5年ぶり3作目。Robyn、Sampha、yMusicのRob Mooseらが参加。
これまではR&B寄りインディ・ポップと呼ぶのが相応しい音楽性だったが、今回はそんなコードワークは作曲の基本に置いたまま、リズムのダンス・ミュージック化が本格的に進行。結果Arthur Russellから連なるクィアなディスコの最新型とも呼べるものに。シンセや打ち込みのキックにより総体の質感はエレクトロニックなものの、随所で生のギターやベースが重要な役割を担っているのもまたArthur Russell的。ギターのBryndon Cookは要所で山下達郎を思わせるタッチも披露、日本のギタリストも注目すべき存在だ。
冒頭の曲名からもわかるようにアフリカンな要素も多分に取り入れられている。それと生演奏の尊重が絡んだ結果の必然としてか、スピリチュアル・ジャズとデトロイト・テクノの交差点のようになっている終盤3曲は、クィア、スピリチュアル・ジャズ復興、(アフロ・)フューチャリズムといった10年代後半の音楽シーンを彩ったキーワードの総決算な趣もあり、批評家やミュージシャン、熱心な音楽ファンまで2010年代を捉え直すために必聴の作品だろう。それでいてAdamの個の、ある種内省的なエモーションが作品を駆動させている事が本作をより一層得難いものにしている。
アートワークとシンクロしたクィアなピンクヴァイナル、DJにも嬉しい45回転カッティングで音質も良好、更にインナーグルーヴにも”仕掛け”がある事からヴァイナル大推薦。
49. Dos Monos - Dos City

Clipping.やJPEGMAFIAらオルタナティヴなヒップホップの奇才を数多く送り出したDeathbomb Arcから登場した日本のヒップホップ・ユニット。
Dos Monos - Dos City: ”現代のセロニアス・モンク”なんて文句が巷に跋扈する昨今ですが…え?誰も言ってない?
48. Robert Glasper - Fuck Yo Feelings

グラミーを受賞した『Black Radio』等で”ジャズの新作”を再び他ジャンルリスナーからも注目される舞台に引き戻したジャズ・キーボーディスト、ラッパーを多数招いてこれまで以上にヒップホップに寄せた、”ミックステープ”と称しリリースされた新作。
基本編成はもちろんグラスパーが鍵盤、ベースにはグラスパーとも長年の友でありCommon、Maxwell、Q-Tipと錚々たるメンツを支えた凄腕Derrick Hodge。そしてドラムには宇多田ヒカル『初恋』参加で日本でも一気に知名度を拡大した現在世界最高峰の一人Chris Dave。
グラスパーの単独名義なものの、Cannonball Adderley『Somethin’ Else』のMiles Davisばりに…とは言い過ぎだろうが、しかし確実に最も存在感が強いのはクリスのドラムだ。最早伝統芸になったJ DillaやMadlibのヨレを意識したドラミングはもちろん、複数の極端なチューニングを施したスネアを使い分けてのダイナミックなプレイ、戯画的なヒップホップとしてスネアとキックを配置する中でも単なるタイムコードに留まらない繊細だが攻めたハイハットワーク。このドラマーを追いかけて聴くだけでうっとりしてしまう。
無論主役もただの添え物で居続けはしない。Herbie Hancock御大とエレピでアヴァンギャルドなインタープレイの応酬を聴かせる「Trade In Bars Yo」に圧倒されないものはいないだろう。ゲストラッパーの中では、若手YBN CordaeとベテランYasiin Bey (元Mos Def)が特に素晴らしいパフォーマンス。
47. Suchmos - The Anymal
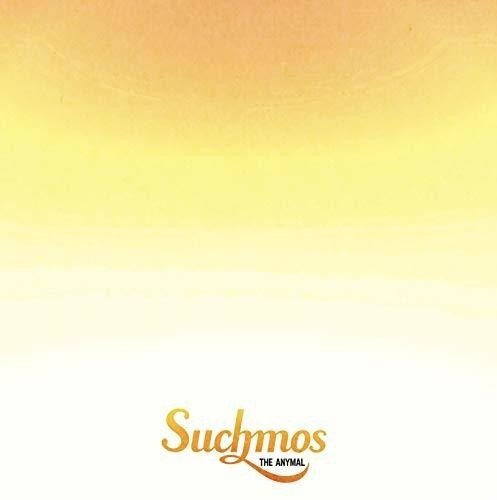
「Stay Tune」の大ヒットでシティポップ・リバイバルをお茶の間レベルまで拡散させた日本の若手バンドがサイケでブルージーな路線へ大胆な転換を披露した作品。
Suchmos - The Anymal: シティポップ・リバイバルはリドリー・スコットの夢を見るか?
46. 細野晴臣 - HOCHONO HOUSE
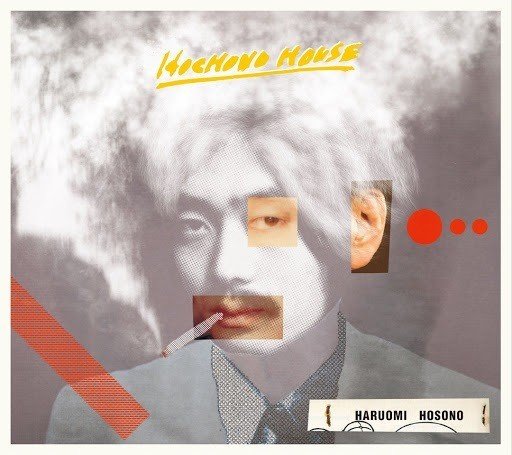
言わずと知れた日本音楽界最重要人物、最新ソロはバンドサウンドだった1st『HOSONO HOUSE』の曲順をひっくり返し完全に1人でリメイクした作品。
弾き語りトラックもあるものの、全体としてはアコースティックでのルーツ・ミュージック探究が続いた近作からエレクトロニクス中心に揺り戻している。とはいえ歌メロは大筋残されリコードも少なく、75年作『TROPICAL DANDY』の「Honey Moon」を93年作『Medicine Compilation』で再演した時ほど大胆な変化は感じない。
エレクトロニックなアプローチは近年のトレンドのどのジャンルや言葉で括ってドンピシャな訳では無いが、細野からの影響を公言しているVisible Cloaksら欧米若手からも吸収していると、未だ最先端の探究を続けていると、そう認識するには十分過ぎるアンテナ感度の健在を示している。
が、”エレクトロニック・リメイク!”なんてコピーを付けるには、歌メロをアコースティックギターで紡いだ「終わりの季節」あたり牧歌的過ぎるし、何より重要であろう新録というコンセプトから外れて70年代のライヴ音源を入れちゃったりもしている。普通ならばコンセプトの不徹底だとか散漫だなんて批判対象になりそうな部分を、何か深い意味があるのではと勘ぐってしまう。ただ煙に巻かれているだけなのかもしれない。しかしそれで構わない。それこそ細野晴臣を聴く喜びなのだから。
45. Kel Assouf - Black Tenere

サハラ砂漠を旅する遊牧民トゥアレグ族の面々によるハードロック・バンド。アフリカ音楽愛好家、一筋縄では行かない音楽を求める好事家はもちろん、HR/HMを主とするリスナーに「また”ハードロック+〇〇”か」とスルーせず聴いて欲しい。
2019年ベストアルバム補完ミドルレビュー集2: Kel Assouf, Kim Gordon, The National, Bonnie ‘Prince’ Billy & Bryce Dessner & Eighth Blackbird, Iggy Pop, Visible Cloaks & Yoshio Ojima & Satsuki Shibano, Uboa
44. Jack Larsen - Mildew

2020年代の飛躍に最も期待したいソロ・アーティストのデビュー作。
冒頭「Spirit」はKraftwerkを思わすシンセで幕を開けるが、全体にUS・ドイツ・UKという3国からの音楽要素の配置バランスが同じくクラフトワークにインスパイアされたDavid Bowie『Station To Station』と重なる。USからはR&Bを中心と解釈してのポップ要素を引き出し、ドイツからは実験的エレクトロニクスの要素を引き出す。そしてJackはシカゴ拠点ではあるが、その要素を重ね合わせるセンスは先述デヴィッド・ボウイらの70年代の仕事に端を発しUKに脈々と受け継がれてきたそれに近い。
Ariana GrandeとAshraを同じ箱に入れてしまったような「Rigid」をもしボウイが聴いたらどう反応しただろう。若手をこのように評する事に反感を抱く方もいるだろうし、あまりそこに拘り過ぎても本作のここで紹介しきれない多様性を見逃しかねないが、あえて言いたい。激しいギターやドラムは無くとも、国籍や出身がUKで無くとも、ボウイを筆頭にJohn LennonにThom Yorke等々とUKからロックの枠組みそのものの拡張を果たしてきた面々の後継者として今最も相応しいのはこのJack Larsenではないか、と。
43. Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

クリストファー・クロス以来の偉業を成し遂げた人
現時点では(どちらかというとFKA Twigsの話なのだけど)こんな記事も書いている: インダストリアル/EBMからArca〜FKA Twigs、そしてBillie Eilish:マシーン・ミュージックとエモーション
Review coming soon
42. marewrew - mikemike nociw

角松敏生のバックや沼澤尚らと組んで文字通りダブ等の要素を取り入れたOKI DUB AINU BANDによって伝統音楽以外のリスナーにも射程を広げた、アイヌの伝統楽器トンコリ奏者OKI主催のChikar Studio所属女声4人組アイヌ音楽グループの3作目。
これまでの作品におけるパフォーマンスは、どこかレーベルのそしてアイヌ音楽全体の偉大な先人安東ウメ子(故人)に対して剥き身でのパフォーマンスでは敵わないという腰が引けた形に映る所もあったが、ややポップで厚めなプロダクションの初作、装飾を取り払う事に挑戦した前作を経て、今作は堂々とした振る舞いを聴かせている。
それはアイヌ音楽入門における新たなスタンダードとしての風格を獲得したと同時に、「きらきら星」を引用したラストを筆頭に、かつて伊福部昭が行ったようなアイヌ音楽の構造をミニマル・ミュージックとして捉えてより伝播性を高め広めていくヒントも散りばめられている。
41. Weyes Blood - Titanic Rising

Natalie MeringによるSSW的ソロ・プロジェクト、名門Sub Pop移籍後初作、通算3作目。2010年代においてオーセンティックなロックの作法に則りつつ時代に背を向けないアーティストの背中を常に支え続けたFoxygenのJonathan Radoがプロデュース。
ジョナサン・ラド仕事の多くのように随所にThe Beatlesを香らせる。冒頭「A Lot's Gonna Change」のピアノからしてJohn Lennon『Imagine』に源流を求められるサウンドだ。しかしそんなサウンドを散りばめつつも作品を”ビートル・マニアへの供物”化させてしまわないのもまたジョナサンの手腕で、表題曲「Titanic Rising」から「Movies」というアンビエント〜ニューエイジ・リバイバルな流れは実に効いている。
無論ナタリー・マーリングの才能も語られねばならぬ。前述「A Lot's Gonna Change」での儚くも力強い名唱や、「Wild Time」での複雑な構成をシンプルな美にまとめきる作曲力には身が震える。
”チェンバー・ポップ”という言葉をここ20年程度のUSインディにおけるものと感じる向きも、60年代終盤から脈々と連なるものと感じる向きも、両方が切なさと共に高い満足感を得られるであろう名作。
40. Sunn O))) - Life Metal / Pyroclasts


Life Metal: Spotify / Bandcamp / LP
Pyroclasts: Spotify / Bandcamp / LP
結成から21年、最早重鎮と言えるドローン・メタルの巨人デュオ。
5枚目以降はコラボ作品を含めてもやや寡作寄りだったのが嘘のように2019年は単独名義でフルサイズのアルバムを2枚リリース。共にエンジニアは、これまで絡みが無かったのが不思議な轟音ギターの名匠Steve Albini。アートワークも対になっており、本稿では2枚セットで評価する。
先に出た『Life Metal』は実質的なコラボ作品集と言えるほどゲストの存在感が強い。Anthony PaterasのオルガンやT.O.S. Nieuwenhuizenのシンセも非常に重要な役割を担っているが、なんといっても再注目はチェロのHildur Guònadóttirだろう。トッド・フィリップスの話題作『ジョーカー』の劇伴も手掛け高く評価され、その他客演も多くこなし2019年音楽シーン裏の主役とさえ言える存在感を示したヒドゥルの、最も素晴らしい演奏が聴けるのはここであると言って構わないだろう。特に「Novæ」におけるワン・ノート・ソロが生み出す緊張感は常軌を逸している。
次に出た『Pyroclasts』にも一応ヒドゥルは参加しているが、こちらはよりGreg AndersonとStephen O’Malleyふたりの関係性にフォーカスした作品と言えよう。近い時期のセッション同じエンジニアだけに世界観も似ているが、デュオの緊密さは『Life Metal』とは異なるサイケデリックな陶酔感を産んでいる。こちらもまた非常に魅力的だと前置きした上で、どちらか一方のフィジカルを買うのであれば『Life Metal』を推薦する。
39. James Blake - Assume Form

00年代末にポスト・ダブステップとしてクラブシーンを賑わし、その後初のアルバムでは10年代のSSWの在り方を決定づけたシンガー/プロデューサー。己が主役となったディケイドの締め括りに放った作品。
Review coming soon
38. NOT WONK - Down The Valley

北海道は苫小牧を拠点にするエモ・バンドの3rd。
地元贔屓だもんで名が売れてきた頃から気にしてはいたのだけど、正直な所今一歩踏み込めずにいた。センスも一定以上の演奏力も感じるが、どうもグルーヴも直線的でアレンジもベタっとした日本のギターロックバンドが陥りがちな穴に片足を取られている感が否めなかった。
それが本作で一気に殻を破っている。一聴した段階では何が決定的な変化かわからなかったのだが、ギター/ヴォーカルを務める加藤のele-kingインタビューを読んで氷解した。本作の制作にあたって近年のUKジャズからの影響が大きかったというのだ。
それはジャズという言葉の指す範囲が再び拡張している昨今においても、決して所謂ジャズ・ファンが聴いて高確率で好きになると言うほど前面には出ていない。それでも前作と本作を聴き比べると、グルーヴに増した立体感の差異はHenry WuやYussef Dayesらに由来すると考えればしっくり来る。
その変化は元々のメロディセンスをも更に際立たせ、エモーションを膨らませる事にもまた成功している。まだ残る若々しさの疾走と、若いばかりではいられなくなった焦燥感とが共に胸を鷲掴む。先述のような問題に陥りがちな日本のギターロックが参照すべきヒントは、土臭さを残しつつもダンス・ミュージックとしてのグルーヴに拘りを持ったUKジャズにあったのかもしれない。
37. Kim Gordon - No Home Record

オルタナティヴ・ロックの祖たるノイジーなロックのレジェンド、Sonic Youthの元ベーシスト/ヴォーカリスト。バンド解散後、ファン心理に複雑な描写も話題を呼んだ自伝を経て完全単独名義としては初のフル・アルバム。
2019年ベストアルバム補完ミドルレビュー集2: Kel Assouf, Kim Gordon, The National, Bonnie ‘Prince’ Billy & Bryce Dessner & Eighth Blackbird, Iggy Pop, Visible Cloaks & Yoshio Ojima & Satsuki Shibano, Uboa
36. black midi - Schlagenheim

このUKの若き4ピースバンドに関してはアルバムに先んじて出た(A/B面ともにアルバムには未収録の)12インチシングルのレビューとして既に記事を書いている。
もちろん、その12インチに収められた2曲だけを以て彼らの全てを語り尽くす事は出来ず、「Western」で聴けるPink Floydの牧歌的な楽曲のようなフォーキーなスタイルに始まり唐突に激情ハードコアそしてファンクめいたリズム隊の絡みと移り変わるアクロバティックな作曲、続く「Of Schlagenheim」におけるエレクトロニクスやポストプロダクションの比重を高めたアレンジといった要素は、先の12インチのみでは伺い知れぬ部分だ。
しかし本作の一番の魅力といえばやはり先の12インチレビューでも触れたドラマーMorgan Simpsonを中心としたアンサンブルにあるだろう。極端な言い方をすれば、コード進行・メロディ・大まかなリズムパターン・ギターリフといった一般的に”作曲”の領域とされる部分の程度はどうあれこのメンバー4人が揃って演奏すれば何にせよ良く聴こえるような魅力がある。
そういう意味では、先に触れた「Western」のような派手に展開する楽曲も決して失敗では無くむしろ非常に魅力的なものの、現在の彼らのあり方を最も象徴していると言えるのは、ギターとベースはほぼほぼ表拍頭で杭を打ち付けるように特定のノートを鳴らすのみというミニマルなワンコード楽曲「bmbmbm」ではないか。
まだ年齢的にも若い事もあり、果たしてこのバンドがこの先どのような道を歩むのか、ミニマルに純化していくのか派手な展開が増えるのかはたまたエレクトロニクスの比重を高めるか、いやいや思いがけぬポップさを志向していくのか…非常に楽しみな存在だ。
35. Nivhek - After its own death / Walking in a spiral towards the house

Grouperとしての活動が最も知られるアブストラクトなアーティストLiz Harrisによる新名義。
ぶ厚いコーラスの多重録音やピアノ弾き語り等も披露しつつも、それをリヴァーブの海に沈めてしまう等して一筋縄では聴かせず、またフィールドレコーディングも多用する事で、通り一遍のSSWとも大きく異なるがアンビエントやドローン、ノイズといったカテゴリにも安易に収まる事を拒むそのサウンドは、名義を変えたからといってそれほど大きくは変わっていない。進行感の強いコード展開やメロディを用いずともメランコリックかつセンチメンタルな情感に訴える独特な魅力も健在。
デジタル・リリースでは4曲構成という形になっているがLPでは時間表記とともにパート毎に名前が付けられており(盤面自体にトラック分けの溝は無し)、2部構成の後半は前半部分でベルの音によって演奏されていたパートから装飾を取っ払ったいわばStripped-downヴァージョン(厳密にはLP表記のパート名で「Thirteen」とされているパートのみ前半ではギター、後半はベルで演奏されている)。このすっきりした音でLiz Harris節が聴けるのはなかなかに新鮮。現代音楽というかポスト・クラシカル的にも聴こえ、Brian Enoの名作『Music for Airport』を思い出したりそのイーノにも影響を与えたエストニアの現代音楽作家Arvo Partを思わせたりもする。この世の終わりに鳴っていて欲しい音。
34. VILOD - The Clouds Know

ミニマル・テクノの重鎮Ricardo Villalobosと、Sun Electric等で知られるMax Loderbauerによるユニット2作目。2人は単なる連名による共作もあるが、この名義で志向しているのはDJユースなフロア志向をほぼ捨てたジャズ寄りの表現。
クラブミュージック〜IDMを踏まえた電子ジャズ、と言うと、90〜00年代に飽きるほど聴いたよ、という向きも少なくないだろう。そしてジャズの新作がヒップホップとのクロスオーバー等により再び他ジャンルのリスナーからの耳目も集めるようになった中、かつてのそういった試みはそのルーツとしてリスペクトを集めるよりもむしろより時代の徒花としての扱いが強まったようにも思える。そんな時代に本作は、過去の電子ジャズを踏襲するでも反発するでもなければ文脈を引き継ぎつつ評価をひっくり返そうというものでもなく、かといって現在形のジャズとして音楽リスナーの多くに想像されるであろう形にも特に目配せはしていない。その他の10年代に音楽メディアを賑わせたトピックを表立って取り入れる事すらせず、ひたすら己の電子音で己の解釈のジャズを鳴らす。孤高を貫いた結果としてChristian ScottともRobert Glasperとも違った形でジャズの最新系に辿り着いている。
このユニットの大きなインスピレーション源であろう所謂電化マイルス期Miles Davisの名盤『Bitches Brew』のカオティックな中に香る土臭さがベトナム戦争の泥に塗れたゲリラ戦だとしたら、本作の冷徹さはドローン爆撃機だ。
33. Anderson .Paak - Ventura

もう既に多くの音楽リスナーに説明不要の存在だろう。ドラマーとしても手練なUSの男声R&Bシンガー。
シンガーとしての歌唱力とドラマーならではのグルーヴセンスは言わずもがなとして、Dr. Dreをエグゼクティブ・プロデューサーに迎えFocus…がミックスしたその音像は、生活のシーンに寄り添うある種機能美的なポップでありながらも音響派的な聴き方をしたくなるほどの構築美。Kadhja Bonetのような若手からBrandyにPharrell、Andre 3000、果ては御大Smokey Robinson(!)までを呼び、Miguel Atwood-Fergusonのストリングス・アレンジやKelsey Gonzalezの冴え渡るベースプレイも素晴らしい。それだけネームバリューある面々を集めても散漫になったりパーティ・アルバム的にしてしまうのでは無く自分の色できっちり染めて纏めている点も流石で、2019年におけるポップ・ミュージックの理想形とすら言えよう。
32. Fennesz - Agora

坂本龍一との幾度にも渡る共演が知られる叙情派グリッチ系エレクトロニカの第一人者たるギタリスト。
熱心なファン…と言わずとも、坂本を筆頭とした他アーティストとの共演作であったり今や金字塔的不動の名盤『Endless Summer』程度の知識でも、決定的に目新しい要素は無い。細かな部分のアップデートや時代へのアダプトを軽視すべきでは無いがしかし、概ね”いつものフェネス”と称して問題ないだろう。だがそれで何が悪い、という説得力に満ちた美しさがある。
Brian Wilsonを思い出さずにはいられない冒頭曲のタイトルに現れた内向性とアートワークが示す水のイメージが折り重なった所で描かれるノスタルジックなサウンドスケープに思わず涙。
31. Meitei 冥丁 - Komachi 小町

新興レーベルMetron Recordsからのリリースとなった日本の異端電子音楽家の2枚目。
ざっくりと音の傾向を言えば、Visible Cloaksから夕方の犬あたりのVaporwaveとニューエイジ・リバイバルの交差点にいるようなアーティストと、近年の坂本龍一やTim Heckerのような楽音と非楽音の境目を曖昧にする試みとの間、といった感じだろうか。
要するにアート的というか一般にポップと見做される形とは遠い音楽なのだが、幽霊画をジャケにしてそのまま怪談の語りを乗せていた前作に対し、ジャケを美人画にした本作は音響に対するフェティッシュが純化・前面化され、さらには「Ike」や「Nami」といった名前のトラックでそのまま水音をサンプリングしているなど、クドくならない程度にパッケージそのものがある種の解説となっているのはこういった電子音楽に耳慣れない向きにも親しみやすい点だろう。
さらに無音部の活用や深いサブベースといった要素も実に2019年的で、極度に抽象化したBillie Eilishのように解釈する事も…?
30. Haviah Mighty - 13th Floor

カナダの女声ラッパー、初フル・アルバム。Polaris Music Prize受賞。
カナダらしいと言うべきか、USのR&Bが脈々と積み上げてきた意匠とUK的なグライム寄りシャープネスや欧州耽美なウワモノが渾然一体となったバラエティ豊かな内容。さらにはチカーノっぽい哀愁のギターやソカ〜トロピカル・ハウスなビートと中南米にも目配せして見事に演ずる。これをひとりで手掛けているのだから舌を巻くが、プロデューサー/ソングライターとしてのみならずラッパーとしてのスキルも高く、言葉数を詰め込む力技もそれ一辺倒にならないフロウの幅広い引き出しも披露。
この先が恐ろしくなるほどの才能。特に中盤の流れがエモーショナルで良い。
29. Ana Roxanne - ~~~

Seihoも名を連ねるStones Throwのエクスペリメンタル部門的傘下レーベルLeaving Recordsよりリリースされたアジアン・アメリカン作家のデビュー作。
シンセを中心とした非常に穏やかなトーンで統一されており、音の傾向を指して言うならアンビエント、昨今のリバイバルを踏まえて言えばニューエイジ、そう形容できる事は間違いない。しかし、チルアウトと言うように音を自らの挙動に寄り添わせる事も、メディテーションと言うように自ら積極的に没入し同一化する事も拒む感触がある。聴き手を強制的にノスタルジアの海に引き込んでそのまま放置し途方に暮れさせるような作りで、要するに需要側の随意のままになる音楽では無い。通り一遍なアンビエントとして考えるより長回しを多用したアートフィルム的な感覚に近いだろう。
公言している影響源から読み解けば、西洋やインドの宗教音楽への造詣がある種聴き手の姿勢を正すような振る舞いに繋がっているか。一方でLPのジャケにまで表記しているような20世紀のR&Bからの影響、これがなかなか掴めない。「In A Small Valley」においては影響も何もバックグラウンドにAnita Bakerを小さな音でそのまま流してしまっているが、まさかこれだけを指すものではあるまい。といって単にコマーシャルなコピーであるとかミスリードだとかで切り捨てるべきでは無い、と何かが直感に訴えるが、それは実に巧妙に隠されている。それを暴こうと思わせる事こそが本作が人を惹き付ける最も重要なトリックか。
28. Clipping. - There Existed an Addiction To Blood

Spotify / Bandcamp / LP (このスプラッター・ヴァイナルこそ最も本作に合ったフィジカルだと考え、ここでしか見つからなかったのでDiscogsを貼ったが、英語での取引経験の無い者には推薦しない)
初期は00年代的グリッチ系エレクトロニカをヒップホップのテクスチャーに落とし込みラップを乗せていた。このユニットの目的は言わばヒップホップおよびラップ・ミュージックのサウンド的拡張と言えるが、本作はタイトル通りのホラーめいたコンセプトと多様なサウンドで聴き手を惹き付けつつ、そのスタイルに至る着想の根源を随所で仄めかす重要作になっている。
Clipping. - There Existed an Addiction To Blood: 鮮血とリスペクトの美学 (年間ベストアルバム28位)
27. The National - I Am Easy To FInd

Spotify / 2LP / Deluxe 3LP
最早USインディ・ロック界における重鎮とすら呼べる地位を築いたブルックリンのバンド、8作目。現代的エレクトロニクスとロックバンドとして対峙しつつ、北米大陸が連ねてきた美しきソングブックの血脈を更新した大傑作。
2019年ベストアルバム補完ミドルレビュー集2: Kel Assouf, Kim Gordon, The National, Bonnie ‘Prince’ Billy & Bryce Dessner & Eighth Blackbird, Iggy Pop, Visible Cloaks & Yoshio Ojima & Satsuki Shibano, Uboa
26. Flying Lotus - Flamagra

00年代から孤高に先端を走り続けてきたLAのビートメイカー。そのサウンドの進化はジャズの学習と内省を同時に深める事との並走関係で成り立ってきたが、本作はバラエティ豊かに少し肩の力を抜いている。
Flying Lotus - Flamagra: ジャズのエンゼル、集めてもらおう!おもちゃのビンヅメ地獄! (2019年間ベストアルバム26位)
いいなと思ったら応援しよう!

