
麻生田町大橋遺跡 土偶A 88:3河川立体交差点
新城市(しんしろし)の一鍬田(ひとくわだ)と八名井(やない)の間に存在する牟呂松原幹線水路と宇利川(うりがわ)の立体交差点上の森を迂回するために一旦、県道69号線に昇り、今水橋(いまみずばし)を渡り、再び牟呂松原幹線水路脇に降る通路の反対側に、参拝する予定でいた牟呂用水神社の社頭に通じる表参道がありました。
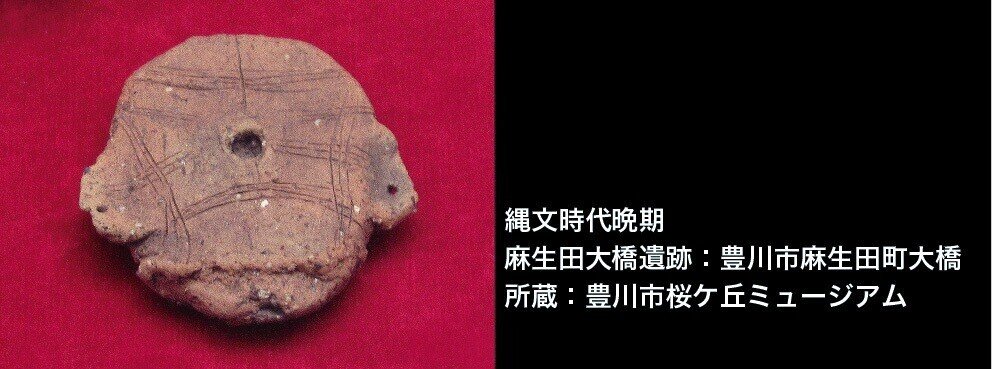


牟呂用水神社のアスファルト舗装された表参道は県道69号線の通っている北北西を向いているので、社頭にある石造八幡鳥居も北北西を向いている珍しい神社となったようです。

牟呂用水神社の社地の西側にも一般道が通っていますが、そちら側に社頭を設けると西向きになってしまうので、それを避けたのだと思われる。
愛車を表参道の入り口に突っ込んで、石鳥居をくぐると、参道は地図では大きなカーブを描いて西に向かっているのだが、実際には参道はほぼ右に直角に折れていた。
表参道が折れると10mあまり先に瓦葺入母屋造平入で白壁にガラス戸とガラス窓を持った拝殿が立ち上がっていた。

ここは丘陵の上に位置するので、社殿の基壇は高くなく、30cmほどしか無かった。
賽銭箱は脚の付いた旧い形式のものだ。
拝殿の軒下にはこの神社が牟呂用水神社であることを示す唯一のものである扁額が掛かっていた。

賽銭箱前で参拝したが、水に関係のある神が祀られているのは確実だとは思ってはいたが、この記事を書くために調べたところ、以下の神が祀られていることが初めて判った。
・水波能米神(ミズハノメ)
・天水配神
・国水配神
・杉下平四郎(牟呂用水事業に功績のあった人物)
等々
ミズハノメは『日本書紀』では「罔象女神(ミツハノメノカミ)」、『古事記』では「闇御津羽(クラミツハ)」と表記され、おそらく、映画『君の名は。』のヒロイン宮水三葉(みつは)はこの神名から取られたのだと思われる。
記紀では罔象女神も闇御津羽も、ともにイザナミの尿から化生したとされている。
その生誕神話からも、龍神ではなく、水神とされている。
たいていは配祀神(主祭神の脇に祀られる神)として祀られる神だが、ここ牟呂用水神社では牟呂用水を守るために祀られた神なので、珍しく主祭神として祀られている。
天水配神と国水配神は水波能米神を主祭神とするために配祀された水神なのだろう。
本殿の裏面には玉垣の中に大きな石祠が祀られていたが、この石祠に関する情報は見当たらなかった。

牟呂用水神社の社頭から県道69号線を北西に横切って、牟呂松原幹線水路に降りて行くと、こちら側にも樋門が設けられていたが、こちら側は一鍬田側の樋門と異なり、水門が上げられていた。

なんと、この樋門の250mあまり下流にも樋門らしきものが見えている。
ここは八名井(やない)で、右岸には2つの野球グランド、左岸には畑地が広がっている。
八名井の東西2基の樋門の中間点に橋が架かっており、その橋上から上流側の東樋門を撮影したのが下記写真。

二つの山が重なって立ち上がっているが、手前の山は低山で地図に名称は表記されていなかったが、一番奥の山は標高356mの風切山(かざきりやま)だ。
八名井の西側の樋門に至ると、

なんと、ここでも牟呂松原幹線水路と地図に名称表記の無い用水路Aが立体交差していた。
そして、牟呂松原幹線水路に設けられた樋門に見えていたのは用水路Aに設けられた樋門であることが判った。
同じ八名井西樋門脇の通路上から上流側の牟呂松原幹線水路〈上記MAP内表記(A)〉を撮影したのが下記写真だが、牟呂幹線水路と松原幹線水路との間の分割壁が水没している。

水位の上がる、水が豊富な場合には両幹線水路を分ける必要がないのだろう。
同じ八名井西樋門脇から、南東方向から流れてくる用水路Aを撮影したのが以下写真だ。

この用水路A脇に設けられた樋門は用水路A下をくぐっている牟呂松原幹線水路に水を落とすための樋門のようだ。
上記写真奥を左右に横切っている白いガードレールは県道69号線のものだ。
ところで、この2本の水路が交差している場所を詳細な航空写真で確認していたところ、実は用水路Bもこの交差点を通過していることに気づいた。

3本の水路は以下のように重なっていた。
上層:用水路A
中層:用水路B
下層:牟呂松原幹線水路
しかも用水路Bは3河川交差点の下流側では牟呂松原幹線水路に架かった水路橋として牟呂松原幹線水路の上を越えて流れているようだ。
◼️◼️◼️◼️
早くも牟呂松原幹線水路に関わる神社と2ヶ所目の水路の立体交差点。2河川が交差する水路は複数見てきたが、3河川がほぼ同一の場所で交差している例は初遭遇でした。はたして、3河川が完全に同じ場所で重なっている例は存在するのでしょうか。
