
麻生田町大橋遺跡 土偶A 185:高層ビル街の檜の橋
岡崎市菅生町(すごうちょう)の高岩弁財天から、乙川(おとがわ)沿いの北岸の道を西に向かい、290m以内に位置する明代橋北(みょうだいばしきた)交差点に至ると、その交差点の南側が明代橋に面していました。
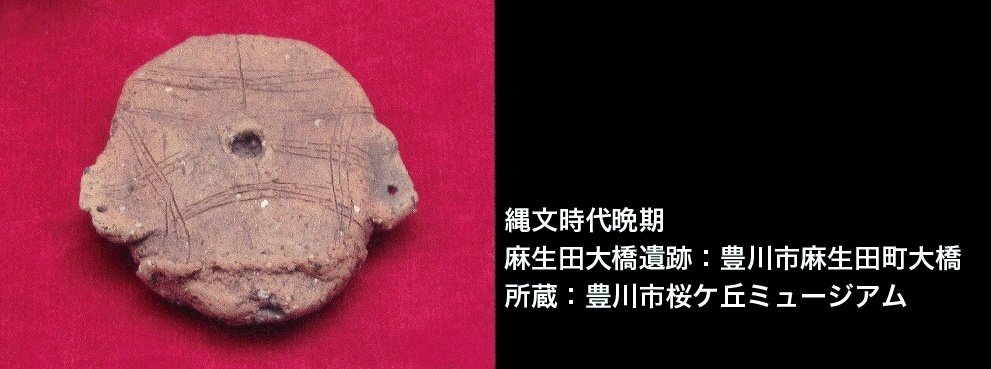


明代橋上から上流側を見下ろすと、乙川は左手にうねっており、明代橋すぐ上流の両岸には高水敷上に通路が通され、それが豊かな樹木に覆われていた。

乙川の水面を見ると、奇妙なことに気づいた。
すぐ上流の左岸(上記写真右手)の水面に2ヶ所、葦や雑草が茂っている場所が頭を水面上に出していたのだ。
最上流には、吹屋橋が架かっているのも見えているのだが、吹屋橋とここ明代橋の間の水面上に何かが頭を出しているのはそこだけだった。
カメラでUPにしてみると、片方の雑草の生えている場所は土砂が堆積して、そこに雑草が生えており、もう片方の葦が頭を出している部分には土砂は見えず、水中から葦が茎を伸ばしていた。

その2カ所の向こう岸には、ここまで見なかった、小型の石で組まれた石垣がL字型に組まれており、そのすぐ上流側は水面にまで下れる階段が設置され、石垣の上の通路はわざわざ山なりの坂道にしてあり、坂道の麓は水面近くまで降りられるようになっている。
地図をチェックすると、ここに「東岡崎舟着場」という表記があるのに気づいた。
調べてみると、ここでは夏季限定で乙川観光船による「岡崎城下舟あそび」が行われていることが判った。
観光船といっても、10人くらいが座って乗れる木造船で、乙川の涼と夕焼け、3つの橋と岡崎城のライトアップを楽しむことができる納涼船だ。
階段状の部分が舟乗場所になっているようで、岸に少し引っ込んだ石垣で護岸された場所が舟の係留場らしい。
それは分かったものの、水面上に土や葦が頭を出している理由は不明だった。
一方、明代橋上から上流側を見下ろすと、すぐ目の前の下流に架かっている桜城橋とその向こう側にビル群が見えていた。

康生通南(こうせいどおりみなみ)の高層ビル群だが、その向こう側に岡崎城跡が存在する。
左岸(上記写真左手)の高水敷に通された通路はかなり広くなっている。
この部分で乙川の川幅は120m近くあり、水面幅は70mあまりとなっている。
右岸(上記写真右手)をみると、水際の階段の所々に、以下のように円形に土を露出させた花壇のようなものが設けられていたが、特に花は植えていないようで、雑草で覆われていた。

明代橋から乙川沿いに180mあまり下流に向かうと、表面は木造にしか見えない桜城橋に至った。
プレーンな素木の親柱には「桜城橋(さくらのしろばし)」と切り抜いた素木がレリーフ状に取り付けられている。

この部分を観ただけで、素木とスチールとコンクリートが巧みに組み合わせられて築造された木造橋であることが解る。
「桜城」という名称の城があったわけではなく、ここから西北西350mあまりに存在し、桜の名所になっている岡崎城を「桜城」として橋名にしたものだ。
桜城橋は「橋上公園」というコンセプトで架橋された橋で、基本的に歩行者しか立ち入れない橋になっており、橋上には屋根付きの休憩所も設置され、この後、飲食店も設けられるようだ。
コロナ禍で、飲食店設置は延期されていたのだろう。
桜城橋上から上流側を望むと、目の前に赤茶色の欄干を持つ明代橋が見えている。

両岸はビル街に入っているが、乙川の沿岸は豊富な樹木に包まれている。
左岸(上記写真右手)の水面縁の階段には所々、自然石を組んだ場所があり、植物が繁殖している。
桜城橋上から下流側を望むと、左岸(下記写真左手)の高水敷は広くなり、緑地が設けられていた。

乙川は左にカーブしており、その先に架かっている殿橋が見える。
その橋名も徳川家康に関連しているのだろう。
高層ビルは右岸に集中しており、その下流側に見える森は菅生神社(すがうじんじゃ)の杜のようだ。
桜城橋は床も欄干もヒノキの素木が使用されており、橋脚も角丸で白っぽい石垣を組んだ体裁になっていて美しい。

桜城橋から乙川の右岸(北岸)沿いの道を下流に辿って410m以内で殿橋(とのばし)の北側に面する殿橋北交差点に到達した。
この橋は桜城橋とは異なり、鉄筋造で、親柱もブロンズの照明具を頭に乗せたゴシック建築風の意匠が施されたものだった。

殿橋上から下流側を望むと、左岸(下記写真左手)の高水敷はさらに広がり、左岸堤防の土手はスタンド状にコンクリートで護岸されていた。

右岸には岡崎城の天守閣のシルエットが見えてきた。
◼️◼️◼️◼️
この部分の乙川の左岸は明大寺本町(みょうだいじほんまち)になっています。町名は、かつてここに存在した妙大寺の寺号に由来するものとされています。ここには1988年以降、地名として「竜美(たつみ)」という名称が使用されてきており、公立の小・中学校の校名に組み込まれています。
