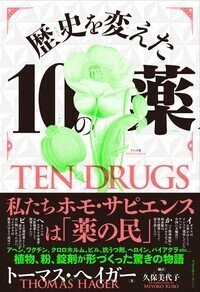ワクチン開発についての歴史 『歴史を変えた10の薬』より
こんにちは。メディア事業部のIです。
今回は、アメリカ人のメディカルライター・トーマス・ヘイガー著『TEN DRUGS』の訳書で、アヘン、クロラール、ヘロイン、バイアグラなど怪しげな薬品やワクチンやペニシリンなど医療を大きく進歩させた薬品など、10の薬の歴史的な背景や意義について述べられている『歴史を変えた10の薬』を紹介します。
『歴史を変えた10の薬』
昨今話題となっているワクチン開発についての歴史を振り返ってみます。そこにはとある女性の活躍がありました。
レディ・メアリーの悲しみ
1600年代後半、英国貴族の令嬢として生まれたメアリー・ピアポント(1689-1762)は裕福な生活を送っていました。女性作家を目指し、両親の決めた結婚を反故にして、自分で選んだ相手と駆け落ちをするというスキャンダラスな人生を送りましたが、聡明な人物だったそうです。
しかし、順風満帆にみられた生活は一転、愛する20歳の弟を天然痘で失い、2年後本人も天然痘を罹患しました。天然痘は疱瘡〔ほうそう〕とも呼ばれ、致死率が高い病気でした。日本においても恐れられており、失明やあばた跡が残ります。
「人痘接種」の元祖「植え付け」
メアリーの夫・エドワードがオスマン帝国の英国大使に任命され、メアリーは息子とともにコンスタンティノープル(現・イスタンブール)に行きました。
コンスタンティノープルでは、メアリーは偏見を持たず、ムスリム世界やオスマントルコ人のことを学ぼうとしました。そうした文化交流の中でメアリーは気づきます。ムスリムの女性たちの傷のない美しい肌。天然痘の傷跡がないのです。
現在の常識からいうと不衛生かもしれないのですが、コンスタンティノープルでは「植え付け」という人痘接種に当たる行為をしていました。肌に傷を作り、そこに軽症の天然痘患者のかさぶたと膿を混ぜたもの(!)を針の先につけて付着させるものです。
当時のヨーロッパ人はもちろん野蛮な行為だと受け容れませんでしたが、メアリーは息子に植え付けを施し、無事に免疫を得ることができたのです。
臨床試験の末、国王の許可、反人痘接種運動
1721年春、ロンドンで天然痘が流行します。当時の英国の医師たちは古代の理論に基づいて現代医学では全く意味のない治療を行っていました。しかし、それは医師たちにとって大金を稼ぐ手段となっており、イスラム教徒への差別的感情も相まって「植え付け」は受け入れられませんでした。
メアリーは英国に戻ってからも娘に人痘接種をさせる現場を見学させるなど、社交界でこの方法を絶大アピールします。その経過を目にしたり耳にしたりした多くの貴族たちは人痘接種を依頼しはじめ、ついに英国皇太子妃キャロラインは子どもにこの接種を行おうとします。ですが、国王ジョージ1世はそれを拒否します。
そこで、囚人や孤児を使った臨床試験が行われます。これは現在の人権意識から考えると許される行為ではありませんが、史上初の臨床試験だといわれています。
この結果により、1722年春、国王は娘への人痘接種を許可し、多くの医師が人痘接種をはじめ、英国貴族たちや一般の人々も人痘接種を受けられるようになります。
しかし、反対運動も起きました。差別的な主張、宗教的な主張、政治的な主張などがありましたが、人痘接種の死亡率は自然伝播の死亡率の4分の1という報告(1729年)があり、ましたが、なお抵抗のある医師もいました。そこには様々な試行錯誤がありました。
人痘から牛痘へ エドワード・ジェンナー
人痘接種はアメリカやヨーロッパ中に広まります。これはメアリーの勝利といってよいのでしょうが、彼女のことはあまり知られていません。
皆さんがご存じのように「ワクチンの父」といわれるエドワード・ジェンナー(1749-1823)がより安全な牛由来の天然痘、牛痘接種を行いました。ワクチンのvaccaはラテン語で「ウシ」という意味があります。世界的な名声を得ることになるのです。
現在のワクチン接種につながる歴史をみていくと、メアリー・ピアポントという女性の活躍がありました。それが、ムスリム世界から伝わったものとは私も知りませんでした。
どのように人類が病に対峙してきたのか、薬品を開発してきたのかの歴史をこの本から学ぶことができます。新しい薬品の開発には、医学や薬学だけではなく、政治や宗教ともかかわっているのがとてもよく分かります。それは現代も変わらないですよね。
コロナのワクチン接種についても色々考えさせられるところがありました。
☆すばる舎公式Twitterもぜひフォローお願いします!☆