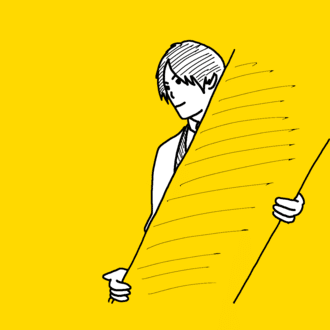30年目の音楽の透明感と手触り
今週発売されたGLAYの17枚目のアルバム「Back To The Pops」
僕がファンであるという贔屓目を除いても、良いです。
良きポイントはたくさんあるのですが、今回とにかくアンサンブルが圧倒的。
ピアニスト清塚信也さんが参加した楽曲もあります(M12)すごいタイトル。
調律のお客さんで数年前からGLAYにハマったという音楽の先生がいて、「ふだんポップスは全く聴かないけど、GLAYのアンサンブルは本当に心地よいんです」と言っていました。聴き慣れている自分にとっては「言われてみればそうか」くらいだったのですが、今回それをものすごく実感しました。
ドラムとの絡みでさらに魅力的になる歌、かっこいいギターのフレーズの裏でそれをサポートするもう1本のギター。気持ち良いシンセの音はベースラインの賜物だったり。
GLAYの魅力って音楽的な部分は当然として、メンバーの人柄や関係性も含めて好きというファンも多いです。でもこのアルバムは、仮にそれらの要素を全部取っ払ったっとしても純粋に音楽として良いと、自信を持って言えます。
GLAYの楽曲に普段は「色」を感じるんですよね。でも今回の楽曲たちは透明に感じます。だからこそ初の試みの「くじ引きで曲順を決める」が成り立ってるのかなと。そして透明だけど、それぞれちゃんと手触りがあります。
長く続いているミュージシャンの楽曲にどうしても付き物の、“文脈や関係性を知らないと100%楽しめない”が無くて、GLAYを初めて聞く人には確実にこのアルバムをお勧めします。
ちょっと突っ込んだ話、2016年くらいからGLAYは、明言はしないまでも明らかに「すっぴん」であることを目指していました。
それは単純にメイクや衣装の見た目にも現れていましたし、それまでだったらキーボードやストリングスが入るだろうところに敢えて使わない構成や、シンプルなアレンジやフレーズ、少し粗くも感じるボーカルテイクの選び方など、音楽的にもその方針は強く感じていました。
僕はよくないファンなので正直その方針転換にあまりピンと来なくて、数年離れていました。実際にチグハグな部分はあったと思います。でも2021年くらいからだんだんと「最近のGLAY、めちゃくちゃ魅力的なのでは?」と。
それ以前にもリーダーのTAKUROさんがなにかのインタビューで「GLAYである自分とプライベートの自分の境がどんどん無くなってきている」と話していました。今回それが行き着いた先、生き様と完全にひとつになると音楽はこういう透明性を帯びるのかと。そしてバンドであることのポジティブな摩擦で、その透明感に手触りが加わる。
このアルバムは一聴していわゆる、ザ・GLAYっぽさ全開かと言うとそうではない。
でも細部はどこを切り取っても確かにGLAY
確実に唯一無二。GLAYにしか奏でられない音楽です。
いいなと思ったら応援しよう!