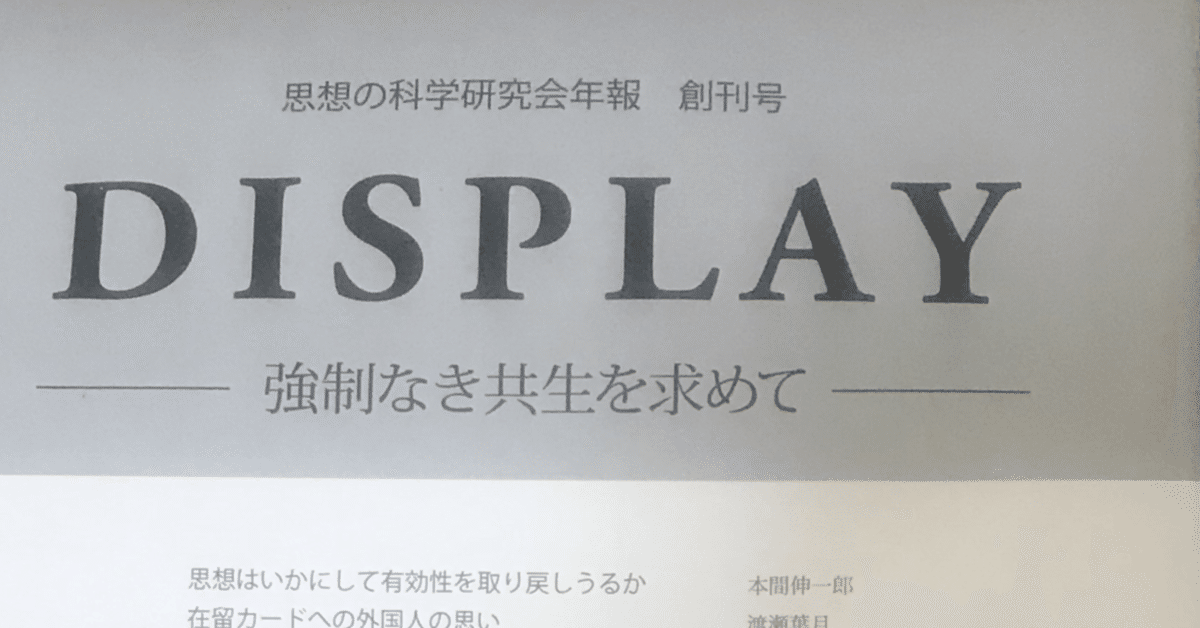
紹介『思想の科学研究会 年報』 ーーー創刊号 DISPLAYーー
思想の科学研究会では、研究会の活動を活性化させ、外側の人にも伝えていくためにも、最近、『思想の科学研究会 年報』が創刊されました。
各号の紹介をしていきたいと考えています。
創刊号について紹介します。
創刊号の名称、DISPLAYについて
『思想の科学研究会 年報』(以下、「年報」とします)は、各号毎に、名称をつけています。
創刊号の名称は「DISPLAY」と名付けられました。
「DISPLAY」というの言葉から、「展示する」という意味を思い浮かべるでしょうが、たたまれたものや、シワを伸ばすという意味合いがあります。
そこから、旗や帆を広げる、もしくは海図や地図、図面を広げるとい った意味もあるのです。研究会の新しい試みへの船出も踏まえて、創刊号に「DISPLAY」と命名しました
目次と構成
年報の創刊号は大きく五つのパートから構成されています。
まずは目次を提示します。
創刊号『DISPLAY』目次
寄稿
思想はいかにして有効性を取り戻しうるか 本間伸一郎
在留カードへの外国人の思い 渡瀬葉月
「罪なき者、石を投げよ」の濫用に思う 中島義実
特集【研究会の活動を振り返る】
70年座談会
司会:後藤嘉宏 基調報告:本間伸一郎
参加者:大河原昌夫、塩沢由典、那波泰輔、松井勇起、古田佳之、
安田常雄、山本英政、横尾夏織、吉田桃子
〔再掲論文〕学問の方法とその基本的姿勢
――学問の方法とその基本的姿勢民間アカデミズムの意味を求めて
後藤宏行
連載
ハワイエッセイ 山本英政
介護保険20年と介護人材 田村一
なぜ私は中井正一のメディウム、ミッテル、
二つの概念にこだわり続けているのか 後藤嘉宏
コラム
博多のロックバンド、
そしてフル・ノイズというバンド 橘正博
美の街道、峠の茶店で
―――阿佐ヶ谷『対山館』(東京都杉並区)襾漫敏彦
若法塾成り立ち 渡瀬葉月
思想の科学研究会の活動紹介
構成は、寄稿・特集・連載・コラム・研究会の活動紹介の五つのパートからなります。
寄稿は、会員等の自由な投稿を基本にしています。
連載は、シリーズ化する予定のもので、コラムは、短いエッセイ風のものと考えていました。特に、音楽、美術、教育、文芸関連のものをまとめていこうと企画していました。 実際には、二号以降では、連載とコラムがひとまとまりになっていきます。
特集ですが、公開シンポジウムや地域集会等、研究会の活動を反映させるものや、研究会の歴史を検証するような内容をまとめていこうと考えています。創刊号では、研究会の70年の節目に合わせた座談会を開催しました。
研究会の活動紹介は、シンポジウムの報告、サークルの紹介等、資料的な意味合いが強いかもしれません。
それぞれの構成や個別の原稿に関しては、改めて紹介させていただきます。
年報は、以下のサイトから閲覧可能です。
最近、研究会のサイトは、引っ越しをしました。
投稿に関して
基本的には、一般の投稿も受け入れたいと考えています。ただ、仲間内で制作している同人誌のような性格が強いので、そこを理解してもらった上で投稿を受け入れるつもりです。
まずは、投稿の案内に沿って研究会の方にご一報ください。
創刊の辞
最後に創刊の辞を掲載します。
創刊の辞
雑誌『思想の科学』が休刊となって早や二十三年が経とうとしている。「思想の科学研究会の会員です」と旧知の人に近況を報告すると、たいてい「思想の科学研究会ってあるんですか、まだ?……」と驚いた顔で問い返される。そのことは研究会の顔が雑誌『思想の科学』であったことを紛れもなく証している。実際、雑誌『思想の科学』と思想の科学研究会は二人三脚で歩いてきた。
しかしながら雑誌『思想の科学』が、その五十年の歴史のなかで思想の科学研究会の同人誌や機関誌であった時期はほとんどない。そのなかで、思想的な分野の商業誌として、論壇で一定の地位と名声をかち得てきた。雑誌『思想の科学』と思想の科学研究会は、協力関係とともによい意味での緊張あるいは競合関係を維持し続けてきた。いいかえると雑誌『思想の科学』は思想の科学研究会の標榜する多元主義を具体化し、売り上げ増に伴う運動の拡がりをもたせるために、外部のライターに依存しがちであった。
これに対して今われわれが公にしようとしている『思想の科学研究会年報』は、視点の多様性と運動の拡がりが大切であるという雑誌『思想の科学』の方向性はしっかりと受け継ぎつつ、会員主体の雑誌をめざす。
幸い電子出版の普及し始める時代を迎え、少部数しか需要のないアイテムであっても成立する状況になりつつある。そこでわたしたちは、雑誌『思想の科学』とは別の、新たな会の顔として『思想の科学研究会年報』を刊行する。
思想の科学研究会員に執筆や企画立案を促すことを、会員主体の雑誌として第一にしつつも、それと同時に、研究会の理念と目的に賛同する人々には門戸をどんどんと広げていきたい。多元主義、民間アカデミズム、大衆文化研究、等々の言葉で表される「思想の科学研究会の理念」については、確かにわれわれの研究会が先鞭をつけたことは、われわれも誇ってよい。鶴見俊輔氏をはじめとするわれわれの研究会の先導者たちの運動の成果もあって、いまやそれらの理念は、少なくとも言葉としては多くの人びとが共有し、またわれわれと似た活動をする団体も少なくないのが現状である。しかし言葉としての理念にまとめきれない何か、また、これから気づくべき何かが、まだあるはずである。それらを自覚し、次世代に繋いでいき、彼らにそこに生命を吹き込んでもらう責務を、われわれは負っている。そのような社会的使命を果たしていくのに、このささやかな雑誌の創刊が僅かながらでも貢献できたら、それに勝る喜びはない。
後藤嘉宏
