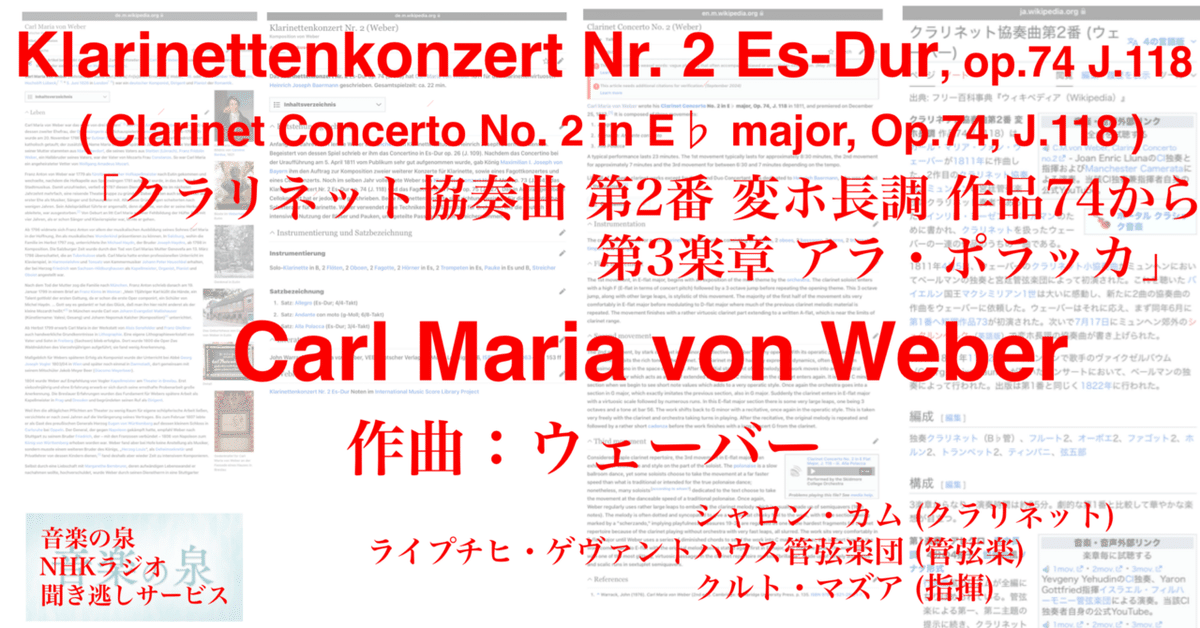
ラジオ生活:音楽の泉 ウェーバー「クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74から 第3楽章 アラ・ポラッカ」
聞き逃しサービス 2025/01/18 放送
〜
音楽の泉
〜
〜
「クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74から 第3楽章 アラ・ポラッカ」
( Clarinet Concerto No. 2 in E♭ major, Op. 74, J. 118 )
[ Klarinettenkonzert Nr. 2 Es-Dur, op. 74 J. 118 ]
作曲: ウェーバー ( Carl Maria von Weber )
シャロン・カム(クラリネット)
ライプチヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(管弦楽)
クルト・マズア(指揮)
(6分58秒)
〜
開始より33分52秒頃 (終了より16分08秒前頃)
〜
〜
配信終了 2025/01/25 05:50
(すでに配信終了してます)
番組情報
Google検索 URL>
https://www.google.co.jp/search?tbm=vid&hl=ja&source=hp&biw=&bih=&q=Carl_Maria_von_Weber+Clarinet_Concerto_No_2_Op_74+3rd_Movement
Bing検索 URL> https://www.bing.com/videos/search?q=Carl_Maria_von_Weber+Clarinet_Concerto_No_2_Op_74+3rd_Movement
Bing検索 URL> https://www.bing.com/videos/search?q=Carl_Maria_von_Weber+Klarinettenkonzert_Nr_2_op_74
〜
〜〜
〜〜〜
☆★☆ ウェーバー「クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74」について【目次】☆★☆
〜〜〜
〜〜
1. ウェーバー「クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74」について
1.1 Wikipedia JA(日本版)の抜粋
1.2 Wikipedia EN(英語版)の抜粋、および、その日本語翻訳
1.3 Wikipedia DE(ドイツ版)の抜粋、および、その日本語翻訳
〜〜
〜
〜〜
2. 作曲者:ウェーバー について
2.1 Wikipedia DE(ドイツ版)の抜粋、および、その日本語翻訳
2.2 ウェーバーの作品リストへのリンク・Wikipedia EN(英語版)
〜〜
〜
<<< 以下、参照しているWikipediaなどへのリンクはそれぞれの先頭あたりで紹介してます。>>>
〜
〜〜
1. ウェーバー「クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74」について
1.1 Wikipedia JA(日本版)の抜粋
〜〜
〜
クラリネット協奏曲第2番 (ウェーバー)
Wikipedia JA(日本版) URL> https://ja.wikipedia.org/wiki/クラリネット協奏曲第2番_(ウェーバー)
〜
クラリネット協奏曲第2番 変ホ長調 作品74(J.118)は、カール・マリア・フォン・ウェーバーが1811年に作曲した、2作目のクラリネット協奏曲。ミュンヘンの宮廷管弦楽団のクラリネット奏者であったハインリヒ・ヨーゼフ・ベールマンのために書かれ、クラリネットを扱ったウェーバーの一連の作品のうちの一曲である。
1811年4月5日、ウェーバーのクラリネット小協奏曲がミュンヘンにおいてベールマンの独奏と宮廷管弦楽団によって初演された。これを聴いたバイエルン国王マクシミリアン1世は大いに感動し、新たに2曲の協奏曲の作曲をウェーバーに依頼した。ウェーバーはそれに応え、まず同年6月に第1番ヘ短調作品73が初演された。次いで7月17日にミュンヘン郊外のシュタルンベルク(英語版)で変ホ長調の協奏曲が書き上げられた。
初演は1811年11月25日、ミュンヘンで歌手のヴァイクゼルバウム(Georg Weixelbaum)が開いたコンサートにおいて、ベールマンの独奏によって行われた。出版は第1番と同じく1822年に行われた。
…
【構成】
3楽章からなり、演奏時間は約25分。劇的な第1番と比較して華やかな楽想が目立つ。
…
《》第1楽章 アレグロ 変ホ長調 4分の4拍子 協奏曲風ソナタ形式
行進曲風のリズムが全編にちりばめられている。管弦楽による第一、第二主題の提示に続き、クラリネットが3オクターヴの跳躍によって印象的な登場をする。おおむねソナタ形式の型通りに進み、再現部の第一主題は管弦楽だけで扱われる。カデンツァを挿入する箇所は用意されていないが、その代わり終盤にクラリネットが無伴奏で急速なアルペジオを奏する場面がある。
…
《》第2楽章 アンダンテ・コン・モート ト短調 6分の8拍子 三部形式
憂いに満ちたロマンス。中間部ではクラリネットに技巧的な動きが現れ、「レチタティーヴォ」("Recit.")と記された楽節で劇的な振舞いを見せる。
…
《》第3楽章 アラ・ポラッカ 変ホ長調 4分の3拍子 ロンド形式
ポロネーズ風の軽快なフィナーレ。基本的には小ロンド形式をとり、多彩な楽想が提示される。コーダには当時のクラリネットの性能の限界に挑むようなパッセージが散りばめられる。
…
〜[上記wikipediaより抜粋。]
〜
〜〜
1. ウェーバー「クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74」について
1.2 Wikipedia EN(英語版)の抜粋、および、その日本語翻訳
〜〜
〜
Clarinet Concerto No. 2 (Weber)
Wikipedia EN(英語版) URL> https://en.m.wikipedia.org/wiki/Clarinet_Concerto_No._2_(Weber)
〜
Carl Maria von Weber wrote his Clarinet Concerto No. 2 in E♭ major, Op. 74, J. 118 in 1811, and premiered on December 25, 1813. It is composed of three movements:
1. Allegro
2. Romanze: Andante con moto
3. Alla Polacca
A typical performance lasts 23 minutes. The 1st movement typically lasts for approximately 8:30 minutes, the 2nd movement for approximately 7 minutes and the 3rd movement for between 6:30 and 7 minutes depending on the tempo.
Like all of Weber's clarinet works except for the Grand Duo Concertant, it is dedicated to Heinrich Baermann, who was soloist at the premiere.
…
【Instrumentation】
The concerto is scored for a solo clarinet and an orchestra consisting of 2 flutes, 2 oboes, 2 bassoons, 2 horns, 2 trumpets, timpani and strings.
…
【First movement】
The 1st movement, in E-flat major, begins with an exposition of the main theme by the orchestra. The clarinet soloist enters with a high F (E-flat in terms of concert pitch) followed by a 3 octave jump before repeating the opening theme. This 3 octave jump, along with other large leaps, is stylistic of this movement. The majority of the first half of the movement sits very comfortably in E-flat major before modulating to D-flat major where much of the previous clarinet melodic material is repeated. The movement finishes with a rather virtuosic clarinet part extending to a written A-flat, which is near the limits of clarinet range.
…
【Second movement】
The 2nd movement, by stark contrast in G minor, is reflective of Weber's many operas. With its operatic phrasing, this movement exhibits the rich tone of the clarinet. The clarinet melody has very expressive dynamics, often going from fortissimo to piano in the space of one bar. After the initial statement of the melody, the work moves into an orchestral section in G major which acts as a sort of extended dominant to C minor when the clarinet enters again. It is in the C minor section when we begin to see short note values which adds to a very operatic style. Once again the orchestra goes into a section in G major, which exactly imitates the previous section, also in G major. Suddenly the clarinet enters in E-flat major with a virtuosic scale followed by numerous runs. In this E-flat major section there is some very large leaps, one being 3 octaves and a tone at bar 56. The work shifts back to G minor with a recitative, once again in the operatic style. This is taken very freely with the clarinet and orchestra taking turns in playing. After the recitative, the original melody is repeated and followed by a rather short cadenza before the work finishes with a long concert G from the clarinet.
…
【Third movement】
Clarinet Concerto No. 2 in E Flat Major, J. 118 - iii. Alla Polacca
Duration: 6 minutes and 56 seconds.6:56
Performed by the Skidmore College Orchestra
<<< Music player omit. Refer Wikipedia. >>>
Considered staple clarinet repertoire, the 3rd movement in E-flat major is an exhibition of technique and style on the part of the soloist. The polonaise is a slow ballroom dance, yet some soloists choose to take the movement at a far faster speed than what is traditional or intended for the true polonaise dance; nonetheless, many soloists[according to whom?] dedicated to the text choose to take the movement at the danceable speed of a traditional polonaise. Once again, Weber regularly uses rather large leaps to embellish the clarinet melody which is usually made up of semiquavers (16th notes). The melody is often dotted and syncopated to give a somewhat cheeky feel to the work, with these sections being marked by a "scherzando," implying playfulness. Measures 19-20 are regarded as one of the hardest fragments for clarinet repertoire because of the clarinet playing without orchestra with very fast leaps, all slurred. The work sits very comfortably in E-flat major until Weber uses a series of diminished chords to send the work into C major. However, this is short lived as the work comes back to E-flat with the original melody being stated again first in E major, and then the tonic. The work finishes with one of the most glittery, virtuosic passages in the clarinet repertoire marked "brillante", made up of largely arpeggios and scalic runs in sextuplet semiquavers.
…
〜[Excerpt from above Wikipedia]
〜[上記Wikipediaの日本語翻訳は次の通り。翻訳にはアプリ「DeepL」を使用。]
〜
カール・マリア・フォン・ウェーバーが1811年に書いたクラリネット協奏曲第2番変ホ長調作品74、J.118は、1813年12月25日に初演された。 つの楽章からなる:
1. アレグロ
2. ロマンツェ:アンダンテ・コン・モート
3. アッラ・ポラッカ
典型的な演奏時間は23分。 第1楽章は通常約8分30秒、第2楽章は約7分、第3楽章はテンポによって6分30秒から7分。
グラン・デュオ・コンチェルタントを除くウェーバーのクラリネット作品と同様、初演時のソリストであったハインリヒ・バールマンに捧げられている。
…
【】楽器編成
クラリネット独奏と、フルート2、オーボエ2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、ティンパニ、弦楽器からなる管弦楽のための協奏曲。
…
【】第1楽章
変ホ長調の第1楽章は、オーケストラによる主主題の提示で始まる。 クラリネットのソリストが高音F(コンサート・ピッチで言えば♭E)で登場し、その後3オクターブ跳躍して冒頭の主題を繰り返す。 この3オクターブの跳躍は、他の大きな跳躍とともに、この楽章の様式的なものである。 楽章の前半の大部分は変ホ長調でゆったりと進み、その後変ニ長調に転調して、前のクラリネットの旋律的素材の多くが繰り返される。 この楽章は、クラリネットの音域の限界に近い変イ長調に及ぶ、かなりヴィルトゥオーゾ的なクラリネット・パートで終わる。
…
【】第2楽章
第2楽章は対照的なト短調で、ウェーバーの数多くのオペラを反映している。 オペラのようなフレージングで、クラリネットの豊かな音色が発揮される。 クラリネットの旋律は非常に表現力豊かなダイナミクスを持ち、しばしば1小節の間にフォルティッシモからピアノへと移行する。 メロディーの最初の声明が終わると、作品はト長調のオーケストラ・セクションに移り、クラリネットが再び登場するハ短調への拡張ドミナントのような役割を果たす。 ハ短調の部分では、短い音価の音符が現れ始め、非常にオペラティックなスタイルになる。 オーケストラは再びト長調のセクションに入るが、これは前のセクション(同じくト長調)を正確に模倣している。 突然、クラリネットが変ホ長調に入り、ヴィルトゥオーゾ的な音階に続いて何度も走る。 この変ホ長調の部分では、非常に大きな跳躍がいくつかあり、そのひとつは56小節目で3オクターブと1トーンも跳躍している。 作品は再びオペラ風のレチタティーヴォでト短調に戻る。 クラリネットとオーケストラが交互に演奏し、非常に自由に演奏される。 レチタティーヴォの後、オリジナルの旋律が繰り返され、やや短いカデンツァが続いた後、作品はクラリネットの長いコンサートGで終わる。
…
【】第3楽章
クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 J. 118 - iii. アッラ・ポラッカ
演奏時間: 6分56秒6:56
演奏:スキッドモア大学管弦楽団
<<<音楽プレーヤー省略。 ウィキペディア参照。 >>>
クラリネットの定番レパートリーとされる変ホ長調の第3楽章は、ソリストのテクニックとスタイルの見せ所である。 ポロネーズはゆっくりとした社交ダンスだが、伝統的なポロネーズよりもはるかに速い速度で演奏するソリストもいる。 繰り返しになるが、ウェーバーは、通常半音階(16分音符)で構成されるクラリネットの旋律を装飾するために、かなり大きな跳躍を定期的に用いている。 旋律はしばしば付点され、シンコペーションで表現される。 第19-20小節は、クラリネットがオーケストラなしで非常に速い跳躍をスラスラと演奏するため、クラリネットのレパートリーとしては最も難しい断片のひとつとされている。 ウェーバーが一連の減和音を用いて作品をハ長調に移行させるまでは、作品は変ホ長調でとても心地よく収まっている。 しかしそれも束の間、作品は再び変ホ長調に戻り、元の旋律はまずホ長調で、次にトニックで述べられる。 作品の最後は、クラリネットのレパートリーの中でも最もきらびやかでヴィルトゥオーゾ的なパッセージで締めくくられる。
…
〜
〜
〜〜
1. ウェーバー「クラリネット協奏曲 第2番 変ホ長調 作品74」について
1.3 Wikipedia DE(ドイツ版)の抜粋、および、その日本語翻訳
〜〜
〜
Klarinettenkonzert Nr. 2 (Weber)
Wikipedia DE(ドイツ版) URL> https://de.m.wikipedia.org/wiki/Klarinettenkonzert_Nr._2_(Weber)
〜
Das Klarinettenkonzert Nr. 2 Es-Dur op. 74 (J. 118) hat Carl Maria von Weber 1811 für den Klarinettenvirtuosen Heinrich Joseph Baermann geschrieben. Gesamtspielzeit: ca. 22 min.
…
【Entstehungsgeschichte】
Anfang des Jahres 1811 lernte Weber in München den Klarinettenvituosen Heinrich Joseph Baermann kennen. Begeistert von dessen Spiel schrieb er ihm das Concertino in Es-Dur op. 26 (J. 109). Nachdem das Concertino bei der Uraufführung am 5. April 1811 vom Publikum sehr gut aufgenommen wurde, gab König Maximilian I. Joseph von Bayern ihm den Auftrag zur Komposition zweier weiterer Konzerte für Klarinette, sowie eines Fagottkonzertes und eines Cellokonzerts. Noch im selben Jahr vollendete Weber sein Klarinettenkonzert Nr. 1 f-Moll op. 73 (J. 114), das Klarinettenkonzert Nr. 2 Es-Dur op. 74 (J. 118) und das Fagottkonzert F-Dur op. 75 (J. 127). Das in Auftrag gegebene Cellokonzert hat er jedoch nie geschrieben. Beide Klarinettenkonzerte sind richtungsweisend für die romantische Sololiteratur für Klarinette. Weber verwendet neue Techniken beim Schreiben für Orchester, wie die deutlich intensivere Nutzung der Bläser und Pauken, und geteilte Passagen in den Streicherstimmen.
…
【Instrumentierung und Satzbezeichnung】
《》Instrumentierung
Solo-Klarinette in B, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Hörner in Es, 2 Trompeten in Es, Pauke in Es und B, Streicher
…
《》Satzbezeichnung
1. Satz: Allegro (Es-Dur; 4/4-Takt)
2. Satz: Andante con moto (g-Moll; 6/8-Takt)
3. Satz: Alla Polacca (Es-Dur; 3/4-Takt)
…
〜[Excerpt from above Wikipedia]
〜[上記Wikipediaの日本語翻訳は次の通り。翻訳にはアプリ「DeepL」を使用。]
〜
クラリネット協奏曲第2番 変ホ長調 作品74(J.118)は、カール・マリア・フォン・ウェーバーがクラリネットの名手ハインリヒ・ヨーゼフ・ベアマンのために1811年に作曲した。 演奏時間:約22分。
…
【生い立ち】
1811年の初め、ウェーバーはミュンヘンでクラリネットの名手ハインリヒ・ヨーゼフ・ベアマンに出会った。 彼の演奏に触発され、コンチェルティーノ変ホ長調作品26(J.109)を作曲した。 1811年4月5日に初演されたコンチェルティーノが聴衆に大好評を博した後、バイエルン王マクシミリアン1世から、さらに2曲のクラリネット協奏曲、ファゴット協奏曲、チェロ協奏曲の作曲を依頼された。 同年、ウェーバーはクラリネット協奏曲第1番ヘ短調op.73(J.114)、クラリネット協奏曲第2番変ホ長調op.74(J.118)、ファゴット協奏曲ヘ長調op.75(J.127)を完成させた。 しかし、委嘱されたチェロ協奏曲を作曲することはなかった。 どちらのクラリネット協奏曲も、ロマン派のクラリネット独奏曲の流れを作った。 ウェーバーは、管楽器やティンパニの使用を大幅に増やしたり、弦楽器パートに分割されたパッセージを用いるなど、オーケストラのために作曲する際に新しい技法を用いた。
…
【楽器編成と楽章】
《》楽器編成
ソロ・クラリネット(Bb)、フルート2、オーボエ2、ファゴット2、ホルン2(E♭)、トランペット2(E♭)、ティンパニ(E♭とB♭)、弦楽器
…
《》楽章名
第1楽章:アレグロ(変ホ長調、4分の4拍子)
第2楽章:アンダンテ・コン・モート(ト短調、8分の6拍子)
第3楽章:Alla Polacca(変ホ長調、3/4拍子)
…
〜
〜
〜
〜〜
2. 作曲者:ウェーバー について
2.1 Wikipedia DE(ドイツ版)の抜粋、および、その日本語翻訳
〜〜
〜
カール・マリア・フォン・ウェーバー
Wikipedia EN(英語版) URL> https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carl_Maria_von_Weber
Wikipedia DE(ドイツ版) URL> https://de.m.wikipedia.org/wiki/Carl_Maria_von_Weber
〜
Carl Maria von Weber (vollständiger Name Carl [Maria] Fri[e]drich Ernst [von] Weber; * 18. oder 19. November 1786 in Eutin, Hochstift Lübeck; † 5. Juni 1826 in London) war ein deutscher Komponist, Dirigent und Pianist der Romantik.
…
〜[Excerpt from above Wikipedia]
〜[上記Wikipediaの日本語翻訳は次の通り。翻訳にはアプリ「DeepL」を使用。]
〜
カール・マリア・フォン・ウェーバー(正式名:Carl [Maria] Fri[e]drich Ernst [von] Weber; * 1786年11月18日または19日 in Eutin, Hochstift Lübeck; † 1826年6月5日 in London)は、ロマン派時代のドイツの作曲家、指揮者、ピアニスト。
…
〜
〜
〜〜
2. 作曲者:ウェーバー について
2.2 ウェーバーの作品リストへのリンク・Wikipedia EN(英語版)
〜〜
〜
List of compositions by Carl Maria von Weber
Wikipedia EN(英語版) URL> https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_compositions_by_Carl_Maria_von_Weber
〜
〜〜
〜〜〜
〜〜〜〜
〜〜〜〜
〜〜〜
〜〜
〜
