
【感想?レビュー?】メタファー:リファンタジオ RPGに正面からぶつかった、本当のRPG
こんにちは、なるぼぼです。
ついに、メタファーをクリアしました。
色々な因縁のあったこのゲーム。
プレイ前からペルソナみたいなゲーム画面を見せられ、実際に遊んでいてもアーキタイプが自分の解釈していたATLUSのシステム観と相違があったことに気づかされ…。
自分が望んでいたRPG感とかけ離れていた本作のシステムに、恐ろしく不快感を覚えていました。
一時期は不満が爆発して、記事に起こして全部ぶちまけていました。
ただ、クリアして思うのは、このゲームこそ今生まれてくるべき作品であり、まごうことなきATLUSの傑作であるということです。
上の感想はもう過去のものになりました。
今思うのは、ただただこのゲームが素晴らしいということだけです。
本記事では、そんな認知がひっくり返った原因と、クリア後に思う本作の魅力を、メガテンファンの立場からお話していこうと思います。
よろしくお願いします。
※案の定ですがネタバレ注意です
1.歴代シリーズを詰め込んだシステム
まずは、本作のシステム面から。
本作のシステムは、歴代シリーズの良いところをふんだんに詰め込んだ、贅沢なものと言っていいでしょう。

まず目につくのが、ペルソナシリーズから続投している「カレンダーシステム」。
カレンダーに沿って昼と夜で行動を行い、ステータスや人との交流を通じてRPGパート用の育成を進めていくというシステムです。
ペルソナシリーズを代表するようなシステムですが、本作でもその面白さは健在です。
次になんのステータスを上げようか、どのような行動をしようか、そういったことを考えながら日付を消費していく楽しさは、病みつきになる中毒性があります。
また、本作では旅の移動でまとめて日付を消費するイベントが追加され、その移動中も仲間と交流したり、自分のステータスを上げたりできるようになりました。
町と移動中でできる行動も異なるうえに、移動中はランダムイベントも盛り込まれていて、できることがかなり増えています。
カレンダーシステムの育成の楽しさはそのままに、冒険出来るRPGらしい楽しさを盛り込んだ、画期的な内容だったと思います。

同じくペルソナシリーズから続投しているのが「ボンドシステム」。
特定の人物との絆を深めることで、育成ステータスの上昇や商店の値引き、新たな技の習得が出来るようになる、というシステムです。
こちらは、選択肢によって変動していた好感度ステータスが変化しなくなりました。
どの選択肢を選んでも進行に影響はなく、会話のタイミングと主人公のステータスに影響を受けるだけなので、選択肢による反応を素直に楽しむことが出来ます。
コミュストーリーをシンプルに追いかけることができるので、選択肢に悩まされることなく、スイスイと進められるのはありがたかったです。

最後にプレスターンバトル。
プレスターンバトルは、真・女神転生Ⅲをベースとしつつ、合体魔法「ジンテーゼ」などを搭載した、シンプルなものになっています。
ペルソナのワンモアプレスシステムは一切廃止、系統としてはアバタールチューナーシリーズと同じものになっています。
個人的に、今の女神転生のマガツヒシステムやニヤリシステムは結構余分だと思っていたので、ここまでシンプルにしてくれて取っつきやすかったです。
原点となるアバタールチューナーの3ターンしかない問題点もパーティが4人になっていることで解決していますし、かなり理想に近いバトルシステムに仕上がっています。
ペルソナから入ったユーザーも、「次に回す」コマンドや回避されてターンが一気に奪われる緊張感などを味わえるため、ワンモアプレスとは全く違った新鮮さを感じられる、良いシステムです。

このように、システム周りは歴代の良いとこどりをしています。
また、しっかり各システムにブラッシュアップがなされていることで、取っつきやすさが極限までそぎ落とされており、遊びやすさもしっかり担保されていると思います。
ATLUS初心者にも自信をもっておススメできるかも。
2.アーキタイプに潜む「止める」面白さ
さて、続いて今作のシステムの一つ、「アーキタイプ」についてお話しします。
「アーキタイプ」とは、各キャラが装備できる装備品のようなもので、付け替えることでスキルを一気に変えることができます。
また、プレイヤーのレベルと別にアーキタイプのレベルも存在し、レベルを上げることで新たなスキルを習得できる、という育成システムです。
結構斬新なシステムに見えますが、これも歴代メガテンシリーズからの引継ぎで、ペルソナ2とアバタールチューナーにて採用されていました。

さて、僕はここがメタファーの問題点だと考えていました。
というのも、ペルソナ2やアバタールチューナーはレベリングありきでこのシステムを導入していたからです。
本作はダンジョン攻略中に全回復が容易にできず、レベリングが困難なカレンダーシステムを搭載していたため、相性が最悪だと思っていました。
ペルソナ2やアバタールチューナーを全くうまく活用できていない。
そう思っていました。
…ただ、これは意図的なものであったと気づかされました。

どういうことか。
本作は、あえてレベリングを制限し、育成できるアーキタイプを制限することで、各キャラに「役割」を意識づけるようにしていたのです。
例えば「ハイザメ」というキャラ。
ハイザメは盗賊系のスキルとの相性が良く、高い素早さを生かして攻撃を回避したり、相手に攻撃しながら命中率デバフをかけて有利に戦闘を組み立てることができます。
また、素早さが高いことから先制で動きやすく、バフデバフをかける要員としても非常に効果的であり、軍師や道化師のアーキタイプとの相性も良くなっています。
一方で、全体攻撃系のスキルや闇属性以外のスキルを覚えにくいため、魔法職や雑魚狩りのキャラクターとしては不向きです。
このように、ある程度キャラクターに得意不得意を作ることで、状況に応じてキャラクターを交代したりアーキタイプを切り替えたりすることで、戦闘をより楽しめることに、終盤になって気づかされました。

実際、プレイしていると序盤はスキル習得に苦しめられます。
最初に仲間になるのが前衛の物理スキル適正のキャラのため、魔法を習得しプレスターンの弱点を突いてターンを増やすという戦術が取りにくいからです。
しかし、魔法キャラが一気に加入する中盤からは様々なスキルを扱えるようになり、戦術の幅がグッと増します。
こうして幅が広がったことで、誰を選択し誰を控えにするか、そしてどのタイミングで入れ替えながら戦略を組み立てていくかという、長期戦を前提とした役割分担の戦法が本作の理想解であることに気づかされました。
実際、交代時にプレス半減ができる能力がつくようにもなっており、本作はこの戦い方が推奨されています。
アバタールチューナーは良くも悪くも各キャラの個性が際立たないゲームだったため、シエロを支援役にする程度の差しか出ませんでした。
本作はそうしたキャラごとの差異を際立たせながら、時間制限もつけることで、かなり考えながらゲームを進めるようプレイヤーを誘導しています。
実際、終盤はぶっ壊れスキルが大量に出てくるため、役割分担を際立たせていると歴代最強クラスのパーティが完成したりします。

また、これは意図的なのかわかりませんが、本作はこうした役割分担があることを見ると、ある種アーキタイプがジョブのような役割をしています。
実際戦士とか魔術師とか言ってるわけですから、ジョブそのものを意識しているのかもしれません。
ジョブといえばファンタジーRPGの典型。
何にでもなれると言いながら、本質的には役割を根底にしているところが、地味にコンセプトに合致していて面白いなと思いました。

視点を変えるだけでもシステムが一気に面白くなることに気づかされて、このゲームの凄さを感じました。
後述するつもりではあるのですが、今の時代だからこそ、アーキタイプはこうあるべきだったのかもしれません。
3.プレイヤーを離さない、最高のストーリー
さて、お次はストーリー。
ファンタジーRPGらしい、というわけではないのですが、個人的にはかなり色々なものを踏襲していてよかったと思います。

本作のストーリーの肝は「王権ファンタジーに自由選挙制度が入ったら、何が起こるのか」というものでした。
実際、王権派として既存社会の維持を唱えるフォーデンと、力による自由主義を唱えるルイとの対立が、物語の軸になっています。
主人公は往時の呪いを解くため、呪いをかけたルイに敵対する立場として動き回っていきます。
なので、プレイヤーは政治+ファンタジーを軸として、ゲームが進行していくことを理解します。
実際、ここはメガテンのLNCを踏襲したものであり、フォーデン側を法と既得権益を守るロウ、ルイ側を自由と混沌を望むカオス、どちらにも属さず動き回る主人公一行をニュートラルとして解釈することができます。

しかし、中盤にフォーデンが死亡し、ルイが台頭することで物語が一気に動いていきます。
そもそもフォーデン脂肪の前に主人公がルイの殺害に成功しているのにもかかわらず、影武者を用いてルイが復活していたという手の込んだ戦略から面白いです。
そして神器により政敵であるフォーデンを目の前で殺害し、腹心であったはずのフィデリオさえ躊躇なく殺してしまうシーンで、開いた口がふさがらなくなりました。
早々にフォーデンが退場しロウ側は崩壊、主人公一行もルイに一番近かったフィデリオが殺されるだけでなく、大聖堂で殺したはずのゾルバが復活していたという点も含めて、かなり色々なところに驚かされます。
何より、政治×ファンタジーのメガテンリスペクトとして最後まで進んでいくと思っていた展開が、フォーデンの死亡により一気に塗り替わっていく様が見事でした。

これ以前は、ルイに取り入ろうとしていたこともあってか、結構ストーリーが動きません。
マルティラはストーリーこそ面白いものの、根幹であるルイやフォーデンにはほとんど絡みません。
ジュナが仲間になるシーンは緊迫する部分も多いものの、結果的に作戦が成功するためこれまたストーリーが動きません。
ビルガ島もそこまで大きな展開があるわけではなく、同行してきたフィデリオとバジリオの好感度が上がるぐらいです。
だからこそ、アルタベリー到着からとんでもない勢いでストーリーが動き始め、ギアがかかる感じが最高でした。
これ以降、王子の復活や王の魔法の意図などでなんとなく察することのできる展開もありますが、基本勢い良くストーリーをぶん回してくれるので、展開がわかってもあまり気になりません。
ペルソナ5でも思いましたが、最近のATLUSは中盤以降のストーリーの盛り上げ方が結構うまいと思います。

また、本作は歴史的なJRPGを意識しているところもあってか、テンプレ的な要素がちょこちょこ出てくるところが却ってほほえましいです。
例えば、終盤にルイが世界を掌握した後、「俺と一緒に世界をリセットしないか」と提案されるところは、もろ「世界の半分をお前にやろう」と同じです。
かなりの場面で、ファンタジーRPGを意識した展開が出てきたりするので、RPGマニアはしっかりと楽しめると思います。あと、モアが最後に王として出てくるくせに父親面してくるところとかは、声優も相まってペルソナ2のフィレモンを思い出しました。
ビンタ出来る選択肢が欲しかったです。

4.ファンタジーとは何か
さて、お次は本作の「ファンタジー」というものへの解釈について。
これも前記事で疑問を抱いていましたが、実際遊びきってみると本作のファンタジーらしさに気づくことが出来ました。

そもそも、僕は最初「ファンタジーRPGの再解釈」という本作の触れ込みに、あまり納得がいっていませんでした。
実際の中身がメガテン的であり、民主主義を王権的ファンタジー世界観に突如持ち込むというコンセプトは面白いものの、種族差別など社会的な部分はほかのRPGでも語られていましたし、今更感を感じていました。

しかし、実際はもう一歩踏み込んだ内容になっていました。
本作の「ファンタジー=幻想」は、幻想と現実がファンタジー世界から見ると逆転しているという現代社会との対比だけでなく、幻想(理想)と現実によるギャップを埋めようとする理想への追求も示していた、という2面性があります。
幻想と現実の対比に、二重の意味があるのです。

前半の幻想と現実の対比は、本作にプレイヤーが介入している点や、新宿がマップとして登場するなどの現代社会を仄めかす描写に現れています。
幻想小説により理想として描かれる現代社会が、現代におけるファンタジーの世界と対比構造になることで、プレイヤーにファンタジー世界のリアルな認識を与えることができます。
実際、この描写がなければ種族差別や宗教などに対して、「いつものファンタジーRPGだよね」と思わせてしまうでしょう。
あえて幻想小説で現代社会を理想とすることにより、今が幸せでファンタジー世界は「黒い部分が隠されていない、闇が深い世界だ」と思わせ、プレイヤーが「変えなければいけない」と思えるベースを作り出しています。

一方で、本作は主人公たちが思う理想、つまり幻想小説の中身である現代社会の構造に、ルイが現実的に不可能であると突きつける、理想と現実のギャップによる追及の問題も描かれています。
本作では、主人公たちの望む社会は現代社会にかなり近く、差別がなく選択の自由が与えられ、ひとりひとりがしっかりと生きていけることが前提になっています。
一方で、実際の社会は国王が理想をあきらめ、ルイによる歪んだ理想が現実として立ちふさがっていました。
彼の理想は武力による強弱でのみ身分を決め、弱きものは淘汰するという社会です。
それは強きものだけを残して生きていく、種の本能に限界まで近づいた社会であり、集団社会の超現実的なあり方だと言えます。
だからこそ、主人公たちが残した現代社会に近づいた考え方と、根本的に対立します。

本作は、こうした幻想の解釈が、ストーリーを進めるごとに前者から後者に切り替わっていく点が面白いです。
幻想と現実が世界観だと思っていたら、最後には思想に行きつく。
どこまでも幻想を追い求めるということが、結果的に理想に行きつくという、ファンタジーRPGの根本を再解釈したようなストーリーの構成は、僕は面白いなと思いました。

また、本作では主人公の名前入力とは別に、プレイヤー自身の名前を入力するシーンがあります。
これは、最後の最後にプレイヤーの名前を出して、主人公を導いていたのはあなただったという視点を与えるという使い方をされています。
いわゆるメタ要素と言われるものですね。
ただ、このやり方は率直に言えば陳腐です。
メタ要素は現代では当たり前のように使われますし、「MOTHER2」ではスーパーファミコンの頃からプレイヤーを作中に介入させていました。

しかし、本作はあえてこのやり方を使っています。
というのも、幻想と現実という主題があり、幻想小説の世界が現代であるからこそ、プレイヤーを介入させたときに「幻想小説の住人」として立ち位置がわかりやすくなっているのです。
これによって、急に作品と自分がつながるのではなく、比較的穏やかに、わかりやすくプレイヤーと作品が繋がるようになっています。
また、幻想世界の人間として主人公を操作する立場と言われるからこそ、最後の最後に出てくる「ありがとう」の言葉が、プレイヤーに染みるようになっています。
やり方や与える印象まで「MOTHER2」と同じ内容なのですが、違った方法でプレイヤーに言及するために、王の魔法の最後のピースというやり方を用いたのは一周回って斬新だと思います。
それに、最後にメタファーの世界の一部になれたことは、なんだかんだ言って嬉しかったです。
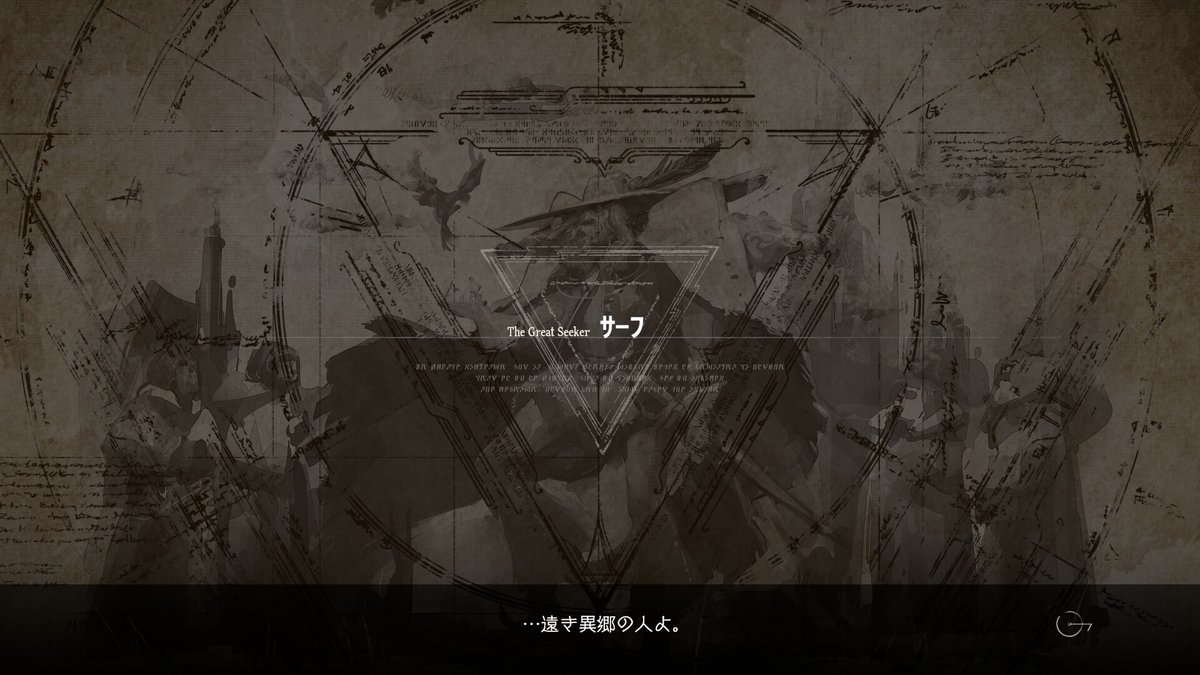
本作は、ファンタジーRPGという内容に対して、幻想と現実の対比を用いつつ、歴代の名作とは違った形でファンタジーの可能性をこじ開けました。
今までのRPGのノウハウが全部詰まっているのに、そのどれとも合致しないような独特さがあるのが、メタファー独自の強みだと思います。
ファンタジーRPGの再解釈が、クリアしてようやく理解できました。

5.「ルイ」という男と、完成されたカオス
さて、続いては本作の最も語りたい部分、アライメントのお話。
というか、本作はほぼ「ルイ」という男にアライメントの全てが詰まっているので、実質ルイ個人の話です。
僕は、本作最大の功績は「ルイ」という存在を完成させた点だと思っています。

まず前提から。
「ルイ」という男は、軍に所属する一人の男でありながら、王の魔法の存在にいち早く反応し、現政権から王に最もふさわしかったフォーデンに真っ先にかみついた男です。
カリスマ性の塊で、人心を掌握する演説は見事なものです。
武力もすさまじいもので、各地に現れたニンゲンを次々に討伐している、優れた戦果も持ち合わせています。
また、徹底した力による公平を唄う存在で、力さえあればどんな種族でも関係なく、安定した地位と生活が保障されると説きます。
歴代メガテンにおける「ルシファー」及び「ルイ・サイファー」をモチーフとしていることは、容易にわかるでしょう。

では、歴代の「ルイ」は何を説いていたのか。
彼が登場するのは「真・女神転生」からですが、言ってしまえば今作のルイと大体同じです。
しかし、立場がかなり違います。
「真・女神転生」では世界を説くものの自身は物語にほぼ干渉せず、達観した立場にいます。
「真・女神転生2」では世界がロウのディストピアになってしまっているため、悪魔王として地下世界に追いやられた悪魔たちを救済しようとする存在になっています。
ある種救世主的な立ち位置になってしまっており、ロウ側のサタンが選民思想で残ったやつ以外全員消すというイカれた思想になってしまったことも相まって、正義面していました。
真Ⅴではルシファーが世界を支配できた魔界が舞台となっていますが、最後に出てくる彼はまたも達観してしまい、輪廻からの脱却を目指そうとするだけの存在になっています。

そういった歴代のルイと比較すると、本作のルイは、かなり久しぶりに「純粋なカオスを語る」存在です。
彼の語る「理想」は、歴代ルイと同じように力の強さが支配する社会を述べますが、本作はそこに迷いやゆがみが一切なく、純粋に力のある者だけが生き残るようにするというストレートさがあります。
歴代のルイは悩んでいたり思想に歪みが出たりと純粋なカオス世界を語っていたわけではないため、気持ちのいいカオス論を語る彼は、見ていてこちらも気持ちが良いです。
主人公と対峙するときも力に魅せられたような発言をするため、力だけが全てという思想が全開で出ています。最高。

また、歴代メガテンはカオスに対してかなり寛容で、今までルイを敵対視するように見せてきませんでした。
どちらかというと虐殺はロウの役割で、カオスはそこまで暴れまわっていませんでした(強いて言うなら真1のヤマ裁判と、真4の爆炎の東京だけだと思います)。
だからこそ、ルイが人々をニンゲンに変え、生き残った者だけが新たな社会を形成できるというぶっ壊れたカオス論を語ったとき、本当に痺れました。
この思想、めちゃくちゃにイカれていて悪いことではあるのですが、悪魔が跋扈する社会でも生きていける超人類という発想が、あまりにも純粋にカオスなんです。
LNCの目線でゲームを遊ぶことが多い立場として、ここまでカオスをヴィラン扱いし、敵対しなければならない存在にしたタイトルは、他に類を見ません。
恐らくペルソナ5(怪盗団はカオス側の存在)との対比なのでしょうが、それにしてもここまでカオスを悪意的に描いたのは見事だと思います。

さらに、ストロールが作中たびたび「ルイの思想を完全には否定できない」と言ったり、ハイザメも「彼には同情するところがある」と、仲間がルイを完全否定できないところも、今回のルイの思想の強さを物語っていると思います。
ルイはもともとエルダ族で、故郷の村をフォーデンに焼き払われたことにより、理不尽のない社会を作り出すことを決意していました。
実際、王子の呪いもフォーデンに濡れ衣を着せられているなど、ルイ自身にも結構不憫なところがあります。
そうした理不尽を味わった彼だからこそ、力によってすべてを淘汰し新たな社会を作るという思想に、完全な否定ができないのです。
これが本当に見事で、LNCのうちN至上主義にさせないような強さを感じます。

さて、LNC的にみると、本作はN=ニュートラルを「逃避」として示しているという部分にも注目しなければなりません。
本作のニュートラルは主人公一行なのですが、それ以前に存在していた前王「ユトロダイウス5世」もニュートラルです。
彼は王の魔法のトリガーであり、フォーデンに実権を握られ腐敗する政治に諦観し、未来を変えられる新たな存在に期待して民の信託に頼ろうとしました。
彼のこの行為は、一見すれば信託に任せる新たな統治のよう見えますが、実際は自分が世界を動かすことから逃げただけであり、逃避とさして変わりがありません。

そして、モアとして幻想に身を任せようとしたことで、彼の思想は幻想への逃避に行きつきます。
今ある世界の存在を無視し、新たな世界で生きていこうとするさまは、法にも混沌にも頼らない、ニュートラルの一つの形です。
自分だけを信用するという点では、真・女神転生Ⅲのムスビのコトワリが一番近いかもしれません。
ペルソナ5では丸喜の逃避がロウとして見られましたが、本作では逃避がニュートラルの一つのあり方として存在しています。

一方で主人公一行が出した答えは、弱者を自分たちの手で救い上げ、全員で形作っていく社会でした。
彼らは前王の逃避による自分だけの救いを求めるのではなく、全員で社会を形作ることで理想郷を見出そうとする、対話の社会構造でした。
この構造、一見すれば真・女神転生Ⅲ以降のハッピーエンド的ニュートラルのように見えるのですが、実際は全種族に生存の場を与える、真・女神転生で語られた調和のニュートラルエンドになっています。
太上老君は、法と混沌を消すことはできないから、調和による社会を生み出し、無為自然の中であるがままに生きることを説きました。
実際、メタファーのクリア直前の世界では、仲間の存在によって被差別種族の台頭が起こる一方で、未だに解消されない被差別種族の貧困問題が語られます。
社会的に不利な者や不和を起こす者を淘汰するのではなく、受け入れつつも妥協案を模索する。
本作の主人公たちの生み出した社会は。人間中心社会を結論付けるハッピーエンド的な女神転生のエンディングよりも、よっぽど本質的なニュートラルを語っていると思います。

本作はファンタジーRPGなのであまりLNCに触れないかと思っていましたが、ルイの存在がLNCを際立たせ、帰着もより本質的なニュートラルの社会を生み出すという、歴代でもかなりLNCをしっかりと捉えていた作品だったと思います。
凄まじい出来でした。

6.本作に見える、アバタールチューナーの影
最後に、個人的なエゴを。
本作は直接的にメガテンやペルソナ、世界樹のオマージュと言えるような要素が多々あるのですが、僕は本作は言及していないだけで、アバタールチューナーの雰囲気がそこかしこにあることを感じていました。
ここでは、リンケージ(合体魔法)がジンテーゼとして受け継がれているなど直球的なところは別として、個人的に似ているなと思ったところをお話していきます。

まず思っていたのが、本作発売の背景が結構近いところ。
本作は新規IPでありながらメガテンやペルソナの要素が色濃く残っています。
とはいえ結構思いきっていて、悪魔がほぼ登場しないところとか、そもそもの世界観がファンタジーなところとかは、メガテンシリーズとは大きく違う点です。
その点で見ると、アバタールチューナーもメガテンの派生作でありながら、メガテンの中枢である悪魔会話や悪魔合体を排除した、思い切った作品です。
メガテンシリーズ・ペルソナシリーズという主流を残しつつも、一気に切り替わるような挑戦的な作品という点では、両者は共通しています。

実際、中身もジンテーゼ以外に共通していると思った部分があります。
それがストーリー。
本作、一部の展開にアバチュを思わせるような展開があるんです。
何となく感じていたのがマルティラの女王とラストでの仲間の戦闘シーン。

マルティラでは、女王ジョアンナがニンゲンを自分の赤子に見立てて領民を食わせていました。
全く展開は違うんですが、個人的にこれを見ていてジナーナを思い出したんです。
ジナーナはメリーベルという集団のリーダーでありながら、仲間を食うことができないため空腹によって狂ってしまい、最後には主人公たちに牙をむいてきます。
なんというか、対比とはいえお互いに無情感があるんですよ。
情から仲間を殺せないジナーナと、情から領民を食わせていたジョアンナ。
真逆の事をしているのに、どちらも感情は理解できてしまう上、こちらが手をかけなければならないため何ともつらいシーンです。
序盤ということもあり、ジョアンナの真相を知ったときにはジナーナが頭をよぎっていました。

もう一方の最終戦でのシーンは、カラドリウスに乗り逃亡を図るルイに対して、仲間が決死の戦闘を仕掛けるというものです。
全員死んでしまうような展開になるのですが、どうしてもアバチュ2のラストダンジョン突入前を思い出していました。
アバチュ2では、主人公サーフとセラを狂った太陽に突撃させるために、仲間全員が死亡します。
特に印象的だったのがシエロ。
彼はサーフとセラが乗った飛行機に敵の戦闘機を近づけないため、囮として動き回り撃墜されしまいます。
その前に放つ「笑ってないとブスになるぜ」や「本当の楽園で会おう」というセリフは否が応でも印象に残ります。
本作でも、操縦士ニューラスがカラドリウスに突っ込んで決死の逃亡阻止を図るのですが、その際に出るセリフが「生きてたらまた会おうぜ」なんですよね。
空中での戦闘シーンということも相まって、見た瞬間シエロしか思い出せませんでした。
なんかこう、見せ方がズルいですよね…。

そんな感じで、どことなくアバタールチューナーを思わせるようなシーンがあったのが、印象に残っています。
あくまでエゴかもしれませんが…。

思えば、途中でお話ししたアーキタイプも、時間がなくレベリングできない現代だからこそ生み出されたシステムで、アバチュに最大限のリスペクトがあったのかもしれません。
アバチュはレベリング重視すぎるあまり、戦闘と育成に膨大な時間がかかります。
それを、忙しい現代ようにブラッシュアップしたのが、アーキタイプだったのかもしれません。
アバチュのシステムを最大限尊重したシステムだと思うと、今のアーキタイプというやり方もある種最高のシステムだったのかも。
アバチュが好きすぎるあまり痛烈に批判してしまいましたが、クリアした今は良かったとさえ思います。

何よりも、時代が変わったことで失われてきたいろんなものが、本作を起点に再度注目されてほしいと強く思いました。
アバチュの影がところどころにあったり、プレスターンも真・女神転生Ⅲをベースにしていたりと、本作はどことなく歴代作品の面影があります。
僕はペルソナ2からメガテンシリーズに入ったので、割と歴代作品に理解がある方だと(勝手に)思っていますが、やっぱり取っつきづらいのも事実です。
ペルソナユーザーからすると、メガテン本編も触りづらいかもしれません。
そんな時に、メガテンとペルソナの中間、そしてアバチュリスペクトな本作が出てきてくれた。
これほど嬉しいことはありません。
本作を起点として、ペルソナユーザーがメガテンに目を向けたり、シリーズの過去作がちょっとでも日の目を浴びてくれたら嬉しいな、と思うばかりです。

7.終わりに
いかがでしたでしょうか。
発表当初から納得していなくて、凄く複雑な思いで始めた本作。
途中でやっぱりダメだと思っていましたが、最後まで遊んでみるとその真価に気づけたような気がします。
前記事のコメントでもアーキタイプの役割的立ち位置が書かれていて、「そう思ってみるとそうかもしれない」と感じていたのですが、最終版のロイヤルの解放から一気にその傾向が強くなって、「こういうことだったのか」と気づかされたりしました。
本当にありがとうございました。
本作は、新たなATLUSを本気で感じられるゲームだったと思います。
ペルソナ5の上手くまとめてブラッシュアップするやり方をベースにしながら、新たなIPで挑戦を掲げるというのは、中々真似できない芸当です。
何より、成功したシリーズのユーザーを新規IPに持ってこさせながら、過去作のイメージをも刷り込ませようとしています。
メガテンとペルソナをつなぐ良い架け橋になってくれる、そんな作品だと思います。
これを機に、メガテンやデビルサマナー、アバチュなどペルソナ以外の作品に触れる方が増えてくれることを、切に願うばかりです。
さて、次回の更新予定ですが、何かしらPS1タイトルか、「黄金像シリーズ」の話をいい加減まとめたいと思っています。
できるかはわかりませんが…。
相も変わらずですが、気長にお待ちいただけるとありがたいです。
それではまた次回。
さよなら~。

