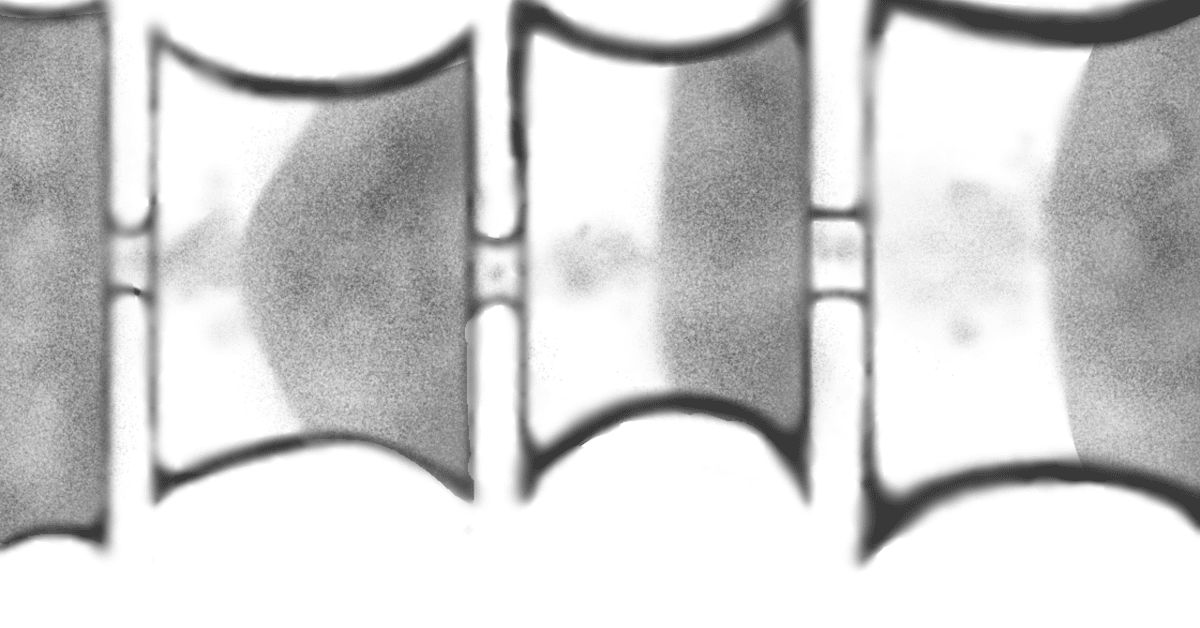
銀の砂時計
私の骨髄には、銀の砂時計が埋まっている。
寝転がりながら、自分の肉体〈カラダ 〉が出す音だけを聞いていると、よく分かる。
死んだ星を細〈ほそ〉く砕き、その白粉〈しらごな〉を硝子の背骨の管に通したもの、それが私。
星の瞬きや、妖精が囁く音よりも、絹の糸に茜珊瑚や金の粒を通すよりも、輝かしい、ささめきながら降り積もる、溶けない雪のような、その音。
全ての砂が脳の頂点まで達すれば、その時が私の寿命、今際の際。
その砂時計を、もう一度反転させれば、私は生き返ることが出来る。
砂が達する前に、砂時計を延々と回し続ければ、永遠に生きながらえることも出来るだろう。
だとすれば、両手を地について、あべこべに立ち、歩き回ろうか、なんて。
今生は、脳の上蓋まで砂が達するが早いか、それとも私が自分で硝子の背骨を砕いてしまうが早いか。
血と肉の國
二つの大岩の間で、私は永遠に擦られている。
石臼のようにぴったりした二つの面に、私は挟まり、意識が生まれてからこれまで、休むことなく擦られている。
肩を削られ、両腕をもぎ落とされ、体の側面と太ももを潰され……しまいには私の体の核がまろび出でた。
その核は、母岩を削り取られるダイアモンドのように、岩と岩の間で火花を散らし、しばらく拮抗状態となった。
少しして、ミシリという音がして、核の表面にヒビが入った。
それを滅びの始まりに、核は粉々に砕け散った。
核は、燦雲母〈きらうんも〉のように、下の台地に降り注いだ。
そこは何もかも、私の血と肉で出来た台地。
石も、木も、山も、谷川も、何もかもわたしの血肉でできている。
肉の台地を裂いて進むは、血の河。
腕茎の上に咲くは、指を開かせた華。
肉の地面には、髪の毛の芝生が蔓延っている。
頭上には、太陽と月のように二つの大岩が浮かび、慇懃無礼な風袋で、終わらない仕事を続けている。
その世界には、雲もないのに、白い雪のような細かい欠片が降り注ぐ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
