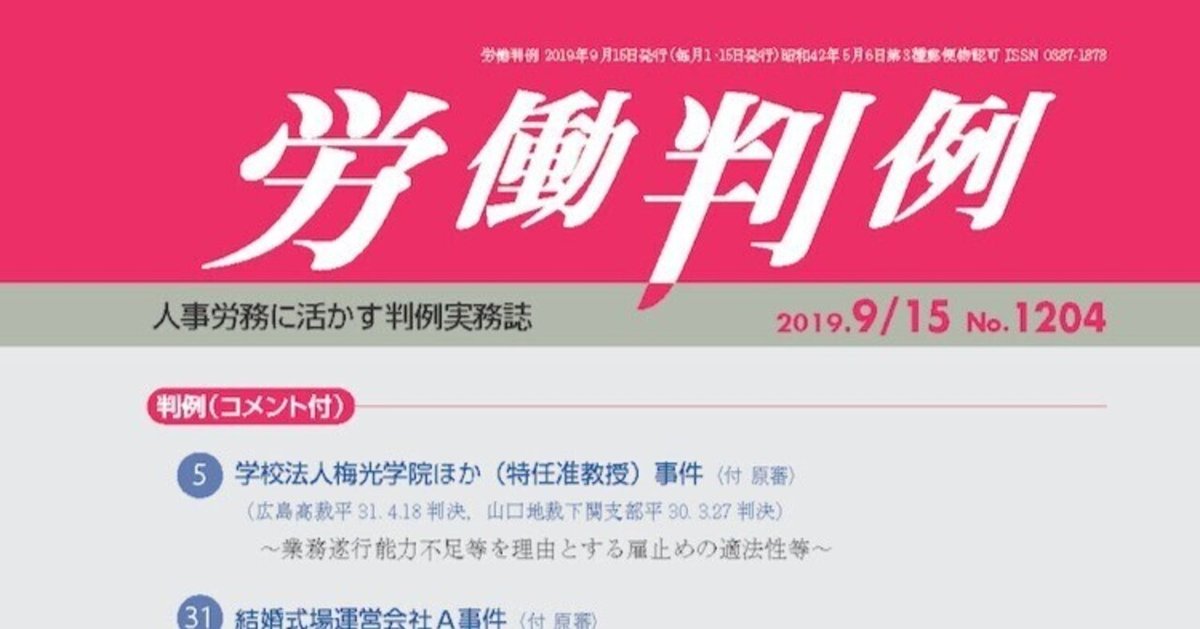
労働判例を読む#120
【セブン-イレブン・ジャパン(共同加盟店主)事件】東京地判H30.11.21労判1204.83
この事案は、セブンイレブンYの店舗を経営していたXが、賃金の不払いや、付随義務違反(安全配慮義務に反して傷害を負わせた)等を理由に損害賠償を請求した事案です。裁判所は、Xの請求を全て棄却しました。
1.判断枠組み
ここでの主要な争点は、Xの労働者性です。契約によってがんじがらめであり、経営者ではない、労働者だ、というのがXの本音のようですが、このような「労働者性」は、労基法や労契法だけでなく、労組法でも問題になるところです。この事案では、労基法(賃金関連)や労契法(安全配慮義務関連)が問題になりましたが、判決の中では、特にどの法令の「労働者性」かは特に明示されていません。根拠法令によって若干その範囲や内容が異なりつつありますが、その点の検討は、ここでは行いません。
この「労働者性」に関する、この裁判例の判断の特徴は、判断枠組みを示したことにあります。
すなわち、この裁判例は2段階で労働者性を判断する、という枠組みを示しました。
1段階目は、形式的な判断です。
すなわち、Xが独立した法人の代表者や個人として、Yと事業契約を締結し、店舗を経営していたのであって、事業者と相容れない、と判断しています。すなわち、取引の法的な形式が重視されるのです。
2段階目は、実質的な判断です。
すなわち、裁判所は、①指揮命令関係、②時間的・場所的拘束性、③代替性(但し、②と一体に検討されています)、④報酬決定、⑤その他、についてそれぞれ実態に沿った検討を行いました。
この結果、「Xの事業者性を減殺し、Xの労働者性を積極的に肯定できるまでの事情の存在を認めることはできない。」と結論付けています。
従前、特に法形式と実態の間に齟齬があると争われる事案で、ここまで明確に形式面と実態を意識的に区別して検討し、論じた裁判例があったのか、確認できません(記憶にありません)。けれども、法形式上雇用でないが、実態から見ると雇用だ、と判断される事案では、わざわざ1段階目の判断を示していない場合でも、これと同様の判断構造を採っていたようですので、その判断過程を客観化し、検証可能にした点は、非常に評価されるべきポイントです。
2.実務上のポイント
労働判例誌の当該判例の冒頭解説部分は、形式的な判断を示した点に対し、非常に消極的・批判的なコメントを加えています。
けれども、上記のような客観化のほかに、法制度の整合性などを考慮すれば、このように判断構造を明確に示した点は、高く評価されるべきです。
すなわち、フランチャイズ契約の相手方へのプレッシャーは、両者間の契約(私法)や、下請法や独禁法などの経済法(特に、優越的地位の乱用)が問題にされるべき場面です。市場経済における競争原理の観点から規律すべき関係だからです。この裁判所は、1段階目として、まず法形式によって私法や経済法で規律すべき対象であることを明示しました。
けれども、実態によっては労働法で規律すべき場合もあります。この裁判所も、2段階目として、実態によっては労働法で規律すべき対象であることを示したました。
問題は、この2段階目の評価により、労働法で規律すべき対象であるとされた場合に、経済法で規律されるかどうか、です。この裁判例では、「事業者性を減殺」する、と表現しているため、私法や経済法の適用を想定していないようにも読めますが、労働法のルールによって契約内容が修正されることになるであろうことを考慮すれば、私法や経済法の適用が完全に排除されるのではないと考えられます。経済法は経済法の規制趣旨によって適用範囲が決定されるため、この領域では、労働法のルールと、経済法のルールの両方が適用される可能性が高い、と評価できるでしょう。
すなわち、2段階目の評価により、労働法で規律すべき対象であるとされた場合、この者は、労働法と経済法の両方で保護される可能性があるのです。
にもかかわらず、労働者性に形式的な判断を持ち込むのはおかしい、と何の根拠も示さずに非難することは、ルールの在り方を検討すべき判例評釈の在り方として、非常に視野の狭い、誤った方法であると言わざるを得ません。むしろ、弱者保護、という観点から見れば、この2段階の方法の方が、経済法と労働法のそれぞれの保護の可能性を検証できることになり、より手厚くなるはずです。さらに言えば、経済法と労働法の役割分担に関する議論が盛んになってきた現在(厚労省と公取委との連携が模索され、フリーランス保護の在り方が検討される、など)、もしかしたらこの裁判例が示したような、両者の競合する可能性が否定される可能性もある中で、あえて両者による保護が競合する可能性を肯定した点は、弱者保護を重視する立場であれば積極的に評価すべき様に思われます。
労働判例誌の解説の良し悪しは置いておくとして、この裁判例は、①従前、明確に示されなかった判断構造(法形式と実態それぞれの検討)を明確にして客観化し、検証可能にしたこと、②経済法と労働法の役割・適用範囲を議論すべき枠組みが明確になったこと、等の点で、今後の労働者性の問題を検討する際の参考になると思われます。
例えば会社としても、「契約上」どのように評価されるか、相手方が事業者と評価されるだろうか、という1段階目の問題と、「実際の運用上」どのように評価されるか、相手方が労働者と評価される可能性があるだろうか、という2段階目の問題を、それぞれ意識して検討することで、取引先との関係を検証することがより容易になるのです。
※ JILA・社労士の研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!
