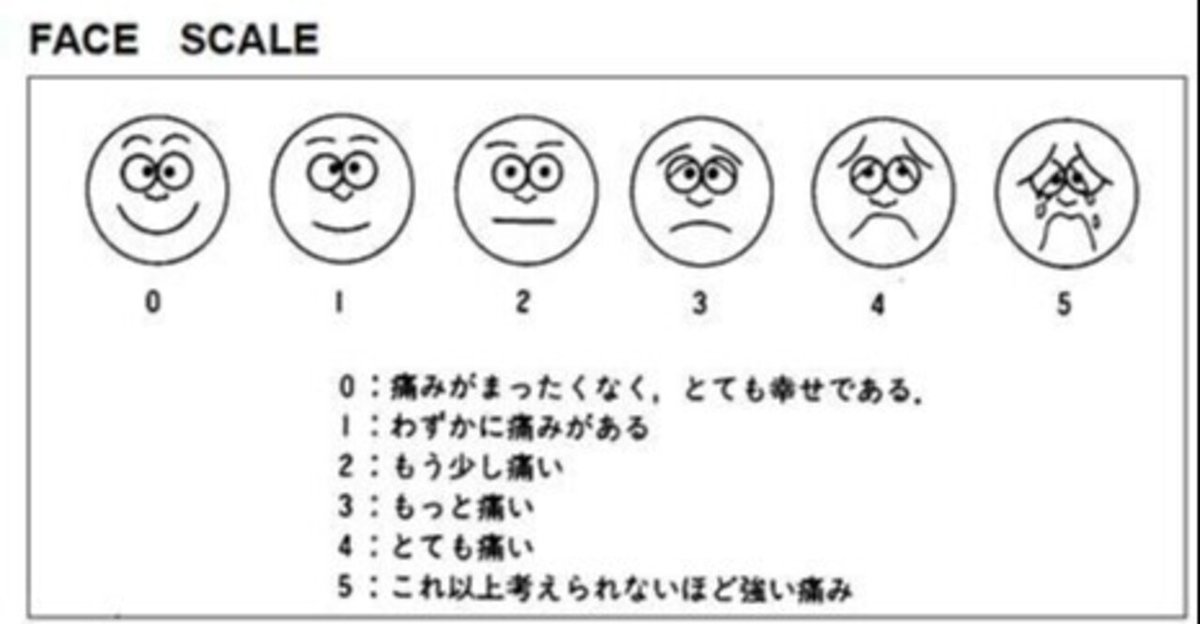
問診(疼痛検査)から臨床につなげるヒントはないか?
今回は疼痛評価から評価・介入へどう考えていくか書いていこうと思います。整形の外来患者さんは「ADL自立だけど、痛みがあって困っている」といった方が多いです。そこで、僕は問診(疼痛評価)でこのように考えています。
①どこの部位がいつから痛いのか→急性痛or慢性時痛によって患者教育をどうする?
②どんな動きで痛みが出るのか?→どんなストレスが加わることで痛みが出ているのか?
③なぜ、そのようなストレスが生じるのか?→隣接関節との関係性を考える
④疼痛が軽減する動作はあるか?→患者教育としての運動療法、今後の介入の方向性を考える
このように問診から展開できないかと考えていきます。それぞれ詳しく書いていこうと思います。
①どこの部位がいつから痛いのか?
ここで考えるのは
「軽い運動・局所の安静などでリラクゼーション方向に患者を教育するのか、がっつり運動して積極的に運動をしていった方が良いのか」考えます。
訴えを聞いてみて「一週間で急に痛みが出てきた」、「二日前に膝をひねって痛めた」→急性痛かも?
「もう何年も腰が痛い」「長時間歩くと膝痛い」→慢性時痛かも?
もし、急性時痛であれば局所を積極的に動かすとより炎症を遷延化させてしまいます。患者さんの中には治そうとしてより頑張って患部を動かして組織の損傷を遷延化させてしまう例があります。(五十肩など)
なので僕は急性時痛かなと思ったら患者さんには「局所の損傷は時間がたたないと修復されない、動かすとより増悪してしまう、こういうポジショニングをとると負担が減る」といった説明、介入としては軽い運動による患部のリラクゼーション、患部以外をよく動かすようなトレーニングを指導します。
逆に、慢性時痛であれば患者さんには「どこか他の場所が動いてなくて結果としてその場所に痛みが出るくらい、負担が集中している」といった説明、介入としてはその動きが足りてない部分の運動療法をおこなっていくといった展開をしていきます。(ピラティスなど)
このように、問診で患者さんに自分がどんな痛みが生じているのか、いまは何をするべきなのか説明することで信頼関係を築きつつ、患者さん自身にも自分の身体がどんな状態なのか考えるきっかけになると思います。
個人的な主観なので間違いもあるかもしれませんが、みなさんの臨床の参考になれば幸いです。また続きを次回以降書いていきたいと思います。最後まで読んで頂きありがとうございました。
いいなと思ったら応援しよう!

