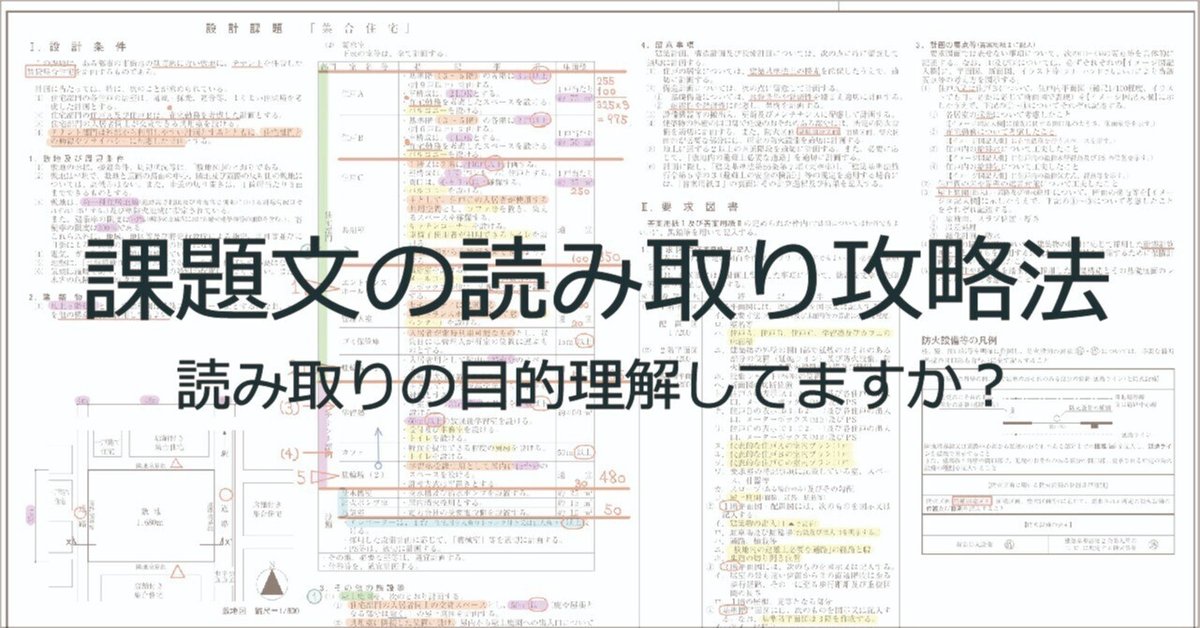
一級建築士製図試験_6《読み落とさない課題文の作り方。課題文の情報は「価値」と「量」に分類して読む》
皆さんこんにちは。
昨年S資格長期クラスでチューターをつとめたYAP(やっぷ)がお送りします。
もうすぐS資格の長期製図コースが開校する時期になりました。
今年製図試験を受験する方々は、10月の本試験に向けてそろそろ勉強を始めているのではないでしょうか。
今回は多くの方が読み落としをすることで、採点の土俵にも乗ることすら出来なくなってしまう課題文の読み取り方法について解説をしていきます。
昨年の課題文の読取り方法を今一度見直したい方、今年初めて製図試験に挑戦する予定で、課題文の読み取り方法を予習したい方は是非最後まで読んでいただければ嬉しいです。
私自身が実際にやっていたアンダーラインの引き方を令和3年本試験の課題で実践していますので、参考にしてみてください。
それでは行ってみましょう!
結論
「課題文の読み取りは情報を「価値」と「量」に分類して読む」
その結果、読み落としを防止し、エスキスでの検討も格段にしやすくなります。
資格学校では課題文を3回読めと言われることもあります。ただ、何も意識せずに何回読んでも読み落としは発生します。
課題文の読み取りの「目的」を理解していない人が多いことを昨年のチューター経験で痛感しました。
課題文は設計条件であり、そのすべての条件には試験元が念密に考えた関係性があります。
絶対に課題文の読み取りを作業にはしないでください。
課題文の読み取りは目的を持ち、能動的に取り組んでください。
また、この記事を読んで理解できない部分があれば、是非TwitterのDM等で気軽にご質問ください。
丁寧に1つずつ解答し、いただいた意見をもとに記事も分かりやすく更新していく予定です。
ここから先は
¥ 100
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
