
【今日は何の日?】令和6年12月16日|今日の記念日・出来事・暦など
令和6年12月16日(月)は?
紙の記念日
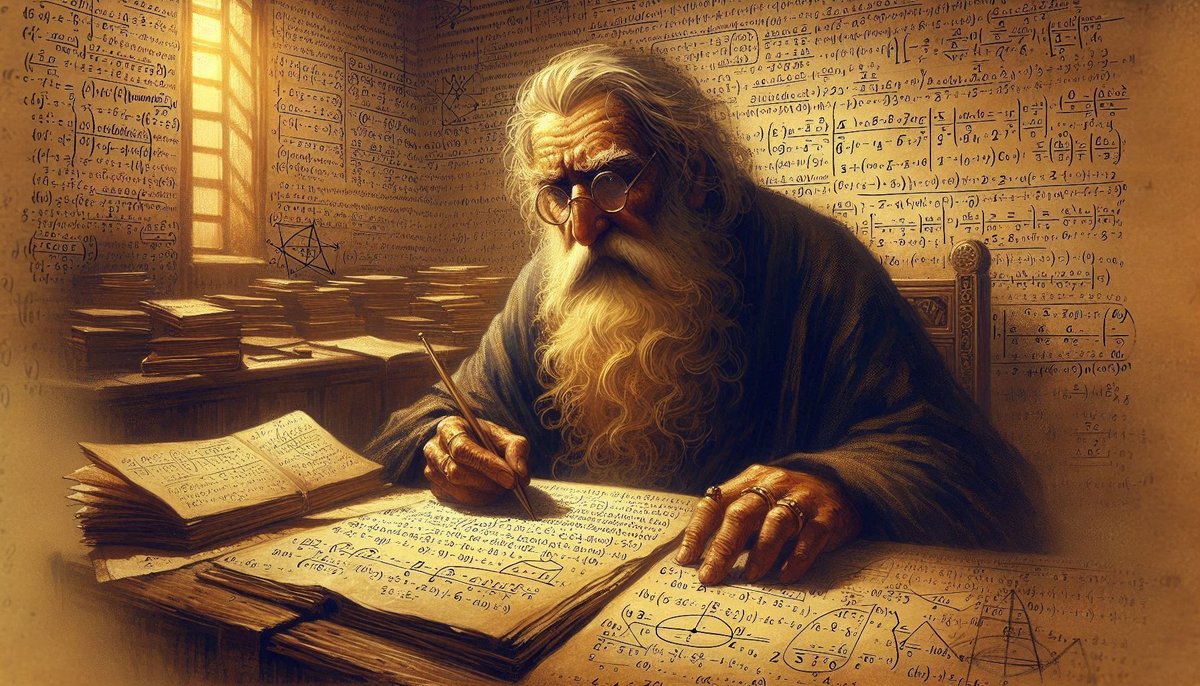
1875年12月16日、王子製紙株式会社の前身となる抄紙会社が工場の営業を開始したことを記念して制定されました。
この抄紙会社は、実業家・渋沢栄一が大蔵省紙幣寮から民間企業として独立させ、明治時代に入って間もない1873年に設立しました。 当時、洋紙の多くは輸入に頼っていましたが、この抄紙会社はその国産化を推進し、後に王子製紙株式会社の前身となりました。
その後、合併を繰り返し、国内市場の8割以上を占める巨大製紙会社へと成長しました。しかし、1949年に戦後の財閥解体政策によって解体され、苫小牧製紙・本州製紙・十條製紙の3社によってその事業は引き継がれました。(この3社はその後の再編により、現在の王子ホールディングス(旧:苫小牧・本州)と日本製紙(旧:十條)になっています。)
「紙の記念日」を制定した背景には、西洋の水準に対抗するための本の普及や、出版事業の活性化が主な目的としてありました。
電話創業の日

1890年のこの日、日本で初めて東京市内と横浜市内で電話が開通しました。
当時、東京には155台、横浜には44台の電話が設置され、電話料金は東京で40円、横浜で35円という定額制でした。電話の回線をつなぐ役割を担ったのは電話交換手で、千代田区に設置された電話局では、7名の女性と2名の夜間専門の男性が対応していました。
逓信省による電話交換局のサービス開始以来、電信・電話は逓信省の管理のもとで運営されることとなりました。
この「電話創業の日」は、電話普及の発展を願って制定され、その後、大阪、神戸、長崎など、対応エリアは次第に拡大していきました。
いい色髪の日

花王グループの販売部門で、生活者に「花王商品とその価値を届ける」役割を担う花王グループカスタマーマーケティング株式会社が制定。
自分で髪を自由に染められるセルフへアカラーを、記念日を通して正しい使用方法などの情報発信を行い、その楽しさを伝えることで、市場のより一層の活性化を図るのが目的。
日付は「いい色」の「いろ」に合わせて16日で、一年を通じてセルフヘアカラーを楽しんでもらいたいとの思いから毎月16日を記念日としたもの。
旧暦:11月16日
六曜:友引(ともびき・ゆういん)
良い意味でも悪い意味でも友を導く、とされる日。 祝い事は良いですが、葬式などの凶事は避けるべきとされています。
元々は「共引」と書き、「引き分けて勝負なし」という意味があった日ですが、後に「友引」と書くようになってからは、「友を引きこむ」という意味合いが広く知られるようになり、上記のとおり、慶事には向いていると考えられ、結婚式の日取りとしても人気ですが、葬式などは避けられます。
六曜(ろくよう・りくよう)とは、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の6つの曜を指し、日にち毎に縁起の良い、悪い、を判断する考え方です。「先勝」→「友引」→「先負」→「仏滅」→「大安」→「赤口」の順で繰り返されています。
六曜は中国から始まり、日本には鎌倉時代に伝わりました。江戸時代には縁起の良し悪しを判断するものとして広まりました。
六曜は根拠のない迷信と見なされることもありますが、日本の文化の一部として受け入れられています。

日干支:甲寅(きのえとら/こういん)

十二支の一つである寅(とら)に当たる日で、12日ごとに巡ってくる吉日。
この日は特に金運に縁があるとされ、「金運招来日」と呼ばれています。
古くから、虎は金色の縞模様が金運の象徴とされ、邪気を追い払う神聖な動物と考えられていました。そのため、寅の日には財布の購入や宝くじの購入など、お金に関することをするのに良い日とされています。 また、毘沙門天は財福の神様として信仰されており、寅の日は毘沙門天の縁日でもあります。 毘沙門天を祀る神社や寺院にお参りすることで、金運や開運、商売繁盛などのご利益を得られるとされています。 特に、寅の年の寅の月、寅の日にお参りすることで、最も大きな力をいただけると言われています。
寅の日には、以下のようなことをすると良いとされています。
財布の購入や使い始め
宝くじの購入
開業・開設
旅行や引越し
車や家具などの納入
ただし、結婚や葬式を行うのは避けるべきとされています。これは、「千里を行って千里を帰る」という虎の特性から、元の状態に戻ることを意味するため、婚礼では離婚につながる、葬儀では亡くなった方が戻ってきてしまうというイメージがあるからです。
2024年の残りの寅の日は、以下のとおり。 12月 16日、28日
寅の日に関連する行動を計画する際は、これらの日付を参考にすると良いでしょう。 金運アップや願い事が叶いやすいとされる寅の日に、良いことが起こるよう願っています。
日家九星:一白水星(いっぱくすいせい)
二十八宿:心宿(しんしゅく)
祭祀、移転、旅行、新規事に吉。
造作、結婚に凶。
盗難に注意。
十二直:満(みつ)
全てが満たされる日。
新規事、移転、旅行、婚礼、建築、開店などは吉。
動土(地面を掘り返して土を動かす)、服薬は凶。

七十二候:鱖魚群(さけのうおむらがる)

六十二候。「大雪」の末候。
海で大きく育った鮭が、産卵のために一気に川を遡上するする頃。
川で生まれた鮭は、海で大きく成長し、産卵のために故郷の川へと帰っていきます。古来より人々は、この「鮭の遡上」を神秘的な現象としてとらえてきました。
鮭は、海中で1〜5年を過ごしますが、自分の生まれた川をよく覚えており、長い海での生活の後でも、ほとんどの鮭は元の川に戻ってくると言われています。この帰巣本能は、鮭の鋭い嗅覚によるものと考えられています。
産卵のために一心不乱に遡上する鮭は、まったく食物を取らず、役目を終えると力尽きます。こうして鮭は次の命を育み、その生命の循環を続けていくのです。
七十二候は、一年を七十二等分し、それぞれの季節時点に応じた自然現象や動植物の行動を短い言葉で表現し、約五日間ごとの細やかな移ろいを子細に示したものです。
暦注下段:帰忌日(きこにち)
「帰忌」とは天棓星(てんぼうせい)の精が人家の門戸を塞ぎ帰宅を妨害するとされる日。
里帰り、旅行帰り、金品の返却など、帰宅に関することが凶とされる。
暦注下段とは、暦の最下段に書かれていた日々の吉凶についての暦注のことで、単に下段とも言われています。古代中国から続く占術である農民暦が基になっています。
科学的根拠がない迷信としての要素が多く、明治時代に旧暦からグレゴリオ暦へ移行するときに政府によって禁止されましたが、当時の庶民は密かに使用し続けました。それ以前にも何度か当時の朝廷や政府によって禁止されることもありましたが、根強く残り続け、現代では自由に使用できるようになりました。それだけ庶民に強く支持されてきた暦注とも言えます。
選日:
三隣亡(さんりんぼう)
土木建築の凶日であり、建築に関わることをしてはいけないとされる日です。 この日に建築にまつわることをすると、その家だけでなく三軒隣りまで亡ぼすといわれています。
八専(はっせん)
八専とは、陰暦の壬子(みずのえね)から癸亥(みずのとい)までの十二日間のうち、丑・辰・午・戌の四日を除く八日間。一年に六回あり、この期間は雨が多いとされます。また、嫁取り、造作、売買、仏事などを忌む。
いいなと思ったら応援しよう!

