
【今日は何の日?】令和07年01月26日|今日の記念日・出来事・暦など
令和07年01月26日(日)は?
文化財防火デー

日本の貴重な文化財を火災や災害から守ることを目的として、毎年1月26日に実施される記念日です。この日は、1949年(昭和24年)1月26日に起きた法隆寺金堂壁画の火災を契機として制定されました。
法隆寺金堂壁画の火災
奈良県の法隆寺は、世界最古の木造建築として知られ、日本の仏教文化を象徴する重要な寺院です。しかし、1949年の火災で金堂の壁画が焼失し、国宝級の文化財が失われてしまいました。この出来事は、文化財の防火・防災対策の不備を浮き彫りにし、多くの人々に衝撃を与えました。
文化財防火デーの目的

防災意識の向上:文化財を守るためには、日頃からの防災意識が欠かせません。火災だけでなく、地震や台風などの自然災害からも保護する必要があります。
防火訓練の実施:この日を中心に、全国の寺院、神社、博物館、美術館などで防火・防災訓練が行われます。これにより、関係者の防災技術や対応力を高めます。
一般市民への啓発:文化財の価値や、それを守るための取り組みを広く知ってもらうための啓発活動も行われています。
主な活動内容
消防訓練:消防隊と連携した大規模な訓練が行われます。消火器や消火栓の使用方法の確認、避難経路の確保などが含まれます。
防災セミナー:専門家を招いた講演会やセミナーで、最新の防災情報や技術を学びます。
啓発イベント:ポスター展示やパンフレット配布などを通じて、一般の人々に文化財保護の重要性を訴えます。
帝銀事件の日
帝銀事件(ていぎんじけん)は、1948年(昭和23年)1月26日に東京都豊島区で発生した、日本犯罪史上でも有数の大量殺人・強盗事件です。この事件では、帝国銀行(現・みずほ銀行)の椎名町支店で、行員や関係者16名が毒物を飲まされ、そのうち12名が死亡しました。
事件の概要
犯人の手口:犯人は厚生省の職員を装い、「赤痢が発生したため予防薬を投与する必要がある」と偽って銀行内に入りました。
毒物の投与:犯人は行員たちに毒物(青酸化合物)を飲ませました。これを「予防薬」と称していたのです。
犯行後の逃走:行員たちが意識を失った後、犯人は現金16万4,500円(現在の価値で数千万円相当)を奪い、姿を消しました。
捜査と逮捕

捜査の難航:事件直後から大規模な捜査が行われましたが、手がかりは乏しく、犯人特定は困難を極めました。
平沢貞通の逮捕:絵画商であった平沢貞通が、約7か月後に容疑者として逮捕されました。
自白の経緯:取り調べの中で平沢は自白しましたが、その後一貫して無実を主張し続けました。
裁判とその後
死刑判決:平沢は一審から最高裁まで死刑判決を受けました。しかし、この判決には多くの疑問が残りました。
再審請求:平沢とその支援者たちは、生涯にわたって18回の再審請求を行いましたが、いずれも認められませんでした。
獄死:平沢は約32年間の獄中生活の末、1987年(昭和62年)に獄中で病死しました。死刑が執行されることはありませんでした。
事件の疑惑と問題点

物的証拠の不足:明確な物的証拠が乏しく、平沢を犯人と断定する決定的な証拠はありませんでした。
自白の信憑性:取り調べ中の自白には、拷問や誘導があったのではないかと指摘されています。
真犯人説:一部では、GHQや731部隊など、他の組織や人物が関与しているのではないかという説もあります。
社会への影響
司法制度への不信:この事件は、日本の司法制度に対する大きな不信感を生み出しました。冤罪の可能性や、自白に頼る捜査手法の問題が浮き彫りになりました。
メディアの役割:マスコミによる過熱報道や世論の影響力について、社会的な議論が巻き起こりました。
文化への影響:この事件を題材にした小説や映画、ドキュメンタリーが多数制作され、日本の文化にも深い影響を与えています。
現代への教訓
冤罪の防止:帝銀事件は、冤罪を防ぐための司法改革や取り調べの可視化などの議論を促進しました。
人権意識の向上:被疑者の権利や取り調べ手法の適正化について、社会全体で考えるきっかけとなりました。
歴史の風化防止:このような事件を風化させず、後世に伝えていくことの重要性が認識されています。
この事件は戦後間もない日本の混乱期に起きたものであり、社会の不安定さや司法制度の課題を浮き彫りにしました。現代においても、冤罪や司法の公正性の問題は重要なテーマとして議論されています。
モンチッチの日

※モンチッチではありません
「モンチッチ」をはじめとするぬいぐるみ、人形、オルゴール、雑貨などを企画・製造・販売する株式会社セキグチが制定。
世界中で愛されているマスコットキャラクター「モンチッチ」の魅力を、さらに多くの人に知ってもらうことが目的。
日付は「モンチッチ」の誕生日である1974年1月26日。
旧暦:12月27日
六曜:友引(ともびき・ゆういん)
良い意味でも悪い意味でも友を導く、とされる日。 祝い事は良いですが、葬式などの凶事は避けるべきとされています。
元々は「共引」と書き、「引き分けて勝負なし」という意味があった日ですが、後に「友引」と書くようになってからは、「友を引きこむ」という意味合いが広く知られるようになり、上記のとおり、慶事には向いていると考えられ、結婚式の日取りとしても人気ですが、葬式などは避けられます。
六曜(ろくよう・りくよう)とは、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の6つの曜を指し、日にち毎に縁起の良い、悪い、を判断する考え方です。
「先勝」→「友引」→「先負」→「仏滅」→「大安」→「赤口」の順で繰り返されています。六曜は中国から始まり、日本には鎌倉時代に伝わりました。江戸時代には縁起の良し悪しを判断するものとして広まりました。六曜は根拠のない迷信と見なされることもありますが、日本の文化の一部として受け入れられています。
日干支:乙未(きのとひつじ/おつび)
日家九星:五黄土星(ごおうどせい)
二十八宿:昴宿(ぼうしゅく)
神仏詣、祝い事、開店に吉。
十二直:破(やぶる)
物事を突破する日。
訴訟、出陣、漁猟、服薬に吉。
祝い事、契約事は、凶。
七十二候:水沢腹堅(さわみずこおりつめる)

七十一候。「大寒」の次候。
厳しい寒さで沢の水も凍りつく頃。
一年で最も寒さが厳しくなるこの時期、池や沼の水面は、溶けたり凍ったりを繰り返しながら氷が厚みを増していきます。 この時期は、一年で最も低い気温が観測されることが多く、多くの地域で氷点下になる日も珍しくありません。 ちなみに、日本の観測史上最低気温は-41℃で、1902年(明治35年)1月25日に北海道旭川市で記録されました。
七十二候は、一年を七十二等分し、それぞれの季節時点に応じた自然現象や動植物の行動を短い言葉で表現し、約五日間ごとの細やかな移ろいを子細に示したものです。
雑節:冬土用
「土用」は、四季の変わり目を知らせる期間のことで、立春・立夏・立秋・立冬の直前の約18日間のことを言います。それぞれ「春土用」「夏土用」「秋土用」「冬土用」とも呼ばれています。
「冬土用」は「立春」(2月3日)前の18日間となります。
土用期間中は「陰陽道の土を司る神様、土公神(どくしん・どこうしん)が支配する期間」と考えられており、土の気が盛んになる期間として、動土、穴掘り等の土を犯す行為や殺生を慎まなければならないとされています。
各土用の最初を「土用の入り」(どようのいり)と呼ばれ、最後の日は「節分」となります。
冬土用には、「未(ひつじ)の日」に「ひ」のつく食べ物や赤い食べ物を食べると良いと言われています。「ひ」のつく食べ物としてはヒラメ、ヒラマサ、ヒジキなどがあり、赤い食べ物としてはトマト、リンゴ、イチゴなどがあります。
暦注下段:大明日(だいみょうにち)
七箇の善日の一つ。
「天と地の道が開き、世の中の隅々まで太陽の光で照らされる日」という意味があり、「太陽の恩恵を受けて、全ての物事がうまくいく」とされる何事にも縁起のいい日。
他の凶日と重なっても忌む必要がないとも言われています。
暦注下段とは、暦の最下段に書かれていた日々の吉凶についての暦注のことで、単に下段とも言われています。古代中国から続く占術である農民暦が基になっています。
科学的根拠がない迷信としての要素が多く、明治時代に旧暦からグレゴリオ暦へ移行するときに政府によって禁止されましたが、当時の庶民は密かに使用し続けました。それ以前にも何度か当時の朝廷や政府によって禁止されることもありましたが、根強く残り続け、現代では自由に使用できるようになりました。それだけ庶民に強く支持されてきた暦注とも言えます。
選日:天一天上(てんいちてんじょう)
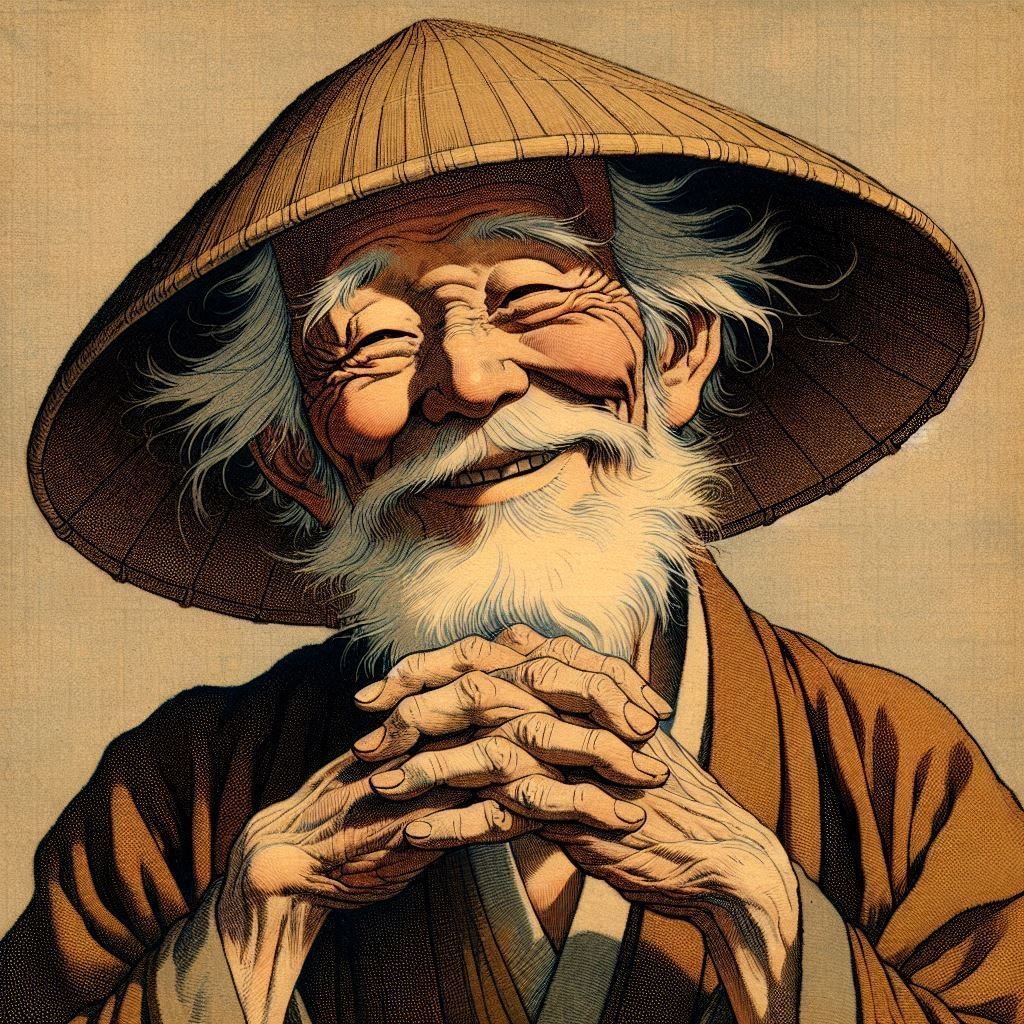
方角の神様である天一神(てんいちじん)が天に上っている期間。
癸巳(みずのとみ)の日から戊申(つちのえさる)の日までの16日間のこと。この間は天一神の祟りがなく、どこへ出かけるにも吉とされています。

天一神が天に昇っている間は、代わりに日遊神(にちゆうしん)と呼ばれる神様が天から降りてきて、家の中に留まるといわれています。この神様は不浄を嫌うため、家の中を清潔に保っていないと日遊神がお怒りになり、祟りを起こすともいわれています。
いいなと思ったら応援しよう!

