
ターナーアクリルガッシュ「くまごろEdithion」でプラモ塗れたよ!ほか2本です。
◯ターナーアクリルガッシュ「くまごろEdithion」でプラモ塗れたよ!
ターナーさんから、くまごろさん監修によるこういったセットが発売されます。ハンドメイドでの使用でチョイスしたモノとのことです。
これをモデラ―目線から注目してみると、
キャラクターモデルであればチューブのままor2色まで混ぜればスタンダードな色は網羅できそうなナイスなチョイス。
メカにのワンポイント塗装に嬉しい金銀パールに、金属色の下地にピッタリ暗黒ブラック収録
くまごろEdition!すごい!本当にすごいんだ!

というわけで発売前にも関わらず自身でプラモに使えそう!とつぶやいちゃったのもあり、いきなりですが発売前に同じ色の組み合わせで塗ったものを発表させていだきます。

バンダイ『SD 三国創傑伝 張飛ゴッドガンダム』です。何を思ったのかスミ入れまでセットのモノのみ縛りで敢行したのもあって粗い面も多々ありますが、シール指定の箇所含めどうしても塗装されてない箇所の部分塗装などを行ってみました。しかしさすがアクリルガッシュ。腕や胸部バルカン部の白の発色は素晴らしいですね。剝げたのかおもいっきり右腕に青が見えてるけど

加えて今回は、童心に帰るという意味を含めキットのプラにそのまま塗るという方法で塗ってみました。そう、そのまま塗ってみたのですが……

プラそのままだと肝心の塗り始めでなかなか乗ってくれません。仕方なく一手目はきれいな発色は諦め「足付け」程度に乗ればいいと割り切り、どうにか色を重ねていって完成させた(あくまで完成と言い張る)ものが冒頭の写真になります。一度色が乗れば比較的スムーズなのですが、部分塗装で補う色数も多く、最後の方は真顔になっておりました。時間かかんね。
どうしたものかとタイムラインを眺めていると、先ほどのセットを発売するメーカーさんからこんな記事が。
個人的にはクレオスさんの水性サーフェイサーを下地としてよく使っています。成型色を活かして作りたい方も多いと思うので、そういった方にはサンディングで足をつけることをおすすめしています。 https://t.co/wnfDBFUsOM
— ターナー色彩 模型ホビー担当 (@turnerhobbby) November 21, 2024
それ、早く言ってよぉん(某クラウドサービス並感)
※念のため申し上げておきますと、今回の塗装に関しては筆者がたまたま思い立ってたまたま生プラチャレンジなるものを敢行しただけなので、公式さんの方には断じて落ち度はないです。
アクリルガッシュをプラモデルで塗るには、こういった他のツールのフォローが必要なようですね。
◯アクリルガッシュをプラモデルで使う理由

はいというわけで雑な導入をご覧いただきありがとうございました。こっからが本題だぁ。
ここまでこの時点で茶番もりもりの記事をご覧いただいているということは、プラモデルをアクリルガッシュで塗りたい!もしくはプラモデルをアクリルガッシュで?なんで?と皆様感じていただいていることでしょう。。特にそう思っていない方も、そうかな…そうかもと自信がない方も、長いけどよろしければ最後までご覧ください。
手っ取り早く何が必要なのか教えろ!俺にもやらせろ!見てみたい!!アクリルガッシュがどこから来てどこにゆくのか!!という方はツール紹介のあとに一度まとめた項目がありますので、目次から「・導入にあたってのとりあえずまとめ」に飛んでみましょう。

それでは改めてアクリルガッシュとプラモデルについて考えていきたいと思います。まずはアクリルガッシュ自体について。
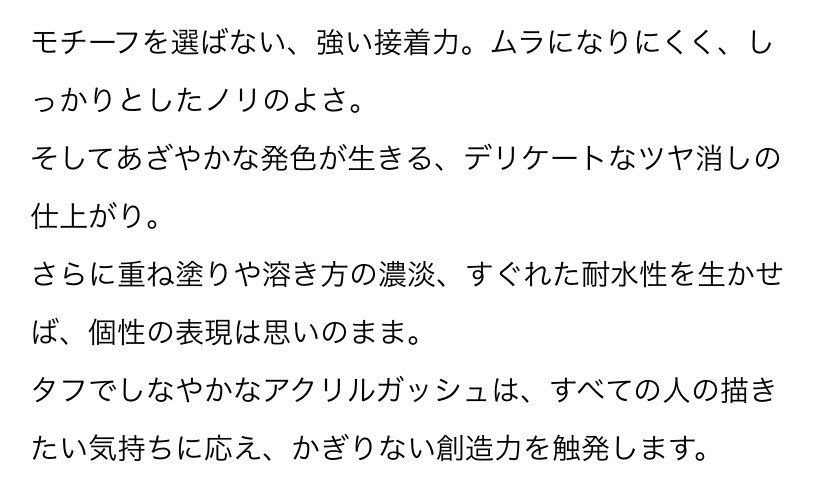

https://www.turner.co.jp/art/gouache/
ターナーさん公式で答え出てたわ。
答えは出てましたが、私から補足として、他社さんのツールと比較しつつプラモデルの使用における導入の意義、メリットとデメリットについて紐解いていきましょう。

・溶剤不使用によるメリット
国内で流通している「水性」と謳っている塗料は、大きく分けて有機溶剤を使用しているかいないのか(後者はエマルジョン系と呼ぶみたいです)という括りで明確な違いがあります。なんで?と思われた方。ワシにもよくわからん。ラッカー系との差別化とかあるんじゃね?(適当)水で洗浄可能というのは共通点のようだ。
アクリルガッシュは純粋にチューブに入っている絵の具なので、もちろん後者に当たります。
まずは溶剤が含まれている塗料について(ここでは水性ホビーカラーを挙げさせていただきます。ゆるして)。
それ単体でプラへの食いつき、塗膜を形成してくれるというプラモデルに最適な特性を持っているのですが、それの引き換えにか、粘度の高さと下地を溶かしてしまうことでの筆ムラや色ムラの発生のしやすさにより、あえて語弊があるように申し上げると筆塗りには向かない塗料です(とあえてこの記事では定義させていただきます。リターダーの併用などで綺麗に塗装されてる方もたくさんいらっしゃいます)。
なお難なく塗り重ねられるエアブラシでの使用に関しては超スピードの乾燥時間、隠蔽力もそこそこと文句なしの性能です。引き合いに出してしまった水性ホビーカラーも、昔のは使ったことないけどリニューアルによって格段に使いやすくなっての使用感とのことです。水性ホビーカラー!すごい!本当にすごいんだ!

ここでアクリルガッシュの方に戻りましょう。引き合いに出させていただいたものと比較してみると、見方を変えればアクリルガッシュはプラへの食いつき、単独での塗膜の形成を犠牲にして溶剤使用の筆ムラの煩わしさから解放された塗料であるともいえます。
水でも溶けるしメディウムの補助があればより快適な筆運びが可能、素晴らしい発色に隠蔽力、乾燥時間の速さでストレスなく塗っていけます。色のラインナップも文字通り多彩です。混色しても意図しない濁りは発生しづらいのも長所として挙げていいでしょう。
逆に、メディウムが入ってない状態なので溶剤を使用すればエアブラシの塗装にも問題なく使用できます。(水でも吹けるらしい。どちらにせよ溶くのに多少コツは要ることと、乾燥が早すぎる点などフォローが必要な点が何個かありますです。)
神にも悪魔にもなれる塗料ということですね。
水性塗料共通の特徴ではありますが、水での洗浄も可能です。すぐに水で落ちないような濃さのときや固まってしまった場合も、マジックリンで洗浄することが可能です。

素晴らしい塗料です。アクリルガッシュ!すごい!本当にすごいんだ!あなたもこれからガンガン使っていきましょう。

・溶剤不使用によるデメリット
……今一番大事な部分をスルーした気がします。ボールドになっている「プラへの食いつき、単独での塗膜の形成を犠牲にして」という部分です。
そう、プラモデルに使用する塗料として見直してみると、特に前述のようにツルツルのプラスチックの面に塗るための適性が、アクリルガッシュはごっそり欠けているということにもなります。(レジンはわからん素材の表面の関係ですぐ塗れるのかもしれん)単独の塗料として塗れない。これはわりと致命的な問題です。

とはいえ何も手立てがないのかといえばそんなことはありません。最初にお伝えしたように一応塗ること自体は可能なものというのは変わりませんし、他のツールを使用することで、十分にフォローそして快適な使用ができるものであります。
次項では、塗装環境によってどのツールを使っていけるのかを含めてそのハードルを飛び越えていきましょう。
ついでにせっかくなんで、同じエマルジョン系塗料の同士、シタデルやファレホが気になっている方もご一緒にぜひ(途中で対決させる項目も書こうとしたのですが既にクソ長いのもあって早々に没になりました)。
そうそう、下地とトップコート。え?ファレホくんはプライマーとポリウレタンバーニッシュ、シタデルくんは色付きプライマーとアードコートがあるからいいって?いやいやそんなこと言わずに。

◯アクリルガッシュ導入にあたり
プラに塗装するにあたり、アクリルガッシュ導入の利点と下地作り、及び塗装面を保護するための準備はやった方がいいということは長い茶番の末におわかりいただけたと思います。
しかし同時に、例えばスプレーを使用するのであればスプレーを吹ける環境、筆塗りで済ますにしても溶剤を使用するなら(自分を含む)居住者の同意が必要と作業環境の構築についても考えなければいけなくなります。このへんの導入の煩わしさがプラモデルの塗装においてアクリルガッシュが今ひとつ浸透してない理由の一つじゃないすかね……
生プラ直塗りを振り返る
スプレー使用による下地作り・トップコート
筆塗りで完結させる方法
合わせて便利なメディウム
スミ入れについて
1.生プラ直塗りを振り返る
前述の通り塗れるこたぁ塗れます。
一手目にプラに乗らないのも前述の通り。発色させるまでに色を重ねるのは苦行の域に入っていると言っても過言ではない気がする。
特にガシガシ可動させるガンプラなどのキャラクターモデル、ゲームの駒として使用するウォーハンマーなどのミニチュアゲームにおいては塗装面の保護という意味でも不安が残ります。

それでも、最低限最後の段階まで行けば色は乗りました。一部ハゲてたけどとすれば、後述のツールなどでどうしてもどれも採用できないとしても最低限達成は可能ということでもあります。これは心強い指標になります。俺もやったんだからさ

2.スプレー使用による下地作り・トップコート
いきなりですが、先に答えになりそうな記事がありますので引用させていただきます。
2-1.水性プレミアムトップコートスプレー
用途:下地+仕上げ
溶剤使用:あり
本来塗装面を保護するトップコートの中で、つや消しの細かいザラザラの表面をつける特性を下地作りに利用してしまおうという方法。こちらの記事を見たときはたまげたと同時に唸らされた記憶があります。もちろん仕上げのトップコートもできますし、スプレーの使用が可能であるならトップコート含めてこれ一択でいいかも。うーん合理的。もう全部あいつ一人でいいんじゃないかなこの理屈なら色の乗り具合は変わるかもしれませんが半光沢でも可能ですね。
こちらで補足すると、緑缶の『プレミアム』と銘打っているシリーズはしっとり全体を濡らすように吹き付けることを推奨しております。これは、ベランダ、屋外で吹き付ける際にもある程度スプレーの勢いに任せて吹いて問題ないということでもあり、外で細かい塗膜のコントロールをしなくて済むというのはわりと大きいポイントです。(さすがに垂れるまで吹いちゃアレですが)同社の青缶の方だと多く吹き付けちゃダメ!とかで肝心の屋外使用の際逆にビビりすぎで白化したりとかなりシビアだった記憶がありますので見かけてもまずは緑の方推奨。塗膜もカッチリ作ってくれますし、総じてスプレーが使用できるならオススメできる一品です。
余談ですが、ガンプラではつや消しを推奨されることが多いとは思いますが、ウォーハンマーなどのモデル自体が小さめのモデルに関しては半光沢の方が気に入っております。ちっちゃいのにつや消しするとせっかく塗り分けた色の発色とか境目とかボンヤリする気がするんよね。
2-2.水性サーフェイサー1000スプレー
用途:下地
溶剤使用:あり
ターナー模型ホビー担当さんが挙げていたツールがこちら。よくプラモデル塗装で名前が挙がるサーフェイサーですが、水性のものは比較的最近登場したもので、国産で使いやすい下地剤が出るという発売予定の一報が出たときは歓喜したのを記憶しております。
先に謝罪しておくと、瓶の方には大変お世話になっておりますがスプレーの方は使用したことがないです(始めたときからしばらく経ってから出たんじゃあ)。瓶の方の使用感からするとたぶん快適に使えるんじゃないかなあ。
ちなみに1000という数字は、1000番相当までヤスリがけしたのと同じくらいの表面になるよ!ということです(でいいんだよね?)。1000番までヤスリがけした面程度に整えれば快適に塗装できるということでもあるのでしょう(たぶん)。
同時に浅い傷を埋める機能もありますが今回は割愛。同ブランドで500という数字のモノもありますが、番手が荒くそっちの機能がメインのようなので最初は手を出さない方がいいでしょう。
2-3.その他製品
この他試せていませんがシタデル、ファレホなど海外メーカーのプライマーサーフェイサー、瓶の塗料をスプレーで吹けるようにする『イージーペインター』など選択肢はまだまだあると思いますが今回は割愛。少なくとも導入に関しては高いモノに無理に手を出さなくても問題ないかなとは感じます。とはいえみないいモノということは変わらないと思いますし、今回はプラに絞っていますが他の素材に塗れるようになるというメリットもある(と思う)ので、よろしければ検討してみてください。シタデルの方はショップさんのブログから拝借。
スプレー使用時のさらっとまとめ
スプレーについて軽く総括すると、やはりさすがに溶剤レスというものはなさそうです。使用される溶剤はラッカー系ほどは危険ではないでしょうし、ツンと鼻に来る強めのアルコールという感じですので無茶苦茶不快というわけでもないですが。
屋内で段ボール+紙などの簡易ブースで使用される際には、ムチャクチャ危険ということはないと思いますが、スプレーでの噴霧量もありますししっかりと換気は必要でしょう。屋外での使用の際にも、流れた霧がご近所にご迷惑をかけない程度の場所で吹くか段ボールで仕切りを作るのが無難かと思います。
それらも含め、使用できる環境が構築できるのであれば、先述のツールの使用感も含め第一の選択肢として問題ないと思います。
使用していくうえで空き缶たくさん出るのやだよ!とか煩わしさが出てきたら、そんときは塗装ブースの構築とか筆塗りでの下地作りとか次の一手を考えてみましょう。

3.筆塗りで完結させる
スプレー吹くのは難しい!という方は、(どうにか)筆塗りだけで下地と仕上げを(一応)可能だとは思います。苦しい表現が多くなっているのは少し無理が出てきているということでもあります。まあ生プラで塗れたんだからやってやれないことはないですぜ!たぶん。
3-1.U-35バーニッシュ(ほか絵画用バーニッシュ)
用途:仕上げ
溶剤使用:なし
ここでターナー製品の登場。
筆塗りで作業を完結させるために先に考えなきゃいけないのが、仕上げのトップコート。上述の水性トップコートには瓶タイプもあるのですが、こちらも溶剤成分が強め。一発で筆ムラなく塗れるに越したことはありませんが、筆塗りでの難易度はかなり上がります。下地なら削ったり最悪ドボンすればいいでしょうが、こと仕上げで失敗したら目も当てられません。このうちマットの方はもはや定番となった関節に塗ると保持力が復活するという小技で使うマットバーニッシュそのもの
もちろん筆ムラ自体に気をつけなきゃいけないことは変わりませんし、溶剤成分がない分ガシガシ動かすにはやはり心許ない強度には落ち着く感じすかね。思ったよりかはカッチリした塗膜にはなってくれたんすけどね。
参考になるかはわかりませんが、6年ほど前に塗装し同様に絵画用バーニッシュで仕上げた面を貼っておきます。


3-2.ファレホ ポリウレタンバーニッシュ
用途:仕上げ
溶剤:いくらかマイルド
似たような使用感で使えそうなのがファレホさんから出ているバーニッシュ。ポリウレタンと銘打っているものあって、先ほどのものより強固な塗膜が形成されます。
水での希釈が可能ということもあり溶剤による「泣き」の心配はほぼないとは思います。が、塗膜の形成のためかこれはこれで使用感が独特なんすよね(漠然としてますがなんも考えずに塗ると、大失敗とは行かずとも微妙に濁ったり跡が気になったりとなんか微妙な仕上がりになるというかなんというか……)。いいとこ取りと言いたいところではあるのですが、入手性含め自信を持ってオススメと強く言えないのが辛いところ。結局最後にこれ挙げたけど
未使用なのですが、さっきチラッと挙げたシタデルのコートが存外答えに近かったりするのかなあ。量がね…要検証。
3-3.ヤスリによるサンディング
用途:下地
溶剤:塗料じゃないのでナシ!
下地の方に移りましょう。
先ほどサーフェイサーの項で少し触れた、番手で下地を作るという工程をそのままヤスリでやろうという方法です。いわゆる表面処理ですね。表面処理の必要性というのはしばしガンプラ界隈などで議論されるようですが、今回は色乗らないからやるという明確な目的があるのでキャンセルだ。前述のサフのように、1000番相当に仕上げれば問題ないと思います。逆にディテール、モールドを潰したり余計な傷をつけないためにも、最初は細めの番手に絞っていいでしょう。百均のスポンジヤスリなら細目に入っている600~1000番、3Mのスポンジヤスリならスーパーファイン~ウルトラファインくらいまですかね。1000番だけでヤスるんでもええんかな?後々ゲート処理をやりたくなった際などにも大いに役立つでしょう。
……思い出してみると、私が初めてアクリルガッシュで塗る際にはこの方法でした。塗装とはまた別の作業にはなりますが、入手性含め存外わりと丸い方法なのかもしれません。
当時は何気なくガンプラ製作の方法を真似して四苦八苦しながら百均のスポンジヤスリ片手に進めてましたが、まさか生プラだと色が乗らなかったとは思わなんだ。
3-4.水性サーフェイサー(瓶タイプ)
用途:下地
溶剤使用:あり
先ほどスプレーの方で紹介させていただいたモノの瓶版。エアブラシ塗装の際はエースとしてお世話になっております。
筆塗りでムラなく、また意図せずモールドを潰さないための濃度調整のためにも瓶生のままではなく、水性用のリターダーを併用するなど個人的にはいくらかフォローが必要だと思います(が特にこれは人によって意見分かれそう。瓶生だとモールド潰れるかなとビビりすぎなんかなあ)。
試せてないけどこちらで伸ばすといい使用感になるというのをチラホラ見かけるがどうなんだろう。リターダーが入るなら乾燥時間は伸びるだろうしなあ。
3-5.ファレホプライマー
用途:仕上げ
溶剤:いくらかマイルド
こちらも折衷案として、ファレホさんから出ているバーニッシュもあります。こちらはお値段と入手性にに目をつぶれば(ある程度)自信を持ってオススメできます。私も導入にあたり、何か下地材がないもんかと最初に出会ったのがこちらだったりします。実は色の方は全然使ったことがない
水性サーフェイサー導入後も金属を含めたプライマーも兼ねているので、それらを含めた立体物を製作する際重宝しています。また、グレー白黒以外にも多くの色がラインナップされているので下地にして発色の手助けにも。
ファレホシンナー特有の甘ったるい匂いがしますが刺激臭という意味ではいくらかマイルド。
筆塗りで下地を作るならこちらの方が溶剤成分もマイルドに感じます。水での希釈も可能ですが、前述の金属にも使えるプライマーの成分なのか容器の下に塊になりやすいので、そういったところを掬って誤ってモールドなんかを潰さないように気をつけましょう。とにかくよく振ること。
グリーンスタッフワールドさん、アーミーペインターさんなど、主に海外メーカーのブランドでも同様の商品がいくらかあるようです。それらも合わせ、全ての作業を筆塗りで完結させるのであればこのあたりの水性プライマーと呼ばれるアイテムが……うーん多少入手性に難があることを除けばそこそこオススメすかね(歯切れが悪い)。
3-6.その他製品
まだ試せていないものの中では、アクリジョンベースカラーも筆塗り適性が高いということなので、そのうち試してみたいものの一つです。番手でいうとえらく粗目の表面になるという評判も聞くので不安でもありますが
もう一つ試せていないものの中で気になるツールがあるのですが、オチで使いたいので取っておきます
筆塗りで完結させる際のさらっとまとめ
先ほどよりもちょっと歯切れの悪いまとめになることをご容赦ください。
まず下地は使用感だけで言えば、入手性に少し難は出てきますがファレホプライマーなど海外発水性プライマーが比較的丸いか?ヤスリがけによる作業ができそうなら細目の番手でそちらも検討してみてください。
トップコートはファレホバーニッシュが比較的丸いか?猛練習が必要と言わずとも何も考えずに塗るとん?となりそうというなんとも微妙なラインです。
とりあえずこのあたりをオススメさせていだきますが、もっといいのがあるよ!と最適なのがあれば適宜更新していきたいと思います。あとみなさんがそれ広めてきてください(他力本願)

4.合わせて便利なメディウム
ここまではアクリルガッシュを定着させるための下地と保護するための仕上げについて見てきました。
ここでは、アクリルガッシュを平滑にムラなく筆塗りするために助けとなるメディウムを見ていきましょう。
もちろん、水でといての使用も十分可能ですので、導入時はとりあえずそのまま試してみるのもいいかもしれません。ちょっと前にホビー担当の人も言ってた気がした。同時に、水でも使用可能ということは、より適したツールの用意もあるということでもありますので、導入時に初期投資としてひとつ試してみるのもいいかもしれません。精製水買うくらいならメディウムでいいんじゃないかな
てことで、各社から発売されている数のわりに実際に手に取った種類が多くないことと、最後までまとめた段階でメディウムとスミ入れのことに触れてないことに気付いたのもあって駆け足での紹介になることをご容赦ください。
ホルベイン ペンチングメディウム
用途:アクリルガッシュの希釈
溶剤:なし
現在私が愛用している一品。乳白色をしたシャバシャバのメディウムで、使ってきた中では希釈のしやすさ、平滑に塗るという性能において今のところ満足できているツールとなっております。シタデルカラーの使用感にはあと一歩及ばんけど
ホルベイン ペンチングソルベント
用途:アクリルガッシュの希釈
溶剤:ほんのり
私が導入に際し初めて使用したのがこちら。ほんのり溶剤成分が入っているようです。何回か触れているツンと鼻につく臭いもないわけではないですがマイルド。
最近でも(こちらとは別の溶剤なのですが)ウォーハンマーなどミニチュアの細かい箇所の塗り分け、すぐ発色させたい場合はこういった溶剤成分込みのものも使用も併用しております。
とはいえ、やはり溶剤を使用している以上、特にガンプラなどの平滑な広い面での使用においてムラや泣きは気をつけたいところ。今回のようなプラモでの導入に関しては無理に使用しなくてもいいかも。
シタデルカラー ラーミアンメディウム
用途:アクリルガッシュの希釈
溶剤:なし
こちらもブログから拝借。シタデルカラーでの少し透明感を出したいときのうすめ液という位置付けのようですね。
アクリルガッシュを溶く際にも問題なく使用可。これ混ぜるだけだとシタデルカラー単体での使用感にはもうちょい及ばないけど量は少なめですがヨドバシ通販とか入手製に問題がなければ一手目で導入してもいいかもしれません。量に対して少しお高めですが、上で挙げたメディウム含め筆塗りならそうすぐには使い切らないし、初期投資としてはそんな変わらんかもですね。
https://www.turner.co.jp/brand/u-35_med/n-u-35-mattemdi/
ターナー U-35マットメディウム
用途:アクリルガッシュの希釈
溶剤:なし
今回の張飛ゴッドの塗装で使用させていただいたのがこちら。実は今回初めて使用したものになります。
上で紹介したものに比べてドロっとした粘度で、アクリルガッシュもしっかり溶けます。……なんですが、これ単体で希釈する際にはこの粘度要るか?となっているのが今のところの感想。筆に含んだ水分とかと併用して塗りやすい粘度にせよということなのかもしれません。
溶く際にシャバシャバになりすぎた!など他のメディウムと併用の際は便利かもしれませんが、導入の際にどれか選ぶとするならこれでなくてもいいかも。

5.スミ入れについて
やっとここまで来たぜとりあえずのまとめの前に最後にスミ入れについて。特にガンプラで多用される(スケールモデルでもかな?)モールドの境目に沿ってハッキリとした境界線をつける技法ですね。
こちらに関しては、上で挙げてきたトップコートを使用できるかによって使用できる塗料や方法自体が大きく変わってきます。エナメル系とか別の塗料紹介しなきゃとかいよいよめんどくさくなってきたのであえてスルーしようとも思ったのですが、主にトップコートが可能かを中心に何個か方法を挙げていきたいと思います。丸投げする形にはなってしまいますが、そのうち導入できそうな方法からチョイスしていただければと思います。
5-1.エナメル系塗料
作業前のトップコート:必要
拭き取り:対応するうすめ液によって可
先にネックになりそうな部分をまとめておきます。
強烈ではないが灯油のような匂いがする
それぞれ対応するうすめ液との連携が前提
アクリルガッシュ使用時はトップコート(光沢か半光沢)での補助が必須。プラのままだと侵食して破損する可能性もあるのでどちらにせよほぼ必須か。
以上の要素が何か引っかかる場合は、無理に導入しようとせず下で紹介する2つの方法を検討してみてください。

改めてエナメル系について。まず匂いなんですが、強烈ではないにせよ灯油のような匂いがします。ウェザリングカラーの方は比較的マイルドですが、苦手or苦手そう、特にリビングなどで使用するば無理に導入しなくてもいいかもしれません。程なく止めてしまったのですが、昔エナメル塗料に少し手を出しときに臭いとオカンに怒られたのを思い出しました。あんときはうすめ液も使わずプラに直接塗るとかデンジャラスなことやってたわ。
続いて使用方法。上記の適合表の特性により、ラッカー系もしくは今回紹介してきたアクリル系の水性トップコートによる塗膜を形成しておけば、下地を侵さずに対応するうすめ液できれいに拭き取れます。これによりモールドにだけ色をつけようというのがエナメル系によるスミ入れですね。
拭き取る関係で、逆にザラザラだと拭き取りづらくなるので光沢〜半光沢が適しているようです。塗料を乗せる都合上3割くらいつや消し成分があるのがベストらしい※先ほどの筆塗りで済ます項で仕上げ剤について全体的に歯切れが悪かったのは、そこで紹介したツールでかつ筆塗りでの方法だと拭き取りまで含めると塗膜の強度に若干不安が残る、というのも理由としてあります。
こういうので薄めるのじゃ。性能とペイオフというのはありますがタミヤさんのエナメル溶剤が比較的パーツ破損の危険度が高いらしい。
毛細管現象(というらしい)により、モールドにスッと入ってくれるのも特徴です。こういった特性により、スミ入れでは重宝されておりますし、いわゆるプラモデル用塗料がそれぞれ塗膜の形成がマストみたいになっているのはエナメル塗料との連携が前提なのも理由かもしれません。、似たような特性を持つウェザリングカラーも同様の方法が利用できますので、合わせて紹介させていただいた次第です。
この特性による注意点として、前述のなんたら現象の代償か、プラへの浸食によるパーツ破損の可能性がどうしてもつきまといます。私は実際にもげてしまったということはないのですが、ある程度エナメル溶剤が浸食できない塗膜を形成すれば問題ありませんので、どちらにしても保護面を作ることは必須と言えるでしょう。テンションがかかっているところが特に危ないということなので、関節やダボ穴に負荷がかかっていそうな部分は外して作業した方が無難とのこと。
んで実際の希釈の方法と使用法なのですが(ウェザリングカラーについてはわざと振らずに下に溜まっている濃い顔料を利用する方法もあるので、)詳しく紹介しているところは多くあると思いますので各自ご確認ください。(丸投げすまん)
乾燥した後なら上で挙げてきた水性トップコートが可能ですので、スミ入れした面の保護も問題なし。ウェザリングカラーを使用しているなら、更に汚し塗装にチャレンジしてみるのもいいでしょう。(ごめんこれも気になったら調べてみてね)

※さらに余談ですが、もちろん通常のエナメルカラーはそのまま色として塗ることも可能です。(スミ入れ用だとシャバシャバすぎだしウェザリングカラーは汚し用なので用途が違う)塗膜の弱さ、エナメル塗料だけでは他の色を重ね塗り不可能という短所はありますが、アクリルガッシュ→ここで挙げたツールでトップコート→エナメル系という手順を踏めば、すぐに拭き取れる部分塗装に使える塗料として有効な選択肢になるでしょう。乾燥後にトップコートをすればスミ入れにももちろん移れます。
追加の初期投資としてもそれほど高いものではありませんし、扱い自体は慣れればそれほど難しくありません(何より綺麗に拭き取れると感動する!)。
が、前述の通り臭いを含めてネックになるところも何点かありますので、後述する方法もあり少なくとも初めて塗装する場合は無理に導入しなくても問題ないでしょう。サラッと流すつもりが結局長くなってしまった。別記事とかの方が良かったかなあ

5-2.アクリルガッシュでそのまま塗る

作業前のトップコート:不要(完全にではないが光沢でコートする方法もアリ)
拭き取り:不可。ただし部分塗装していない部分ならマジックリンなどで拭き取り可。
今回の張飛ゴッドくんはこの方法で塗ってみました。細かいところにそのまま描いていこう!
前述のエナメル塗料のように、塗装した面から塗って、はみ出したところを拭き取ることはできません。塗装面にさらにスミ入れする場合は頑張って窪みに色をつけていきましょう。はみ出したら元の色で塗ればいいのです。
完全に拭き取れるわけではありませんが、先ほどエナメル塗料で触れたように一旦光沢でトップコートしてツルツルの面にし、乾燥する前に乾いた綿棒などである程度は拭えます。どちらにせよ乾いたらアウトなので利用するときは気をつけましょう。ツルツルにしたから今度色修正するときに色が乗らないという振り出しに戻るジレンマ。
一方プラの成形色のままの部分(画像では顔や肩の白い部分に黒でスミ入れしたところ)に塗装した際、はみ出した部分はマジックリンやアルカリ電解水などで拭き取ることも可能です。もちろん塗ってあるところにマジックリンがかかったら溶けてしまうので気をつけましょう。


部分塗装せず、モデルの成形色のままでスミ入れだけパパっと仕上げたい!というときはマジックリンをお供とすることで、この方法で済ますことも可能でしょう(強度の心配はあるがなんならスミ入れ目的だけならトップコートもいらんかもしれん)。
また、アクリル系塗料を溶かすもので拭き取っても問題ない、ラッカー系やアクリジョンで塗装した面に拭き取りを使用したい場合にも有効なテクニックとのことです。こ私はやったことないけど
5-3.アクリル系ウォッシング用材
作業前のトップコート:不要(完全にではないが光沢でコートする方法もアリ)
拭き取り:不可。ただし部分塗装していない部分ならマジックリンなどで拭き取り可。
ちょいとめんどくさいことを後に書きますので先にざっくりと。私がはじめての塗装の際使用したのが、上のファレホウォッシング用の塗料というものになります。
同じアクリル系塗料で、アクリルガッシュと使用感は根本的には変わりませんが、元々用途に合わせて希釈されているのもあってより窪みにスッと入ってくれます。アクリル系だけでまとめたい場合はどちらも十分に選択肢に入れていいでしょう。もちろん同じアクリル系の仲間なので塗装面に溶剤で拭き取れないことと、ツルツルの面にすればある程度は拭うことも可能というのも一緒。成形色仕上げの際のお手軽スミ入れ塗料としても一緒だしなんならその目的だけならシェイドカラーやウォッシング塗料だけでもいいかもしれない。
スミ入れ全般のさらっとまとめ
先にスミ入れについて総括すると、追加のトップコートが可能かによって使用できるものが変わってきますので、紹介してきたアイテムと合わせて導入を検討してみてください。自分で書いといてなんですが、拭き取れるかどうかは変わってきますがエナメル系がないとダメ!というわけでもないのですね。
成形色のままでいいならお手軽スミ入れも可能というのも前述の通り。それ目的の導入としても全然アリだと思います。(その場合今度はアクリルガッシュが必須か?という新たな問題は出てくるけど)
5-3についての補足

さっき触れたちょいとめんどくさいこと書きます。が、その前に↑の画像をご覧ください。シタデルカラーのペイントセットに付属していたガイドになります。
画像の2のところで掛けているのがスミ入れ「に近い」作業で、ザックリ言うと赤色の部分に濃い「紫色」で下地が避ける塗料を陰影「に近いところを中心」にかけることで、全体を渋くバッチリ決めようといういう作業になります。ウォッシングという作業も兼ねてるんですねかっこいいですね。濃くなりすぎてしまったところは赤で修正せよという指示もありますが、確かにアクリルガッシュとシタデルベースカラーの隠蔽力をもってすればかけすぎても安心です。

……ご覧いただいたように、5-3で紹介したモノはプラモデルにおける所謂スミ入れとは若干異なる用途を想定した塗料になっております。平たく言うと拭き取りが前提の塗料でないということですね。色も赤に対して黒ではなく紫使っとるし。(こちらもラッカー系で塗ってあれば、マジックリンなどで拭き取れるスミ入れ塗料として選択肢に入りうるとは思いますがこれも余談なのだ)これも語弊があるように言うと模型誌における「きれいな」ガンプラの作例のようにグラデーションをかけることをあまり想定せず、黒もしくはそれに近い色でパキッとしたスミ入れで全体を締める!という用途で使用したい場合、意図せずはみ出してしまった際は元の色を塗り重ねることでカバーする、もしくは何回か触れているようにツルツルの面を作り乾く前に拭き取るという方法に落ち着くでしょうか。
アクリル系塗料で完結させ、陰影をつけると同時に暗くなる部分のグラデーションもしてしまおうという、特にシタデルのペイントシステムの大発明であり、同時にガンプラで使用するにはちょっとしたジレンマになり得る要素なのでそんなこたぁわかってるよ!という方はたくさんいらっしゃるとは思いますが記載させていただきました。私はこうやって言語化しようとした際にやっと最近だんだんわかってきた。初めて使用した際は拭き取れないけどなんでこれスミ入れ用なんだろ?ん?ウォッシング???と首を傾げながらスミ入れっぽく色を置いていった記憶があります。
※全くの余談ですが、ゲームの駒として定義することでそもそもキットを購入する意義を作る、色の明暗を主に3本の塗料で完結させるペイントシステム、さらに工具やプライマー含めた必要な製品を自社内の製品で完結させている某英国企業の販売戦略は悪(以下帝国異端審問官の検閲により削除)

https://www.turner.co.jp/art/u35/colour/
さらなる余談ですが、ターナーさんのU-35などガッシュでない方のアクリル絵の具(紛らわしい)の中でも透明色(さらに紛らわしい)で、ウォッシング塗料と同様の作業をできるか時折試しております。同じ方法で使うならより暗い色の方がいいらしい。少なくとも導入時は手を出さなくてもいいんじゃないかな

・導入にあたってのとりあえずまとめ
はいみなさんお疲れ様でした。色々すっ飛ばしてすばらしいことを見に来た方は改めてこんにちは。ここまで挙げてきたアイテムで、塗装環境は構築できそうでしょうか。
一旦ここらで雑にまとめるなら
スプレーが使用できるならまずは水性プレミアムトップコートで下地と仕上げをご一緒に。
筆塗りで完結させる場合入手性にもよりますが、使用感だけで言えばファレホのバーニッシュとプライマーが比較的丸いか?下地はヤスリがけによる作業ができそうならそちらも検討してみてください。
アクリルガッシュの希釈は水でも可。強いて挙げるなら、今のところ個人的に使用した中でオススメできるのはホルベインのペンチングメディウム。
スミ入れはトップコート次第。エナメル系塗料を併せて導入してもいいが、アクリルガッシュだけorシタデルシェイドカラー、ファレホウォッシングなど環境次第で。
成形色のままでいいならマジックリンでの拭き取りをお供にお手軽スミ入れの塗料としても。
(アクリルガッシュである必要性に?はつくけど)それ目的の導入としても全然アリ。
といったところでしょうか。
https://www.yodobashi.com/product/100000001007203454/
スプレーが使用できるかによって選択肢もだいぶ変わってきますし、もちろん私が挙げた以外にも使用に耐えうるツールはたくさんあると思います。もし愛用しているツールが入ってない!などがあればオススメしていただけると幸いです。
特に筆塗りで完結させる方においては歯切れが悪くなってしまい申し訳ありません。これだ!というツールと出会えればまたお伝えしたいと思います。
参考にならないとは思いますが、私が初めてアクリルガッシュで塗ったキットも貼っておきます。

前々から貼っておりました、HGUCガンキャノン量産型です。アクリルガッシュ(一部ファレホプライマーで下地塗り)で筆塗りしたものになります。 pic.twitter.com/qkOFugfBMD
— F (@FzUjGaA99) August 31, 2018
なぜアクリルガッシュだったのか。実は何かキットを塗ってみたいと思いつつくすぶっていっところ、単純にアクリルガッシュが手元にあって、たまたまTLのどこかからアクリルガッシュで塗ったよ!という作品を見かけたという、今振り返るとだいぶふんわりした理由だったりします。
ついでに今アクリルガッシュをメインとしているのも、→水性ホビーカラー→シタデルカラーと浮気を繰り返した結果、ウォーハンマーという英国産ミニチュアゲームの駒(先ほどチラッと名前出したシタデルカラーを出している会社のですね)であるキットを塗るのにええやん!と、今はたまたま主戦力になっているだけというのもあります。

キットによっては水性ホビーカラーメインにしたりするケースもわりとありますが、まあそんだけいい塗料であるというところは確かです。
締めもだいぶふんわりしたものになってしまいましたが、この記事を通じて、アクリルガッシュとは言わずとも塗装するキッカケになったり、塗装環境の構築に少しでもお役に立てれば幸いです。(書き換える前はエアブラシがどうとか変に力んだ締めになってたのは内緒だ)

・その他導入にあたってのオススメ商品
アクリルガッシュなど筆塗り導入に際し便利そうなツールを紹介しておきます。こちらもこれは最初からあった方がいいんじゃない?というのがあれば共有していただけると幸いです。
先ほどアクリルガッシュによるスミ入れでも触れましたが、切っても切り離せないアクリル塗料全般の相棒。なんかもう2回くらい貼った気がするわ。ツール洗浄は当面これだけでもいいんじゃないかな。今回の張飛くんでも部分塗装で成形色との境目ではみ出した箇所やスミ入れの拭き取りでも活躍したのは前述の通り。
あとキッチン掃除にも使えるらしい。
筆がないと始まらない。アクリル絵の具全般の特性で寿命は短めだし、とりあえずこういうのでいいんじゃないすかね。今回も使用してみたのですが思ったより使えてビックリ。
筆を洗った後の水の拭き取りなどに。最近ダブルの方がいい気がしてきた。食器の水分拭き取りにも使えるとのことですが模型用として用意しといた方がいいね。

以上三点でこういうのを作りましょう。乾燥の速いアクリルガッシュなどエマルジョン系塗料を置いておけるウェットパレットです。
先ほどのマジックリンでの拭き取りに。エナメル塗料のふき取りでも活躍するでしょう。メイクにも使えるらしいです。

これらを組み合わせて持ち手と台にしましょう。爪研ぎにも使えるらしいのでニャンコがいるところでは要注意だ。少しお値段は張りますが↓みたいのもあるようです。
※24/11/30追記
『ネコの爪とぎダンボール製』という製品だとハニカムが大きすぎて竹串は保持できませんのでお気を付けください(一敗)。
溶剤込みの塗料使う際はあると便利な酷使枠。なんでこれ錆びないの……他の用途は思いつきませんが模型全般の塗料を扱うのであればぜひ。
また思い出してよさげなのがあれば追記するかもしれないししないかもしれない。
ダシにするような形にしてごめんなさい。もちろんハンドメイドが気になる方もぜひご検討ください。
ついでに拙い作品ですがよかったら見てやってください。
・果てしなきペイント
まとめみたいのは書いちゃったのではいこっからは完全に蛇足でーす。
うーんあとは下地材として、溶剤レスで筆塗りできるプライマーとかあれば導入として完璧なんすけどねえ。



ペミで
イルた
ンクな
ト
ターナーアクリルガッシュ「くまごろEdithion」でプラモを塗れたよ!ほか2本です。 第一部 完
(こっそり。リスト名の通り!使用後のレビューを保証するものではございません!)
