
散歩と雑学と読書ノート

読書ノート
「ゲノムから進化を考える4 心を生んだ脳の38憶年」
藤田晢也、岩波書店、1997

1 はじめに
本書は、松原謙一と中村桂子の両氏が編集した、「ゲノムから進化を考える」全5巻のなかの4巻目にあたる。やや古い著書であるが、私は最初に読んだ時から心と脳の進化に関する名著であると思っている。またこれほど体系的でわかりやすい類書を少なくとも私は目にしたことはない。
著者の藤田晢也氏は1931年大阪市生まれ、1955年に京都府立医科大学を卒業。アメリカのバーデュ大学分子生物学教室講師、京都府立医科大学の病理学教授、同学長を経て、ルイ・パストゥール医学研究センターに所属。
本書以外の著書に「脳の履歴書 幹細胞と私」(岩波書店、2002)、浅野孝雄との共著で「脳科学のコスモロジー 幹細胞、ニューロン、グリア」(医学書院、2009)と「プシューケーの脳科学 心はグリア・ニューロンのカオスから生まれる」(産業図書、2010)の二冊がある。いずれも名著である。
私はこれまでも、noteに「こころ」と「脳」の関連を念頭に幾つかの記事を書いてきた。体系的にこのテーマを述べるだけの能力を持ち合わせてはいないが、今回を一回目として今後「心と脳の風景」と名づけておいて、私なりにこのテーマに沿って、少しまとまりのある記事を不定期になると思うが書いてみたいと考えている。
この読書ノートをその序章と位置づけておきたいと思う。そのために、私はいつものやり方で、内容に思い切り踏み込んだ読書ノートにさせていただこうと思う。
生成AIが巧みに要約してくれるこの時代に私のこのような読書ノートの試みに果たしてどれほどの意味があるのかと「ふっと」思うことがある。それでも続けてみようと思っている。私は偉大な先人や先輩たちの業績にふれながらほんのわずかでも自分なりの考えや発見を追加してみようという試みに、かりに失敗に終わるだけとしても、ささやかながら意味があるだろうと考えている。
本書の目次をみると、「プロローグ 心とはなにか」「1 脳の進化の始まり」「2 合目的性の出現と進化」「3 脳の基本デザイン」「4 脳のサイズからみた脳の進化」「5 皮質の出現」「6 ヒトの脳への進化」「7 人間の英知の発達と心」「エピローグ 脳と心の哲学」となっている。
今回は「ヒトの脳への進化」までを見ていきたいと思う。
2「プロローグ 心とはなにか」
プロローグでは自分の心や他者の心とは何か、動物に心はあるのか、意識とは何か自己とは何か、こうした「心とは何か」という問題を、とくに脳の進化の中で考えてみようと述べられている。
大きなテーマなのでこれから私なりにこの点に関して進化という視点からのみでなく、様々な角度から言及できたらと思っている。
3「脳の進化の始まり」
38憶年の生命の歴史の中で、神経系を初めて獲得したのはカンブリア紀(約5億4100万年前~4億8500万年前)の原始脊策動物である。その系譜に当たるものとして現存している生物の中では、ホヤの幼生に類似するものであったろうということで学者の意見が一致している、と藤田は述べている。
ホヤの幼生は、体はオタマジャクシの形をして、中心に一本の脊索が通り、その背側に神経管という管状の構造がある。その頭端はかるく嚢状に膨れていて脳にあたる。脊索の両側には筋肉細胞が整然と並び、体表は表皮が覆っている。カンブリア紀に出現した原始脊索動物はこのホヤの幼生と類似していて、ホヤをはじめ人間を含めた脊椎動物すべての最初の祖先であったと見られている。
ホヤの幼生のニューロンは脳胞の後半を占める大脳神経節の中にあり、軸索は脊髄の中を束になって走っているだけでほとんど髄管を出ない。髄管の表面に密着した筋肉細胞と神経筋接合をつくり、アセチルコリンを介して信号を伝えている。
ホヤのニューロンの数は数百で、大脳神経節はリズミカルなビートを作り出す神経興奮を発生させる。おそらく脳胞からの視覚、平衡覚、臭覚の入力を受けていて、出力としてビートを制御する機能も持っていると思われる。これは脊椎動物の基本的な生命現象をささえる脳幹網様体の原型とも考えられる。
幼生は明るい方へ、上の方へ泳いでいこうする目的を持った自発的な行動を行う。これは欲望を持つということと同じで、ホヤの個体がそれをどの程度の明晰さで理解し認識しているかは別にして、心の原型あるいは前段階と考えて差し支えないと考えられると藤田は言う。
付記
1)
私は以前(2022.9.8) noteに最古の脊柱動物、魚の脳について記事を書いたことがある。それをここで少し加筆修正したうえで引用させてもらいたい。
「エディアカラ紀・カンブリア紀の生物」(群馬県立自然史博物館、監修
土屋 健著、技術評論社、2013) に書かれていたものの紹介である。
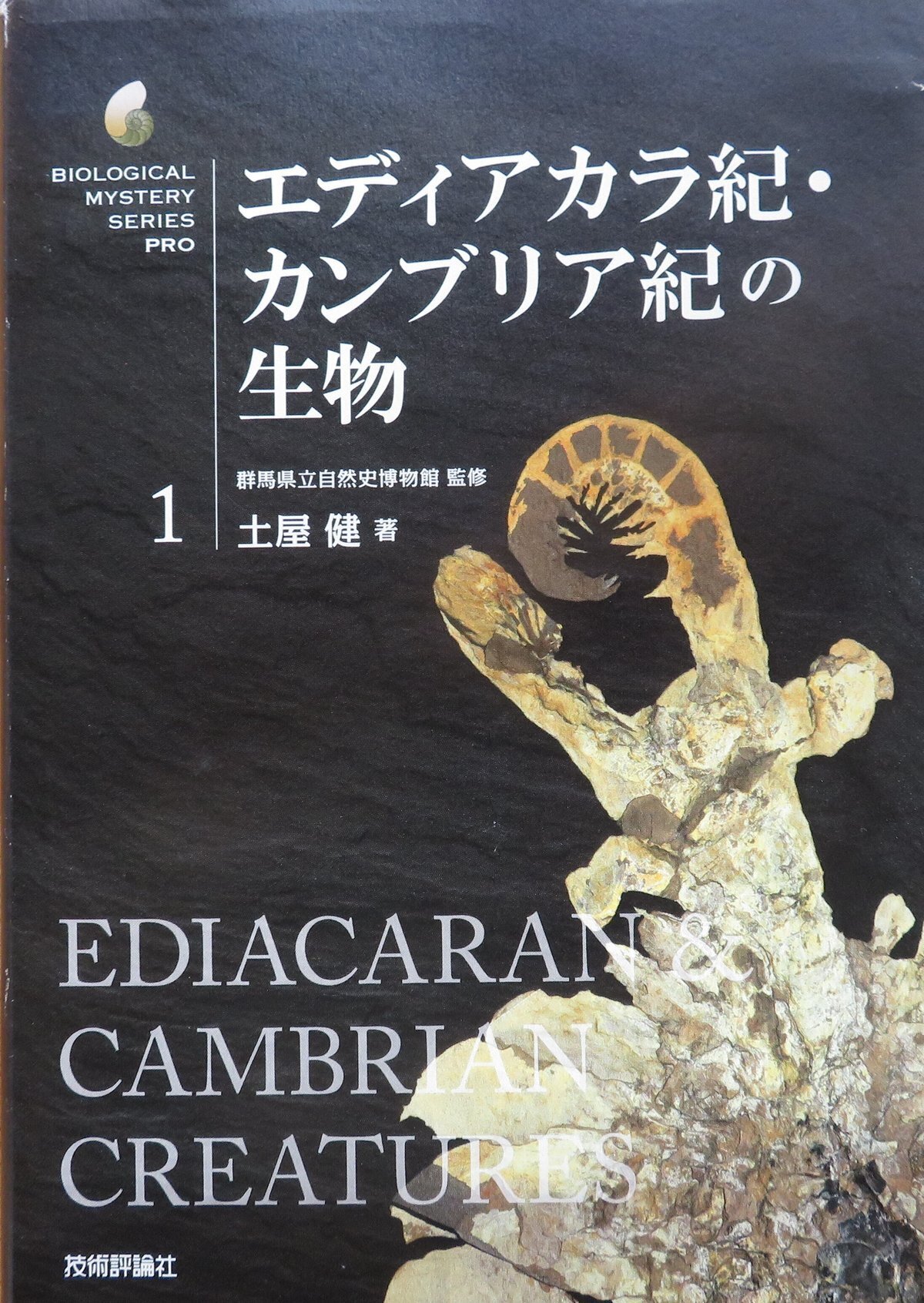
(群馬県立自然史博物館、監修土屋 健著、技術評論社、2013)

(ミロクンミンギアの復元図、90ページ)
現在わかっている限りで、最古の脊椎動物は、1999年に中国のカンブリア紀の岩石から見つかった「最古の魚」で、5億2000万年前のカンブリア紀のもの。ミロクンミンギアとハイコウイクティスと名付けられた。2~3㎝の大きさで、背びれをもって泳いでいたとみられている。眼や口や耳や鼻や鰓をもち視覚、聴覚、嗅覚などの知覚系を備えていたのだろう。明確な「頭部」があり、中には生殖器や消化管の痕跡が確認できるものもある。ハイコウイクティスは100個体以上が群れを組んで生活していたとみられている。現在も生き残っているヤツメウナギのように「あご」のない「無顎類」で、ある程度の硬さのある獲物は捕らえられなかったとみられている。
この「最古の魚」が発見されるまでは、カナダのパージェス頁岩(カンブリア紀の化石の宝庫)で発見されていた、脊索動物の一種であるピカイアが魚類から人間にまでつながる脊椎動物の唯一の祖先候補であった。有名な古生物学者、進化生物学者のグールドがカンブリア紀をめぐる著書「ワンダフル・ライフ」のなかで、強くもなさそうなピカイア(もしくは、その近縁の仲間)が、偶然にも生き延びたことによって、人類へとつながる命脈が保たれたと述べている。
「目の誕生」はカンブリア爆発の、最も重要な出来事の一つである。アンドリュー・パーカーが「目の誕生」(草思社、2003)という著書で「光スイッチ説」という自説を展開して詳しくふれている。三葉虫をはじめカンブリア紀の節足動物の多くが目をそなえていた。中には、5個の目を備えたものや、現在のトンボとそん色のない数のレンズを備えたものもいた。
この時期に視覚という遠隔知覚が発達していたことは驚くべきことだとあらためて私は感じる。カンブリア紀の後に出現した魚類や両生類は嗅覚を中心に生存していたと考えられているようだが、カンブリア紀ではどうだったのだろうか。視覚が重要な意味を担っていたようにも思われる。さらに聴覚、触覚などもすでにそなえていたようである。それらの知覚処理はどのようになされていたのだろうか。今後さらに当時の動物の中枢神経系の研究が進展することを期待したいと思う。
2)
トッド・E・ファインバーグ、ジョン・M・マラッドは、彼らの著書「意識の進化的起源 カンブリア爆発で心は生まれた」、勁草書房、2017、および「意識の神秘を暴く 脳と心の生命史」、勁草書房、2020、のなかで意識の進化に関して興味深い説を展開している。
彼らは原初的な心(意識や情感)をカンブリア紀の生物が獲得していたと考えられると述べている。いろいろと考えさせられるこの著書に関しては別な機会にも取り上げることができたらと思っている。また私が関心を持つシェリントンのいう脳の遠隔知覚の特徴である投影性(著書の中では参照性とされている)もこの時期に獲得されていたと彼らは述べている。その参照性という神経系の特徴をファインバーグらは次のように適格に記述しているので引用しておきたい。
意識経験が脳自体を参照することはない。つまり、いかなる経験も脳内のニューロン(神経細胞)の発火として知覚されず、主観では発火にまったく気づかない。むしろ経験は、外の世界の何かや、体表や体内の何かを指し示すよう参照されるのである。この参照性は、「心的イメージ」として外的世界へと投影される外受容的経験や、また体内の状態を部分的ないし全体的に経験する内受容的経験および感情的経験の特徴となる。
「意識の進化的起源
カンブリア爆発で心は生まれた」(7ページ)
4 合目的性の出現と進化
38億年前の原始地球上に有機分子が安定して存在しうる条件が整って、始生代が始まり、生命を担う分子グループが出現すようになってから3億年ほどで単細胞生物(嫌気性バクテリア)が創造されたのは驚くべき早さだったといえる。それから脊索動物の出現(カンブリア紀)まで、なんと原生代の約29憶年の歳月がかかった。

生命の基本的な性質は、①自発性をもって行動すること、②自分自身を存在させ続けること、および③自分自身と同じものを生産することである。始原代に出現したRNP(RNAとタンパク質の複合体)ワールドは少なくとも②と③の条件を満足している。なお今日の生命の基本的なコードを担うDNAはRNA複製酵素から変異した逆転写酵素によってRNAをもとに作られた。
自己複製を安定して担えるDNA・RNA・タンパク質合成系の分子群を内包し、膜につつまれて自発的な合目的行動が行える原始細胞が形成されるまでには多くのトライアンドエラーが繰り返された。原始細胞は膜を介して外部との間で情報を伝達しあい、生存のために合目的な自由運動をおこなっていた。すなわち細胞一個でも可能な感覚、運動、その制御の機能を進化させていた。
約6億年に始まったカンブリア紀以前に出現した多細胞動物はおそらく多数の細胞が接着して集塊を形成していただけだが、カンブリア紀に出現した多細胞動物では細胞間の機能分担が可能になり、感覚と運動を分担する細胞が分化していった。運動機能は筋肉細胞が分担、外胚葉をつくる細胞から細長い軸索を備えたニューロン(神経細胞)が分化して、外界の刺激を受けてアセチルコリンなどの伝達物質を分泌して筋肉細胞を収縮させていた。
アセチルコリンのように、今日の生物が利用している神経伝達物質の少なくとも一部はニューロンが形成される以前に原始の海の中で作られていたと考えられている。
さてニューロンは単純なものからさまざまな形のものへと進化していった。そうしたニューロンの集まりが、節足動物のダンゴを串刺しにしたような神経節の神経系や腔腸動物の網状の神経系を作り上げていった。
こうしたニューロン集団の作る体制は脊椎動物になると一変した。
脊椎動物の脳では、第一にマトリックス細胞という中枢神経系全体の母体細胞を創造した。そして、第二にそのマトリックス細胞を上皮組織のシートの形に配列し、それを巻いてできあがった神経管という構造を脳発生の出発点にした。このデザインを採用したことが脊椎動物のその後の中枢神経系が高度に発展する可能性を与えた。
5 脳の基本デザイン
たぶん5億年ほど前のカンブリア紀の前半には、ホヤの幼生のような単体節の原始脊索動物の次を担う多体節脊索動物が現れた。その当時の生物と近縁の生物が現存のナメクジウオである。ナメクジウオの中枢神経系は頭端で膨れてはいないが、多数のニューロンが集中して機能的な脳をつくっている。その後方に続く脊髄は多くの運動・感覚ニューロンや反対側に情報を伝える交差ニューロンを含んで、脳の先端から脊髄の末端まで、交互に規則正しく感覚性神経と運動神経が出る構造を確立した。ただし、本当の末梢神経は次の魚の時代になって初めてつくられた。
ナメクジウオの運動は躯幹筋を交互に収縮させ体をS字状にくねらせるものである。この運動はカンブリア紀にナメクジウオのような原始脊索動物が発生したときに成立した。それはその後の脊椎動物が水中を泳ぐ基本的なパターンである。S字運動の交互のリズムの制御には同じ側を上下するニューロンのほかに、索ニューロンとよばれる交差性のニューロンが有効にはたらいたと考えられている。
この交差性という性質は魚や有尾両生類の延髄にある巨大なマウトナーニューロンによって体現されていた。人間を含めてすべての脊椎動物にみられる神経交差の体制はこのマウトナーニューロンの遺伝子機構が現在も存続していることを示している。
古生代が進行してシルル紀に入ると(約4億3000万年前)原始魚類(円口類)に大きな変化が現れた。鰓の一番先端が顎骨を備えた強力な顎に進化したのである。顎のある魚類が出現したときに、脳神経の体制はすべての現存する脊椎動物に共通するパターンとして確立した。
デボン紀(約4億年前)の化石として見つかった魚(ユーステノプテロン)の脳もヒトと共通していることがわかり、12本の脳神経はヒトと同じ順番に並んでいたことが分かったという。ただし大きな違いは大脳の構造が匂いを嗅ぐだけの中枢で原始的でサイズも小さいため終脳とよばれていることである。この「ユーステノプテロン」の脳の構造は、終脳(大脳)、間脳、中脳、後脳(小脳)、延髄、脊髄の順に並んでいる。中脳の腹側と延髄は脳幹と呼ばれる。そこには脳幹賦活敬とよばれるニューロンの集団があり、脳幹網様体ともいわれて、呼吸や心臓の働き、S字運動、生殖行動、食欲などを調整し匂いや視覚などの感覚情報がその行動を適切に制御している。
このような脳の神経管とそこかつくりだされる基本的なパターンは現在の広範囲に生息する脊椎動物にそのまま引き継がれている。脳の基本的な設計がこの原始的な魚において決定されたということは驚くべきことだ。
魚から両生類への移行はエポックメイキングな出来事であった。水辺から陸地の広大で豊かな生態的地位が脊椎動物に約束されるようになったからである。しかし脳の進化から見るとこの変化に対してはほんのわずかの変化で対応しただけであった。
6 脳のサイズからみた脳の進化
19世紀末のドイツの精神科医スネルが動物の脳のサイズの意味を考えて、脳の重さと体表面積との比をとって、その値が「精神因子」というべき数値で、精神活動のより高等なものほど大きい値をとると考えた。
スネルは人間の60㎏の体重に換算した動物の脳のサイズの値をPとした。人間のPを1374とすると、魚は3.27から23.5のあいだ、ラットが79、馬が178、犬が203、象が254、イルカが291、チンパンジーが484といった値になる。化石からの計算でティラノサウルスは10.15となった。
本書で藤田はこのスネルの精神因子Pの値を重視しながら脳の進化について述べている。
藤田は化石両生類や恐竜のような化石爬虫類はほとんど現生の魚類・両生類・爬虫類とほぼ同じ値のP(2.8から23.5)に入ることが見出されていると述べている。カンブリア紀の脊椎動物が出現した後さらに3億年続いた古生代で脳のサイズは大きく増加していないということである。最も爬虫類の脳ではそれまでの魚類と比べて嗅覚以外の中枢(視覚や聴覚)が出現していたてんに質的な違いがみられている。
白亜紀の末(約6500万年前)に全地球を襲った気象の大変化(小惑星の衝突による寒冷化)に適応できない恐竜を含むほとんどの爬虫類が絶滅し、体温の恒常性を獲得した原始哺乳類が適応して次第に増加していった。
新生代の初めの暁新生・始新生(約6500万年前から3600万年前)の初期哺乳類のPは平均してほぼ43であることが分かった。次の1000万年で86となり、さらにその時点から現在までの2600万年のあいだで170のレベルにまで進化した。
哺乳類のこの脳容量の増加は、主として大脳半球の成長による。爬虫類の脳にはなかった新しいニューロン集団が新皮質として現れた。
この新皮質クローンがつくるニューロンは、形態的には皮質のなかに6層構造を作り、視覚や聴覚や触覚・筋肉や関節の知覚などの体性感覚系の入力を受け、皮質内部や間脳のニューロンと密な相互結合をつくり、脳幹や脊髄の運動ニューロンを支配する上位制御系を形成していた。旧皮質や古皮質が嗅覚系入力を主体としていたのとは違いがある。
スネルの精神因子の増大はもっぱらこの新皮質の増加によって実現されたものである。中世代末期から新世代の7000万年以上に及ぶ期間で、哺乳類と若干でも似た脳容積の増加を示したのは鳥類のみであった。ちなみに鳥の中で最大の脳容量を持つのはカラスでPは238にまで達している。この値は先に述べたが、現存の哺乳類のPの平均値(約170)を凌駕している。
魚類や両生類や爬虫類は脳容量の増大を示すことができず、知能を活用した生態的地位のすべてを、哺乳類と鳥類のために明け渡すことになった。
付記
哺乳類と鳥類以外に無脊椎動物の中で頭足類(タコやイカなど)が複雑な神経系を獲得してきたことが知られるようになってきた。また昆虫も優れた知性を備え、米粒のような脳で人間とは異なる仕方で知覚や認知を行い、苦痛や喜びを感じている可能性が示唆されている。ここではタコについて拙著「こころの風景、脳の風景Ⅱ」の「読書ノート」より引用しておきたい
「タコの心身問題 頭足類から考える意識の起源」
ピーター・ゴドフリ=スミス著、みすず書房、2018年11月
著者は哲学者で練達のダイバー。無脊椎動物の中で唯一、頭足類(タコやイカ)が、ヒトやトリとはまったく異なるルートで複雑な神経系を獲得してきたことを、私は本書によってはじめて知った。タコは極めて好奇心旺盛な生き物であり、その腕には中枢からは独立して作動する神経系があるという。またある種のイカにはエピソード記憶のようなものが観察されるという。神経系は感覚と運動のループを仲介する役割を担いながら多くの能力を進化させてきた。確かにまるで地球外の知的生命体のようなタコの神経系の研究はこれからもヒトの意識や感情や記憶の起源を考えるうえで大きな刺激を与えてくれるだろう。またタコは二歳くらいで急速に老化し死んでしまうという、老化のメカニズムの研究にもタコは極めて興味深い生き物である。
7 皮質の出現
皮質は、ニューロンの集団が厚さほぼ一定の層状の配列をとり、脳の表面に接して広がったもので、哺乳類では大脳と小脳の皮質が顕著に発達。鳥類や爬虫類・両生類・魚類では大脳皮質の発達は不完全で、もっぱら小脳と中脳視蓋にみられるだけである。
脊椎動物の中枢神経系は、初期胚に現れる神経管に由来する。神経管は上皮性の管で、この管の壁は放射状にぎっしりと詰まったボーリングのビン状の細胞からつくられている。この細胞は見かけも機能も均一のマトリックス細胞である。この細胞は発生初期から管の内側の脳室に面した場所でだけ活発に増殖する。この細胞は分裂の周期に合わせてエレベーターのように上下運動をする。
藤田はこのマトリクス細胞説を中心に胎児と生後の早い時期に脳の構造がどのように作られていくのかを述べている。藤田の専門分野であり、なかなか興味深いのだが、ここでは詳細は省略させていただき、簡単に触れるだけにさせていただく。
皮質の発生の第一期ではマトリックス細胞が増殖を繰り返す。第二期になって、そのマトリックス細胞から次々と作り出されるニューロブラストが、マトリックス細胞の突起の束をレーンとしてエレベータ運動をしながら、脳の表面に6層をなして並び、円柱状(コラム)の機能単位を形成する。第三期ではマトリックス細胞からグリア細胞が分化してくる。さらに皮質には血管が侵入してくる。
こうした人間の脳の発生の問題も含めて、脳の構造と機能に関しては別の機会にふれたいと思う。
、
8 ヒトの脳への進化
脳の容量の増加からみて、哺乳類の中でも群れを抜いて早い進歩を示したのは霊長類である。小型の夜行性動物であるリスとネズミに似た霊長類が哺乳類から分かれたのは白亜紀(約7000万年前)のころである。
この霊長類の祖先は森林地帯の木の梢に住み、小枝の間を動き回って、昆虫や木の実を常食としていた。おそらく突然変異によって彼らの中から遠隔性知覚である視覚と聴覚が充実し、特に両眼視によって距離感を正確に把握し、手を使ったつかまり運動が上手なものが出現して生態的地位を占めていったと思われる。この当時の霊長類の脳容量は現生の食虫目に属するハリネズミのP71に近かったと想像されている。
今から5000万年前の始新生に由来する霊長類であるキツネザルの化石が見つかっているが、そのスネルの精神因子Pは150で、当時の哺乳類の平均値43と比較してずば抜けて大きい値を示している。後頭葉の視覚中枢や前頭葉・頭頂葉の運動中枢がかなりの程度まで進化していたと推定される。
霊長類の二大分岐の一つである真猿亜目の共通の祖先から、終局的にはヒトへと向かう進化が開始されたのは、約3500万年から2500万年前の漸新世のアフリカ大陸であったとみられている。しかし当時の様子を知る完全な頭蓋が見つかっておらず、散発的にヒト的な猿が現れ直立傾向を示し、脳の容量も増えていったと思われるが、環境に充分適応できずに消えていったと考えられている。3600万年前から400万年前の間、ヒト的な化石がまったく発見されていない。
脳におけるヒト化は350万年前に生存していたアウストラロピテクス・アファレンシスからだろうと見られている。
さらに約220万年前の地層から発見された化石がヒトへの進化の経路にかなり近いものと見られている。アウストラロピテクス・アフリカヌスで、化石は6歳くらいの子供(タウングス・ベイビー)と見られている。発見者のダートはその頭蓋骨の化石のカーストから、月状溝やシルヴィウス裂を読み解きその位置がサル脳よりもヒト脳により近いと指摘している。また計算されたPの値は557でチンパンジーより少し大きい値であった。
200万年前に出現したホモ・ハピリスはアウストラロピテクス同様に直立二足歩行を行い、連合野はさらに増加し、ブローカ野(言語の運動中枢)が認められている。このことからホロウェイは、ホモ・ハピリスこそ「言語を話すことのできる最初の原始人だった」と述べているが、必ずしもすべての学者の賛同を得てはいない。またPの値は741にも増加している。
350万年前のアウストラロピテクス・アファレンシスから現在のヒトの脳までの進化がどのようになされたのかを見るうえで、藤田はタンパク質やDNAが劇的に変化したという証拠は見つかっていないとしている。そのうえで、残る可能性としてマトリックス細胞の増殖からみた進化の可能性について述べている。
つまり、第一期のマトリックス細胞増殖や第二期のニューロン産生の時間が延長するように突然変異が固定することによって、脳のサイズが増加するように進化した可能性があること。さらにマトリックス細胞のサブクローンの分化による質的な進化がみられることが指摘されている。
そもそも新皮質そのものが旧皮質のマトリックス細胞の枝分かれしたサブクローンによって創造されたものである。視覚中枢についてみておくと、ブロードマンの大脳構築マップによる後頭葉17野は、視覚の第一次中枢で聴覚とは直接つながらない、17野は霊長類の進化の初めから現在までの約3500万年のあいだ、後頭葉の広い領域を占めて保存されてきた。その17野を親クローンとしてサブクローンである18野が分岐し、さらに18野が次のサブクローンである19野を発芽させた見られている。このように新皮質が増大し新たに視覚機能を獲得しその間の連合も強めていった。
ヒトの脳への進化を着実に進めたのは、ホモ・エレクティス(直立原人)でアフリカでは約150万年前に、ジャワ島では約70万年前(ジャワ原人、Pは992)、中国では約50万年前(北京原人、Pは1212)に出現している。
ホモ・エレクティスは頭蓋の形態からヒトの言語中枢に相当する原始的な構造を獲得していたと考えられている。また火を扱い、骨から作った道具や石器を使っていたといわれている。彼らが集団内で何らかのコミュニケーションを行っていたとみられているがどのようなものかは不明ではある。身振りや発声などを通じて火の管理などをおこなっていたのだろう。
ヒトの脳の進化で次の時代を代表するものは10万年前から出現したネアンデルタール人と3万5000年前の化石から命名されたホモ・サピエンス・サピエンス(現代人)である。脳の容量と形態に両者の間には多くの共通てんがある。しかし、脳の構造の細部においては現代の人のものとは多少の違いがあると言われている。ともあれ、両者は一つの種の種内変異体にすぎないと見られている。本書の記載にはないが、実際両者は一時共存していて交配も行われていたことが知られている。
新型コロナが流行していた2020年9月30日のNature誌に、ドイツの研究者ベーボ博士が発表した論文にそのことと関連したことが述べられていて、驚いた記憶がまだ生々しい。記事によると、すでに新型コロナウイルスホストジェネティクスイニシアチブでは、3番染色体のある領域の遺伝子の多様体(バリアント)が重症化リスクを高める(人工呼吸器を必要とする可能性が3倍になる)ことが分かっていたが、ベーボ博士の研究によると、この領域の遺伝子組成が5~6万年前に交配したネアンデルタール人がもたらしたものであることが分かった。しかも、南欧で発見されたネアンデール人の遺伝子にはそれは存在していたが、シベリアでのネアンデール人の遺伝子やデニソワ人の遺伝子には見いだせなかった。さらに、興味深いことに、この遺伝子バリアントは欧米や南アジアの人種には見いだせるが、東アジアやアフリカの人種には見られなかったという。
ネアンデルタール人は4万年ほど前に絶滅した。その理由は、感染症によるという説もあるが必ずしもはっきりはしない。
アウストラロピテクスからこれまでの脳の皮質の進化を見ると、比較的な意味で大きかった感覚野や運動野が脳全体のサイズの成長と同じ速さで成長せず、結果として縮小整理され、ゆっくりと連合野をつくるマトリックス細胞のサブクローン増殖が上回っていく。進化の年月の間でサブクローンの分裂回数の増加に差が生じ大脳皮質各部の連合野が拡大していった。そのなかでも言語中枢の発達が中心的であった。それがヒトへの進化の最大の特徴であった。
9 おわりに
本書はこの後さらに「人間の英知の発達と心」そして「エピローグー脳と心の哲学」へと続くが言及することは省略させていただいた。
私は心の進化にとって「言語とコミュニケーション」の発達が最も重要と考える。そのことは別の機会の課題としておきたい。
もう一つ私の関心事をあげておきたい。それは「知覚システム」の進化に関してである。すでに述べたことであるが、カンブリア紀に生命が初めて神経系獲得をなしたときの最もエキサイティングな出来事は目の獲得を通じて得られたた視覚系の進化である。その視覚系は当時すでに聴覚や嗅覚、触覚など他の知覚系と協働するシステムを形成して、現存生物の知覚の原型を獲得していた。
私はヒトの知覚系の仕組みに関心を持っている。その原型が5億年も前に出来あがっていたということに私は進化の奥深さと生命の不思議を感じている。知覚の脳科学にはまだまだ謎の部分が多い。自動運転車のような機械による知覚的仕組みも含めてさらに考えてみたいと思っている。
