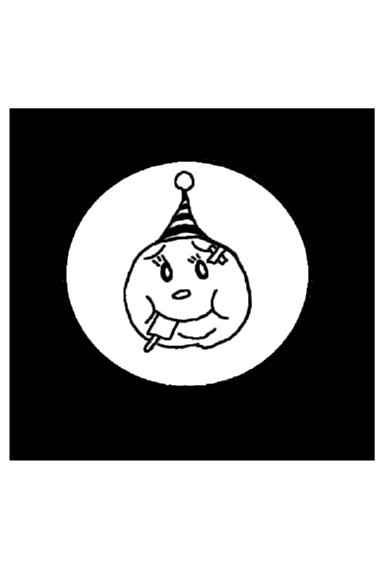『パーラー・ボーイ君、補助輪を外す』
ある日のお昼すぎ、パーラー・ボーイ君は自分の自転車のわきにしゃがみ込んで、モンキーレンチ片手に四苦八苦していました。
最近、午後になると、ポップな車でアイスクリームを売りにくる屋台がパーラー・ボーイ君の家の前を通りすぎます。
パーラー・ボーイ君は、アイスクリーム屋さんの基地が知りたくて、毎日、自転車で車の後を追いかけますが、19番ストリートを右折するときに、補助輪が付いていると、重心を右にかけても車体が思うように傾かず、コーナーをタイトに曲がり切ることが出来ません。
そのせいで、コンマ3秒ほどロスしてしまい、先にある信号にギリギリで引っかかってしまうのです。いつもその信号でアイスクリーム屋さんの車を見失ってしまいます。
パーラー・ボーイ君は最初、お父さんに補助輪を外してくれるように頼みましたが、お父さんは、「パーラー・ボーイ君は、まだ小さいからダメだよ」と言って、聞いてくれませんでした。
しかし、ダメだと言われて、素直にあきらめるパーラー・ボーイ君じゃありません。それならばと、自分で補助輪を外そうとしているのですが、なかなか上手く出来ません。
そこへ、友達のハインツ・ハラルド君がやって来ました。ハラルド君は半年前にドイツから引っ越してきた男の子です。
「グーテンターク、パーラーボーイ君。ボクがやってあげるよ」
ハラルド君はパーラー・ボーイ君からレンチを受け取ると、器用に補助輪を外しました。さすが、マイスター制度の在る国からやって来ただけのことはあります。
「見たところ、君の自転車は日本製の様だね。まあ、日本製も悪くはないけど、どうせなら、たとえ自転車であっても、車と名のつくものは、ドイツ製を選ぶことをオススメするよ。現にオリンピックでもドイツはチームスプリントで日本をやぶって――」
子どもながらに、ゲルマン魂のかたまりであるハラルド君がお国自慢を長々としているうちに、アイスクリームの屋台がやって来ました。
パーラー・ボーイ君はすぐさま自転車に飛び乗り、屋台の後を追おうとしましたが、初めてコマなし自転車に乗るパーラー・ボーイ君は、少しも進まないうちにコケてしまいました。
ヒザや、オデコを擦りむいてしまったパーラー・ボーイ君。
「大丈夫!? パ―ラー・ボーイ君!!」
ハラルド君は心配そうです。
「ボクの家に来なよ。ドイツ製のクスリを塗ってあげるよ。ドイツはメディカルの面でも世界一の国だから、きっとよく効くよ」
ハラルド君の心配をよそに、パーラー・ボーイ君はオデコをおさえながら、テレくさそうに笑いました。

その日の夕方、仕事から帰ってきたお父さんは、パーラー・ボーイ君がオデコにカットバンを貼っているのを見て、
(また、なにかヤンチャ遊びをして、ケガしたんだな)
と察しました。
お母さんからケガの理由を聞いたお父さんは、
(この子は言っても聞かないな)
と、あきらめて、それならせめて出来るだけ痛い思いをしないように、今から自分が自転車の乗り方をレクチャーしてあげようと思いたち、
「もうすぐ晩ゴハン出来るのよ」
と言う、お母さんの声を無視して、パーラー・ボーイ君を外へ連れ出しました。
「パーラー・ボーイ君、お父さんが後ろ押さえていてあげるから、思いっきりペダルを踏んでごらん」
パーラー・ボーイ君が言われたとおりに自転車を漕ぎだすと、お父さんも後ろを持ちながら一緒に走りだしました。
最初はグラグラしていた自転車の動きが、しだいに安定してくると、お父さんは、
「パーラー・ボーイ君。お父さん手はなすからね」
と声をかけました。
“コクン”とうなずくパーラー・ボーイ君。
しかし、いざ手を離す瞬間になると、お父さんは、
(パーラー・ボーイ君、もしコケたらどうしよう。かわいそうだな)
という思いが湧いてきて、なかなか手を離せません。
(もしコケて痛い思いしたら、パーラー・ボーイ君、お父さんのことキライになっちゃうんじゃないかな。もう一緒に朝のウォーキングやってくれなくなったら寂しいなぁ)とか、
(パーラー・ボーイ君にケガさせたら、お母さんに怒られちゃうな、そしたら、一緒にお風呂入ってくれなくなるのかな)とか、後ろ向きなことを考えている内に、お父さんは完全に、手を離すタイミングを逃してしまい、気がつくと30分近く、5キロ以上の距離を自転車の後ろを押さえた状態で走っていました。
お父さんが疲れていくのと反比例して、パーラー・ボーイ君は何かコツをつかんだのか、自転車のスピードはドンドン上がっていきます。
「パーラー・ボーイ君、パーラー・ボーイ君! もっとゆっくりでいいから。もっとゆっくりでいいから!」
お父さんの叫びなどお構いなしに、パーラー・ボーイ君はグイグイ自転車を漕ぎます。
力尽きたお父さんは、ついに自転車から手を離して倒れました。
お父さんの手から離れた自転車は、〝フラフラ〟と、あやういながらも何とかバランスを保ち進んでいきます。
「パーラー・ボーイ君! 乗ってるよ! 自転車のれてるよ!!」
お父さんは大喜びで地面から飛び起きました。転んだ拍子にズボンが破れてしまっていますが気になりません。
パーラー・ボーイ君も嬉しくて、いつもの笑顔がこの時は3割増しです。
ゆれながら進む自転車のヨコを、偶然にあのアイスクリームの屋台が通りすぎていきました。
向こう見ずな性格のパーラー・ボーイ君は、迷わずに後を追いかけました。
けれども、アイスクリーム屋さんはこの時すでに仕事を終えて、会社に戻る途中なので、営業用のながし運転とは違います。とてもパーラー・ボーイ君のような子どものあしで、追いかけられるスピードではありません。
それでもパーラ・ボーイ君は必死で追いかけて、一生懸命に自転車を漕ぎすぎたせいで、バランスをくずし転んでしまいました。
遠ざかっていく車が、やがて見えなくなると、パーラー・ボーイ君は地面に打ちつけた場所とは違う、体の中のどこか別の所が痛むのを感じました。
☆
帰り道、小さなお店でお父さんに買ってもらったアイスクリームを食べながら、2人で自転車を押して歩いていると、お父さんの携帯にお母さんから電話が掛かってきました。
「料理がもう冷めちゃったわよ、早く帰ってきなさい!」
怒っている声が受話器からもれて、パーラー・ボーイ君にも聞こえてきます。
お父さんは慌てて、パーラー・ボーイ君のことを後ろに乗せ、自分でパーラー・ボーイ君の子ども用の小さな自転車を漕いで家へ向かいました。
パーラー・ボーイ君は自転車の後ろで、アイスをほおばりながら、こころの中で、
「明日もいっしょに自転車のる練習しようね、お父さん」と言いました。