
言語学版 ガリレオ ch.3
第3章 ネガティビティー・バイアス
「考えるという行為は、人間に与えられた最大の楽しみだ」
しかし、「考えすぎない」ことが大事だと主張している本がある。

この本では、「考えすぎない」ことの重要性をいろんな仮説に基づいて考察している。
その数、45。 どの仮説も「実に興味深い」。
その1つに「ネガティビティー・バイアス」がある。

つまり、「ネガティブな情報ほど注意が向きやすい」ということである。
たしかに、多くの人にいい評価を受けていても、一人でも否定的な意見があると、そのネガティブな意見が気になってしまう。
このネガティビティー・バイアスは言語を考える上でも面白い仮説である。
たとえば、文の前のほうに否定語を置くほうが、早い段階でネガティビティー・バイアスがかかり、否定の情報であることがより印象付けられる。
この点に関して、英語と日本語は対照的である。
(『日英語の比較-発想・背景・文化』 日英言語文化研究会 より)

英語は否定語のnotが文の前のほうにくるが、日本語は否定語の「ない」が文の最後のほうにくる。
とくに、英語は否定語を前に置く傾向が強い。その証拠に「わざわざ」否定語を先頭にもってくる否定倒置文も可能である。

このように否定語を最初にもってくるほうがネガティビティー・バイアスがかかりやすい。
そのため、英語は「ネガティブ・バイアス言語」といえるだろう。
一方、否定語を文の最後に置く日本語はネガティビティー・バイアスがかかりづらい。
そのため、日本語は「ポジティブ(肯定)・バイアス言語」といえるだろう。
この両者の違いは、否定疑問文の受け答えによく表れている。
(『英語と仲直りできる本』 デビッド・バーカー 著より)

英語のように、否定のNoを最初に置くと、ネガティビティー・バイアスにより、「アメリカに行ったことがない」という否定の情報を強く伝えられる。
しかし、言語の構造的に否定語を最初に置けない日本語では、相手の発言(「アメリカに行ったことないの?」)を「その通りです=はい」と受け止めることによって、否定の情報を伝える。
これを図式化すると、こうなる。

「ネガティブ・バイアス言語」仮説は、どのような現象をどこまで説明できるか、これから「裏付け」が必要である。
(『英語の構造と移動現象』 畠山雄二 著より)

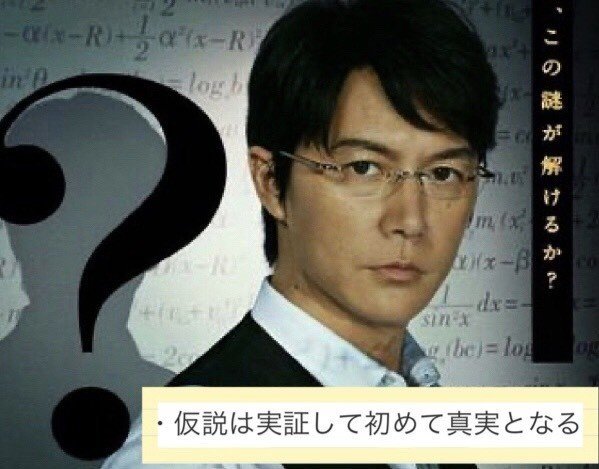
To be continued.
