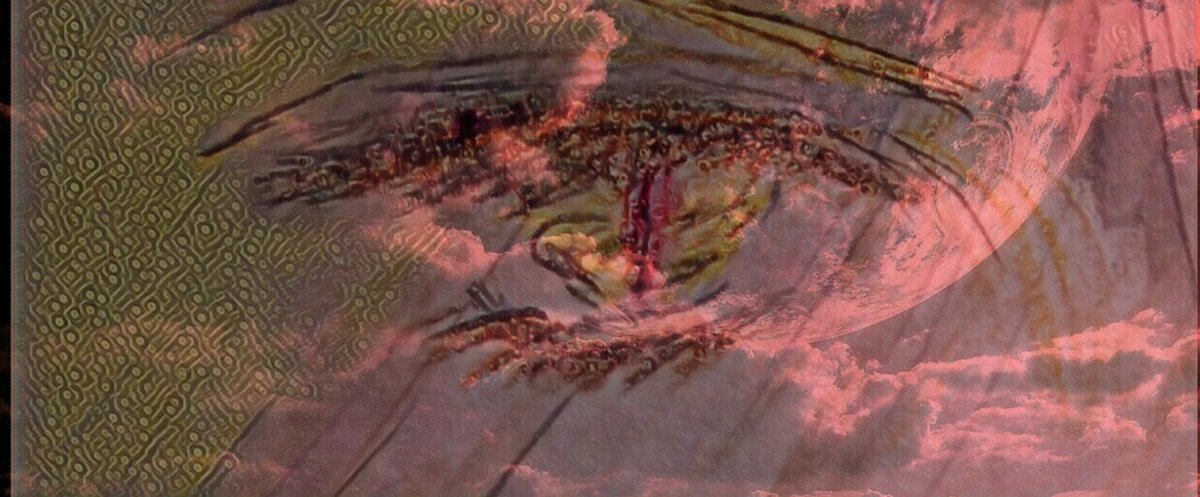
魔都に烟る~part14~
何の感情も宿さない目。自分のことを、本当に見ているのか……それさえわからないようなレイの瞳を凝視する。
「レイ……あなた、私の何を知っているの……?……一体、何が目的なの……?」
ローズの問いに、レイは首筋に添わせていた手を後ろに回して引き寄せた。逸らすことも出来ないほどに強い目線でローズを見つめる。慄きながらも、ローズはレイの目を見つめ返した。
「……全て……聞くつもりがありますか?」
レイの言葉の調子は、ほんの僅かな躊躇いと、しかし有無を言わせないほどの強制感を漂わせる。
「今さら、何を言うのよ……あなただって……あなただって私に同じようなことをしたじゃない!」
恐れを怒りと哀しみの中に封じ込め、ローズは心の内を迸らせた。そんな彼女の様子を見ても、レイの瞳に感情の揺れはない。
おぼろ気ながら、本当はローズにもわかってはいた。
真犯人はローズの力を奪うために、だが、レイは恐らくその力を戻すために、であることは。心身の気だるい余韻とは別に、身体の芯に灯る何か、を感じていたから。
それでも、ローズにとっては同じ屈辱であったことは間違いない。本人の意思などお構いなしに、思うがままにした、と言うひとつの事実において。
「クラーク夫妻は既に“奴”に取り込まれています。あなたを初めて紹介した時、もう彼らはただの傀儡(かいらい)と成り果てていました」
そんなローズの内心を知ってか知らずか、レイは彼女の目を見つめたまま坦々と話を続けた。
負けじとその目を見つめ返しているローズであったが、知らず知らず瞬きを忘れそうになるほどに静かな空間。
だが、一見静かなその空間の歪(ひずみ)には、常人では捉え切れないほど微細な波動が行きかう。
「アレンは両親の様子がおかしいことに気づき、あの夜、私に相談して来たのです」
「……レイは気づいていたの?クラーク夫妻のこと……あの挨拶の時に……」
「……いえ。あの時は私も気づいていませんでした。記憶にある夫妻の様子はあんな感じでしたからね。あの不自然な感じが、逆に自然と言えば自然でした」
レイの説明には淀みも躊躇いもなかった。相変わらず感情はこもっていないため判断はつきにくい。それでも嘘とは思えなかった。
「私はその時に、アレンに言い含めました。何も気づかぬフリをして過ごせ、と。そして護符を渡しておいたのです」
「じゃあ、昨日は何故……」
ローズの問い掛けに微かに頷く。
「奴が身近に潜んでいたからこそ、私の護符が反応して動けず、宴の席に姿を出せなかったのですよ」
「……それなら、私が見たアレンは……」
「当然、本物のアレンではない。きみはアレンに成り済ました奴に誘(おび)き出されたんです」
ローズにとって痛烈な言葉だった。まんまと自ら敵の術中に嵌まりに行ったのだ、と暗に言われて冷静でいられる程、彼女の性格は穏やかなものではない。
目を逸らしたら負けだ、と言わんばかりにレイの目を凝視し唇を噛む。必死に自分を抑えようとしているのが丸わかりであろうが、それでもレイの瞳が揺れることはなかった。
「セーレン様!」
押し潰されそうなその空間に、突然、ヒューズのただならぬ声が押し入った。レイが静かに目線を扉の方に向ける。
「どうした?」
「ただ今、クラーク子爵家のご子息が……」
ヒューズの言葉を受け、レイは一瞬だけローズの方へと目を向ける。そして、すぐに彼女の首筋から手を離して手を取ると、アレンが通された居間へと向かった。
*
「アレン殿?どうなさったのです?」
レイの姿を認めた途端、アレンは青ざめた顔で縋るような視線を向けて来た。
「伯爵……私は……私は……どうしたらいいのですか?」
「落ち着いて。一体、どうされたのです?」
言葉とは裏腹に、心配しているとは全く思えないレイの様子。ローズは改めて身震いしそうになった。
「両親が……両親の様子がおかしいのです……何かブツブツ言ったかと思うと、急に大声を出したり……」
震えながら訴えるアレンに、レイは至って冷静に問う。
「屋敷の中に訪問者や不審者は?」
「いえ、誰も……私が何事か問い質そうとすると、怒ったように物を投げたり……それで慌てて……」
「……こちらに来られた訳ですね?」
「……はい……」
アレンは目を合わせずに答えた。
「……ヒューズ。出かける用意を」
「はい、セーレン様」
レイの言葉に、アレンが不安気な目を向ける。
「アレン殿はここで待っていてください」
その言葉に、アレンはホッとしたように頷いた。余程、恐ろしかったらしい。次いで、レイはローズに目を向けた。━と。
「私は一緒に行くわ」毅然と言い放つ。
「いいのですか?本当に、知りたくなかったことまで知ることになる……かも知れませんよ?」
「だから、今さらやめてよ!」
噛みつくように言うローズを一瞥し、レイは口の中では何かを唱える。
「行きましょう。アレン殿はここを動かないように」
アレンが頷くのを確認し、二人は急ぎ、クラーク邸へと向かった。
