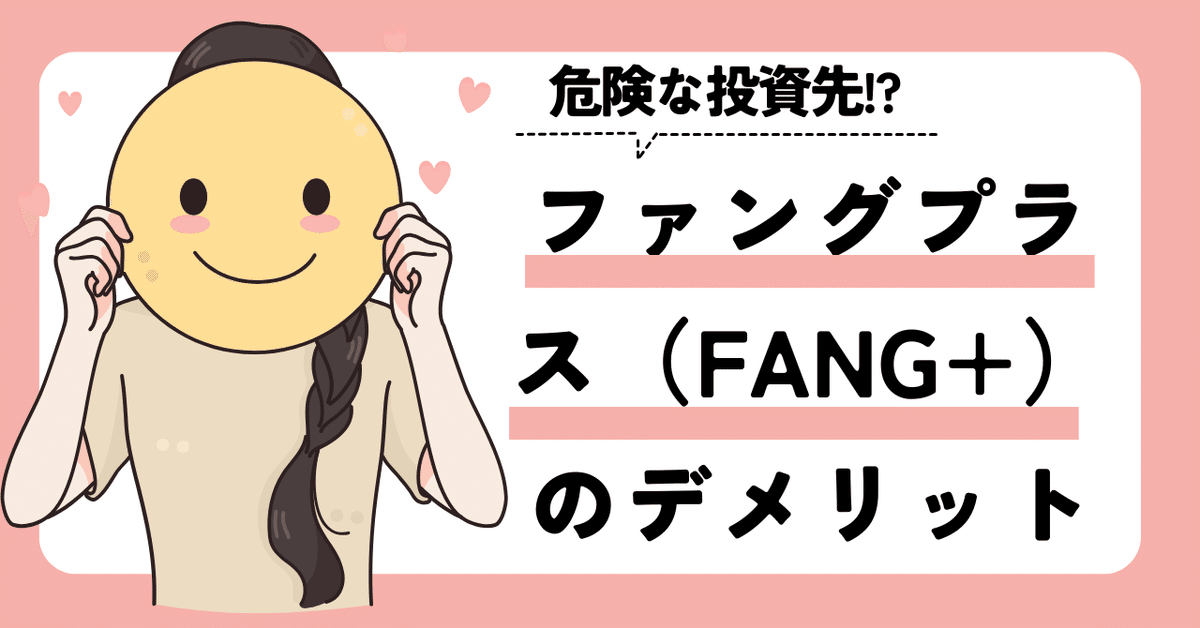
ファングプラス(FANG+)のデメリット。危険な投資先なのか解説
新NISAの「つみたて投資枠」「成長投資枠」どちらにも対応している事や爆発力のある成長性から人気の高いファングプラス(FANG+)
私も少しだけ保有していますが、検索すると「ファングプラス デメリット」とか「ファングプラス 危険」とか関連ワードに出てきていたので、『どのようなリスクがあるのか?』を気にされている方が多くいる事がわかりました。
まぁ、その辺りは当然気になりますよね。
なかなかに魅力的な投資先で人気も高いですが、購入前にはきちんとデメリット(リスク)を知っておく必要があります。
なのでファングプラスとはそもそもどのような投資商品なのか?どんなデメリットがあるのか?などを中心にできるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
そもそもファングプラス(FANG+)とは?

デメリットなどを紹介する前に「ファングプラスとは何?」といった部分を説明していきます。
既知の方は読み飛ばしちゃっても大丈夫です。
FANG+(ファングプラス)とは、Facebook・Amazon・Netflix・Googleの4社を含む、世界規模で大きな影響力を持つ米国企業10銘柄で構成された株価指数の事です。
Facebookの"F"、Amazonの"A"、Netflixの"N"、Googleの"G" 各社の頭文字をとってFANGそしてそれ以外の6社をプラスする株価指数なのでファングプラスと呼ばれます。
米国市場には約3,000の企業が上場しており、ファングプラスはその中からたった10銘柄で構成される株価指数ですが、その10銘柄の時価総額を足した値は米国市場全体の25%以上を占めます。
ファングプラスの構成銘柄は米国株の中枢、大黒柱、精鋭中の精鋭企業が集まったようなイメージです。
✅ファングプラスの成績

2014年9月末時点を100として指数化した時に2023年6月末には10倍以上に成長しているのが分かります。
米国市場を代表する株価指数「S&P500」でも350なのに対して、その3倍以上の差をあけるファングプラスは凄まじい成長力を持っている株価指数であるという事が分かると思います。
この優れた成長率がファングプラスが人気の理由です。
✅構成銘柄の選定基準
ファングプラスを構成する銘柄の選定方法は以前まではICE(米インターコンチネンタル取引所)が選定する、といった要件が入っていたので具体的な選定基準が曖昧だった点がデメリットとされていました。
しかし2022年12月より選定基準が見直しされこれまで曖昧だった部分がクリアになりデメリットの1つは解消されています。
新要件の主なポイントは以下の通りです。
◦投資対象
・米国証券取引所に上場する普通株式
・「⼀般消費財・サービス」、「テクノロジー」、「メディア・コミュニケーション」の3セクターの中から
◦スクリーニング条件
・時価総額50億ドル以上
・上場後60日経過
・6ヶ月平均売買高5000万ドル以上、6ヶ月未満の場合は1日平均売買高5000万ドル以上
◦銘柄選定方法
・「FAANMG」6銘柄は原則取り入れる。
(Facebook,Apple,Amazon,Netflix,Microsoft,Google)
・「FAANMG」以外の4銘柄は
時価総額(35%)
1日平均売買高(35%)
直近12ヶ月株価売上⾼倍率(15%)
直近12ヶ月売上⾼成⻑率(15%)
上記4つの指標の括弧内の比率で加重平均して上位4銘柄を選出
以前との主な違いとして、過去にはアリババやバイドゥといった中国の企業も選出されていましたが、新要件になり米国外に籍を置く銘柄の組入れが不可となりました。
また、新要件では”原則として「FAANMG」は組入れる”となっています。
FANGプラスがスタートした2017年9月の時はFacebook、Amazon、Netflix、Googleを中枢としてプラス6社を追加する、という感じでしたが新要件では「FAANMG」となっており、もはや『ファアアンムグプラス』という名称の方が正しくなってますね。笑
つまり「FAANMG」+4銘柄で構成される株価指数が今のファングプラスという訳です。
ちなみに銘柄入替のタイミングは毎年3,6,9,12月の第3金曜日です。
そのタイミングで入替候補の銘柄があれば入替が行われ、対象のなる銘柄がない場合には変更なしとなります。
◦2024年10月時点の構成銘柄
メタ・プラットフォームズ【META】
アップル【AAPL】
アマゾン・ドット・コム【AMZN】
ネットフリックス【NFLX】
マイクロソフト【MSFT】
アルファベット【GOOG】
エヌビディア【NVDA】
ブロードコム【AVGO】
クラウドストライク【CRWD】
サービスナウ【NOW】
✅ファングプラス連動の投資信託
ファングプラスの動きに連動した投資成果を目指す投資信託は2つあります。
・iFreeNEXT FANG+インデックス
・iFreeレバレッジ FANG+
どちらも株価指数「ファングプラス」への連動を目指す投資信託ですがレバレッジの付いている方は指数の値動きの2倍程度を目指して運用を行う投資信託です。
ハイリターンではありますがその分ハイリスクとなっています。
株式投資を始めてまだ日が浅い方や長期での運用を考えている方は通常のiFreeNEXT FANG+インデックスの方が良いかなと個人的には思います。
ファングプラスのデメリット

高い成長性が期待できるファングプラスですが、その反面気を付けておいた方が良いデメリット・注意点もいくつかあります。
それをご紹介していきたいと思います。
✅手数料が高い
iFreeNEXT FANG+インデックスの手数料(信託報酬)は0.7755%です。
iFreeレバレッジ FANG+の手数料(信託報酬)は1.275%です。
信託報酬は1日にごとに引かれて、その額は信託財産×信託報酬÷365で求められます。
長期保有を前提とした運用の場合、信託報酬の利率の高さは当然ながら投資成果の足を引っ張ります。
例えば100万円投資した時の異なる信託報酬(0.2%,0.5%,1.0%,1.5%)での20年後の投資額がどのようになるか見てみましょう。
(※投資元本100万円のままだと仮定した場合)

20年後を見た時、信託報酬0.2%であれば3.9万円の減少で済みますが信託報酬1.5%の場合は26万円の減少になります。
運用期間が1~2年など短期であれば信託報酬の差はそこまで大きく響きませんが、長期になれば例え1%の差であっても合計のコスト額の差は大きくなってしまいます。
iFreeNEXT FANG+インデックスの信託報酬0.7755%を高いと感じるかどうかは人によるとは思いますが、たった10銘柄で構成する株価指数への連動を目指すファンドにしては高いのでは?と感じる方が多くいる印象です。
投資家の方に圧倒的人気のオルカンやS&P500と比較して『高い』と感じている方もいます。
比較例)
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
信託報酬:0.05775%
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
信託報酬:0.09372%
(注意)自分で再現するのはかなり無理
「たった10銘柄の売買だけでこんなにも信託報酬がかかるなら自分でやれば良い」と思う方もいますが、個人でファングプラスと同じ状況を作り出すのはかなり難しいです。
と言うのも、ファングプラスの各銘柄のウエートは等ウエートになっており10銘柄あるので1銘柄あたり10%の割合となっています。
ファングプラスを構成する10銘柄をそれぞれ等しいウエイトになるように購入すればファングプラスを再現する事は可能ですが、それを実現するにはかなりのお金と労力が必要となります。
例えばMETAは1株575.16USD(10/22時点)です。NFLXは772.07USD、MSFTは418.78USDです。この3銘柄だけを1株ずつ買うにも1766.01USD(26.6万円)必要です。
他にもまだ7銘柄ありますし、持ち株数を揃えるのではなく投資額を均等になるようにしないといけないので自分で同じ環境を作るのが難しい事が分かると思います。
iFreeNEXT FANG+インデックスであればそれを投資額100円からでも実現してくれます。
信託報酬が気になる方は自分でファングプラスと同じ環境を作る事を目指すのではなく、ファングプラスの構成銘柄の中から数銘柄のみをピックアップして自分オリジナルの構成を作って運用するのもありかもしれません。
✅個々の銘柄の影響を大きく受ける
ファングプラスは10銘柄のみで構成されており等ウエートなので割合は10%ずつです。その為、1つあたりの銘柄が与える影響が大きくなります。
10銘柄の内、調子悪いのが1銘柄で残り9銘柄の調子が良ければそこまで問題はないですが、調子悪いのが2,3銘柄となるとファングプラスの成長は鈍化してしまいます。
成長性が高い企業に1点集中して投資している事で大きな成長が期待できるファングプラスですが、その内2,3銘柄の業績が悪くなるだけでも大きな影響を受ける点には注意が必要です。
✅業績・セクターに偏り(分散性が低い)
ファングプラスを構成する銘柄の業績・セクターはほぼ被っています。
【META】:IT・通信
【AAPL】:IT・通信
【AMZN】:サービス
【NFLX】:IT・通信
【MSFT】:IT・通信
【GOOG】:サービス
【NVDA】:IT・通信
【AVGO】:IT・通信
【CRWD】:IT・通信
【NOW】:IT・通信
最近ではAIブームに牽引される形で半導体業界が絶好調で、おかげでIT・テクノロジー企業の多いファングプラスは大きく伸びました。
ただこの先も今までのように好調な業界であり続ける保証はありません。
業績・セクターが分散されていない事で、もしその業種の成長性が鈍化した時やIT・テクノロジー関連の企業が多いので景気後退時などには大きな影響を受けて値下がりする可能性があります。
株式投資の世界には「卵は一つのカゴに盛るな」という有名な格言があります。
カゴが落ちると全ての卵が割れてしまうため、分散投資の大切さを説いた格言なのですが、ファングプラスの場合は分散性が低いのでリスクはややある商品だと思っておきましょう。
✅ビックテックがいつまで成長を続けるか不明
ビックテックとは世界的に見ても大きな影響力を持つ巨大IT企業群の事を言います。
ビックテックの事をGoogle,Apple,Facebook,Amazon,Microsoftの頭文字をとってGAFAMと呼んだりします。
これらIT・テクノロジー関連企業は新技術の出現や業界の急速な変化によってリーダー企業がこれまでも変わってきた歴史があります。
GAFAMが10年後も今と変わらず圧倒的な影響力を持っているかもしれませんが、他の企業の台頭により落ち目になっているかもしれません。
もしそうなった時に、ファングプラスはビックテックの5企業は基本固定となっているので株価が大きく下落する可能性があります。
まぁ、ただこの辺りは銘柄選定の見直しなどがされて今は基本固定となっている銘柄でも除外されるような動きになる可能性もあるとは思います。
✅地政学リスクが増えた時に大きく下がる可能性
PER,PBRなどを見れば分かりますがファングプラスを構成する巨大ハイテク株は割高の状態で常に推移している傾向にあります。
それは数値上、株価が割高であってもそれ以上に将来性や成長性が評価されて買われているからです。
常に投資家から高い期待値を持たれているので、決算が好決算であっても期待値以上の決算でない場合は下落するリスクも含んでいます。
また、ロシアのウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化など地政学リスクが高まった時には巨大ハイテク株は利益確定売りが出やすく、その影響で株価が急落する事もあります。
この先、世界的な地政学リスクが増えるとファングプラスは大きな影響を受けやすいでしょう。
ただ、リスクが懸念していたよりも大事とならなかった時の戻りも早いという特徴もあります。
まとめ

ファングプラスのデメリット・注意点を幾つかご紹介してきましたが、ファングプラスが危険と言う訳ではありません。
投資である以上、当然どんな投資信託でもリスクはあります。
そのリスクを事前に知った上でメリットと天秤に乗せてメリットの方があると思えるかどうかです。
最後にファングプラスはこういった方に向いている。というのをまとめておきます。
✅ファングプラスが向いている人
・成長性などを加味した時に信託報酬が高いとは思わない方。
実際に自分でファングプラスの環境を整えるのは、まあ無理です。それを投資信託であれば100円という少額からでも購入可能で投資信託なので積立投資の設定も出来て手間もかかりません。
そのコストとしての信託報酬0.7755%が高いと思わない方は向いています。
・ある程度のリスク許容度を持つ方
ファングプラスは業種・セクターの偏った10銘柄構成である事で分散性が低く、株価が影響を受けやすいとデメリットで触れた通りボラティリティ(資産価格の変動性や変動率)の大きい投資商品です。
以下の図はファングプラスとS&P500、ナスダック100をファングプラスの取引開始された2017年11月から比較した図です。

見て分かる通りですが、2022年少し手前3指数とも株価が下落している時、1番下落率が大きいのがファングプラスです。
ただ、その後の伸び率が大きいのもファングプラスです。
株価が未来永劫伸び続ける投資商品などありません。なのでファングプラスもまたいずれ大きく下落する時が来るでしょう。
その時でも狼狽せずに冷静な判断が出来る、ある程度のリスク許容度を持つ方は向いています。
大きく下がるのにメンタルが耐えられない、と思う方はS&P500などを検討するのが良いかもですね。
・10年後、20年後でもビックテックの影響力は変わらないと思える方
好調な米国市場を牽引しているのは間違いなくビックテックやエヌビディア、ブロードコムなどの半導体株・ハイテク株です。
その企業だけに集中して投資するファングプラスは当然成長性も高いのですが、この先もこうしたIT関連企業やハイテク株が変わらずに成長をし続けると思える方は向いています。
以上、ファングプラスのデメリット等についてでした。
個人的にはファングプラスは面白い商品だと思っています。
ただ、S&P500やオルカンに比べるとリスクの高い商品だと分かっているし結構ビビりで堅実タイプなのでメインの投資先ではなく控えめな額を投資しています。
自分の投資スタイルや性格も考えながら検討してみましょう。
それでは、またねー😉
かりんちゃんのブログ↓
最近、日本株もちょこちょこ再開しだして、XやYoutube、ネットなどで色々と情報収集している時に見かけたかわいい子。
わたしが日本株を触る時はけっこうその時々で話題になってる”テーマ株”を重要視しているんだけど、そのテーマ株をまとめるのが上手で早いひと。
それに分かりやすいからとても参考になる
ゆうなと同じようにX以外にもブログとかで情報発信してる子と仲良くなりたいって気持ちもあってかりんちゃんのブログを紹介中。
日本株さわってる人はおすすめだよー😉🔽
