最高裁がフリーランス差別を撤廃していた
原告(三宅勝久、寺澤有)が「記者クラブいらない訴訟」で主張しているのは、「取材・報道の自由は、フリーランスにも通信社や新聞社、テレビ局の記者にも、差別なく保障されなければならない」というものである。
これに関して、2025年2月14日、原告は新たな準備書面(主張、立証をまとめた書面)を東京地裁へ提出した。最高裁が、取材・報道の自由において、フリーランスと通信社や新聞社、テレビ局の記者との差別を容認していた判例を実務面で変更していることを指摘している。
重要な裁判で判決が言い渡されると、裁判所は報道機関へ判決要旨を交付する。記者が法廷で傍聴していても、裁判官が読み上げる判決を子細漏らさずメモすることは不可能であり、そもそも、民事裁判の判決は主文(「被告は原告に対し、○○万円を支払え」などの結論)のみ読み上げられ、理由は読み上げられないことがほとんどである。正確な報道を行うためには、判決要旨が不可欠なのだ。
1996年9月19日、私は松山地裁で元警察官3人に対する銃刀法違反事件の判決公判を傍聴することとなった。3人は暴力団から提供された拳銃を所持していたとして起訴されていた。その拳銃を捜査で発見、押収したかのように偽装し、拳銃の押収丁数を水増ししようとしていたのである。
田村秀作裁判長は判決を言い渡す前に、「判決要旨を希望する報道機関は、あとで取りに来てください」と述べた。
判決公判が終了したあと、私は広報を担当する総務課へ判決要旨を取りに行った。しかし、菰田斎課長は「判決要旨は記者クラブ加盟社以外には交付できない」と拒否した。
その後、私は松山市内で元警察官3人に対する取材を行ったあと、菰田課長へ電話をかけて、「正確な報道を行うため、判決要旨を交付してほしい」と説得した。長電話のすえ、菰田課長は「正確な報道を期し、今回は特別に配慮して、判決要旨を交付する」とこたえた。
ところが、松山地裁へ判決要旨を取りに行くと、菰田課長が沈痛な表情で、「上司が『判決要旨は記者クラブ加盟社以外には交付できない』と指示してきた」と伝えた。私は菰田課長に同情し、「そういう不当な対応は、私が裁判を起こして変える」となぐさめた。
1999年9月17日、私は「松山地裁が判決要旨を交付しなかったのは、フリーランスと記者クラブ加盟社の記者を差別するもので憲法14条1項に違反し、フリーランスの取材・報道の自由を侵害するもので憲法21条1項に違反する」として、国に対し、損害賠償126万円を請求する訴訟を提起した。代理人は堀敏明弁護士(後日、佃克彦弁護士も加わった)。
2000年10月5日、東京地裁(大坪丘裁判長)は「記者クラブは、我が国の報道分野において一定の役割を果たしているものであるから、松山地裁が松山地裁の司法記者クラブに判決要旨を交付することで足りるとし、それ以外の報道機関には特に交付はしないという取扱いをすることが、その目的との関連で著しく不合理なもので、裁量判断の合理的な限界を越えているとは言い難い」として、憲法14条1項違反も憲法21条1項違反も認めず、私の請求を棄却した。
2001年6月28日に言い渡された東京高裁(細川清裁判長)の判決も、東京地裁の判決と同様の判断で、私の控訴を棄却している。
一方、最高裁は検討の余地があると考えたのか、2年近くも審理していた。しかし、結局、2003年6月12日、泉德治裁判長は「憲法違反にあたらない」として、私の上告を棄却した。
上記の訴訟を、私は「第1次記者クラブ訴訟」と呼んでいる。その後、記者クラブの違憲性を問う訴訟を、第2次、第3次……と提起しているからだ。しかし、残念ながら、それらの訴訟も第1次記者クラブ訴訟と同様、「フリーランスと記者クラブ加盟社の記者を差別しても、憲法14条1項や憲法21条1項には違反しない」という判断を踏襲している。
ところが、である。2024年5月27日、私が最高裁に対し、「最高裁が保有する記者クラブに関連する文書」の情報公開を請求したところ、同年9月30日、「報道機関等への判決要旨等の交付について(事務連絡)」という2017年7月25日付の文書が公開された。これが、なんと、「判決要旨を交付する目的は正確に報道してもらうため。記者クラブのみならず、広く報道機関(フリーランスも含む)に交付してさしつかえない」とする内容なのだ。
つまり、最高裁は、事実上、第1次記者クラブ訴訟で私が主張していたことを是認しているといえる。「判決要旨を記者クラブのみに交付し、フリーランスには交付しなくても、憲法14条1項や憲法21条1項に違反しない」という自らの判断を覆したわけである。
以下、2025年2月14日付の「原告ら準備書面(6)」の全文を掲載する。なお、「甲○」は原告が提出している証拠の番号、「乙○」は被告が提出している証拠の番号のことだ。
原告ら準備書面(6)
(1)最高裁判所が、事実上、「第1次記者クラブ訴訟」の判例変更を行っていること。
令和6年(2024年)5月27日付で原告・寺澤有は最高裁判所に対し、同裁判所が保有する記者クラブに関連する司法行政文書の開示を申し出た。
同年9月30日付で最高裁判所は原告・寺澤に対し、上記の文書を開示した。その中には、平成29年(2017年)7月25日付の「報道機関等への判決要旨等の交付について(事務連絡)」(甲81)が含まれていた。以下、同文書から引用する。


〈判決や決定などの要旨等(以下「判決要旨等」という。)については、これまでも各庁において司法行政上の便宜供与として報道機関等へ交付されているものと承知していますが、判決要旨等を交付する目的が、裁判結果等の内容を報道機関へ周知し、正確に報道してもらうためのものであることからすると、司法記者クラブ(所属の報道機関)からの依頼に基づいて作成された判決要旨等については、当該司法記者クラブ(所属の報道機関)のみならず広く上記の目的にかなう報道機関にも交付して差し支えないものと考えているところです〉
「判決要旨等を交付する目的が、裁判結果等の内容を報道機関へ周知し、正確に報道してもらうためのものであることからすると、司法記者クラブ(所属の報道機関)からの依頼に基づいて作成された判決要旨等については、当該司法記者クラブ(所属の報道機関)のみならず広く上記の目的にかなう報道機関にも交付して差し支えない」というのは、原告・寺澤が「第1次記者クラブ訴訟」(甲32)で主張していたことと同一である。しかし、「第1次記者クラブ訴訟」では、東京地方裁判所も東京高等裁判所も最高裁判所も原告・寺澤の主張を認めなかった。
「第1次記者クラブ訴訟」の判決が最高裁判所の決定で確定したのが平成15年(2003年)6月12日。それから14年後、最高裁判所は、事実上、「第1次記者クラブ訴訟」の判例変更を行う「報道機関等への判決要旨等の交付について(事務連絡)」を内々で各高等裁判所や各地方裁判所、各家庭裁判所へ発出した。遅きに失したとはいえ、最高裁判所は記者クラブ加盟社の記者とフリーランスとを差別する合理的な理由はないと判断したわけである。
「報道機関等への判決要旨等の交付について(事務連絡)」が開示されたあと、原告・寺澤は同文書をフリーランス同士で共有した。すると、令和6年(2024年)10月15日、札幌在住のフリーランスの小笠原淳氏が札幌高等裁判所に対し、同月18日に判決が言い渡される民事訴訟の判決要旨を交付するよう申請した(甲82の1)。そして、札幌高等裁判所は小笠原氏に対し、同訴訟の判決要旨を交付したのである(甲82の2)。実務上も、「第1次記者クラブ訴訟」で原告・寺澤が主張していたとおりの取り扱いがなされている。
(2)記者クラブの存在自体がジャーナリズムの在り方と相反し、憲法21条1項に違反すること。
小笠原淳氏といえば、令和6年(2024年)4月、鹿児島県警の本田尚志前生活安全部長が同県警の不祥事に関する公益通報を行った相手として知られる。どうして、本田前部長は、鹿児島拠点の通信社や新聞社、テレビ局ではなく、札幌在住のフリーランスへ公益通報を行ったのか。小笠原氏は被告・共同通信社の依頼で寄稿し、『南日本新聞』にも掲載された記事(甲83の1~2)で次のように述べている。
〈今回の鹿児島の件で多くのメディアから取材を受けることになった筆者は、繰り返し問われた。「告発文書はなぜ札幌のあなたに届いたのか」と。いや、私が選ばれたわけではなかろう。あなたたちが無視されただけではないか〉
本田前部長が通信社や新聞社、テレビ局の記者たちを無視したのは、原告・三宅勝久が『山陽新聞』の記者で警察の記者クラブに配属されていたときに経験したような警察と記者クラブとの癒着を同様に経験していたからであろう。原告・三宅は陳述書(甲75)で次のように述べている。
〈警察幹部と記者クラブのメンバーで頻繁に宴会を開きました。記者も警察官も休みが少なく夜勤があり、突発で呼び出されるといった労働環境が似ていることもあり、双方に宴会を楽しみにする雰囲気がありました。記者クラブの部屋に広報担当の職員が果物やカニなど食べ物を差し入れることがたびたびありました。警察幹部や職員から「ちゃん」づけで呼ばれるほど親しくなります。長時間労働の相当部分を庁舎内の記者クラブの部屋に入り浸りになる生活を送っていると、警察の言うことはすべて正しいという感覚になっていきます。私も知らないうちにそうなっていたと思います〉(5~6ページ)
従前、原告が主張、立証してきた「記者クラブの存在自体がジャーナリズムの在り方と相反し、憲法21条1項に違反する」は、今回の鹿児島県警の不祥事でも証明されている。なお、原告・寺澤有は、鹿児島県警の不祥事で記者クラブが果たした「役割」について、月刊誌『リベラルタイム』へ寄稿している(甲84)。
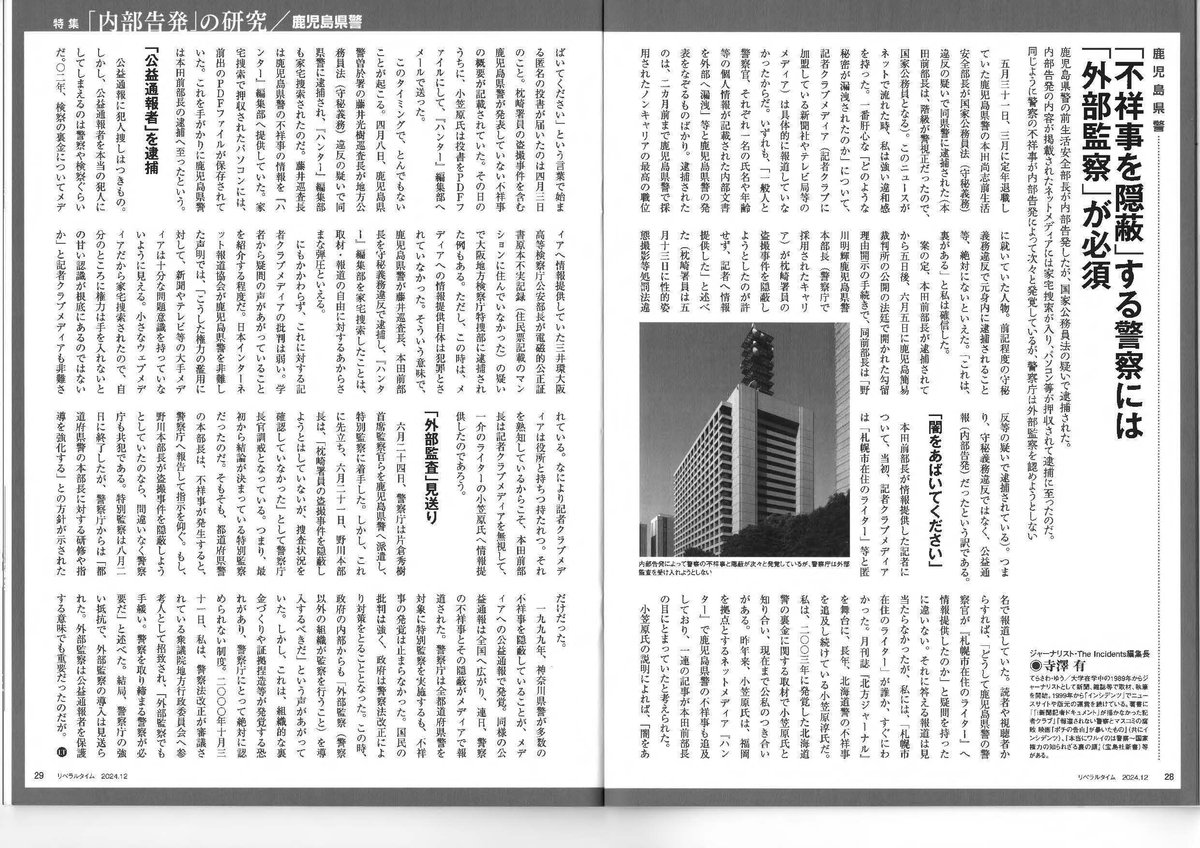
(3)最高裁判所はフリーランスの実績を判断するさい、「媒体に定期的に記事等を提供する」という基準を採用していないこと。
前出の「報道機関等への判決要旨等の交付について(事務連絡)」(甲81)で、最高裁判所は「判決要旨等の交付先として相当と考えられる報道機関の例」を以下のように取りまとめている。
各庁に対応する司法記者クラブ加盟社及び以下の報道機関又は記者
(1) 日本新聞協会会員
(2) 日本専門新聞協会会員
(3) 日本地方新聞協会会員
(4) 日本民間放送連盟会員
(5) 日本雑誌協会会員
(6) 日本インターネット報道協会会員(法人会員のみ)
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者
(8) 上記(1)から(6)までの発行する媒体に署名記事等を提供した実績を有する者(交付申請の際に、該当記事を疎明資料として提出させることが相当。)
これは総務省の会見規約(乙3)などを参考にしたと考えられる。

しかし、総務省の会見規約では、フリーランスで会見に参加することができる者を、「上記AからFの中に掲げる企業・団体(原告注:日本新聞協会会員など)が発行する媒体に定期的に記事等を提供する者」としているのに対し、最高裁判所の取りまとめでは、フリーランスで判決要旨等の交付先として相当と考えられる者を、「上記(1)から(6)まで(原告注:日本新聞協会会員など)の発行する媒体に署名記事等を提供した実績を有する者」としている。つまり、最高裁判所は、同趣旨の箇条書きから、わざわざ、「定期的に」という語句を取り除いたわけである。
その理由が原告の主張、立証と無関係なはずがない。従前、原告は「『媒体に定期的に記事等を提供する』というのは、フリーランスの実績を判断する基準としてそぐわない」と主張、立証してきた。すなわち、以下の場合などは、どんな実績があるフリーランスでも、「媒体に定期的に記事等を提供する」のは困難だからだ。
(1) 大きな記事を執筆するため、取材に専念しているとき。
(2) 単行本を出版するため、取材や執筆に専念しているとき。
(3) カメラマンや編集者といった記事を執筆する以外の仕事に専念しているとき。
(4) 各種試験や知識習得のため、勉強に専念しているとき。
(5) 自分自身や親族の事情で休業せざるをえないとき。
総務省の会見規約などが作成された当初から、原告らフリーランスは機会あるごとに「『媒体に定期的に記事等を提供する』というのは、フリーランスの実績を判断する基準としてそぐわない」と主張してきた。それが奏功し、総務省や内閣府などでは、規約の基準にかかわらず、フリーランスが会見に参加することができるようになった(甲17、甲18の1~2、甲19の1~3、甲20の1~2、甲24、甲46の1~3、甲86の1~2)。同様の基準の緩和やフリーランスの実情を踏まえた運用は、細野豪志首相補佐官(当時)が主催する政府と東京電力の共同記者会見でも見られている(甲第85号証)。


フリーランスの実績を判断する基準とその運用については、原告らフリーランスがネットや刊行物でいくつもリポートしてきた。最高裁判所が「報道機関等への判決要旨等の交付について(事務連絡)」を作成するさい、それらをうかつにも見落とすとは考えにくい。最高裁判所も「『媒体に定期的に記事等を提供する』というのは、フリーランスの実績を判断する基準としてそぐわない」と判断し、「媒体に署名記事等を提供した実績を有する」という基準を採用したのであろう。
あまつさえ、「青潮会主催の記者会見に関する規約」(乙2)では、〈「定期的」は、申請時から過去半年以内に2回程度の署名記事を目安とする〉、「青潮会主催の記者会見に関する規約」(乙4)では、〈「定期的」は、申請時から過去半年以内に2回の署名記事を目安とし、申請の都度、青潮会への記事の写しの提出を求めるものとする〉としている。


もっぱらフリーランスを記者会見から排除することを目的とした基準といえる。このような不当な基準をふりかざし、原告らを記者会見から威力をもって排除した被告らの行為は違憲、違法以外のなにものでもない。
(4)裁判所は「差別されない権利」を確立した権利として取り扱うべきこと。
従前、原告は「鹿児島県知事が公人の義務として開く記者会見に、原告らがフリーランスの権利として参加しようとしたところ、被告らが威力をもって妨害したこと(以下、本件妨害行為)は、憲法14条1項が保障する『差別されない権利』に違反する」と主張、立証してきた。
「差別されない権利」は、近年現れた学説だが、令和5年(2023年)6月28日に東京高等裁判所で言い渡された判決(甲52)でも認められている。
この判決が、令和6年(2024年)12月4日、最高裁判所の決定で確定した(甲87)。西日本新聞社が社説(甲88)で「『差別されぬ権利』定着を」と主張しているとおり、今後、「差別されない権利」は確立した権利として取り扱われるべきである。
もっとも、青潮会加盟社で本件妨害行為に加わり、アパルトヘイトと同一視されている取材の現場でのフリーランス差別を推し進めた西日本新聞社が社説で「『差別されない権利』を認める画期的な司法判断が確定した。部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす取り組みに生かしたい」「差別されない権利は部落差別だけでなく、障害者、性的マイノリティー、外国人などさまざまな差別の防止や被害救済に活用したい」などと主張しているのは失笑を禁じえない。
以上
いいなと思ったら応援しよう!

