
解説『一度読んだら絶対に忘れない文章術の教科書』
これまで数多くの文章術本を読んでまいりました。
もう学ぶことなんてねーだろ、と斜に構えて読んでみたら、
「あれ、基本的で大事なことなんだけど、意外とどの本も触れていないぞ」と思えることを教えてくれる本でしたので、紹介させてください。
本書では、大きく3つのステップが紹介されていまして、
①「大きな問い」を立てる
②「大きな問い」を「小さな問い」に分解する
③「小さな問い」に答えを出す
シンプルにこれだけです。
「おいおい本当にこれだけ?」
「こんなんで、いい文章なんて書けるかよ」
「こちとら、何冊、文章術の本を読んだと思ってるんだ」
「文章術本を読むたびに、語彙だのロジックだの接続詞だの言われて、頭パンパンなんだよ」
…と思いますよね。
なので、僕がこの3ステップを再現してみましょう。
センター試験の現代文が半分も取れなかった僕でも再現できるのであれば、この本は本物といえるでしょうから。
大きな問い:スッと詰まらず読める文章術とは?
まず、本書の大きな問いをおさえるところから。
本書が解きたがっている問いは「読み手が詰まらずに読める文章術とは何か?」です。
これに一言で答えを出すと「問いを立てて答えを出す技術、これがこの本が教える文章術ですよ」となります。
小さな問い①:なぜ問いを立てると文章を書きやすいのか?
では、なぜ問いを立てることが、文章を書くことにつながるのか?
答えは「人間、質問されると思考が進んで筆が進みやすいから」です。
例えば、私も苦手なのが「自己紹介を3分間でお願いします」という指示。
スライド1枚にまとめようと思っても、なかなか筆が進まない。
しかし、
「これまでの経歴は?」
「趣味は?」
「最近うれしかったことは?」
…と聞かれるとどうですか?
もっというと「これまでの経歴は?」を
①どの会社で、どんな業務やプロジェクトを経験したか、印象に残っているやつ3つは?
②①でどんなスキルを手に入れた?
…とさらに細かく問いにして分解してあげると、どうでしょう。
むしろ、自己紹介を3分間で収めるのが難しくなってきません?
それくらい、書くことが溢れ出してくる。
これが、問いのパワーです。
小さな問い②:どうやって問いを立てればよいのか?
問いを立てると、答えやすくなるのはわかった。
でも、今みたいに問いをちょうどいい塩梅で刻んでいくためには、どうすればいいんだ?
結局、そこが難しくて躓くわけなんだが?
これが、次に気になる問いですよね。
まあ、そうやって疑問を抱いた方は、その時点で問いを立てることに成功しているわけなのですが。
どうやって問いを立てるのか?
答えは、WhatとWhyの2つの問いを使ってみてください。
What(どういうことか?)を問う
具体的には?を問う
抽象的には?を問う
この2つの意味合いがあります。
①具体的には?を問う
言葉の定義を問う、具体例を問う。これが、具体を問う、ということです。
例えば、本書について書こうと思うと
「本書が掲げる文章術とは何か?」
→問いを立てて答えを出すこと
「例えばどういうこと?」
→今まさにこの投稿こそが、本書を実践した具体例になっている
…と表現がややこしくなってしまいましたが、こんな風に考えていくと、話を具体化することができます。
②抽象的には?を問う
具体化の逆は抽象化。
抽象化とは、他にも当てはまるロジックを見つけ出すこと。
例えば「文章を書くときに、大きな問いを小さな問いに分解する。この頭の使い方は、タスクを分解して段取りを立てるときにも使えるよね」といったように、他にも当てはまるか?を考えるのも、文章を組み立てるコツの一つです。
Why(なぜか?)を問う
原因・根拠・動機を問う
比較を問う
①原因・根拠・動機を問う
なぜ?には3種類あるそうで。
原因:「なぜその出来事が起こったのか?」を問うもの
根拠:「なぜそう考えるのか?」を問うもの
動機:「何のためにやるのか?」を問うもの
例えば、就活でよく聞かれる「なぜ弊社を志望したのですか?」という質問には
・動機:何のために入社したいのか
・根拠:なぜ↑の動機を抱くようになったのか
を分けて答えなくてはなりません。
このように、原因・根拠・動機を意図的に使い分けられるようになると、文章をより強固なものにできます。
②比較を問う
比較もまた、思考を促して、文章を豊かにしてくれます。
例えば「この本の魅力は何か?」と問うよりも「他の文章術本と比べて、この本の魅力は何か?」と問うたほうが、より具体的に考えを巡らすことができます。
今回ご紹介している本は、他の文章術本と違って
・語彙や接続詞の使い方にはほとんど言及していない
・あくまで「問いの立て方」にフォーカスすることで、文章の骨格をつくる方法を教えてくれる
そんな魅力があります。
さて、ここまでの内容を図にまとめるとこんな感じでしょうか。
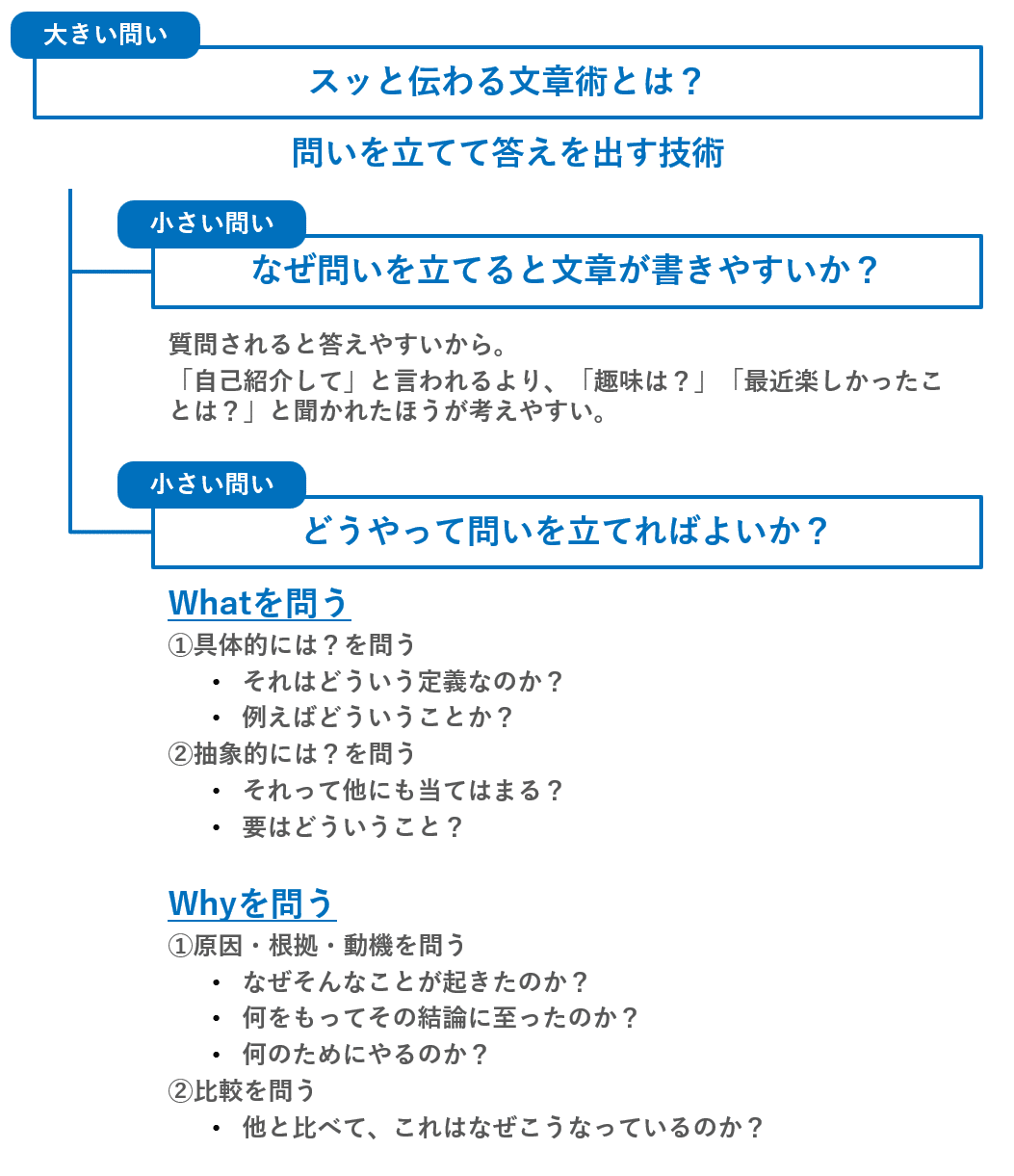
具体と抽象を行き来するための、もう一押し
問いを立てると、何を書けばよいかが決まる。
問いを立てるときは、「具体的には?」と「抽象的には?」を考えるとよい。
では、具体的にどうやって「具体的には?」や「抽象的には?」を問えばよいのか(ややこしくてすみません)。
個人的に好きな本がありまして、『賢さをつくる』という本です。
本書によると「頭がいい人=具体と抽象の往復運動が得意な人」と定義できるそうです。
では、どうすれば「具体と抽象の往復運動が得意な人」になれるのか?
頭がいい人とは「具体と抽象の往復運動が得意な人」である。頭の良さをさらに分解すると、「具体と抽象の距離が長い」「具体化と抽象化のスピードが速い」「具体化と抽象化の回数が多い」の3つの要素に分けることができる。
具体と抽象は「どっち偉くて、どっちが下」という関係ではないため、上下ではなく左右の関係で表現する方が望ましい。
思考を右(=具体)に振るためには、下記の問いを考えてみるとよい
4W1H(いつ、どこで、だれが、何を、どのように)
たとえば?
TPO(時と所と場合は?)
思考を左(=抽象)に振るためには、下記の問いを考えてみるとよい。
Why(なぜ?)
要するに?つまり?まとめると?
本当は?本当に?
目的は?
そもそも?
こんなことを考えていくと、いわゆる「具体と抽象の行き来」が可能になります。
図にまとめるとこんな感じでしょうか。

まとめ
改めて『一度読んだら絶対に忘れない文章術の教科書』で語られていた、文章を書くときのポイントをまとめておくと、次の3つでした。
①「大きな問い」を立てる
②「大きな問い」を「小さな問い」に分解する
③「小さな問い」に答えを出す
この頭の使い方って応用ききますよね。
例えば、上司から「チームの懇親会のお店探しておいて」と頼まれたとするじゃないですか。
「チームの懇親会のお店はどこがいいか?」と大きな問いのまま考えると、大変なんですよ。
でも
・1人あたりの予算は5000円以内か?
・オフィスから徒歩10分以内にあるお店か・
・個室はあるか?
・外で喫煙は可能か?
・(一番偉い人が日本酒好きなので)日本酒の種類は10種類くらいあるか?
…と小さな問いに分解して、それらを食べログなり一休なりの条件欄に突っ込めば、お目当てのお店にたどり着きやすくなります。
・・・と、普段からやっている頭の使い方なわけです。
これを、文章を書くときにも応用すればいいじゃないか、と言っているのが本書です。
うん、なんとも再現性の高い、素晴らしい本だなと思います。
ここから先は
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
