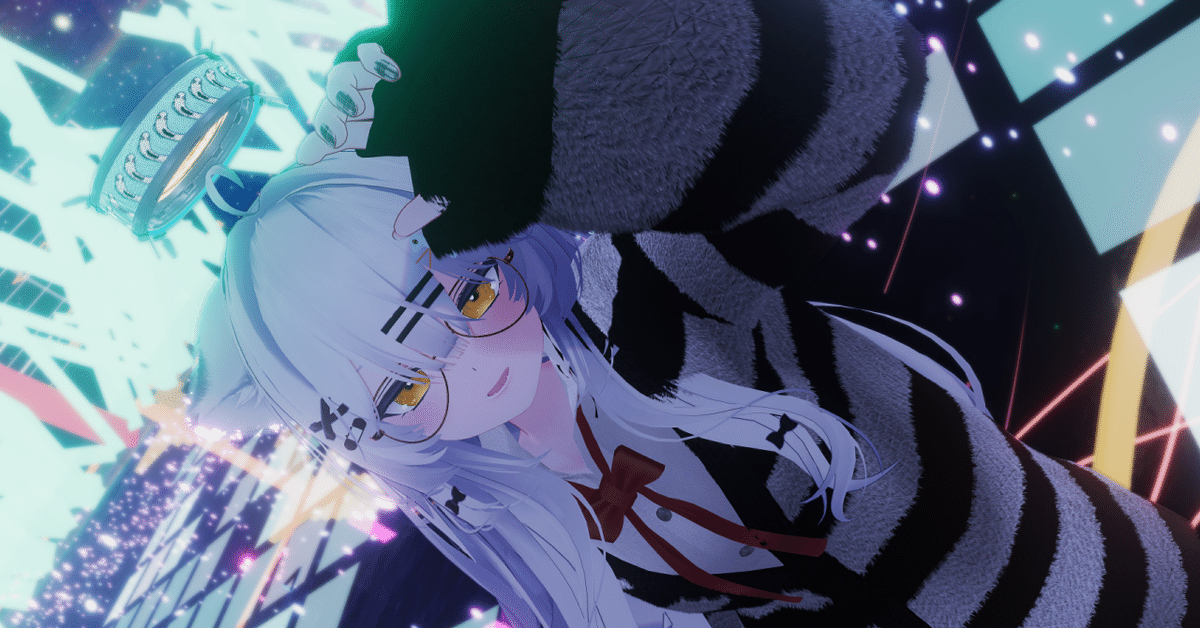
"愛されない"VRChatter
はじめに
今日もついった〜〜〜らんどには、"愛されない"VRChatterたちの苦しみの声が木霊する。
「所詮ネットの世界の話」などと揶揄する人もあろうが、無論彼ら彼女らは生身の肉体を持った人間なので、その苦しみは普遍的なリアルだ。
この記事は人気者になりたいVRChatterや現代社会で孤独に苦しむ人たちへ向けて、「愛される自分」を作るための特別な魅力を手に入れる方法を紹介するものでは全くない。
今回はその「愛されない苦痛」がいったい何からもたらされているのかをいくつかの視点から考えていきたい。
例によって私の実感ベースのお気持ち長文なのでそのつもりで。
加えて特別のお願いとして、この記事を読んで決して納得しないでほしい。
では始めよう。
(ちなみにサムネは記事の内容とは一切関係ありませんが、なんか手元に瑞希のギフトコードがひとつ余っているので欲しい方は私のTwitterかBlueskyに「アド街を見た」と言ってください。「私も見た」と答えますアド街は終了しました)
「苦しみ」はどこから?
「『愛されない苦痛』がいったい何からもたらされているのかってそりゃ『愛されないこと』に決まっているだろう」という声が早速聞こえてきそうだが、「愛されない」ということは本当に苦しいのだろうか?
例えば、砂漠で水を求める人はその渇きに苦しんでいるのであって水の不在そのもので苦しんでいるわけではない。無論これはうがった屁理屈だが、こと心理の問題においてはこういった問題の分解が現実の役に立つ。
さて、「愛されなくて苦しい」はどう分解できるだろうか。
まず、愛というのは他者からの存在の承認である。そして苦しみというのは主観ベースなので、重要なのは「愛されている」という客観的な事実ではなく実感だと言えるだろう。さらに「愛されない」と「苦しい」の間に隠された不満足(上記の例えで言うところの「渇き」)は「自己を肯定できない」という状況を指すと考えるのが自然だ。これらをつなげると「他者からの承認の実感によって自己を肯定できておらず苦しい」ということになる。
今回は
①他者から愛されないこと
②他者からの愛を実感できないこと
③自己を肯定できないこと
の三要素に分けてそれぞれの解決方法を探っていく。
なおこれらの構造として念頭に置くべき事実は、苦しみの直接的な原因は③であり、②はあくまでその原因の可能性の一つに過ぎず、さらに①は②の原因の可能性一つに過ぎないということである。
①他者から愛されないこと
結論から言うと、他者から愛される最も確実な近道は「他者を愛すこと」である。
人との仲を深めるには侵襲性が不可欠であり、愛というのは境界を踏み越えるポジティブな力だ。どちらかが踏み込まなければいけないなら、常に自分から歩み寄ることで相手の動きへの依存を減らすほうがより多くの絆を築くことができるに決まっている。
純粋なテクニックとしてそういった駆け引きを行う人間も確かに存在するが、特別な事情がない限り純粋に「人を愛する」選択をする方が、長期的には双方にとって良い結果をもたらす。そもそも好きになることができない人間とわざわざ仲を深めて愛されることを多くの人は望んでいないだろう。
ではこの方法で「愛されない苦しみ」から逃れることができるのか? 答えはノーだ。
なぜなら、他者を愛する能力は、自分を愛する能力と深く結びついているからである。他者を愛せる人は、多くの場合、自分自身も愛することができる。そしてその結果、自己肯定に他者からの承認を必要としなくなる。つまり「愛されない苦しみ」そのものが、こうした人々には縁遠いものなのだ。
さて、無価値なアドバイスが一段落したところで、世間にはびこる有害なハウツーについても決着をつけておこう。
「他者から愛されたい」と考える人々は、しばしば特別なスキルや権威ある実績によって他者にとっての自分の価値を引き上げようと試みる。無論それらの営為は尊いものだが、こと「愛される」のを目的とするならナンセンスな手段だと言わざるを得ない。
考えてみてほしい。誰かを好きになるとき、そこに優れた技能の有無は関係するだろうか? あるいは逆に、嫌いな人が広く認められる功績を持っていたなら好悪は反転するだろうか?
人間にとって直感は覆し難い強烈な力であり、物事の好き嫌いは実利的な価値判断の遥か手前で直感によって決まる。
たとえば、嫌いな人間が高いスキルを持っていても、それは単に「スキルを持った嫌いな人間」になるだけだ。イーロン・マスクもドナルド・トランプも間違いなく卓越した能力の持ち主ではあるものの、世界中のあらゆる人から愛されているとは言い難い(むしろ高い能力によって多くの人から嫌われているとさえ言える)。
人間が人間の存在そのものを愛するなんてことが不可能であったとしても、「愛する」というのはまさに相手のあらゆる要素に「価値」を超えた愛着を持つ能力であり、つまり私が言いたいことは、「他者から愛される」ために何かをするのは基本的に無意味だということだ。
②他者からの愛を実感できないこと
VRCで何らかのコミュニティに属しているなら、一度くらいはTwitterで「私のことなんて誰も好きじゃない……」というようなフレンドの嘆きを目にしたことがあるだろう。
まさに記事冒頭の「"愛されない"VRChatterたちの苦しみの声」のことだが、たいていは寂しさとともに「普通に結構好かれてると思うけどな」あるいは「私は好きなんだけど……」というような感想を抱くのではないだろうか。実際に「好きだよ!」と直接伝えられてもなお殻に閉じこもり続けることすらある彼ら彼女らの背景にあるのはいったい何なのだろう?
前段で「『他者から愛される』ために何かをするのは基本的に無意味」などという救いのない結論を出してしまったが、なんだかんだ通常人は誰かからそれなりには愛されているものだ。むしろ問題となるのは「それを実感できないこと」である。
理由の一つとして、そもそもそういった人たちが求めているのは愛ではない。ということが考えられる。
その声をよくよく聴いてみると「具体的にどこがいいと言ってくれない」「自分に特別なところは何もない」など、とかく形にこだわることが多い。
しかし前段でも触れた通り、本来人を好きになるのにそういった「価値」というのはあまり影響しないため、愛されたいと願いながらそういった価値にこだわるのは矛盾している。
つまり彼らが求めているのは存在の諸要素への根拠なき肯定であるところの愛ではなく、自分を信じさせるに足る形ある承認で名のある何者かになることなのだ。
人ひとりが口にする「好きだ」という言葉には根拠がなく、自己を確立するのには不十分だと彼らは考える。自らの何が「優れて」いるのか、その特性を通してどんな人間として振る舞えばよいのか。他者からの評価によって自分の輪郭を得ることこそ、彼らにとって不安を和らげる方法なのだ。
しかし形ある評価というものは盤石なように見えて非常に不安定である。仏教から言葉を借りるなら、形あるものは必ず崩れるからだ。
脚の速い人もいずれは年老いて走れなくなる。優しい人も気に食わない人間を邪険にすることはあるだろう。スクショを自慢したVRC初心者はプロのカメラマンかもしれない。形ある承認で自己を確立するということは、そういったあらゆる小さな擦れで自己像そのものにヒビが入るということだ。
そして何より、外から承認をされて一時は満足したとしても、他者からの評価に依存して自己を確立している時点でどこまで行っても足元が崩れる恐怖からは逃れ得ない。他者の主観を完全にコントロールすることなどできないからだ。
このように「愛」とは似ても似つかない根拠ある承認によって何者かになりたがる彼ら彼女らは、それでもなお「愛されたい」という言葉を選ぶ。
この認知の歪みも結局他人を愛するという経験が不足しているせいだと言える。人間が人間をどうやって愛すのか、きちんと内面化できていないのだ。
また本論からはズレるが「他者から愛されない自分」をことさらに主張するのはそのような不幸な立場に自分を押し込めることで「愛さない他者」へと責任を転嫁する被害者意識が働いている場合もあるので、苦しむ友人をケアする側に回りたいのならこの視点も頭の片隅に入れておいたほうが良いだろう。(本人としてはそうして苦しみを回避しているわけで、表現そのものは咎められるべきものではない)
③自己を肯定できないこと
繰り返し述べた通り、愛されないのも、それを実感できないのも、その根源は結局「自分を愛し他者を愛す」ことができないという状況だ。そしてそのことに関して、私にアドバイスできることは何もない。
私はたまたま「人を愛する才能を持って生まれた側」であり、「人を愛せない人」が遭遇する苦しみや痛みを想像することはできても、それを完全に理解することはできない。人が人に人を愛する方法を教える? 土台無理な話だ。
世界の欠如への愛が人への愛と繋がるとか、自己評価と自己肯定感は独立だとか、客観的に見て人生は唯一無二だとか、愛されるより愛する方がよほど気持ち良いとか、自分なりの「愛の理屈」はいくらでも挙げられるが、きっとこんな言葉は私以外の役には立たないだろう。苦しみを小手先の言葉で鮮やかに解決などできない。現実とは「ただそうある」だけだからだ。
それでも「なんか人間嫌いだな」くらいの調子で人を愛することを諦めないでほしいとは願っている。というか、人生なんてものに価値を見出すなら、最終的に人を愛するしか道はない。
だから私が贈るのは一言。
スピッツを聴きな。
さいごに
さて、「愛されない苦しみ」というものを一つのやり方で言語化してきたわけだが、始めにお願いした通りこの記事を読んで決して納得しないでほしい。
ここまで「他者からの承認の実感によって自己を肯定できていないのは苦しい」という前提で話を進めてきたが、そもそも「自己が肯定されないことは苦しい」が真だとしても、自己肯定の方法は他者からの承認に限らずたくさんある。「他者からの承認の実感がない」というのは本来「その方法で自己肯定することはできなかった」というだけのことであり、それがそのまま「苦しみ」となってしまうのは他者から借りた物語性(ナラティブ)のせいだ。
物語性とは言葉という嘘で現実を好きに切り取り、ありもしない"意味"を他人の世界に侵入させる「嘘の中の嘘」である。
いいねが多いやつが愛されてる・たくさんに愛されてるやつが偉いといった価値観、スキルが有るやつは愛されるという因果関係への過剰な信奉。どれも社会に住まう他人の物語がもたらしたものだ。
そしてもちろん、私にとっては人生の実感であるこの記事も、あなたにとっては「他人の物語」でしかない。Twitterでときおり流れてくる「VRCでかわいいと言われるには特別な個性や技術が必要」「お砂糖ができない人は喋り方が不快」といった誠実さの欠片もないテキストたちと同じくらい、あなたにとっては無意味だ。
人間にあるのは身体と五感だけであり、人生は体験の積み重ね以外の何かではありえない。それらの連なりが一見意味ありげな軌跡を描いていたとしても、物語とあなたは現実にはまったく関係ないのだ。
家系ラーメンの一口目のスープ、電車の窓から見えた群青の空、joinしてきたフレンドが私の名を呼ぶ声。感動とときめきの瞬間が意味もなく現れては消えるこの人生が幸せとか不幸せとか、とやかく言われる謂れはない。誰だって。
以上、次会うときまであなたが世界のままならなさや他人の失敗や自分の醜さを愛せますように。それでは。
12/19 「③自己を肯定できないこと」にちょっとだけ加筆。アドバイスの不可能性を強調。
