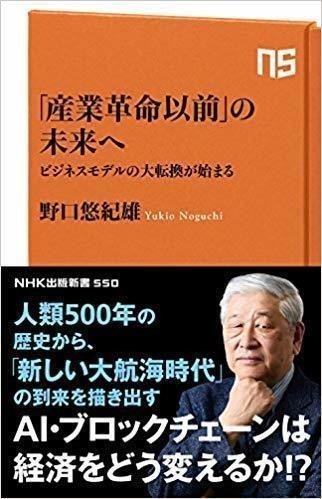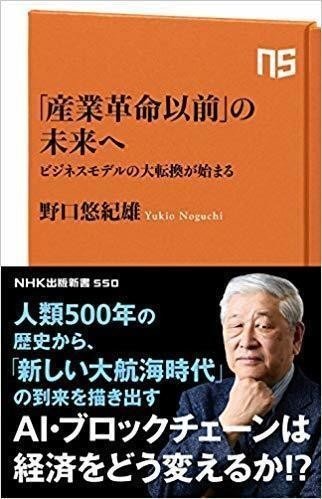第4章 IT革命の勝者GAFA
1.GAFAとは
<時価総額でトップ5を占めるGAFA>
現在、アメリカの時価総額のトップ5は、新しく生まれた産業の新しい企業によって占められている。それらは、インターネット関連製品のアップル、検索エンジンのアルファベット(グーグル)、ソフトウェア開発のマイクロソフト、SNSのフェイスブック、ネット通販のアマゾン・ドット・コムだ(図表4-1)。
これらの企業群は、マイクロソフト以外の4社の頭文字をとって、「GAFA」と呼ばれる。なお、動画配信のネットフリックス(Netflix)を入れてFANGと言われることもある。
これらの企業が提供するサービスは、いまや多くの人にとって、仕事や生活の欠かせない一部になっている。
Googleが提供するGmailが突然使えなくなれば、仕事がストップしてしまう。iPhoneが使えなくなったり、マイクロソフトが提供するウィンドウズに故障が生じれば、(それに代替するものがないわけではないが)、仕事や生活のスタイルをかなり大きく変えなければならなくなる。GAFAの時価総額が巨額なものになるのも、当然のことだ。
図表4-1と図表3-1を比べれば、登場している企業が大きく違うことが分かる。
これは、図表3-1が売り上げ高のランキングであり、これと時価総額のランキングである図表4-1が同じではないためだ。
仮に売上高利益率や将来の期待成長率に大きな差がないとすれば、売上高のランキングと時価総額のランキングは一致するはずだ。そうならないのは、基本的には将来の成長可能性の違いによる。
つまり、図表3-1にあるのは、成長率が低い「過去の企業」だ。それに対して、図表4-1にあるのは、成長率が高い「未来的な企業」なのである。

<新しい会社が、新しいアメリカを作った>
GAFAは、従来のアメリカ大企業とは異なる企業文化を持ち、イノベーションを先導した。GAFAは、IT革命の勝者である。
GAFAが時価総額リストのトップを占めるようになったのは、ここ数年のことだ。そもそも、GAFAは、1980年代には、存在しなかったか、存在していても小さな企業だった。
アップルがiPodを売り出し、GoogleがIPOをしたのが2004年のことであるから、GAFAの台頭は、この10年余りの急速な変化だ。それが目立つようになったのは、この5,6年のことである。
21世紀になってからのアメリカの成長は、GAFAに代表される企業の成長に支えられてきた。
現代のアメリカは1980年代までのアメリカと大きく違うが、伝統的な企業が時代に適応して変貌することによって変貌したのではない。
新しい会社が登場して、新しいビジネスモデルを作り上げたのだ。GAFAは、伝統的な企業とは大きく異なるビジネスモデルを持っている。従来からある技術を使って、それを効率化することで利益をあげているのではない。新しい技術を用いて、従来からある事業のやり方を転換させてしまったのだ。そして、従来の企業を乗り越えた。
日本にこうした企業が登場しなかったことが、「失われた20年」の基本的な原因だ。
<新しい会社が、新しいビジネスモデルを作り上げた>
グーグルの収入は広告料だという意味で、グーグルは広告会社だ。ただ、従来の広告代理店とは違う。
広告ではあるけれども、検索という技術に基づいている。この検索技術は、高度なものだ。グーグルはサービス業ではあるけれども、技術に支えられているという点で、製造業とあまり違いがない。
グーグルは、検索連動広告という新しい広告方式を用いることによって、従来の広告代理店とはまったく異なるビジネスモデルを確立した。これについては、本章の3で詳述する。
フェイスブックも新しいタイプの広告業だ。SNSという新しい方式で個人情報を集め、それをもとに広告を行なっている。
アマゾンは、流通業だが、ウエブショップであり、従来の流通業とはまったく異なる。「ロングテール」と呼ばれる商品(滅多には売れない商品)を適切に扱うことによって、現実店舗を打ち負かした。
ロングテールを扱うには、きわめて多数の商品から消費者が自分の求める商品を見出せるような仕組みを提供する必要がある。そのため、検索エンジンでアマゾンの商品が上位に来るような工夫をしたり、類似商品を見出しやすいようにしたり、購入者の評価を載せたりしている。
次項で述べるように、アップルも、製造業ではあるが、工場がない。だから、サービス業なのか製造業かがあまりはっきりしない。
重要なことは、製造業とサービス業の中間であるような分野が成長しているということだ。
<アップルが確立したビジネスモデルは、ファブレスと水平分業>
アップルは製造業だが、iPhoneという新しい製品を開発し、世界的水平分業という新しい生産方式を確立することによって、新しい製造業のビジネスモデルを切り開いた。
第3章で見たように、IT革命によって水平分業が始まった。それまで垂直統合でPCを生産していたアップルも、i-Podの生産から水平分業に転換し、新興国のEMS生産を活用して低コストでの生産を行ない、高い利益を実現するようになった。
これは、世界中のメーカーから部品を調達し、最終組み立てはEMS(エレクトロニクス製品の生産受託企業)に委託する方式だ。アップルは、EMSとして台湾のホンハイの子会社フォックスコンを用いている。
この方式は、市場を通じた流動的な関係であるという意味で、系列メーカーとの間での固定的な関係である垂直統合生産とは異なる。
これによって、ファブレス化、すなわち、工場を持たない製造業が可能となった。アップルは、製造工程を自社内に持たず、企画・設計と販売に集中している。
製造業がファブレス化すると、利益率が高くなる。なぜなら、開発過程の利益率は非常に高いからだ。今まで誰もつくってなかったものを作り出す。そのことの利益に対する貢献は非常に大きい。
アップルは、iphoneというものを発明した。これは携帯電話のような格好をしているが、携帯電話ではなく、コンピュータだ。こういうものがあり得るということを考え出し、その基本的な設計をした。それが非常に大きな価値を生み出した。
そして、これを販売する。リンゴのマークがあると、人々は、この機械は信頼できると思って買う。これはブランド力だ。ブランド力をもって販売することも利益率が高い。
その半面で、製造過程の利益率は低い。中国が工業化することによって、利益率はますます下がっていった。アップルは、製造の利益率が下がってきた過程を自社では行わず、中国を利用した。
そして、利益率が高い部分だけに特化したのだ。つまり、アップルは、考えることと売ることしかやっていない。製造過程を抜いてしまったわけだ。このため高収益が可能となったのだ。
これは、新興国が工業化した世界において、先進国の製造業が歩むべき方向を示している。このように変身した製造業は、サービス産業とあまり変わらなくなる。製造業とサービス産業という区別が、あまり重要性を持たなくなるのだ。先端的な分野では、製造業とサービス業の差が曖昧になりつつある。
こうした変化に対応できたか否かは、アップルとシャープを比べると明らかだ。前者は水平分業、後者は垂直統合だ。そして、これは、アップルとシャープの差だけでなく、より一般的に、日本経済とアメリカ経済の差なのである。
2.GAFAを作った人々
<アップルを作ったスティーブ・ジョブズ>
スティーブ・ウォズニアックが設計してガレージで作ったAppleIをスティーブ・ジョブズが販売したのは、1976年のことである。翌年発売されたAppleIIは大成功を収め、PCの時代が到来した。
このストーリーは、19世紀のカリフォルニアのゴールドラッシュで、リーバイ・ストラウススがブルージーンズを作り上げた物語と重なる(注)。この2つは、何となく雰囲気が似ている。
どちらも、大企業の大工場で作られた製品ではない。どちらも、権威や権力とは関係がない。政治家の庇護や独占的支配力といったものとも、無縁だ。
スティーブ・ジョブズが2011年に亡くなったとき、そのニュースは世界中の新聞のトップ記事となり、いくつもの雑誌が特集を組んだ。ジョブズに関する本も、数多く刊行された。
彼以外のどんな経営者が(あるいは政治家や文化人が)死去したところで、このような扱いはされないだろう。
スティーブ・ジョブズの死は、なぜ多くの人に悼まれたのだろうか?
それは、多くの人が望んでいた「夢」を、彼が実現してくれたからだ。
彼が実現した「夢」とは、「こんなものがあったら便利なのにな」というものである。それだけでなく、「カッコよくて、人に見せたくなる」(英語で言えば、cool!と言いたくなる)ものだ。iphoneは、この両方の条件を満たしていた。だからこそ、熱狂的なファンを獲得したのだ。
1981年、大型コンピュータを支配する超優良企業IBMが個人用コンピュータ(PC)に乗り出したとき、アップルコンピュータは、"Welcome, IBM. Seriously"(ようこそIBM。いや、僕は真面目だよ)という全面広告をウォール・ストリート・ジャーナルに掲載した。ガレージ発企業の面目躍如たるものがある。
ジーンズを履いてIBMコンピュータを操作したら、およそ場違いだ。しかし、ジーンズ姿でiphoneを使うのは、サマになる。この2つは、同じ文化圏に生息しているのである。
ジョブズの言葉。「どうすれば起業家になれるか?自分がほんとうに情熱を傾けられるものを探すことだ」「毎日、ああ、今日はすばらしいことをしたなあと思いながらベッドにはいりたい」。
好きでしようがないことを追及し、それが新しい製品とビジネスを生む。それに成功した企業の時価総額が、世界第1位になってしまう。アメリカでは、こうしたことが現実に生じているのである。
(注)リーバイストラウスとブルージーンズについては、拙著『アメリカ型成功者の物語り』(新潮文庫)を参照。
<グーグルを作ったラリー・ページとセルゲイ・ブリン>
グーグルを作ったラリー・ページとセルゲイ・ブリンは、スタンフォード大学コンピューターサイエンス学科の大学院生だった。
1996年頃に、自分たちの論文をもとに新しい検索エンジンを作った。それまでの検索エンジンとは違って、彼らのエンジンは、人々が知りたい順に検索結果を並べる非常に優れたものだった。大学のコンピュータを使ってテスト公開したところ、多数のアクセスを集めた。
大学のコンピュータではアクセスを処理できなくなってしまったので、大学の外で事業として行うこととし、98年に 「グーグル」という妙な名の会社を発足させた。1998年に会社を設立したときには、他のネットベンチャーのように、ガレージで操業していた(しかも、知人の家の)。
事業の拡張に必要な資金は、ベンチャーキャピタルからの出資を仰いで調達した。
グーグル検索エンジンのデモを見た有名なベンチャーキャピタリスト、アンディ・ベクトルシャイム(サン・マイクロシステムズの共同創業者で)は、即座に出資を決断し、10万ドルの小切手を切ると言った。 ところが、それを受け入れるのに必要な銀行口座をグーグルが持っていなかった、という逸話がある。
この出資でオフィスを構えることができるようになった。その場所が、パロアルトの ユニバーシティ・ アベニュー 165番地にある自転車屋の2階だった
従業員は、03年には300人程度に過ぎなかった。だから、伝統的大企業と肩を並べるようになるとは、誰も考えていなかった。
彼らはまた、ゴルフ嫌い(つまり、接待サービス嫌い)だった。そして広告嫌いだった。彼らは、論文の中で、従来型の広告の害悪について論じていたほどである。
3で述べるように、グーグルが始めた「アドワーズ広告」は、小企業や零細企業がインターネットで申し込んで行う広告だ。それまでの、大企業の広告とは全然違う。
グーグルは、最初は、「プレミアム広告」と呼ばれた大企業の広告を導入した。これがかなり順調な成果を挙げていたにもかかわらず、それをやめて、小企業向けのアドワーズ広告を始めたのである。
それは、大企業から広告をとるため、営業活動をするのが嫌だったからだろう。顧客をディナーに招待して説明するなどという仕事は、彼らの望むところではなかったのだ。それだからこそ、アドワーズ広告を始めたのだろう。
グーグルは、検索エンジンを変えただけではなく、広告のビジネスモデルをも変えたのだが、それは、創業者の人柄によるところが大きいように思われる。
<Facebookを作ったマーク・ザッカーバーグ >
「フェイスブック」は、マーク・ザッカーバーグと、彼のハーバード大学のルームメイトたちによって創業された。
大学には、新入生の写真や出身高校などを載せた「フェイスブック」という印刷物が従来からあった。しかし、電子版がなかった。それを求める学生の声が強かったが、大学は消極的だった。個人情報を巡る法的なトラブルが起こる危険を恐れたためだ。
そこでザッカーバーグらがはじめたのが「コースマッチ」だ。
講義名をクリックすると、受講生一覧が表示される。学生をクリックすると、受講している講義の一覧が現われる。
これがなぜ評判になったかと言えば、学生たちは、ある講義を誰が受講しているかに強い関心を持っていたからだ。それについての情報は、友人の範囲を広げるのに役立つ。
有り体に言えば、「デートの相手に接近するのに役立つ」。あるクラスで美人の隣に座る幸運に恵まれたら、コースマッチで検索して彼女が取っている他の講義が分かるので、それを取るのだ。
ここには、交友関係の構築を偶然にまかせず、積極的に行なおうという欲求が現われている。これが、SNSの本質的な部分だ。このサービスは大成功した。ザッカーバーグは、「人を結びつける方法がいろいろあることを発見した」と述べている。
ここには、多分に「遊び」の要素がある。人と人との結びつきというのは、本質的にそうしたものなのだろう。それをうまく引き出せたことが、Facebook成功の秘密だ。
本章の4で述べるように、遊びの精神は、フェイスブックの現在の本社の物理的構造にも表れている。それが自由な発想を助けている。
<現代のアメリカンドリーム>
以上で述べた人々は、技術の大きな変化によって生ずるビジネスチャンスを適切に掴んだ。その点では、第2章で見た「光ピカ時代」の人々と同じである。技術の大きな変革期には、必ずそのようなチャンスが訪れるのだ。
しかしこれらの人々は、「金ぴか時代」の人々とは性格がかなり異なる。
「金ぴか時代」の成功者の多くは、貧しい生活の中でまともな学校教育も受けず、下積みの仕事の中で人一倍の努力をして這い上がろうとした。資金を貯め、誰かに認められ成功の手がかりを掴んだ。その意味で、典型的な克己・奮励努力型の人々だ。ひと昔前の修身の教科書に出てくるような人々である。
しかし、この章で述べた人々は、以上で見たように、好きなことをやっていたら大成功してしまった。少なくとも、金儲けのために自分の信条を曲げたり、生活を犠牲にしたりしたわけではなかった。やりたいことがたまたま社会の求めていることに合致し、それが途方もない豊かさを生んだのだ。
GAFAの創業者たちは、ベンチャーキャピタルから資金の提供受け、大きな可能性に挑戦し、同時にリスクにも挑戦した。その意味では、大航海時代に新しいフロンティアを切り拓いたコロンブスやマゼランなどのパイオニアたちと多分同じ種類の人間なのである。 金を儲けたいとか、経済を支配したい、といった目的ではなく、自分のやりたいことをやった。そして、その会社の時価総額が世界一になってしまった。これが、現代のアメリカンドリームだ。アメリカは、未だにこうしたことが可能な社会なのである。
3.グーグルの広告ビジネスモデル
<グーグルの無料ビジネスモデル>
新しい事業の成功のために、技術は重要だが、それだけでは十分でない。それを活用するビジネスモデルが重要である。実際、優秀な技術を持ちながら失敗した企業は、数え切れないほどある。
スマートフォンの原形はブラックベリー社のものだが、アップルのiPhoneに敗退した。Google以前にも以後にも沢山の検索エンジンが作られたが、それらのほとんどは消滅した。
問題は、どのようにして収益をうるかだ。検索エンジンがいかに優れていても、それから収益をうるのは容易ではない。
普通の発想なら、検索サービスに課金する。例えば、会員制にする。しかし、こうしたら、Googleは成功しなかっただろう。
まず、利用者が減る。他の検索サービスが無料なら、人々はそちらを利用する。しかも、課金にはコストがかかるので、大した利益は上げられない。
PCに組み込んで、PCの価格の一部に利用料金を含ませる方法も考えられる。マイクロソフトは、この方式で膨大な収入を得た。しかし、グーグルは、これも行なわなかった。では、大企業から、ビジネス用に使用料を得ているのだろうか?しかし、それもない。
そして、検索サービスを無料で提供した。グーグルはそれ以外に、Gメール、グーグル・マップ、ストリートビュー、グーグル・カレンダ、デスクトップ検索など、さまざまなサービスを始めた。これらのすべてが無料だ。従来のメールサービスは有料の会員制だったので、有料にしようと思えばできたはずだ。しかし、グーグルはそうしなかった。
サービスを無料で提供しているのに、どうして巨額の時価総額になるのか?グーグルはどこで収入を得ているのか?
<検索連動広告>
グーグルの収入源は、検索連動広告だ。これは、検索語に関連すると思われる内容の広告を、検索結果の画面に出す方式である。例えば、利用者が「車」と入力すれば、自動車会社の広告を出す。
従来の広告でも、「化粧品なら若い女性が読む雑誌に」というように、広告ターゲットと媒体との関連付けは行われていた。しかし、求めているものは個人によって違う。正確な関連付けのためには詳細な顧客情報が重要だが、それを入手するのは容易でない。
ところが、検索やメールのサービスを無料で提供すれば、非常に詳細な個人情報が集まる。その情報を使えば、人々が求めている内容の広告を打つことができる。連動広告は、Gメールでも行われている。
従来式広告との効率の差は明らかだ。魚がいるかどうか不確かなところに網を投げるのと、魚がいると分かっているところに網を打つとの違いだ。「テレビの広告は見なくても、連動広告は見る」と言う人は多い。
効率がよければ、広告料を安くできる。こうして好循環が起きる。しかも、検索とメールは、グーグルが極めて高いシェアを実現しているので、他の広告業者が同じことをやろうとしてもできない。グーグルの高収益は当然だ。
<アドワーズとアドセンス>
グーグルは、単に検索連動広告を導入しただけではない。新しい仕組みの広告を開発した。
第1は、競争入札方式の導入だ。検索結果が表示される画面には、広告を掲載できる場所がいくつかある。そこにさまざまな検索語に応じて広告を掲載する権利を、入札で決めるのだ。
最も高い価格で応札した者がその位置に広告を掲載することができる。ここにおいて、グーグルは従来の広告モデルとは性格が大きく違う広告モデルを採用したことになる。大口広告主との個別交渉から、公開入札という競争方式に転換したのだ。
入札はインターネットを通じて行われ、落札した企業はクレジットカードで料金を支払う。自動化されて、従来よりずっと簡単になった。単価を低くできるので、零細企業でも広告を出せるようになった。以上のような特徴を持つ広告は、「アドワーズ」と呼ばれた。
スティーブン・レヴィは、『グーグル』(阪急コミュニケーションズ)の中で、「(グーグルは)ネットで莫大な収益を上げる秘密の方程式を解いてしまった」「(これは)人類史上最大の成功を収めた広告システム」であり、「いまでも競合他社はそれに匹敵するモデルを生み出せないでいる」としている。
第2は、「アドセンス広告」であり、これは、一般の人々が書いているウェブページに広告を出すものだ。ページの作成者は、ブログやホームページに広告を貼り付けて収入を得る。
こうして、グーグルのビジネスモデルは、途方もない収益を生み出すこととなった。
4.大企業病から免れうるか?
<ベンチャーキャピタルとIPOの役割>
GAFAは、ベンチャーキャピタルの出資とIPO(株式公開)で資金調達した。Google、 Facebook、アマゾン、アップル。どれもそうだ。
実は、こうした資金調達はGAFAに限ったものではない。IT産業の新しい企業が共通して用いてきた方法だ。
すでに1970年代のアメリカで、インテル、サン・マイクロシステムズ、マイクロソフト、アップルコンピュータなどの企業が、ベンチャーキャピタルから資金を得て成長した。GAFA以外にも、ヤフーやツイッターなどが、ベンチャーキャピタルからの資金援助を得てスタートした。
IT時代において、技術革新は、巨大企業から生まれたのでなく、ベンチャービジネスから生まれた。株式会社組織は、新しい技術を開発するための組織としては、うまく機能しなかったのだ。
ただし、IPOは、株式市場からの資金調達である。そして、IPOの際には、投資銀行が重要な役割を果たす。その意味では、GAFAの資金調達は伝統的な金融の仕組みに依存している。ところが、第6章で述べるICOは、伝統的な金融にまったく依存しない資金調達の仕組みである。
<優れた技術やアイディアが、極めて多額の収益をもたらす>
第2章で述べたように、産業革命以来の潮流は、大規模化、組織化であった。それが工場制工業において効率を向上させる基本的な手段だったからだ。
しかし、いま潮流は、大きく転換しようとしている。優れた技術やアイディアが、極めて多額の収益をもたらすようになったのだ。
すでに述べたように、 GAFAの全てが、このような革新的技術によって支えられている。これらのいずれもが、ごく少数の人間によって生み出された革新的なアイディアだ。
GAFAに限らず、高度サービス産業では、創造性から生み出される革新が、きわめて大きな利益と成長をもたらす。だから、個人の独創性を引き出す労働環境を整備することが、たいへん重要だ。
このため、アメリカをリードする先端ハイテク企業は、さまざまな工夫をして、大企業病に陥ることを避け、個人の創造性を引き出そうとしている。
<大企業病に陥らない工夫>
とりわけ重要なのは、大企業病に陥らない工夫だ。
ジリアン・テットは、『サイロ・エフェクト』(文藝春秋)の中で、組織が縦割りのセクションに分かれてしまう現象が起きているという。
99年にソニーが3つの全く異なるデジタルウオークマンを発表したのが、その例だ。かつては創造力に溢れていたソニーの技術者たちは、際限のない縄張り争いに巻き込まれ、協力する意思や能力を失っていった。
だから、ソニーと同じ運命を辿らないための努力が必要だ。
サイロに陥らなかった例として、Facebookがある。急成長した同社は、2008年にコンピュータ技術者が150名を超えた。「ダンバー数 の理論」という考えによれば、最適な社会集団の規模は150人だ。 そこで、新入社員研修プログラムを取り入れ、内向きの硬直的な集団になるのを防ぐため、非公式な社会的絆を作ろうとした。
Facebookの本社は、大学のように、「キャンパス」と呼ばれている。キャンパスの周りは、サンフランシスコ湾沿いの湿地帯。そこに、レストランはもちろんのこと、それ以外の店もある。つまり、ここは、フェイスブックの本社というより、1つの町になっている。誰でも入ることができるので、観光客もかなりいる。
Googleの本社は、「グーグルプレックス」と呼ばれている。オフィスのほか、公園、世界の料理を提供する無料の社員食堂、フィットネスジムやサウナなどもある。「ブティックホテル」を意識し、「街の広場」のような雰囲気となるよう設計したと言われる。
カフェテリアで1日中食事を提供して従業員間のコミュニケーションを促進しようとしたり、仕事時間の20%を与えられた仕事以外の好きなプロジェクトに使ってよいという「20%ルール」を設定したりしている。
<働き方が変わる>
GAFAのような先端企業における働き方は、従来の大企業とは違う。
ここでの働き方は、産業革命以降の大規模な工場における工場労働者の働き方ではない。こうした職場で重要なのは、統制のとれた軍隊的な組織が、一糸乱れずに行動することではないのである。
ここでは、軍隊的な組織のように規律正しく労働することが重視されるのではなく、自由な雰囲気の中で、個人の創造的な能力を発揮させることが重視される。これは、産業革命以前の独立自営業の雰囲気だ。
そして、規制のない自由な市場の中で経済が発展する。
組織から個人へ、画一性から多様性へという変化が生じている。組織に雇われて安定して働く時代は終わった。それに代わって、個人企業やフリーランサーが重要になってきている。
5.技術のジャイアントはいつまで続くか?
<ビッグデータを支配するGAFA>
2017年4月7日のフィナンシャルタイムズが伝えたところによると、グーグルは、自動運転車を開発している1人のエンジニアに対して、1億2,000万ドル(133億円)のボーナスを与えた。
日本の企業でいかに企業に貢献しても、100億円を超えるボーナスを得られることはないだろう。
先端的なスタートアップ企業も、これでは競争できない。企業価値自体が、1億ドルには及ばない場合が多いからだ。スタートアップが技術を開発しても、グーグルなどに買収されるしか方法がない。
この記事によると、アマゾン、アルファベット、インテル、マイクロソフト、アップルは、年間650億ドル(約7兆2000億円)の研究開発費を支出している。これは、アメリカの株式公開企業400社の合計よりも多い。これらの企業は、技術開発を独占しているのだ。
日本では、企業、非営利団体・公的機関及び大学等の2015年度の科学技術研究費の総額が、18兆9391億円だ。上記5社の数字は、この4割近くになる。
GAFAは、現在の技術開発を支配しているだけではない。将来においても、そうであり続ける可能性がある。
それは、ビックデータという重要な資源を独占しているからだ。人工知能を切り開く可能性は、これらの5社に独占されていると考えざるをえない。
そうであれば、強いものがますます強くなる。GAFAが未来の社会を支配するだろう。
インターネットは社会をフラットにすると言われた。しかし、現実に生じているのは、その逆なのである。
<市場を支配するGAFA企業>
GAFA企業は、技術面でジャイアントになっただけではない。アマゾンは小売業で支配的な位置を獲得するようになり、多くの書店をつぶしてきた。
IT革命は社会をフラット化すると期待されていたのだが、実際には主役が交代しただけで、巨大企業が経済を支配するというう構造そのものは、変わらなかったわけだ。
なぜこうなったのであろうか?
その大きな原因の1つは、インターネットを通じて送金することが難しいことである。Googleのモデルは広告モデルだ。これは、ウェブで情報の有料提供が難しいという事情に影響されている。
アマゾンの場合も、巨大な企業であるために人々は安心してクレジットカード番号を送るが、零細な小売店であれば、このようなことは、難しい。
こうした状況は、次項で述べるように、仮想通貨の発展によって変わる可能性がある。そうなれば、GAFAが支配する世界は、大きく変わることになるだろう。
<広告ビジネスモデルは続くか?>
しかし、GAFAにも弱点がある。
グーグルについて、そのことが言える。
なぜなら、同社の収入の9割近くは広告料収入であり、それが将来も続くかどうかについて、疑問があるからだ。
グーグルの資料によると、2016年の12月期(16年9~12月) において、広告料収入が224億ドル、その他の収入が34億ドルだ。つまり、広告料収入が86.8%を占めている。
同社は、自動運転などの先端的な技術の研究開発を行なっており、これが実用化すれば、きわめて巨額の収益をもたらすだろう。しかしそれは将来の話だ。
問題は、アドセンス広告だ。ウエブページの作成者は、ウエブの情報を有料で売ることができないため、広告にスペースを貸して収入を得ている。
すでに述べたように、アドセンス広告は、ウェブにおける情報発信のビジネスモデルに大きな影響を与えた。
しかし、広告収入型モデルでは、いかにして大量のアクセスを獲得するかが問題となる。それが嵩じて、情報の質が低下した。
ところで、課金型モデルが採用できなかったのは、これまでの送金手段では、少額課金が難しかったからである。
しかし、仮想通貨のマイクロペイメントを可能とする技術開発がなされれば、送金コストはゼロに近くなる。銀行や中央銀行が仮想通貨を発行する場合にも、ゼロ近いコストでの送金が可能となるだろう。
これによって、ウェブにおける有料の情報提供が広まる可能性がある。広告をなくせば、ページはすっきりして見やすくなる。提供される情報の質が高ければ、広告に依存しない情報提供ビジネスモデルが可能になるだろう。
情報の有料化ができても、アドワーズ広告は影響受けないかもしれない。しかし、アドセンス広告が減少する可能性は大いにある。これは、グーグルのビジネスモデルの意外な弱点である。
アドワーズとアドセンスの収入は、ほぼ同額と言われる。だから、全体の広告料収入がゼロになることはないが、現状より大きく減少する可能性は十分ある。
ホームに戻る
野口悠紀雄の新刊書(2018年)立ち読みコーナー