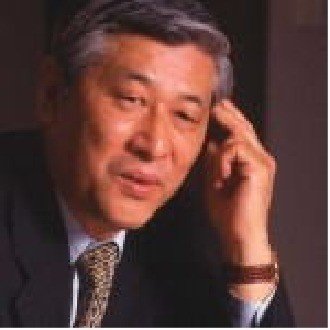「超」AI整理法 無限にためて瞬時に引き出す(第2章の3)
3.分類するな。 ひたすら検索せよ
◇GREP検索を用いていた時代
ITの発達によって、扱う情報の中心は、紙情報ではなく、デジタル情報(電子的な情報)になってきました。PCなどの記憶容量が「ムーアの法則」(もともとの法則は「集積回路上のトランジスタ数が18カ月で倍増する」というものですが、その後、さまざまな電子製品について言われるようになりました)に従って拡大し、スペースの制約はなくなりました。しかし、整理の必要性は高まってきました。なぜなら、大量の情報を保存することになるからです。
デジタル時代には、検索技術が発達し、「整理の方法」は、「検索の方法」になりました。整理法のノウハウの半分は、検索法のノウハウになったのです。デジタル情報時代のモットーは、「分類するな。ひたすら検索せよ」です。
ここで重要になるのが、検索のテクニックです。検索のテクニックとしては、まずウェブにある資料を検索する場合の方法があります。これについては、『超「超」整理法』(講談社、2008年)で書きました。要は、「and検索」を使ったり、関連のありそうな概念をつぎつぎにたどっていくなどの方法(これを「八艘飛び検索」と名付けました)によって目的のサイトを見いだすことです。
本書では、ウェブの検索ではなく、自分が作った資料やドキュメントの検索について考えたいと思います。自分が作った文書の検索の場合には、ウェブ上の文書の検索とは、若干異なる問題が発生します。
『「超」整理法』を書いていた頃に私が用いていたのは、GREPという検索アプリです。これは、それまでの検索が同一文書内のものだけだったのに対して、複数の文書を横断して検索する機能を持っており、きわめて便利でした。これを用いて検索する時期が、かなり続きました。
ところが、文書の数が多くなってきて、これでは収拾がつかなくなってきました。
GREP検索の大きな問題は、検索キーワードとして1つの単語しか用いることができず、「and検索」ができないことです。このため、十分な絞り込み検索ができなかったのです。そこで、捜索するファイル(文書)の範囲を限定することになりますが、限定してもあまりに多くの対象がヒットしてしまうようになったのです。
その後、グーグルが「デスクトップ検索」というサービスの提供を始めました。私もしばらく使っていたのですが、あまり使い心地はよくありませんでした。このサービスは、2011年に中止されています。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?