
初投稿✨
そろそろこの時期から来年の2月21日に行われる 理学療法国家試験に向けて勉強を開始した方が 少しずついるのではないでしょうか??
国家試験は勉強すれば受かるという先輩の アドバイスを真に受けて余裕をかましていましたが、先日受けた模試でとんでもなく低い点数を 叩きだしてしまい少しずつ勉強を始めないと いけないなと焦りを感じました(笑)
国家試験をパスするためにどれくらい点数を 取ればいいのかもうご存じですよね?😉
総得点を168/280を取ること!
ちょうど6割とれば合格できる比較的易しい? 国家試験だと思います。
さらにもう1つ条件があります
実地問題(理学療法士の専門知識が問われる問題)を43点以上(15問以上)取ること!
実地問題とは理学療法士としての専門知識に関する問題で国家試験には40問あり1問がなんと3点 という高い配点を示しています。この実地問題で15問以上取らないと足切りで不合格になってしまいます...

そのため国家試験で高い点数や合格点を狙うには実地問題はあまり落としてはいけないということになりますね😩
今の時期は卒業研究や実習がある学校はあるので12月から本格スタートになる人が多いと思いますが、1日少しずつやっていきましょう👊🏻
そこで今日は『アンダーソン・土肥の分類』についてまとめます👀
アンダーソン土肥の分類とは?

リハを行ってはいけない基準、リハを中止する基準となるものなどをまとめたもので、リスク管理に必要な評価項目です。
これは今年のどこかの模試か国家試験で出ると僕自身思っています(笑)
たしか教科書などの表では、リハを行わないほうが良い場合、途中で中止する場合、一時中断し回復を待つ場合の3通りで列挙されていて正直僕はそれだとかなり覚えづらいと思うので次の4つの違う視点で見てみるのも良いと思います。
1.血圧

血圧は中枢系の疾患などのリハなど高齢者などのリハなどで絶対といっていいほど 必要になってくる評価指標ですね。
まずはリハを行う前にSBP(収縮期血圧)が200以上DBP(拡張期血圧)が120以上あればリハを行わないほうが良いです。血圧がかなり高いですよね。
次にリハ中にSBPが40以上またはDBPが20以上 上昇した場合は中止します。
ex).リハ前150/110→リハ開始後190/125や180/135になった場合は中止。 前者はSBPが40上昇、後者はSBPが40以上 上がってないがDBPが25上昇した
土肥の基準を改変した中村による 理学療法実施基準においても
SBPが200以上DBPが120以上はリハを行ってはいけないと書いてあります🙅♂️
200と120、40と20は数値で 覚えておきましょう!
2.脈拍

次に脈拍に関してです。脈拍の評価として 徐脈、正常、頻脈の3つに分けられることは ご存じですよね?
徐脈<60回/分 60回/分>正常<100回/分 頻脈>100回/分
アンダーソン・土肥の分類では、
リハ前に脈拍数が120回/分以上あれば 行わないほうが良い
60~100が正常なので120ともなれば かなりの頻脈状態ですよね🥵
1秒間に2回以上の拍動ということになります
その状態でリハを開始すると危険なイメージが つくかと思います🤷♂️
次に脈拍のリハ中止基準です
リハ中に脈拍が140回/分を超えた場合は中止する
1秒間に約2.33回拍動する計算になります。 イメージが湧かない人は、1度自分で時計を みながら数えてみましょう⌛️ 結構これも早いと思います。
ここまで大丈夫でしょうか? 次が少し覚えるのが厄介です。
次は脈拍のリハ中断-回復基準になります。
脈拍が120回/分を超えた場合 脈拍が運動時の30%を超えた場合 =2分安静で10%以下に戻らない →運動中止or軽い運動に切り替え ex).通常の運動時80回/分→104回/分(+30%) 2分間の安静で10.4回以下=93.6回/分にならない
もういろんな数字が出てきてややこしいですね(笑)
基準はまず運動前に120回/分を超えていないこと!
次に運動して120回/分を超えないこと、かつ140回/分を超えたら中止
運動時脈拍の30%をもし超えた場合は、2分間安静して10%以上戻ったら再開!!
3.心電図
心波形モニターも大事になってきます。
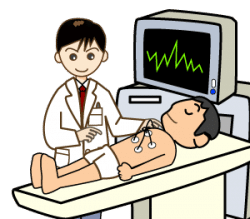
1分間に10以上の期外収縮、心房細動や 心室性頻脈あるいは徐脈出現は中止 1分間に10以下の期外収縮が出現した場合は 一時中断する
心電図に関しては10という数字、期外収縮や不整脈がネックですね。
4.身体所見
これはモニターや血圧など機械に頼ったものではなく、患者の状態を実際に見てリハを行うか 中止するか、中断するか判断するものです。
リハを中止する基準は1つだけです!
リハ中に中等度の呼吸困難、めまい、嘔吐、 狭心痛の出現



おまけでこれは病院にいる患者だけではなくジムに運動に来た高齢者でも起こる可能性があるので、この症状が出た場合はすぐに通報しましょう。
さらにリハを一時中断する基準も1つだけです!
リハ中に軽い動悸、息切れを訴えた場合は中断して回復を待つ
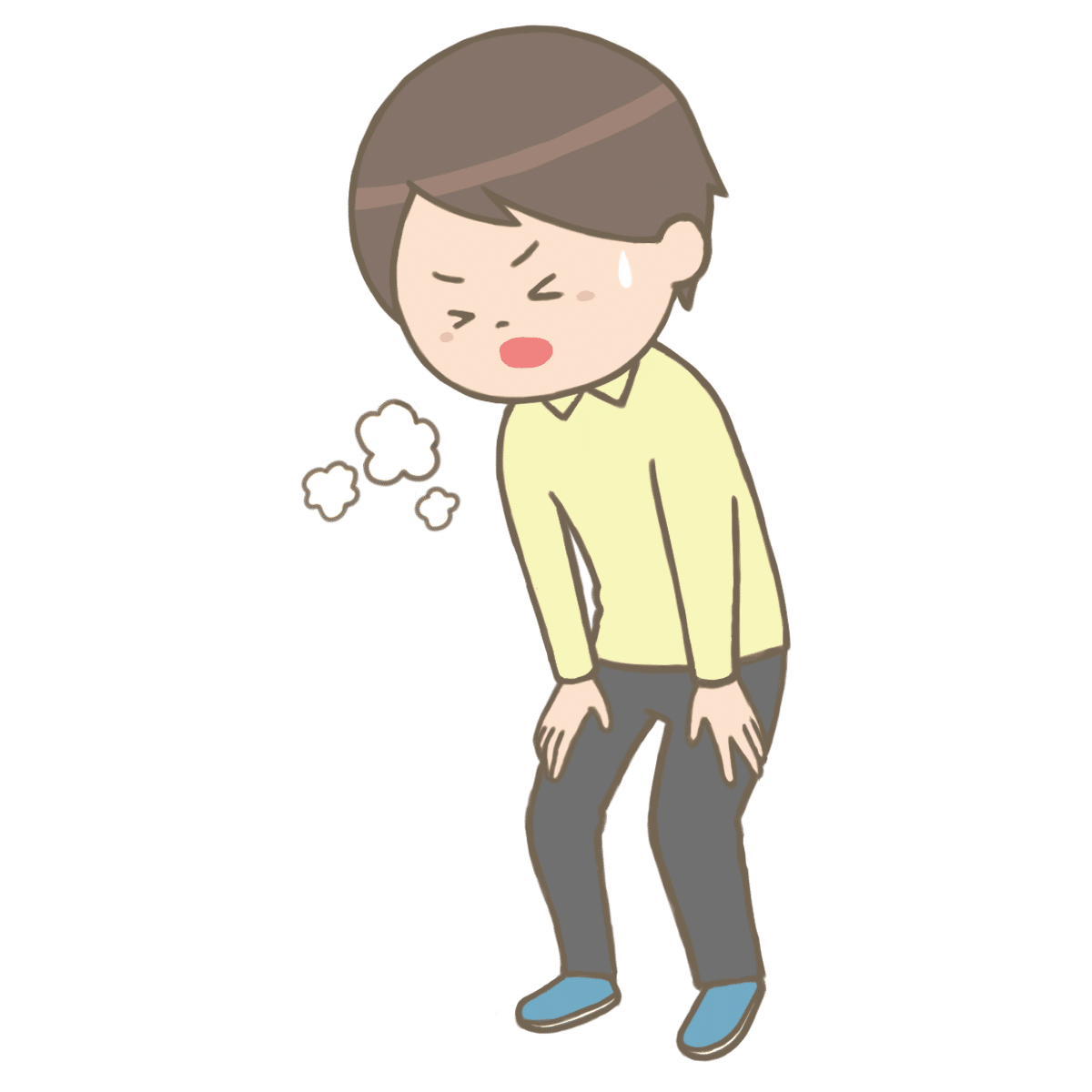
息切れを起こしているのに運動を続けたら最終的に呼吸困難になる可能性もあるので そこは一旦中断しましょう。
最後にリハ前の中止基準になります
1.リハ前に動悸、息切れがある 2.著しい不整脈 3.新鮮心筋梗塞1か月以内 4.労作性狭心症(動くと胸部痛を訴える) 5.うっ血性心不全の所見が明らか

不整脈があればもちろんリハを行うのは危険なのはわかりますよね。最近発症したばかりの 心筋梗塞や労作性狭心症にも注意が必要です。
3つを通して、特にキーワードになるのは
動悸、息切れ、呼吸困難、不整脈、 新鮮な心筋梗塞
といったところですかね?
これで終了です!
アンダーソン・土肥の分類は
1.血圧
2.脈拍
3.心電図
4.身体所見
の4つから構成されたリハを安全に行っていくための指標です
繰り返しになりますが教科書などの表ではリハを行わないほうが良い場合、途中で中止する場合、一時中断し回復を待つ場合の3通りで列挙されていて正直僕はそれだとかなり覚えづらいと思うのでこういった4つの違う視点で見てみるのも良いと思います🙆♂️
最後まで読んでいただきありがとうございました

~沖縄の海~ 撮影カメラ:SONY α7Ⅲ
