
プレトタイプとしてのタモリさん〜Google×スタンフォード NO FLOP! 失敗できない人の失敗しない技術
どんな書籍か
「Google×スタンフォード NO FLOP! 失敗できない人の失敗しない技術」これは、新しいサービスや製品を作ろうとする際に、そのアイデアが本当にニーズのあるものなのか、市場調査ではなく自分で「プレトタイプ」(著者の造語)を数字を使って確かめてみようと説く書籍です。
実際に役に立ちそうな事例と考え方が満載です。翻訳書でリーン開発・スタートアップ系の書籍がいくつかあると思うのですが、間違いなくオススメしたい一冊です。ページ数多いですが、読みやすいのであっという前に読めてしまいますよ。
もう少し詳しく紹介
Part.1「事実を直視しろ」では、「ほとんどの新製品は市場で失敗するーーたとえ、きちんとつくって売ったとしても」として、その理由を説明している。有名で世界のトップレベルにあるような、コカ・コーラ、ペプシコーラ、ディズニー、グーグルなども新製品の投入に失敗しているといいます。
そもそも間違っている = Wrong Itな製品ではなく、そもそもが間違っていない = Right Itな製品をつくるためには、直感・意見・他人のデータではダメで、自分自身でデータを集めよ(YOD)と説いている。
そのためには、プロトタイプよりも前段として、プレトタイプを行うべきだと説きます。プレには、「〜より前に」という意味と「プリテンド」=ふりをする、という意味が込められている。プロトタイプを作ってしまうと、予算と期間がかかってしまうので、その前にプレトタイプをもってして、アイデアの確かさを検証しようと説く。
プレトタイプとは、「そのアイデアをそもそも手がけ、製品化すべきかどうかをすぐさま低コストで確かめるため」に作るもの。
数値で検証できる仮説「少なくともX%のYはZする」を立て、さらには今すぐ実行できる小さいサイズの仮説「少なくともx%のyはzする」として切り出し、実際に実行してみる。どのくらいの人が身銭を切ってまでそのサービスを利用したいと思うのか、そのデータを自分自身で集め、仮説を検証しよう、というのが本書の骨子だ。
プレトタイプの類型
プレトタイプを過去の事例を元に8種類の手法として紹介している。
手法1「メカニカル・ターク型」
採用する技術が高価だったり複雑だったり未完成だったりする際に、その機能で行うことを、人間が密かに行う。サービス利用者はそのことに気づかない。このことによって、どのサービスがどのくらいニーズがあるのかを試す。
事例:コインランドリーに自動折り畳み機を設置する。実際は中に人がいるだが、お金と洗濯物を機械に入れると、折りたたまれて出てくる。これでニーズや、いくらまでなら人は身銭をきって払ってくれるかの検証を行う。
手法2「ピノキオ型」
等身大だけれども機能はついていない質量のものを作り、実際に使いたいと思うかどうか検証する。
事例:PalmPilotとして知られるようになる製品の作者が、実際にPDAのようなものがあったとして使いたくなるかどうか確信が持てなかったため、予算をかけたプロト製品を作る前に、アイデアの確かさを確かめた。
手法3「ニセの玄関型」
どれだけの人に興味を持ってもらえるかを調べる手段として、玄関のみを用意し、サービスや製品が実在するふりをし、どのくらいの人が玄関をノックしてくれるか(興味を持ってもらえるか)を試す手法。
事例:古書店を開こうと検討している人が、定職を辞める前にニーズを確かめた。店舗を借りるのに有望そうな数カ所にて、実際の店舗はまだないが、ドアに古書店の案内だけを掲示し、道行く人がどのくらい気づき、関心を示す、立ち入ろうとしてくれるかを検証した。
手法4「ファサード型」
まだない製品紹介と購入ボタンを設置したウェブページを用意しておき、ほしいと思って購入ボタンをクリックする人がどのくらい現れるかを検証する。「ニセの玄関型」よりも深く、お客候補が購入したいとノックしてきたときに、何かを返す。ウェブサイトを用意しておき「売り切れましたメッセージ」や「入荷次第メールを受け取りたいか」を表示して、リード顧客の情報を得る。
事例:オンラインで車を売ることが当たり前でなかったころ、まだ車の在庫もなかったが、「購入する」ボタンつきのウェブページを用意して、購入されたあとに車を手配した。オンラインで車を売ることができるかどうかを検証した。
手法5「YouTube型」
映像を使って、まだ製品化されていないアイデアや、広く入手できない製品を、ターゲット市場に当てて、どのくらい関心を示してもらえるかを試す。
事例:Googleグラスの開発チームが、製品が完成するかなり前のの段階で、YouTubeに動画を公開、この製品があると生活がどれだけ変わるかを動画でわかりやすく伝えた。
手法6「一夜限り型」
「一夜限り」という名前がついているが、要は期間限定のことで、数時間でもいいし、数ヶ月でもいいが、意思決定するに十分なデータが集まるまでに比較的短い期間に、実験を行う。
事例:AirBnBがまだ出来る前に、その創業者たちがお金に困って、カスタムドメインでサイトを作り、自分たちの部屋を貸し出す告知をしたところ、男性二人、女性一人の計三人の客がつき、ニーズを確かめることができた。
手法7「潜入者型」
「自分の製品を、同じような製品を扱う他人の販売環境にしのばせ、『身銭』を切って購入してくれるくらい関心をもつ人がいるかどうかを見てみる」手法。
事例:サンフランシスコのデザイン事務所が、自分たちのプロダクトのニーズを確かめるために、IKEAの制服をeBayで購入し、潜入して、自分たちの商品を陳列し、買い物客が手に取るかどうか確かめた。ドキュメンタリー動画としてYouTubeにアップしているので確信的だ。
手法8「ラベル張り替え型」
別のラベルを貼り、もとの商品とは異なるものであるように見せかけることができる。人々が関心をもつかどうかを、これで確認することができる。
事例:思考実験で、スタンフォードのカフェで、「パック寿司を買う人間の少なくとも二十パーセントは、通常のパック寿司の半額程度の価格で売られていればセカンドデイ寿司を試す」という仮説を試してみた。
まとめ
ガチのスタートアップのアイデア検証だけでなく、様々なアイデアソンとハッカソンのアウトプットとしても使えるなと思いました。プレトタイプ…以前聞いたことあったけど、具体的に何だっけ、と思ったらタモリさんのこのコントを思い出してください(手法1「メカニカル・ターク型」ですね)。
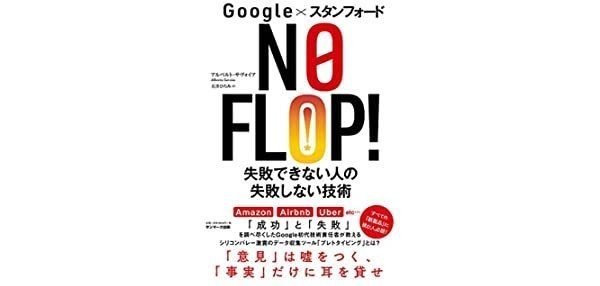
「Google×スタンフォード NO FLOP! 失敗できない人の失敗しない技術」
