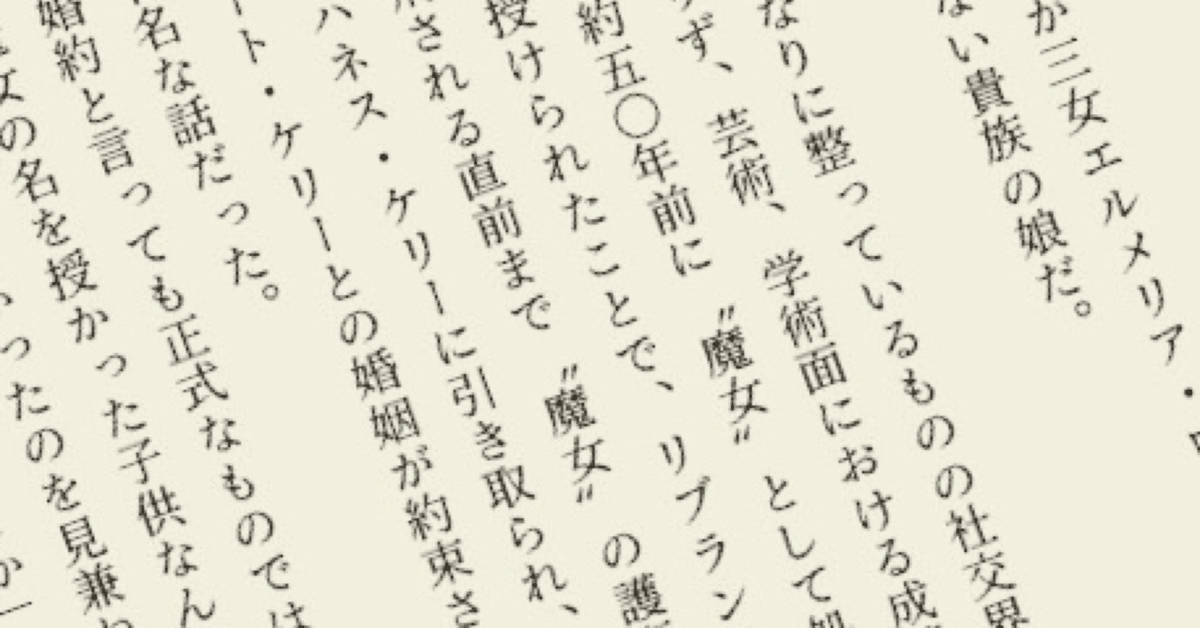
恋に生きた君は知る【11話】
——シェシュティオと話をする上で。
エルメリアがもっとも恐れたのは冷静さを欠いた姿を人目に晒すことだった。
どう足掻いても昂る感情を制御できるなどと考えられるほど自分を見失ってはいないし、精霊界以上に誰の目にも止まらず誰の耳にも入らない場所を知らない。
——精霊魔法が主流とされていた時代には人の往来もそれなりにあったようだが今ではリブラント侯爵家の当主くらいのもの。
信頼関係を築き直すには精霊と人の心は離れ過ぎた。
クレアクリスのように人の心や記憶を読むことのできる精霊が相手でもなければ、当主だった頃の知識を持つエルメリアとて例外ではない。
「知識として存在することは知っていたが……」
思わず、といった調子でシェシュティオが呟けばクレアクリスは喉の奥を鳴らした。
「なんだ。怖気付いたのかお坊ちゃん」
「……そうだな。少し驚き過ぎたようだ」
気を取り直したシェシュティオは、用意された“道”をただ通り抜けるだけで構わないことを確認すると躊躇いもなく——彼にとっては未知の——光の中に入っていった。
それは間違いなく“エルメリア”に対する信頼の表れで。
「ありゃあ確かに忘れがたいわなぁ」
「黙りなさい」
余計な口を挟んできたクレアクリスを睨む。
“彼”は“エルメリア”を女としては見てくれなかったけれど、幼き頃からよく知る友人として、将来を誓い合った者として、慈しんではくれた。
関係が拗れきってなお“彼”以上の理解者を“エルメリア”は知らない。
ため息1つで無理矢理にでも思考を切り替えてシェシュティオの後を追う。
——今日は前世の記憶が失われない理由についてを聞きに来たのだ。
不毛なやり取りを重ねに来た訳ではない。
光の道を抜ければ眼前に広がる白亜の庭園に降り立ち、事前に用意させておいたテーブルに向かう。
「……美しいが、それだけではないな」
茎と葉に至るまで白い陶磁器のような花々と大理石に覆われた地面。
幻想的でありながら、どこか薄寒くもあるここはシェシュティオの言うように“美しいだけ”の場所ではない。
何が隠されているのかを彼が探り当てる前にエルメリアは“答え”を口にする。
「ええ。花はただ魔法で編まれただけのものだけどその下には“範囲内にいる者に嘘を吐けなくさせる”魔法陣が刻まれているわ」
「……俺が嘘を吐くと?」
「いいえ。ただ私が、嘘ではないと証明する手立てもないなんてお粗末な理由に縋りたくないだけ」
全ての嘘が悪意によるものとは限らない。
善意による嘘さえ許されないこの場であれば、どれほど無情な真実でも白日の下に晒されるだろう。
どちらからともなく席に着く。
「それで、あなたの言う前世の記憶が失われていない理由って何なのかしら」
わざわざ精霊界にまで足を運んだとはいえ、好き好んで取り乱したい訳でもなければ無駄話に花を咲かせられるような関係でもない。
単刀直入に尋ねながらも視線を他所に向けたエルメリアを咎めるでもなくシェシュティオは素直に答えた。
「リブラントの秘術を継がせるために魔法を編んだだろう」
「……ええ」
貴族の貴族たる所以の1つに秘術と呼ばれる特別な魔法の存在がある。
これは血を媒介として受け継がれるもので血族の人間にしか扱うことができない。
——つまり、前々世の“エルメリア”が子をなさなかった時点で本来ならば失われているべき魔法という訳だ。
“彼”と“彼女”の間に産まれた子供が“エルメリア”の実子として公に認められたのは、この秘術を扱えたからに他ならない。
「秘術とは盟約であり特権。これを人の身で書き換えることは禁忌にあたる」
「……何よそれ」
「今の家にあった古い文献だ」
そも秘術とは神より賜わったものとされておりリブラント侯爵家であれば“精霊に対する絶対命令権を発動させる”魔法といったように、有事の際には人々の暮らしを守護する力を持つ者として今の地位を認められている貴族も多い。
秘術の失伝は爵位の剥奪にも直結しかねないほどだ。
しかし、血の縛り以外の話は聞いたことがない。
眉を顰めれば年季の入った本を差し出された。
シェシュティオの実家にあったという文献だろう。
受け取れば該当のページを教えられ、サッと目を通す。
「……我が国に伝わる秘術をどうにかして持ち帰ろうと研究した結果ってところかしら」
「マルティカの堅牢さが秘術によって支えられたものであることは歴史が証明しているからな」
「他国にはない力となれば尚更よね」
汎用性と威力を両立させた魔法が広く普及した現代においては秘術の絶対性を頼りとする状況は減ったものの、そうではなかった時代——。
それこそこの文献の筆者が生きていた時代には、秘術を解き明かそうと日夜研究に明け暮れた者も少なくはなかったろう。
「信憑性は高い」
「見れば分かるわよ」
血の繋がりのない相手に秘術を受け継がせるための魔法を独自に編み出す程度には、知識も能力もあったのだ。
記されている内容に間違いがないかどうかの判別くらいは付けられる。
「だけど秘術と記憶に何の繋がりがあるっていうの?」
魔法を発動させるために必要となる対価はあっても代償はなく、ただ1点、条件が揃えられていることだけを求められる。
マルティカ王国の貴族に与えられた秘術が単なる力か盟約であり特権であるか、なんて認識の違いにさしたる重要性はないのだ。
「なら聞くが、秘術の発動に必要な条件とはいったいなんだ?」
「共通点で言うなら血でしょう」
「俺もそう考えていた。だが血はあくまでも媒介なんだ」
ここをよく見ろ、と言われ訝しみながらも文献に視線を落とす。
シェシュティオが指し示したのは秘術の陣を書き写したものと思われる図式だが——。
「ちょっと待って。“肉体の半分が資格者の魔力で満たされている時”? 何でこんな式が」
秘術を扱えるのはその資格を保有する者だけなのだから、わざわざ条件に含む必要がない。
それなのに何故。
「この術式は“秘術を扱う人間の血を調べた結果”発見したものとされている」
「……秘術そのものではなく?」
「そうだ。そして両親の血と魔力が混ざる妊娠の瞬間だけはこの条件を揃えられる」
エルメリアは急いで術式を読み解いた。
これが秘術を扱う資格を与えるための魔法式で、血が媒介でしかないのだとしたら——。
「“資格は加護へ”……」
「神々が魂に施すとされている加護の中に資格を示す何らかのものが付け加えられるってことだろう。つまり、発動に必要となるのは血ではなく“資格を内包している加護”だ」
“エルメリア”が編んだ魔法の術式がどのようなものか“彼”は知らない。
ただ、条件次第では記憶——魂に影響を及ぼすものと考えたのだろう。
そして、きっと、その予想は正しい。
