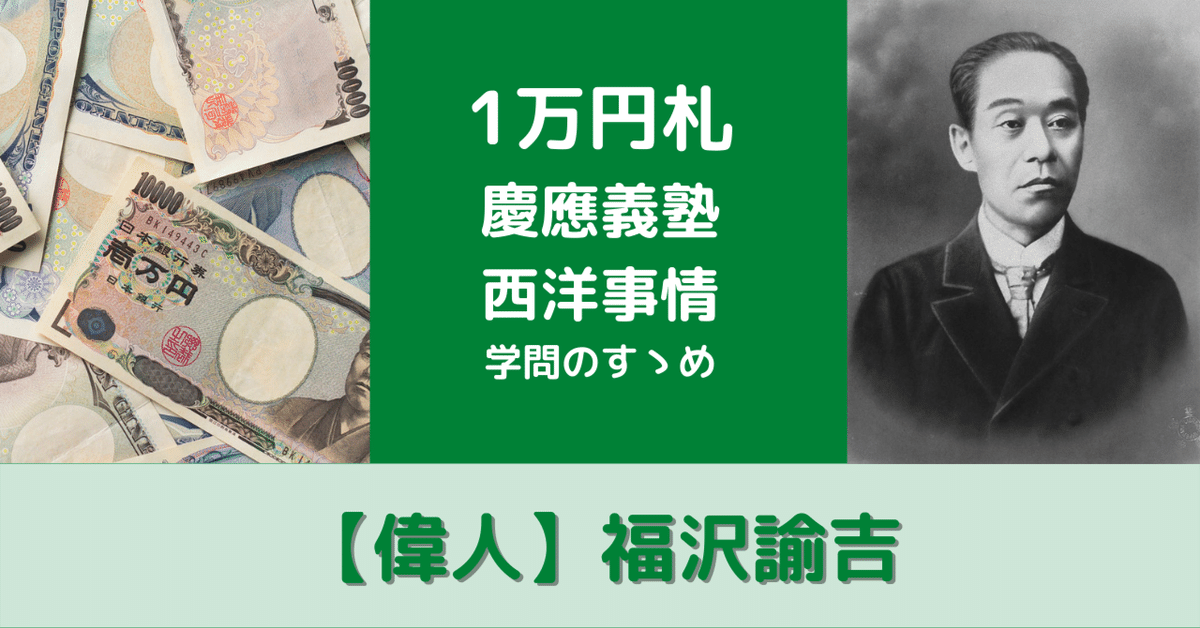
【1万円札】母子家庭から大成功「福沢諭吉」
日本を代表する方々、そんな偉人と聞いて1万円札の肖像にもなっている「福沢諭吉」を思い浮かべる方も多いでしょう。
そんな福沢諭吉氏、我々は普段何気なく「諭吉が!!」とか名前を「1万円札」と呼ぶ変わりに使っていますが、実際どんな功績があり1万円の肖像画になったのか、どんな人だったのかは普段気にしていない。
今回はそんな「福沢諭吉」の功績と人生について見ていきます。2024年に1万円札は世代交代となり、渋沢栄一にバトンタッチされる前に、福沢諭吉氏が一体どんな方だったのか、日本に与えた影響などをさっそくみていきましょう。
この記事は約7分で読めます。
著者:ゆうきが斬る「ゆうき」Powered by CouTree
この記事の動画版はこちらのチャンネルで投稿されます。
この記事は複数のソースを元に制作された物ですが、一部情報の誤りがある場合があります。その際はコメントにてご一報頂ければ幸いです。
福沢諭吉氏の生い立ち

1835年生まれの福沢諭吉、現在の大分県中津市にあたる豊前中津藩(ぶぜんなかつはん)の下級武士の家庭に誕生。2歳の時に父が亡くし、小さくして下駄づくりの内職などをし、貧しい家計を手助け。
そんな福沢諭吉、14歳になると塾に通い始めます。ここまで聞くと幼くして父をなくしていたりしますが、一見普通の学生にもみえます。
しかし19歳の時、中津市から長崎へ移り、蘭学と砲術の勉強を開始。蘭学は今ではあまり馴染みの無い言葉でしたが、当時オランダを通じて日本へ入ってきた海外の学問・文化・技術の事を総称で「蘭学」と呼んでいました。
オランダの事を漢字で表記し「蘭」、それを学んでいたので「蘭学」
鎖国していた当時、入ってくる海外の情報は限られていて、一部の国の学問のみが入っていたのでこう呼ばれていたが、開国後は一般的に「洋学」と呼ぶようになりました。
長崎で学んだ後、大阪にいた蘭学者で医師の緒方洪庵(おがたこうあん)の適塾で学ぶようになり、住み込みで勉強をしていました。
江戸へ向かった福沢諭吉
そして時は経ち1858年、福沢諭吉は23歳になり江戸へやってきます。この頃には日米和親条約が締結されているので、すでに開国状態。
外国人もやってくるようになった江戸で福沢諭吉は自身の蘭学塾を開くことになります。しかし当時、開国した日本を訪れた外国人が使っているのはオランダ語ではなく英語。
今でも外国人が多い街横浜、当時から外国人が多く来ていたスポットですが、そこで使われていた言語が主に英語で、オランダ語が通じないという事にショックを受けた福沢諭吉。
しかし当時福沢諭吉は英語を話すことはできず、身近に英語を教えてくれそうな人もいなかったので、英語ーオランダ語辞書を使い、独学で英語を勉強。
流暢なオランダ語は話せたので、そんなオランダ語を使い、英語の勉強を独学で始め、アメリカに渡航するまでになるのです。
アメリカへ渡ったのは25歳の時、つまり2年間でここまで来ました。
遂にアメリカへ!
1860年、福沢諭吉が25歳になると幕府が募集していた遣米使節団(けんべいしせつだん)へ志願し、咸臨丸(かんりんまる)で渡米します。
このアメリカで培った経験が後の福沢諭吉の功績につながるのですが、アメリカでは身分に関係なく、誰もが能力次第で活躍できるようになる、そんな社会が出来上がっていた事に福沢諭吉は驚き、感動を受けます。
これは自身の自伝書「福翁自伝」(ふくおうじでん)に書かれているのですが、この時のエピソードが面白い。
江戸時代に海外へ行く、それはそれは大事なのですが、開国したてホヤホヤの日本、そんな日本から一歩も出ずに生活していた人から見ると外国は現代の我々の「宇宙」と同じ感覚。
宇宙旅行行ってきました!と同等とも捉えても良い(ちょっと違うが)初渡米。
1ヶ月以上の時間をかけてアメリカはサンフランシスコ市へ向かったのですが、この時に一緒にいたのは勝海舟。
勝海舟のお話はまた今度…
さあサンフランシスコ市に到着した福沢諭吉がまず最初にみたのは、ホテルの床一面に敷き詰められた絨毯。江戸時代の日本では絨毯は高級品で、その上を靴で歩いている。
江戸時代の日本では超高級品だったので、タバコケースに使うのが精一杯、そんな布を床一面に敷き詰め、しかも土足でその上を歩いている事に衝撃を受けます。
福沢諭吉は日本人で始めてツーショットを撮ったと言われているのですが、それはこのサンフランシスコへ渡米した際に現地の写真屋に立ち寄り、撮って貰った一枚。写真屋の娘さんにお願いして、一緒に写ってもらいそれを一緒に船に乗っていた士官たちに見せびらかすというユーモアさもある福沢諭吉。
福沢諭吉イギリスへ!
アメリカから帰ってきた後、次はイギリスへ向かいます。イギリスへ向かうのは1861年、こちらは長旅でイギリスのみならず多くのヨーロッパの国々など多くの場所に立ち寄り、約1年間の計画となりました。
正式に幕府の使節団の一員として、指名されて行くヨーロッパ旅。
イギリスから来た軍艦にのり、途中に香港、シンガポール、インドにもよりながらイギリスへ向かいます。
この時よったエジプト・カイロのピラミッドで撮られた写真もあり、海外各国の文化を見て歩いていた福沢諭吉。
外国諸国を見学し、実際に経験した事で外国の考え方や文化を学び、良いものは日本でも取り入れていく。
福沢諭吉は外国から学べる物は学んで、それを日本でも提供する、その中で最も衝撃を受けた「平等さ」というのが慶應義塾の設立につながっています。
功績その1 慶應義塾
福沢諭吉の最も知られている功績として「学問」を広めようと設立した慶應義塾が挙げられます。
これは現在でも有名私立大学として継続されている慶應義塾大学の前身にあたります。江戸にやってきた頃に開校していた蘭学塾を移転し、港区芝で設立。
毎月授業料が発生した形の「学校」という運営はこれが初めてでした。海外で自身が経験した「平等」を取り入れ、身分に関係なく誰でも教育を受けることができる慶應義塾大学。
アメリカやヨーロッパではすでに身分に関係なく行動が行われていた事、そして福沢諭吉が学問を一番重んじていた人物であった事から、海外へ渡航し視察した事で日本でも平等な教育を提供する、そんな事を掲げて設立されたのが慶應義塾。
個人の私財もふんだんに注ぎ込まれている事、また戊辰戦争の中もひたすら講義を続けており、福沢諭吉が如何に学問が重要だと考えていたかを理解する事ができます。
功績その2 西洋事情の出版
福沢諭吉の功績として「西洋事情」の出版もあげられます。アメリカ・ヨーロッパの視察へ行き様々な文化を身を持って経験してきた福沢諭吉、そんな経験を多くの人に知ってもらい、外国にはどんな世界が広がっていたのかを記したのが西洋事情です。
幕末から明治にかけて出版され、初編3冊、外篇3冊、2編4冊の計10冊を出版。
海外の政治について、税制度について、また国債や紙幣、外国での商売事情から科学技術、教育、新聞、病院、博物館など多くのジャンルにわけ、それぞれを個別に紹介しています。
幕末の日本には存在しなかった西洋の制度や文化を紹介し、良いものは日本でも取り入れていく。
福沢諭吉は海外では法の下自由が保証されていて、平等に教育が行われ、大使を送った外交を行い、他国とも条約を結んでいると記し、これらは現代で見れば当たり前の事ですが、当時の日本から見ればすべてが新しい、衝撃的な物となっていました。
今でも「西洋事情」は出版されていて、販売されているから、当時とはまた違う視点で読むことが出来る。
逆に今では、これらの情報から当時の日本がどんな状況だったのが、どういった制度が確立されていて、今では当たり前のそんな所に驚いていたのか、そんな勉強も出来る。
当時出版された西洋事情が広まり、明治時代では海外の洋服や食べ物、建築方法など多くの西洋文化が取り入れられました。
鎖国が続いていた日本にとってはどれも衝撃的な物、文化開花を行ったのが福沢諭吉の「西洋事情」だと言われています。
功績その3 学問のすすめ出版
福沢諭吉は数多くの本を出版しているが、「学問のすゝめ」が代表作といっても過言ではない。
17編までのシリーズ本となっていて、自由に・独立した・平等に教育を与えるという当時の日本には全く無かった価値観を綴っている。
全員が平等になり、独立し、身分に関係無く教育を受けられるという考えは斬新であったが、それが故に批判も殺到する。
特に学問のすゝめが出版された当時は明治政府が設立された頃、福沢諭吉は欧米諸国のように国民主権国家を構想としていたが、明治政府が選んだもな天皇制国家。
それに対し多くの批判を送るが、当時の世論が「自由な国家」という意識は低く、多くから福沢が批判されてしまう事になる。
そんな意見も目立っていたが、福沢諭吉は「学問」に対しては常に取り組み、誰でも教育を受けれる環境を整え、日本の現代社会へ貢献した人の一人と言われています。
まとめて
福沢諭吉は幕末の当時に多くの他国へ渡航し、様々な文化を経験、そこで出会った新しい考え方やシステムを公にする事で誰でも遠い海の向こう側の世界を手にとって読むことができるようにしました。
また常に学問を重んじていた事から慶應義塾を設立、誰でも身分に関係無く平等に教育を受ける事ができる、そんなシステムを取り入れています。
日本の近代社会へ貢献した人物「福沢諭吉」
彼の幼少期から生い立ち、アメリカ・ヨーロッパへの渡航そして3つの大きな功績について見てきました。
そんな功績が認められ、現在では1万円札の肖像画にもなり、とても親しみのある偉人となっています。
「今日も、生涯の一日なり。」
ー福沢諭吉
最後まで読んで頂きありがとうございました。
もし良ければ良いね、フォローお願いします。

いいなと思ったら応援しよう!

