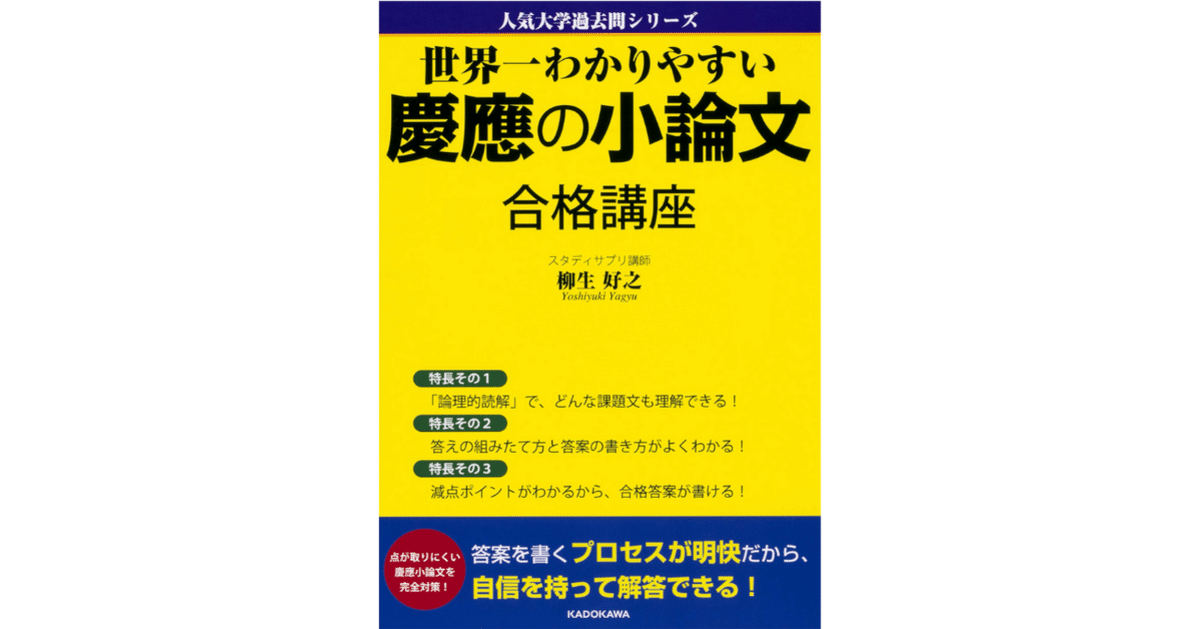
世界一わかりやすい慶應の小論文合格講座
みなさんどうも、こんにちは。
スタサプ現代文講師の柳生好之です。
今回は『世界一わかりやすい慶應の小論文合格講座』について説明いたします。
1,「論理学」のアプローチを導入した
本書では論理学の基礎を導入しました。これまで現代文・小論文の世界で「論理的〜」という言葉が使われていましたが、「論理学」とは異なるものでした。しかし、実際の出題を見ると本当に「論理学」の基礎を使って考える問題が現代文でも小論文でも近年急増しています。
ですから、商学部の問題を使って「論理学」の基礎知識を導入しました。これらの考え方は、法科大学院の適性試験や国家公務員試験の対策指導では当たり前になっていましたが、大学受験の対策指導では導入されていませんでした。大学受験の世界は大きくなりすぎていて、「伝統」を重視する傾向があるように思います。もちろん「伝統」にも良い面はあるのですが、一方で新しい傾向への対応が遅れるということもあると思います。本書では新しい入試問題の対策となるように、他の試験対策では一般的であった「論理学」のアプローチを導入しました。
これに関して「今まで大学受験現代文・小論文の世界でそんなことは誰も言っていなかった」「新しいものなんて胡散臭い」と思う人達もいるでしょう。新しいものに懐疑の目を向けるというのは、珍説が跋扈しないようにするための人間社会の防衛機能です。それ自体は決して悪くないと思います。
ただ、最新の入試問題をよく見てください。そこに答えはあります。
2,近年流行の「データの分析」を導入した
AIブームもあり、近年は「データの分析」が流行しています。数学でも導入されていますね。それが小論文の試験でも出題されるようになったのです。
世の中には様々な「正しさ」があります。「正しさ」の基準を何に置くかを前提とせず、「あれは正しい」「あれは間違っている」と議論するのも不毛な話です。
元来、大学受験は「論理的に正しい」ということを重視していました。ところが、近年は「統計的に正しい」ということが重要視されるようにもなっています。
これも一つの「正しさ」のあり方だと知っておくと良いですね。
本書は実際の慶應の入試問題で「データ」の見方を学べるようにつくりました。
3,「読解型」「議論型」「問題解決型」について分類説明した
慶應の小論文では「読解型」「議論型」「問題解決型」が出題されます。
これらの方の説明は次の記事てくわしく説明してありますので、ぜひ参照してください。
4,各学部の特徴を説明した
慶應の小論文では「読解型」「議論型」「問題解決型」が出題されます。
「読解型」は看護医療学部、文学部、商学部で出題されます。
「議論型」は文学部、法学部で出題されます。
「問題解決型」は経済学部、SFCで出題されます。
それぞれの学部で出題される「型」が決まっていますので、志望学部に応じて「型」を身につけましょう。
ただし、どの学部を志望する場合でも本書は通読することを進めます。全体を通して「論理的思考力」を鍛えられるように作ってあります。
ぜひ小論文の最高峰「慶應の小論文」を楽しんでください。
