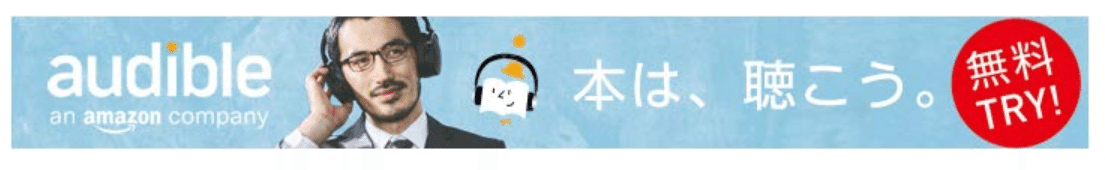【無料note】複合力を身に付ける
これからの時代の生き方を考える上で外せないのがAIの進化。
「私たちはどう生きるか」ということの中に、「AIとどう共存していくか」が入ってくるのです。
「AIって言ったって、自分が生きている間にはそんなに変わらないよ」と思っていた人もいるでしょうけど、迫り来るAIの波を無視するわけにはいきません。
単純作業はもちろんAIの大得意とするところであり、クリエイティブな分野でさえ侵食されつつあります。
以後の世界でまずAIが人間に勝利し、将棋でもAIの優位性が証明されつつあります。
車の自動運転なんて、フィクションの世界のものと思われていたことが確実に「現実」になってきています。
自動運転が本格的に実用化されれば、事故は減少すると言われています。
人間と違って「不注意」というものがない。
また、故障でないかぎり、体調や気分に左右されることもない。
人類は、これまでもさまざまな時代の変化を乗り越えて生きてきました。
産業革命にしても、決して利便性が高まっただけではなかったはずです。
革命的な社会構造の変化の中で、自分たちはどう生きていくかを考え、新しい生き方に向けて、人々は大きく舵を切ってきたのです。
天災で何もかも失ったときも、そこからどう立ち上がるかを考え、実践してきたはずです。
時代というのは不可逆的なものです。
「それがなかった」時代に戻すことはできない。
スマートフォンにしても、さらに機能が進化することはあれ、スマホを使わない時代に戻すことはできないのです。
時代の進化は止められないとしたら、どうするか。
例えば、老荘思想にひたり、スマホやパソコンはもとより、一切のAIに関連するものには手を触れずに生きるということ。
「あのようなものと接触をすればするほど、人間性は失われるのだ」と言い、禅寺にこもるという方法があります。
ですが、それは難しい選択肢になるでしょう。
仕事をしたり、家族と暮らしたり、一般社会でも日常生活から遠く離れることはなかなかできません。
フランスの文化人類学者クロード・レヴィは、『野生の思考』(みすず書房)の中で「ブリコラージュ(器用仕事)」という概念を提唱しています。
未開の地の民族が、物がないならないなりに、あるものを組み合わせて工夫していくということ。
ないならないなりに、あるならあるなりにやるという、柔軟さを表す概念です。
ブリコラージュを成立させるためには、柔軟な状況判断能力が必要です。
そして、状況を判断する力というのは、目の前の現実がどうなっているかを確認・分析しつつ、ここからどうするかという「ちょっと先の未来」を考えるという2方向の頭の使い方、つまり「複合力」が必要なのです。
(続きは本書で↓)