
最短で内科専門医へ導く、J Oslerの教科書 2nd edition
J Oslerにお悩みの内科専攻医と研修医の先生方へ
「日々の臨床が忙しくてJ Oslerに取り組む時間がない」
「J Oslerのルールが複雑で、どう取り組んでいいか分からない」
「内科に興味はあるが、J Oslerの噂を聞くと不安になる」
そのような悩みを抱える皆様に、膨大なリサーチと独自の分析から導いた、word文書50枚に及ぶJ Osler攻略の決定版をお送りします。
はじめに
こんにちは。僕は相川吉剛(あいかわよしたけ @AikawaYoshitake)、2020年4月に内科専攻医となり、3年間で無事にJ Oslerを修了し、23年6月の内科専門医試験に合格しました。
専攻医1年目はCOVID-19の緊急事態宣言の年で、まだワクチンが存在しない世界で内科医の下っ端として院内のコロナ対応に忙殺される日々でした。
専攻医2年目にようやくJ Oslerの症例登録や病歴要約に取り掛かったものの、ルールが複雑でどう取り組んでいいか分からず、手探りで進めていました。J Oslerは新しい制度であるため詳しい指導医や先輩もおらず、後になって振り返るとルールを知らないために多くの時間を無駄にしていました。
・以前のローテ先の経験症例は、今いる診療科の指導医に提出してもいいの?
・初期研修のときに外科ローテで経験した症例、外科紹介として使えるよね
・疾患群が重複しないようにって、要するにコロナばっかり登録したりしなければいいんでしょ
今となっては基本ルールとして理解しているこのようなことも、専攻医当時はよく分かっていなかったために、余計な時間を費やしていたのです。
ここで皆さんにお伝えしたいことがあります。
絶対に自分だけでJ Oslerのルールを把握しようとしないでください。
J Oslerの基本的なルールは、2023年10月以降に内科学会から公表された「J Osler病歴要約 作成の手引き」「J Osler病歴要約 評価の手引き」「J Osler病歴要約 サンプル」の3つに集約されつつあり、複数の資料に分散していたときよりはかなり分かりやすくなりました。

「J Osler病歴要約作成の手引き」「J Osler病歴要約評価の手引き」「J Osler病歴要約サンプル」
さらに、病歴要約は「J Osler病歴要約作成の手引き」に従い作成することがアナウンスされたため、作成の手引が基本のルールブックとなるでしょう。

もしかして、この手引きをきちんと読めば、自力でJ Oslerのルールを理解できると思ってませんか?
たしかに大体のルールは分かるでしょう。ただし、内容が重複しているページも多く、なぜか記載されていないルールもあります。こうした未公開のルールを知らないだけでも、容赦なく差替え(病歴要約の新規作成)となる可能性があるのです。
それ他の資料としては
・J Osler画面右上にある「マニュアル」
・日本内科学会「プログラム整備基準」
・J OslerのHP
・日本内科学会「研修手帳」
・日本内科学会のHP
があり、手引きに載っていないルールについてはこれら古い5つの資料も必要になります。しかし、これらの中にはJ Oslerを進める上では関係のない規則も記載されており、統一した理解は不可能です。
僕は専攻医3年目のときからTwitter(@AikawaYoshitake)上でJ Oslerに関する発信を始めました。フォロワーの方からのDM相談にはすべてお答えし、累計30人の相談に応じる中で改めて知ったルールが多くありました。
また、J Oslerに関する既存の発信はすべて目を通し、ブログ50記事、note 12記事、J Oslerに関して発信しているTwitterアカウント6人、Antta上のパワーポイントスライド2件を徹底的に調査しました。
結果として、wordにして50枚の分量に及ぶJ Oslerルール解説の決定版として「J Oslerの教科書」が完成しました。2023年8月のリリース後、多くの先生方にお買い上げいただきました。そして、同年10月には「評価の手引き」と「作成の手引き」、2024年7月には「病歴要約サンプル」が新しく公表されました。
それらの新しい公式資料とともに、日々Twitterでいただくご質問や情報を加え、大幅に改定したのが今回の2nd editionになります。
「留年せずにJ Oslerを終わらせて内科専門医になりたい」
「差替えのリスクをできるだけ下げたい」
「効率よくJ Oslerのルールを把握したい」
そう思う方は是非、僕のこの記事をお読みになって下さい。
僕自身、専攻医のときは難解なルールに戸惑い、自分は内科医に向いていないのではないかと落ち込み、多忙な臨床とJ Oslerの二重苦に疲弊していました。
この「J Oslerの教科書」は、僕自身が専攻医時代に欲しかったものです。
ただでさえ内科専攻医は忙しい。せめて、J Oslerのルールを効率よく把握し、差替えのリスクを下げるお手伝いをさせて下さい。必ず先生がJ Oslerを突き進む羅針盤となるでしょう。
では始めます。
(以下、添付画像にはすべて引用を明記しており、画像をクリックすると元のサイトにアクセスできます)
LINE公式アカウント
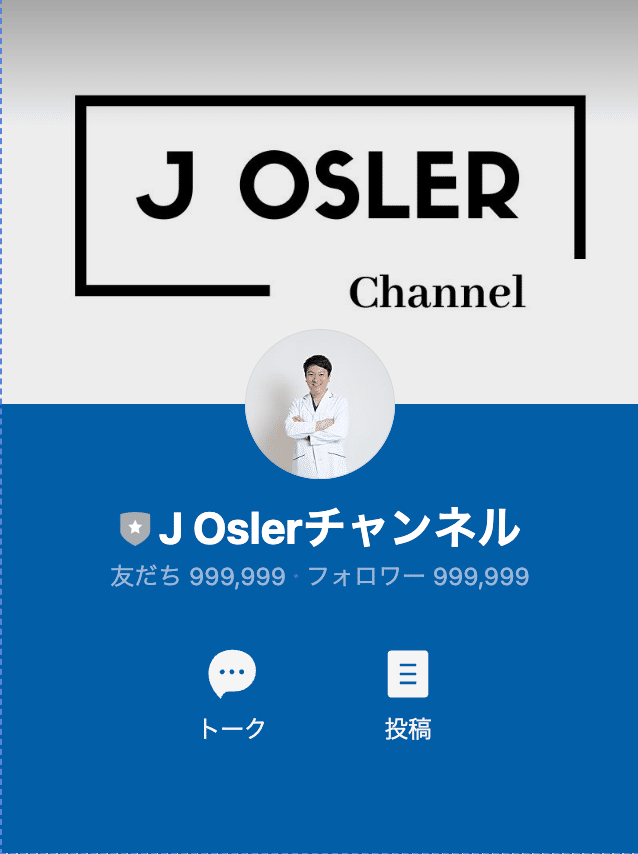
(料金などは一切かかりません)

LINEコミュニティを始めました!現在、40人ほどの方に登録していただいています。noteの更新のお知らせ、オフレコ情報、オフ会のお誘いなどしていくつもりです。
会費や料金などなにもないので、気軽に入ってくださいね!
①基本用語
まずはJ Oslerに登場する用語の定義を確認していきますが、正直この章はおもしろくないので、先に「⑨未公開ルール」などに目を通したほうがいいかもしれません。ただ、J Oslerには独特の用語が存在し、その意味を理解していないと指導医とのコミュニケーションに困ることもあるため、時間のあるときに必ず確認をお願いします。
この章では用語の定義を軽く確認するだけなので、各用語の詳細や対策については、④症例登録から⑨未公開ルールの章を確認してください。
主病名
主病名とは、専攻医が最も労力を割いた病態であり、退院サマリーに登録された主病名ではくてもよいと明言されています。
実臨床、それも高齢者の多い内科領域では多くのプログラムを抱える患者は多いものです。「急性期脳梗塞で救急搬送され入院、その後誤嚥性肺炎、ARDSになりICUに入室した。ICUでは血糖管理に難重した」みたいな症例では、脳梗塞(救急)、肺炎(呼吸器)、糖尿病(代謝)のどれを主病名にしてもいいということです。あなたがどれに一番苦労したと思うか(苦労したということにしたいか)次第で主病名を選んでいいのです。
(血液 疾患群1の出血性貧血に関しては、⑤病歴要約→血液(出血性貧血)を参照)

症例登録
・概要500字+考察300字(院内の上級医1人の承認だけでOK)が160症例
症例登録では、患者IDや年齢・性別、施設名のほか、概要500字と考察300字を記載します。院内の上級医(誰でもいい)の承認を1回だけもらえばOKです。
160症例分必要ですが、幅広い「疾患群」で書きましょう。病歴要約と違い質はいりません。スピード重視でどんどん書いていきましょう。
(疾患群は非常に重要です。⑥疾患群で詳しく書いているので必ず読んでください)
病歴要約
・A4用紙2枚分のガチレポート(診療科の指導医、病歴指導医、院内の責任者、外部の査読委員の4段階の審査が必要)が29症例
A4用紙2枚分のガチレポートです。人によっては「サマリー」「レポート」などと呼びますが、症例登録との区別のためにもきちんと正式名称を使いましょう。
この病歴要約を作成し、二次評価まで通過するのがJ Oslerを突破し、無事に内科専門医を取得するための難関です。
領域
「総合内科Ⅰ」や「呼吸器」、「救急」など、いわゆる臓器別の分類です。領域は時に「分野」と呼ばれることもあり、学会公式の資料でも表記ゆれがあります。
J Oslerではこれらの領域別の他、「外科紹介」と「剖検症例」の病歴要約を合計29個、作成します。
疾患群
非常に重要な概念です。
領域の下位分類でJ Osler独自のもので、疾患群が重複すると病歴要約が無効になる可能性があります。
例をあげると、「悪性リンパ腫」と「多発性骨髄腫」では、同じ血液「疾患群2」であるため、この2つで病歴要約を作成すると無効になります。
⑥疾患群で詳しく解説します。

研修実績→モニタリングのタブを選択して表示される画面
モニタリング
(詳細は⑥疾患群のモニタリングを参照)
下手するとせっかく作成した病歴要約が無効になる「疾患群」の重複ですが、症例登録や病歴要約を作る過程では気づけない仕様になっています。
研修手帳の表に手書きでメモして管理する方法もありますが、「モニタリング」を使うことをおすすめします。メニューのタブから、研修実績→モニタリングを選ぶと、自分が今どれだけ疾患群を網羅できているか確認できます。

ドロップダウンから「モニタリング」を選択!
ここから先は
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
