
1日“27回だけ”撮れるカメラが考えさせる、この時代に“便利じゃないもの”を売る意義ってなんだろう
こんにちは、動画ディレクターの山本です。
前回の投稿から約半年ぶりの投稿になります。その間、長文を書いたのはギズモードのAirPodsのレビューくらいであまり執筆活動ができていませんでした。
2024年も残り少ないですがちょこちょこ更新していこうと思っているので、ぜひよろしくお願いします!
日本のスタートアップから「カメラ」が発売される

今回は日本発のカメラブランドである「kyu(キュウ)」の話です。
kyuは、京都在住の安藤伊織と大川優介による2022年からスタートしたブランド。彼らが今回、「kyu camera」というカメラを発売することを公表したので、このタイミングでkyuについて書いてみたいと思います。
筆者である山本とこのkyuの2人との関係は、同じ96年度生まれの友人。僕が前職を辞めたときに安藤・大川と仲良くなり、一緒に仕事をしたこともありました。
kyuのサイトを見てもらえればわかると思いますが、ビッグな夢を掲げてアート志向に進む感じは、自分とは真逆のタイプ。同い年なのに、ある意味で若くて、ある意味で大人っぽいところが2人の魅力です。
そんな2人が中心となっているkyuが、今回カメラの製品をリリースします。事前に製品の試作を見せてもらったときは「本当にカメラを作ってしまったんだ」と驚いた一方で、「かなりリスクを背負った冒険だな」と思いました。
1日27回だけ撮れる攻めたカメラ
kyu cameraは1回9秒の動画を、1日27回だけ撮影できるカメラ。専用のスマホアプリと一緒に使う。本体のUSB端子をスマホ(リリース時点ではiPhoneのみに対応)に挿すことで、撮影したものを振り返ることや自動編集ができる。また撮影した動画は、アプリ経由で招待をした相手にだけ共有ができる仕組みになっている。2025年5月に発売予定。
kyu cameraは1回9秒の動画を、1日27回だけ撮影できるカメラ。かなり攻めています。
9秒というのは、ブランド名の「kyu」の由来となっている、日常の一瞬を記録として残すのにちょうど良い長さ。
今回の記事では、使い捨てカメラのような27回しか撮れないカメラを、無制限に撮れるデジタルカメラでなぜやりたかったのか? そこにはどんな戦略があるのか?
今回はまだ彼らが公に話していないkyuのコンセプトや戦略などについて、安藤・大川への取材をもとに書いてみます。
割り切ることは誠実ではないのか?
今回の製品「kyu camrera」の直接的な話をする前に、ぜひ知っていただきたい大事な背景があります。
それは大川優介が“クリエイター”という側面を持っているということ。彼はYouTubeで20万人の登録を抱えていて、kyuの事業開発をやりながら、今でも他のブランドの新製品をレビューしています。
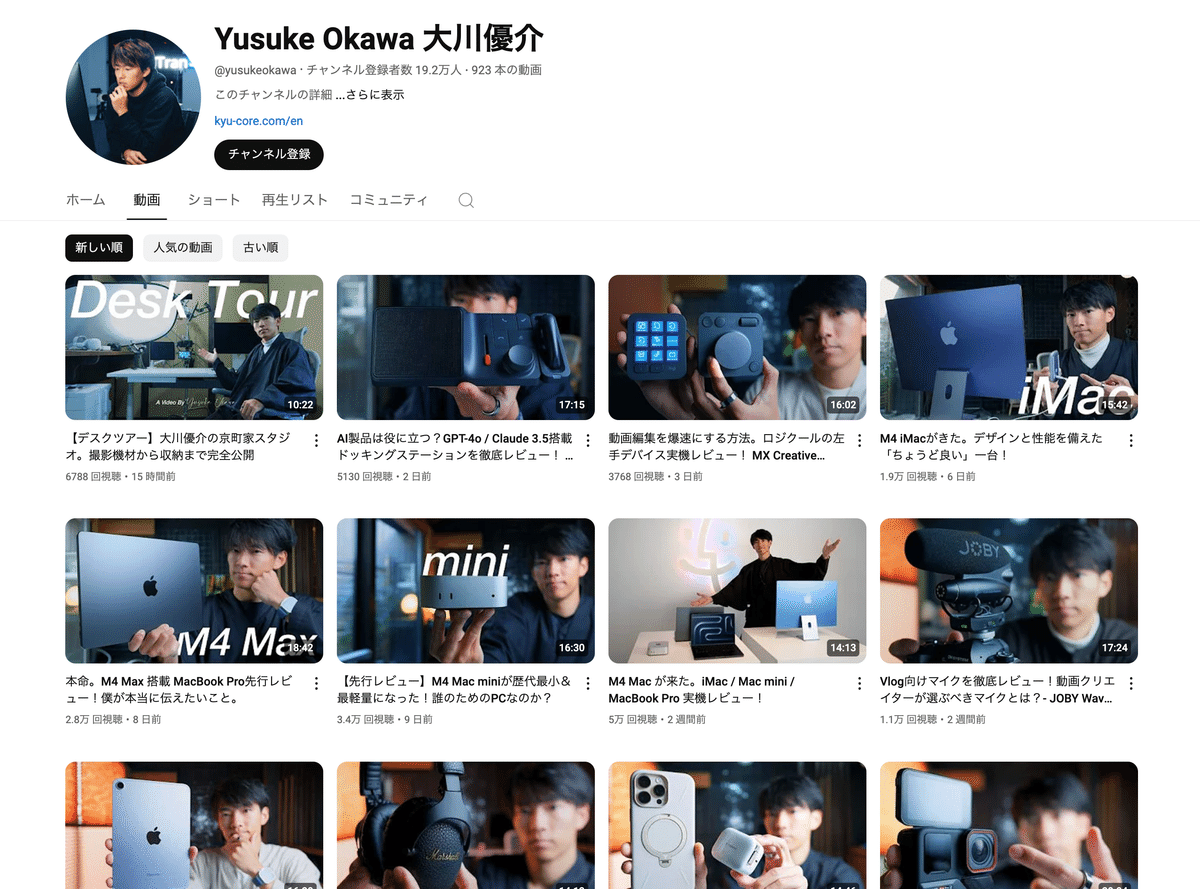
彼とは、このYouTubeチャンネルの動画の方向性についてよく話をします。ショート動画を始めるときの戦略や、Appleの発表会のような大掛かりな取材のときの発信方法について一緒に考えました。
いつも彼と話していると感じるのは、「自分がやりたいこと」と「みんなが見たいもの」のバランスを取ることに対してすごく繊細なこと。つまり自分がやりたいことがあっても、再生数が上がらないとやる意味がないと思っている節があるということです。
昨今のSNS発信者を見ていると、「数字のレースからどのように距離を取るか?」が、一つの大きな課題となっていると思います。僕はこれをインフルエンサーの辞め活と勝手に呼んでいます。
世界一のテックYouTuber・MKBHDも辞め活について話している。
動画を投稿しながらも数字のレースから距離を置く方法は、2つあると考えています。一つは再生数を取るために自分の心を無にして割り切ること。そしてもう一つが、再生数を犠牲にして自分のやりたいことに没頭する方法。
人類がSNSを触って20年弱で分かったことは、“規模の成長”と“自分の理想”を重ねることは、皆んなが幸せになれる方法ではなかったことではないでしょうか。大川もまさにそれに近いことを感じて日々投稿しているはずです。
大川「正直、(僕らの)評価の基準は再生数とか登録者数。ショート動画だと、もっとコピー&ペーストな動画が増えてきて、まさに数字と合理的に向き合わなきゃいけない側面がある。それで稼がないとこういう風に(kyuで)カメラに投資できないからかな割り切っているけど、全然なんか納得はいってなくて。(中略)でも新しいカメラを作る、っていうのを自分がやれちゃったっていうことはすごく自分の中での活動の糧になっている」
大川にとってのYouTubeはkyuのために割り切ってやっている側面があると言えます。これが彼なりの数字との向き合い方であると。
割り切る、と言うと聞こえが悪いかもしれません。しかし、あくまでkyuという活動をするため方法として発信活動をしていて、合理性を持ってやる場所と、自分のやりたいことに集中できる場所を明確に分けているということなのだと思います。
あえてインフルエンサーブランドにしない
そんな背景もあって、kyuは「大川優介のインフルエンサーブランド」ではないところが特徴です。短期的な利益を求めるなら大川優介の冠を使う、という経営判断もあったかもしれませんが、あえてそうしていないところに彼らなりの合理性があります。
安藤「今なぜ、企業に『社会性』みたいなことが問われるようになったかというと、儲かるものって二分化されてるから。少量のものを高く売るっていうのと、大量に安く売るという、このビジネスが最も儲かる。
これは成長論的に言ったらその2つを選んだ方が良いのが原理原則だと思っているけど、次のステップとして、自分のこだわりの範囲内で『成長』っていうこと以外に意義を見出す。そして、ある程度の合理性と両立させながら進めていくことが、多分、優介が体験してることじゃないかな」
大川はクリエイターとして、安藤は起業家として、それぞれ違う専門領域を持っているのにも関わらず、2人とも同じように大規模なマネーゲームからどう距離を置くかについて課題を感じているのがまさに今っぽい。
今の社会の雰囲気として、クリエイターが企業っぽく数字を追うようになり、企業がクリエイターっぽく社会性を追うようになり、両者が近くなっているように感じます。
人と過ごした何気ない瞬間も、
時間が経って思い返せば、かけがえのない思い出に。
そんな日常の空気、時間を大切な「記憶」として残すための、シンプルで美しい製品を開発しています。
kyuのミッションは「人類の記憶を美しく残すことだ」と、設立当初からよく2人は語っていました。お金儲けをしようと思えば、カメラよりも開発費が抑えられて利益が見込めるビジネスもあったはず。
しかし彼らは、kyuをスタートさせた時から「カメラを作ること」は決めていました。自分たちの事業でやるべき範囲を先に決めて、その範囲内で合理性を持ってビジネスをやる、というのが彼らの面白さであると思います。
そんなコンセプトを持った彼らが、ビジネス的に難易度が高いハードウェアを作ったらどうなってしまうのか?
モノの「豊かさ」をアップデートするタイミングがくる

今回発表された製品「kyu camera」は、9秒の映像を1日27回だけ撮影できるカメラ。
しかも写真は撮ることはできず、動画だけ。見返すのはkyuのアプリを通してのみ。動画の画質もすごく良いわけではなく最小限。

僕がkyuの二人から「カメラを作る」と聞いたとき、てっきりこんな感じのカメラを作るのかと思いました。正直これなら「わざわざハードウェアを作る必要ってあったのか?」「尖ってない?」と。
しかしすぐに、これは本当に尖っているのか、この時代に合わせて考え直す必要があると思い直しました。むしろこれは不十分ではなく、必要十分なのではないかと。
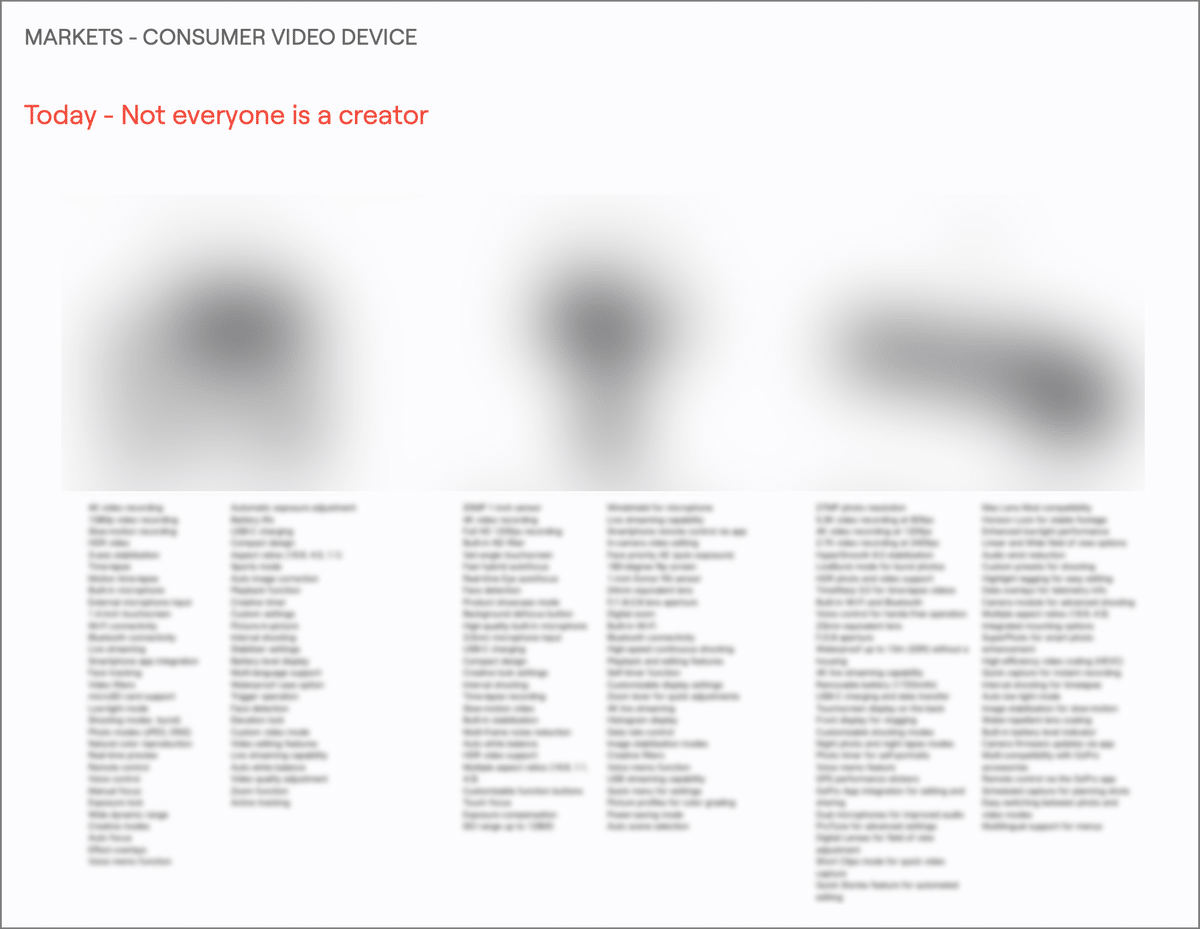
今回kyuについて改めて話を聞くにあたって、とある資料を見せてもらいました。小型のビデオカメラ3機種と、それぞれに搭載された機能をリストアップしたスライドです。
現代のカメラは、さまざまな需要を満たせるように作られている傾向にあります。家族を撮るのに使う人、プロの仕事カメラとして使う人も、いつでも、どんなところでも綺麗に撮れるようになっています。
人は機能が増えることを「それが豊かだ」と考えます。ガラケー全盛期の時代に多くの人が「スマホが欲しい」と思わなかったように、人は誰かが作ったものを後天的に「便利で豊かだ」と思って進化してきた背景があります。
これはカメラやスマホに限らず、世の中のあらゆるモノがそうではないでしょうか?
機能が多くなることの弊害は、手段と目的が逆転することにあると考えています。かつては記録を残すために生まれたカメラが、いつの間にかカメラで撮ること自体が目的化しているように思います。本来楽しいはずのことなのに、いつの間にか撮ることがストレスになっていることはありませんか?
特に昨今のSNSの弊害として、記録を残すこと=「見せたい自分を記録すること」になりがちで、記録を残すことが仕事っぽくなってきている気がします
大川「SNSで発信しているので、不特定多数に見られていることが記録を捻じ曲げてしまう側面もある。それが良い革命でもあるが。本当に大事な記録って、YouTubeの限定公開(知人に共有するためにアップしたもの)だったりするし、それは自分や家族、友人のための記録として残している。それが承認欲求と結びついちゃダメだと思っている。記録マンからすると」
安藤「顔がパンパンで寝起きの大川優介は多分、自分のカメラでは撮らない。けど周りにいる僕らとかは平気で回しちゃう。そんな一瞬が振り返った時に意外と笑える思い出になる」
こうした問いを生み出せるのも、大川自身が発信者であり、さらにカメラ関連のレビュワーでもあることが大きいでしょう。
単に「なんでもこなせる便利なもの」を作らなかったことは、彼らにしかないナラティブで、彼らならではの文脈なのです。
この時代に「便利じゃないもの」を売ることの意義はなんだろうか

総じて、kyu cameraを一言で表すと、「なんでもこなせるわけではないが、ある点においての理想を実現するもの」だと思います。すごくラフな感覚でいうと「便利じゃないもの」ということです。
コスパやタイパといった費用対効果が叫ばれる現代において、こうした主義のプロダクトがどういう風に世の中に受け入れられていくのかも、今後の重要なテーマだと思っています。
はっきり言って、便利じゃないものにお金を払えるほど豊かな人はこの時代にそうそう多くはありません。そこにkyuがどのように向き合うのでしょうか?
安藤「(kyuでやりたいのは)思い出を美しく残すというのは一見高尚で、費用対効果が低そうな領域。大衆向けじゃないし、僕らもマーケットの話する時に、例えば明日の食べ物に困っている方たちが僕らのコンセプトを理解してくださるか?と言うとまだ難しいと思う。
ただ、kyuアプリを使っているユーザーは、一番若い人で2008年生まれとか。その人達って学校生活とか、バイト終わりとか、色んなところで残してる。これは当事者のスタンスと価値観と感受性の問題であると思っていて、僕も若い頃はなんでも目新しくて楽しくて、些細なことでも記録に残していた。
じゃあ今の僕がそうかと言えば、必ずしもそうではない。要はお金を稼ぐことは生きていく上ではすごく重要なこと。だけど僕は、思い出を残してそれを過去の自分として認識をして、未来を決めていくっていうことのほうが、あえてコストパフォーマンスみたいな言い方をすると、よっぽどパフォーマンスが高い体験なんじゃないかなって思っている」
もとより、スタートアップがハードウェアを売るということに関して、kyuはコスト構造が大手のメーカーと比べてもちろん異なります。
開発費からサプライチェーンのコストの圧縮、それによる損益分岐点の見積もりなど、今までの大手ブランドが作ってきたマーケットをあえて踏襲していないからこそやっていける部分も多いにあります。
ただ、ニッチなプロダクトとして小さくまとまるのではなく、最終的には「便利なもの」として大衆向けのプロダクトでありたいと安藤は語っています。

安藤「多くの人が楽しめるものを目指すところは根本にはある。例えばできるだけボタンや設定を減らす、みたいなことは最初の段階から考えていた。本当の意味で必要なものだけにフォーカスして機能を制限している。それはどこから来てるかと言われたら『詳しくない人でも楽しめるものにしたい』という基本的な思想があるから。
ただ、最初からそういう人たちに届けようとすると、焼畑的になっちゃう(編集注:簡単さを売りにしたマーケティングなど、ユーザーへのタッチポイントを単に増やすような売り方になる)。
思想としては多くの人に使ってほしいんですが、それは最終的に達成したいこと。まずは量じゃなく質だと。『たくさん撮れれば良いわけじゃないよね』みたいな話に共感してくれる方だったり、『小さいコミュニティで共有できればOK。だってそれが記録の本質だよね』っていう価値観の方。そういう方々から伝播していき、蓋を開けてみたら『意外とシンプルで便利なカメラだった』という認識を得たい。うちの親でも使える、みたいな感じに最終的にはなってると嬉しい」
1日27回、9秒、ワンボタン。一見、不便に思えるこの制限は、実は最も本質的な使いやすさに繋がっていると。
なんでもできることが豊かなのか?という問いから生まれた「新しい形の便利さ」がここにあるのかも知れません。
2人と改めてkyuについて話してみて、そんなことを考えました。
まとめ
ということで今回は「kyu camera」は発表されたということで、彼らが考えていることや、この時代にハードウェアを作る意義みたいなちょっとお堅い話を書かせていただきました。
筆者である山本は、メディア業界で動画や記事を作りながら「自分が作りたいもの」と「みんなが見たいもの」のギャップに日々、葛藤しています。
冒頭でも書いたように、僕はkyuのことをこういったギャップの延長線上で捉えていますが、これは僕なりの捉え方なので、どう思ったかぜひXなどでコメントをいただけばなと思います。多分kyuの人も喜ぶはず。

