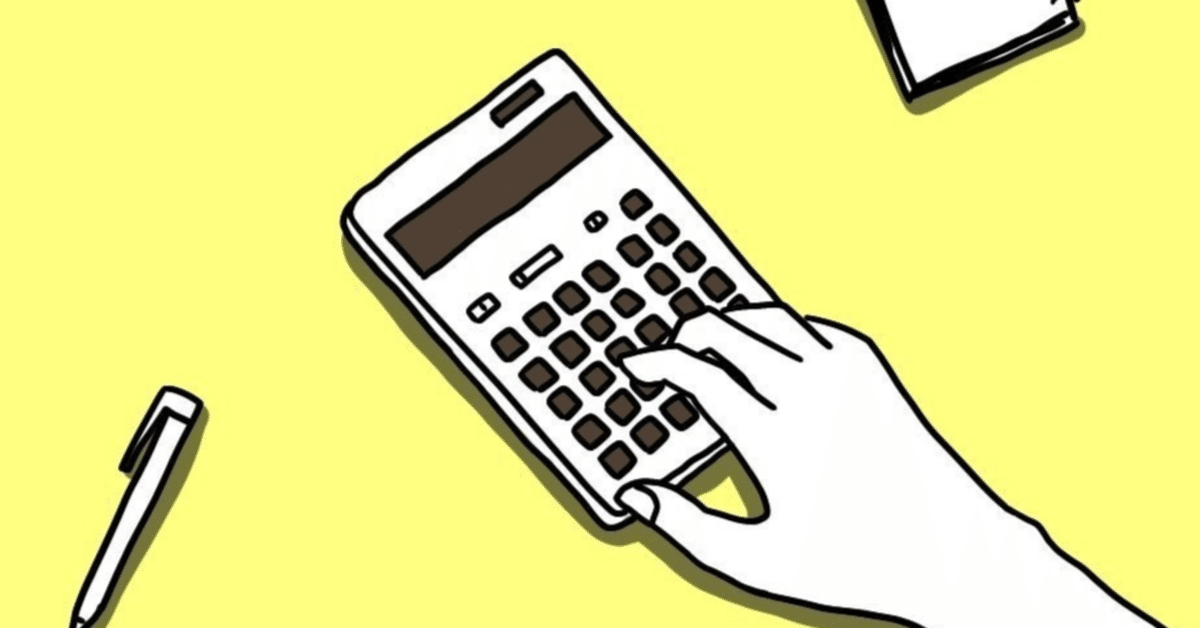
【相棒と共に合格へ!①】電卓の選び方編
こんにちは、山藤あるとです。
受験の必須道具と言えば筆記用具ですが、公認会計士試験の場合、そこに電卓が加わります。
今回は、そんな公認会計士試験の大事な相棒である電卓の選び方編です。
・これから電卓を買おうとしている人
・今使っている電卓がしっくりきていない人
など、多くの受験生に最後まで読んでもらえたらうれしいです。
電卓を選ぶ際のポイントは4つ
受験に使う電卓を選ぶ際に気を付けることは、以下の4つです。
・表示桁数
・0と00のキーの位置
・GTキーやメモリー機能等の機能がついているか
・試験に持ち込めるものか
それぞれ説明していきます。
表示桁数は12桁表示のもの
表示桁数については、12桁表示のものを選ぶことがポイントです。
公認会計士試験では、それなりの桁数の計算を扱うことが多いため、桁数が少ないと不便です。
最低でも10桁は必要と思いますが、わざわざ10桁表示の電卓を選ぶ必要性はほとんどないと思います。
手が小さい人はしっくりくるサイズ感から10桁がいいという人はいるかもしれませんが、それでも12桁ではないデメリットの方が大きい気がします。
シンプルに、受験のスタンダードである12桁表示を選びましょう。
0と00キーの位置はメーカーによって異なる
ほとんどの電卓では、1~9の数字キーなどの配置は同じなのですが、0と00のキーの位置がメーカーによって違います。
これらのキーの位置は、大きく2つのタイプに分かれます。
1の下に0、2の下に00のキーがあるタイプと
1の下に00、1の左下に0のキーがあるタイプです。
ここは好みで選んでよいかと思います。
ちなみに、私は、1の下に0、2の下に00があるタイプです。
特に深い理由はなく、最初になんとなく買ったのがこのタイプだったというだけですが、それに慣れてしまうと違う位置に0と00がある電卓ではもはや打ちにくいです。
よほどの理由がない限り、このタイプは変更しないようにしましょう。
これらのキーの使い方は②電卓の打ち方編でも紹介します。
必須級の便利機能
各種機能については、一般的な卓上電卓なら基本的に備えているものと思います。
必須級の機能としては、メモリー機能とGTキー、定数計算機能、早打ち機能あたりです。
個人的には、これらの中で何を優先するか、と言われれば、早打ち機能と答えます。
あえて言えば、メモリー機能やGTキー、定数計算機能などは、なくてもなんとかできますが、それでもあった方が便利なのはたしかです。
詳しくは③の電卓の便利機能編をご覧ください。
試験に持ち込める要件を満たしているか
これは受験前提の話です。
当たり前の話ですが、試験に使うものなので、試験に持ち込める要件を満たしているものにしましょう。
関数が使えるとかそういうものはダメです。
画面の角度が大きいもの(より垂直に近い感じ)はダメだったような覚えがあります。
(他の席から見えるからとかそういうことと思います)
とはいえ、よほど特殊なものでない限りは大丈夫はなずです。
試験当日まで使い込んだのに、試験当日、使い慣れた電卓が本番で使えないのは避けたいですよね。
まとめ
・12桁表示の電卓を選ぼう
桁数で足かせを作らない方が無難
・0と00キーの位置は好み
よほどの理由がない限り、一度決めたら変えない方がシンプル
・必須級の便利機能があるか確認しよう
早打ち機能以外はなくても何とかなるがあった方がよいのは間違いない
・試験で使える電卓を選ぼう
試験で持ち込める電卓かどうかは確認しましょう
電卓は、受験においては必須の道具です。それだけにきちんとしたものを選びたいところです。
合格後は仕事でパソコンを使うことが多いので、エクセルなどで計算してしまう機会も増えますが、なんだかんだ電卓を使う機会も結構あります。
一通りの便利機能を備えた試験に持ち込める電卓を手に入れ、自分が打ちやすいスタイルでブラインドタッチができるように訓練し、便利機能も使いこなして試験に臨めるよう、使いこなしたいところです。
長い付き合いとなる電卓です。大事に使い、助けてもらいましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
よかった、ためになったと思ってもらえた方は、スキやフォローをしていただけるとうれしいです!
いいなと思ったら応援しよう!

