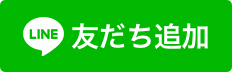裁判所にナイフ持ち込み 刃物と刀剣類、刃体と刃渡りの違いは?
こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
15日朝、福岡市の裁判所に刃渡り9センチあまりのナイフを持ち込もうとした22歳の男が、銃刀法違反の現行犯で逮捕されました。
裁判所にナイフを持ち込もうとしたという点のインパクトが強すぎたニュースですが、その後この事件についてはその後若干の背景が報道されました。
刀剣類と刃物の違い
ところで、銃砲刀剣類所持等取締法(日常用語の「銃刀法」)は、条文をそのまま読んだだけではルールが分かりづらく、「刃物やピストルを持ち歩いていたら逮捕される」というような漠然とした理解しかない方が多いです。
しかし、場合によってはナイフや包丁を持ち歩いているだけで逮捕される可能性のあるルールなので、普通の人でもある程度ルールを理解しておく必要があると思います。
上記の事件でも「魚釣りの道具」として持ち歩いていたため、違法であるとの認識が薄かった可能性があります。
まず、刀剣類と刃物の違いについてです。
銃砲刀剣類所持等取締法
(定義)
第二条
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
条文上はっきりとは書かれていませんが、刃物の方が広い概念で、刀剣類は、刃物のうち武器としての性質を有するもので、刀剣類以外の刃物は調理などの用途で道具として使用される性質を有するものです。
銃刀法にいう「刀剣類」とは(判例の考え方)
社会通念上それぞれの類型にあてはまる形態・実質をそなえる刃物でなければ刀剣類と言えない(最高裁昭和31年4月10日)
刀剣類は、鋼質性材料のものでなければならない(最高裁昭和36年3月7日)
(刀剣類のうち、剣は両刃で刀は片刃を想定しており、それぞれ刃渡りの長さ規制に違いがあります。)
違反した場合の罰則ですが、刀剣類所持の方が重い刑罰となっています。
刀剣類の場合
第三十一条の十六 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して銃砲(けん銃等及び猟銃を除く。第四号及び第五号において同じ。)又は刀剣類を所持した者
刃物の場合
第三十一条の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条の規定に違反した者
ナイフは刃物か刀剣類か
形状によって、どちらにも該当する可能性があります。
ダガーナイフや軍用ナイフは刀剣類に該当する可能性がありますし、そうでない場合は刃物一般としての規制が及びます。
刀剣類の場合、刃渡りの長さによって違反しているかが決まりますが、刃物の場合は刃体の長さによって違反しているかが決まります。
測り方が細かく決まっているため、逮捕した後に計測したら違法ではなかった、ということもそこそこの頻度であります。
上記の事件は「刃渡り9㎝の折り畳み式ナイフ」と書かれてあったため、刀剣類の所持を想定しているようにも読めます。
所持とは
銃砲刀剣類所持等取締法には、所持と携帯という概念があり、刀剣類は、許可なく「所持」することが、刃物は、業務その他正当な理由による場合を除いては「携帯」することが禁止されています。
所持とは占有に近い概念で、保管、携帯、運搬などを含む支配をすることであり、携帯とは鞄の中に入れたり自動車の中に保管するなどして持ち歩くことを指す概念です。
上記の事件は「正当な理由なく」「裁判所に持ち込もうとした」と書かれているため、この部分を読むと刃物の携帯禁止容疑であるようにも読めます。
お店や通販で買えるから適法ということではない
私見ですが、銃砲刀剣類所持等取締法は分かりやすさを重視して全面改正をし、ボウガン(洋弓銃)などの規制も含めて見直すべきではないかと考えています。
許可なく所持が禁止されている刀剣類は販売も規制されているのですが、刃物との明確な違いが一義的でないため、殺傷能力の高い武器が流通してしまいます。基準が明確でないと、独自の解釈がまかり通ってしまう危険性もあります。
一度基準を明示してしまうと、規制をかいくぐる形で脱法的な用具が出回ってしまう可能性もありますが、ルールは分かりやすい方が社会が混乱せず済みます。
また、ボウガンについても早期に規制を検討すべきです。
ボウガンは銃砲にも刀剣類にも該当しませんが、極めて高い殺傷能力を持つ武器となりえるものです。
LINEチャットボットで法律相談を受け付けています
「スマート法律相談」は法律相談に回答するLINEのAIチャットボットです。
「個別相談」で弁護士に直接質問することもできます。
↓↓↓↓↓ 友だち追加はコチラ ↓↓↓↓↓
リリース時に朝日新聞にも紹介されました!
スマート法律相談は、株式会社リーガル・テクノロジーズと、証券会社のシステムを開発する株式会社トレードワークス様が共同で開発しています。