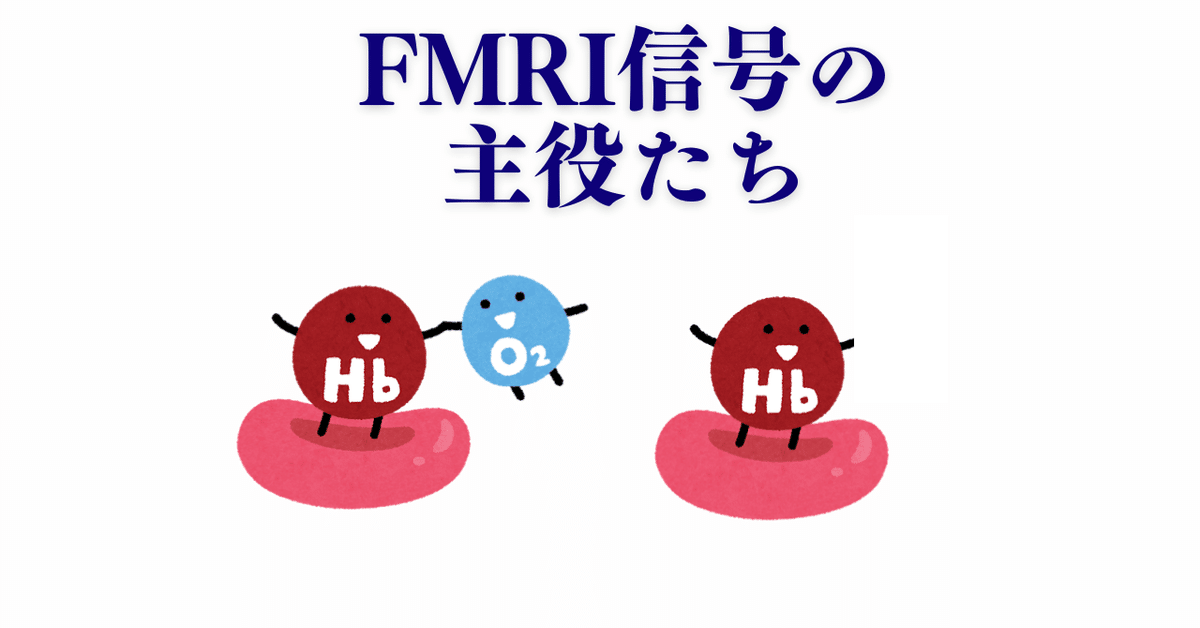
fMRI原理と実践 抄読会ver.2-1 7章
1月の木曜日、記念すべき1回目の抄読会でした。
今回は、自己紹介の時間や質疑応答の時間が多めだったので、201ページまでの歩みでした。
今回から、重要であると感じたorご指摘があった部分をピックアップして書き出していこうと思います。
まとめ① 今回の主役は、オキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビン
BOLD信号の源泉であるヘモグロビン分子の磁気特性は、酸素と結合しているかどうか、による。
オキシヘモグロビン
反磁性;局所の磁場強度を弱める。
デオキシヘモグロビン
常磁性;局所の磁場強度を強める。
※注意※
オキシヘモグロビンは、反磁性と書いてありますが、その影響力の強さに関しては、下部の疑問Q1をご覧ください。
まとめ② BOLD信号の作られ方
前提として、BOLD信号は、脳領域に存在するデオキシヘモグロビンの総量に依存する。
(現在の私なりのmostざっくりな解釈でいくと、BOLD信号は、どれだけ均一な磁場になっているかで大きさが決まる)
ある脳領域で神経活動が生じると、その部分の血流が過剰に増加し、オキシヘモグロビンの供給量は、消費量よりも多くなる。
デオキシヘモグロビンが局所的に減少して、(局所の磁場を強めて、磁場をぐちゃぐちゃにする要因が減るので)BOLD信号が増加する。
一方で、デオキシヘモグロビンが局所的に増加すると、(局所の磁場が強まり、磁場がぐちゃぐちゃになるので)BOLD信号が減少する。
ここまでの疑問
Q1 オキシヘモグロビンも、局所の磁場に対して(弱める方向であっても)影響を与えるのであれば、磁場の均一性がなくなり、BOLD信号が減少するのでは?
A1 オキシヘモグロビンの反磁性は、とても弱いので、ほとんど磁場に対して影響がないと言って良いほど。だから、デオキシヘモグロビンが減って、オキシヘモグロビンが相対的に多い状態では、BOLD信号が増加する。
Q2 デオキシヘモグロビンが減少すると、BOLD信号が増加する、と記載されているが、実際には「増加」はしていないのでは?
A2 厳密には、「増加」はしていないが、BOLD信号を減少させるデオキシヘモグロビンが無くなった、つまり「減少させる要因が少なくなった」という記載が正しいが、ややこしいので、「増加」という記載なのでは。
各図のかいつまんだ説明といただいたアドバイス
Fig 7-2
麻酔の酸素濃度を変えて、デオキシヘモグロビンの存在率を変えたら、デオキシヘモグロビンが多いと考えられる方で信号低下(黒色)が見え始めた。これはデオキシヘモグロビンの影響かも?
Fig7-3
磁場変化に感度が高い撮像方法と感度がそこまでの撮像方法で、デオキシヘモグロビンの影響がMR信号に与える影響を見てみた結果、磁場変化に感度が高い(gradient echo法)で、特にデオキシヘモグロビンによる画像の歪みが大きかった。
(アドバイス) 撮像方法として、spin echo法と、gradient echo法の学習はマスト!
簡潔にいうと、spin echo法は、90度パルスの後に180度パルスを与えて、再度磁場を均一にするので、磁場の違いに感度があまり高くない。一方で、gradient echo法は、180度パルスを与えないので、磁場のばらつき度合いが大きい状態で信号をとってくるので、磁場の違いに対して感度が高い。
(←この辺りは、7章が終わってから、じっくりと勉強します。)
Fig7-4
このまとめは上記参照してください。今回のハイライトです。
疑問点
Q3 デオキシヘモグロビンの影響が信号低下ではなく、歪みとして出てくるのはなぜ?
Q4 デオキシヘモグロビンの影響が、SEで撮像した画像が、酸素化血液とほとんど変化がないのはなぜ?
