
【磁石とコイルで電流を流れさせる】
これまで導線に電流を流すと周りに磁界が発生する、磁界の中で導線に電流を流すと動くことを学んできました。
今回は、磁界を変化させると導線に電流が流れることを確かめます。
<中央構造線とは>
・昨日三重県松阪市の月出の路頭を見にいきました。
写真をロイロで送って、どこが境目か線を引きました。
中央構造線という言葉を知っている生徒は少なかったです。


<自分たちで試す>
・コイルと棒磁石2本と検流計を渡す。
・5分で課題を解決してロイロに写真付きで提出する。
どうすれば電流を流すことができるか
どうすれば大きな電流を流すことができるか
・何の予備知識もない生徒はいろいろ試すので面白い。
棒磁石でコイルをはさむ
棒磁石の中央をコイルに近づける
棒磁石のNとSを同時にコイルに入れる



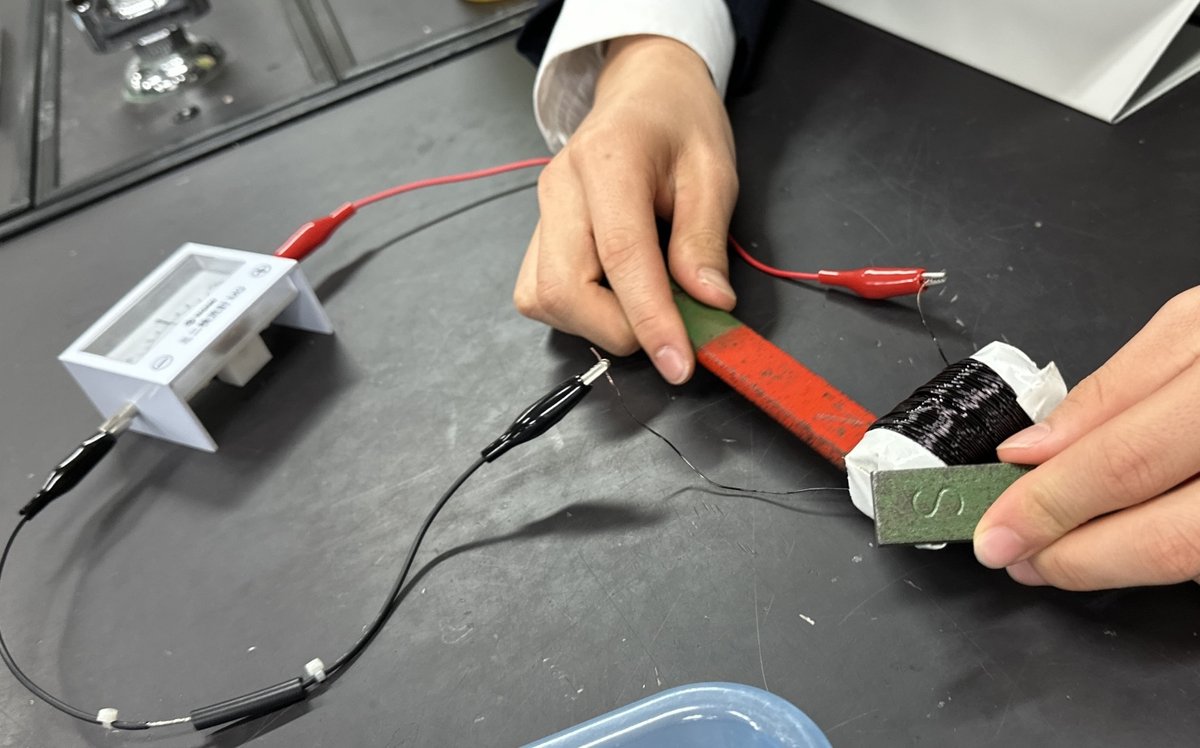


・そのうち、コイルに入れてみる生徒が現れる
初めは机の振動で揺れているのではないかと疑う
電流が流れ続けると期待しているので間違いと思ってしまう

・以前は、丁寧にこちらが指示した通りに試したけれど
自由に発見するスタイルの方が楽しそう。
・ロイロのカードに整理して提出、みんなで一覧を見る
コイルの中に入れると電流ができる
出してもできる
N極とS極をそれぞれ入れると電流の向きが逆になる
勢いよくした方が電流が大きい
磁石を重ねた方が電流が大きい
いろんな気付きがでてくる。


<電流の向きから磁界の向きを考える>
・N極を入れて検流計の針が左右どちらに振れるか観察
ワークシートに向きを記録して電流の向きを確認
・コイルに流れる電流はグーか、ブーかを考える
・右ネジの法則からコイルの上に何極ができるか考える
意外と上がS極と答える生徒が多いが、本当はN極。
この辺りがややこしいらしい。

・N極を引き出すとどちらに振れるか予想して、観察
コイルの上部にS極ができる。
・S極の出し入れについては、自分たちで実験して考える
・コイルの上部に何極ができるかは、「ツンデレ」で解説
来ると反発するが、離れるとくっつきにいく。
・磁石を多くすると電流も大きくなる。

・ムービーで実験をもう一度整理
<言葉の整理>
・電磁誘導と誘導電流、こんがらがちな2つ
・電磁誘導を発見したのはファラデー
これまでに8名の電気にまつわる科学者を紹介してきた
これで最後の9人目の科学者が登場したことになる。
・写真、名前、説明をつなげて、ロイロで年代順に並び替え



・電流の向き、電流を大きくする方法を整理
<地球も大きな磁石>
・北極がS極、南極がN極というと変な感じがしますが
棒磁石がその向きに入っていると考えると磁針のN極が
向くのが北極なので、説明すると納得していました。
・長い導線を回すだけでわずかに電流が流れる
https://youtu.be/jC8nOYUcAoI

<放課後にPBLのムービーを撮るチーム>
・もうすぐPBLの活動が終わります。
まだムービーを撮り終えていないチームがいました。
自主的にチーム全員が残って、コマ撮りムービー撮影をしました。空き缶潰しの原理を小麦粉粘土の玉を使って説明する内容です。はじめは数コマだけ撮ってみたけれど、あっさりしていたので、ちょっとずつ動かす作戦。両手でiPadを支えていたけれどずれてくるので椅子に乗せて撮影をし始めた。空気の粒と水の粒と火の動きの分担がはじまった。何度も何度も取り直して、再生してちぇっくしてを繰り返して終了。でも、後半の缶を潰すところは、イラストが間に合っていないので、今晩仕上げるそう。明日のまるごとPBLの時間で後半のムービーを撮るらしい。間に合うのかな。


