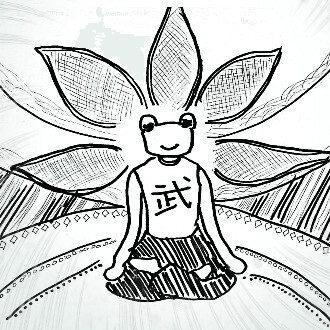再会した彼は予想外のポジションへ登りつめていた 外伝⑥
外伝⑥ 伝統と革新
気に食わない。気に食わない。
女に家門の相続権を与える等と、あの王妃は何を考えているのだ?
そもそも、アドラーが王になってから、今までの伝統が続々と壊された。
そして、ルイーサ王妃だ。
女の分際で鷲の盾に入隊し、剣をふっていたと聞く。それを真似て、女の剣士が増えたと。
そして更に法を改正し、今度は女に相続権を認めた。
この国の、男性が女性を守るという騎士道精神が台無しではないか。
女性は黙って夫や父親の言う通りにしていればいいのだ。
みろ、この混沌とした場を。
新しく設立された春の祭事。王城で行われるのはい良しとしよう。
城内のホールで行われているダンスパーティは、いつもの貴族用のパーティと同じくドレスコードがあり、軽食や飲物が並び、きらびやかな祝に相応しい雰囲気だ。
しかし、このパーティには、身分の制限が設けられていない。
つまり、この場に相応しいマナーを身につけていて、衣装を買う財があり、ダンスが踊る事ができれば、平民であっても参加が可能ということだ。
我々、貴族が下賤な者達と同じ空間を共有するなどと、許されてよいのか!
平民! なぜ、平民の奴らを優遇し、貴族の権利を狭めるようなバカな事をするのだ?
忌々しい事に、娘婿にと望んでいた友人の息子ゴドゥインは、平民の娘と結婚してしまった。同じ侯爵家で、釣り合いがとれる貴重な相手だったというのに。
このままでは、貴族の存在が脅かされてしまう。今日は絶対に、王妃に直接間違いを正してやらねば、気がおさまらぬ。
「ねえ、お父様。いつまでここで立っていなければいけないの? 私、ダンスが躍りたいわ」
「私も踊りたい。入口にいても、誰もダンスの誘いにきてくれないわ」
「もう少し待て」
「あなた。ウラリカとサナリルは、今日のパーティーを楽しみにしてきたのよ。二人は自由に……」
「トリー、少し待てと言ったら、待たぬか!」
不貞腐れる娘二人と、憮然とした妻の顔をみると、より一層腹が立つ。
お前達の為に、色々と手を尽くしている私の思いやりが何故わからんのだ?
無知な娘達にも理解できるよう、説明しようと思ったとたん、会場の外がざわつきが耳に入った。
目をやると、鷲の盾の剣士達5人程が入場してくる。
全員、鎧姿の剣士だが、よく見ると前の3人は女だ。
私は一番前を歩く王妃に近づき、頭を下げる。
「ライン・オウロル・ジャスティン・ヘル・ドュルジがルイ―サ王妃にご挨拶申し上げます」
「ドュルジ侯爵。春の祭典へようこそ」
「この祝いの場に参加でき光栄です。しかし、不敬を承知で、どうしても申し上げたい事がございます
「……聞こう」
王妃が私の顔をじっと見つめる。
なんだ、この威圧感は。
見た目は平凡な顔立ちなのに、眼力が強い。強すぎるぞ、女の癖に。
汗ばむ手をギュッと握りしめた。
王妃と背後の剣士だけでなく、会場内の全員が私が何を言うのかとこちらを見ているのを感じる。
会場が静まり返るなか、私は自身を奮い立たせて、言葉を発する。
この国の伝統を守る為には、誰かが言わねばならない。
「この度の、女性に相続権を認める法改正は女性に負担を強いるものです。今からでも、撤回していただきたく思いお願いを申し上げます! 女性を男性が守るのは、この国の伝統です。うちのように娘しかいない家門は、後を継ぐ男が、入り婿が必要なのです。娘に相続させるなど、そんな可哀そうなことはできません」
勢い込んで大声で訴える私を、王妃は不思議そうに眺めた後、ボソッと呟いた。
「可哀そう、とは。予想外だな」
「はッ……っ。予想外とはいったい……」
言葉の意味をはかりかねていると、王妃は私の後ろの妻や娘を見て、それから私の顔を眺めた。
彼女から放たれる強者のオーラに圧倒される。
くっ、なぜ、私の体は震えているのだ?
王妃はゆったりと、しかし毅然としたトーンで言葉を発する。
「ドュルジ侯爵、なにか勘違いをしているようだが、私は女性が家門を継ぐという選択肢を増やしただけだ。当主になりたくない者に無理強いするつもりはない。当主になるか、それともこれまで通り入り婿をとり夫人として家を支えるという道を選ぶのかは、本人次第だ」
「いや、しかし……。その、選択肢を女性に与えるというのが間違いです」
「なぜだ?」
「その、なぜもなにも……、それが伝統だからです」
「伝統だから、ではわからない。私にもわかるように説明してくれないか?」
「その、ですから……。当主になるのは代々男性の役目です。それが、一番良い方法であり、つまり、伝統として残ってきたのであって……」
「ドュルジ侯爵。現状維持は衰退への道、という格言を知っているか? 」
「伝説の稀代の軍師、ウォルトの言葉ですね。バカにしないで頂きたい。それくらいの教養はございます」
「ならば、なぜ、女性に家門を継ぐ権利の撤回を求めるのだ? 」
「はっ? それと、これとは……」
「伝統とは、ただ維持すればよいものではない。貴族教育を受けた者なら、誰でも知っている常識だろう? 大切な物事のその核は受け継ぎながらも、時代に即した新しいものを取り入れ、より良きものへと改良していく事が肝要なのだ。また、その革新が正しいのか間違いだったかは、すぐにはわからない。今回の法改正も、その是非を決めるのは、私達ではなく、後世の子孫達だろう」
理路整然と話す王妃に、私は自分が小さく縮んでいくような、恐怖を感じた。
いや、いかん。女ごときに、言いくるめられてはならない!
「お、恐れながら、現状維持は衰退への道と言われましても。代々男性が当主になり、そして当主が跡継ぎを決めるのは、伝統でして……」
「その話はもう聞いた。他の言い分はないのか?」
王妃の少し呆れたような声に、汗がふきだす。
焦るばかりで、言葉が出てこない。
「恐れながら、ドュルジ侯爵夫人トリーがルイーサ王妃に申し上げます」
「ドュルジ侯爵夫人、聞こう」
「我が夫、ドュルジ侯爵は不器用な人間でございます。しかし、誰よりも私達家族と家門の事を考える心優しき面も持ち合わせております。この度の不敬、心よりお詫び申し上げます。何卒、ご容赦願えれば幸いです」
突然、私の隣にならんだ妻の行動に、あ然とした。
いつも私の後ろに控え、人前ではおとなしく黙っている妻の、堂々とした発言にただ驚いた。
まっすぐに王妃に向かい合う妻の姿に、私の思考は停止したままだ。
「なるほど。何事もみえる姿と本質は、違っている事が多いという事か。あなたは表に出ず、掌で夫を転がしているのだな」
「ころがすとは聞こえがよくありませんわ。私は後ろから夫を支え、ドュルジ侯爵家を守っております」
「ドュルジ侯爵夫人、感謝する。私はまた一つ、人間について学びを得た。あなたのような女性が存在しているという事実を知る事は、私に勇気を与えてくれる」
「過分なお言葉に、私は喜びで胸がいっぱいにございます。また、ルイーサ王妃のお陰で、娘達に新たな道ができたこと、心より感謝申し上げます。ドュルジ侯爵家は、これまでも、またこれからも、現王家を支持し、ルイ―サ王妃とアドラー王に忠誠を誓います」
「ドュルジ侯爵家の言葉、嬉しく思う。これらかも宜しく頼む」
「光栄に存じます」
私を無視して、会話が進んでいく。
なにか、何かを言わなくてはと思うが、口から言葉ができこない。
今までの価値観が、ガラガラと崩れていくような恐怖とともに、ルイ―サ王妃という想像以上の強者の存在に、どこか高揚している自分がいるのを認めざるを得ない。
王妃は、女ではあるが、私より圧倒的に強い。
知識も、胆力も、生き物としての格が自分より上であり、この人間に敵わないと動物としての本能が私に告げる。
恐れと同時に湧き上がる、期待と興奮。
今までに類をみない、圧倒的な存在に出会えた喜び。強い存在への、単純な憧れ。
ひれ伏したくなる、自身の本能と戦いながら、私は何とか抵抗を試みる。
「わ、我が家門は、確かに王家を支持ししております! しかし、女性は力では男性にかなわないでしょう! 実戦では、女性は男性に守られるべき者です。女性を当主にすれば、狙われてしまう可能性が高まります。私は娘を、そのような危険にさらしたくないのです……!」
なんとか自身の意見を言葉にした私に対し、王妃はニヤリと笑みを浮かべた。
「なるほど、夫人の言う通り、ドュルジ侯爵は家族思いで、心配性な父親なのだな。よし、ではあなたの心配を少し減らす事にしよう。今から、あなたが心配している、か弱い女性がどれだけ戦えるかをお見せしよう。ちょうど城外では模擬の試合をしているところだ。女性剣士の腕前を己が目で確認したい者は、ついて来てくれ。ローレライ、私達も試合に加わるぞ」
「かしこまりました。会場の皆様方、ダンスの最中ではございますが、ルイ―サ王妃や私達女性剣士の実力を見たいという方は、ぜひご一緒にどうぞ」
私達は、王妃一行について、城の外へと出た。ホールにいた多くの参加者も、ほとんどが一緒についてきている。
だだっ広い広場ではあちこちで剣の試合が行われており、多くの観客の声援と、キンキンと剣の合わさる金属音が聞こえている。
横に並び歩く妻は、いつもより楽しそうな表情だ。
娘二人にいたっては、興奮に満ちた憧れの眼差しで王妃を見ている。
気に食わない、気に食わないぞ。
王妃を正す筈が、いったいどうしてこうなってしまったのか……。
この広場での試合は、鷲の盾、つまり王城の剣士達の実力を、貴族や平民に披露するという目的で開催されている。
本気の試合ではなく、剣の練習をみせる主旨の筈だが、どちらを向いても、彼らは木刀でなく真剣を使用している。
近くで見ると、ものすごい迫力だ。
私達貴族も、一応の嗜みとして幼少期に剣を練習する。しかし、彼ら鷲の盾は、私達とはレベルが全く違う。
彼らは、とてつもなく、強い。見るだけで、その事がわかる。いや、感じると言うべきか。
王妃達が、練習をはじめる。
女性は守るべきか弱い存在だという私の今までの考えは、王妃の剣さばきを見て吹き飛ばされた。
王妃は、体格の良い若い男の剣士を相手に、互角に戦っている。
力で勝負せずに、相手を器用にかわし、力を弱化させる。
かと思えば、上段から相手に思い切り打ち込み、ガキーーンと大きな音を響かせる。
しかも、笑みを浮かべながら。
周りを見渡すと、他の女剣士達も、それぞれの対戦相手と対等に試合をしてた。
なんだ、これは。
なんだんだ、この状況は。
女は、男より弱い存在?
いや、見てみろ、この者達を。
王妃も、他の女剣士達も、信じられない程に、強いのだ。
私が彼女達の剣の相手をすれば、一撃でのされてしまうだろう。
強い。あまりにも、強い……。
信じられない、しかし、これが現実なのか。
信じたくない、知りたくなかった……。
「ルイ―サ王妃、もう素敵すぎる!」
「剣の腕も強いなんて、もう最高にカッコいいわ」
「実際の練習試合をこの目でみれるなんて、私も幸せよ。あなた達も、剣を習ってみる?」
「ええ、習いたいわ」
「私も、剣を嗜んでます、って言ってみたいわ。カッコいいもの」
娘と妻達の会話に、もう反対する気力は残っていない。
「あ、アドラー王も来られたわよ」
「え、嘘。王妃と王で試合なさるの?」
「あら、まあ! これはめったにない貴重なお姿よ。しっかり拝見なさい」
アドラー王は、筋骨隆々とした、まさに男のなかの男の見本の様な体躯の持ち主だ。
その王と、王妃は剣を交えている。
まず、体重が倍近く違う。
二人の握っている剣の重さも大きさも、やはり違うだろう。
だが、そんな差をものともせず、王妃は王とやり合っている。
いつの間にか、他の者達も練習をやめ、真剣な眼差しで王妃と王を見つめている。
広場にいる、千人近くの人間が、二人の姿に夢中になっているのだ。
「ルイ様、がんばって」
「王妃様、勝ってください!」
「王、負けられませんよ」
「王様、がんばれ」
歓声が飛びかい、広場はますます熱気を帯びてきた。
その場にいる全員が、剣士も貴族も平民も、大人も子供も、そして女性も男性も。今この瞬間、皆がひとつになっている、そんな感覚を覚えた。
我々全員が、王妃と王の二人を中心とした、強力な磁力に引きつけられた、共に集う仲間なのだ。
そんな心境に至った自身を不思議に思う。
貴族である自分と平民が同じダンスホールにいる事があり得ないと怒っていた自分が、平民を仲間と思うなど。
思わずため息をつき、目を閉じる。
なんという事だ。この僅かな時間で、私はすっかり変えられてしまった。
ルイ―サ王妃は、ただの女性ではない。
私のようないち貴族が、どうこう言える相手ではない。
いやでも、その事実を理解させられた
練習試合をするだけで、人々を熱狂させられる強さと華やかさを持つ剣士。
そこに、性別は関係ない。
ただ、存在の圧倒的な強さが、光り輝いている。
「現状維持は衰退への道、か……」
個人の考えや習慣も、新しいものを取り入れ、改善していく必要があるのだろう。
私は妻に話しかけた。
「トリ―、お前はもしかして、自分で家門を継ぎたかったのか?」
「いいえ、私はあなたに入り婿に来てもらってよかったと思っているわ。でも、時代は動いている。ウラリカとサナリル。娘の為にも、女性当主という選択肢が増えることは大歓迎よ」
「そうか……」
「あなた、皆の前で王妃に意見を述べた姿は、かっこよかったわよ」
「……お前もかっこよかったぞ。まあ、あの場でのお前の発言は驚いたが。しかも褒められてるんだか貶されているだか、わからなかったが」
「フフフフッ……。それで、どう? あなたの意見は、変わったのかしら?」
妻は含みのある笑みを浮かべ、私を見つめた。
私は、素直に心情を吐露する。
「ああ、もう女性が家門を継ぐ事に反対しない。これだけハッキリ女性の強さをみせられたら、反対しようがないだろう。完敗だ。ルイ―サ王妃も、他の女性剣士も、その辺の男では敵わない。私が考えていたほど、女性と男性の差はないのかもしれない」
「あら、まあ。えらく素直ね」
「ふん、いつまでも変化しない頭の固い男だと思うなよ。私だって、革新の重要さは理解している。それに、これ以上駄々をこねて、王妃信者の娘とお前に嫌われても困るからな」
私の言葉に、妻はニッコリと笑った。
「あなた、いつも私達の幸せを考えて行動してくれて、感謝しているわ。ありがとうございます」
「当然だ。私は当主だからな。家族を守るのは私の役目だ」
ワ――ッと大きな歓声が上がった。
どうやら、勝負はついたらしい。
アドラー王の勝利だ。吹っ飛ばされて、地面に倒れたルイ―サ王妃を、王が慌てて抱き起している。
「ルイ―サ王妃、万歳」
「アドラー王、万歳」
王と王妃の、両名を称える声があちこちから上がる。
二人とも、笑顔で手を振っている。
その姿をみて、私の心の奥に、小さな火がついた。
「トリ―、ウラリカとサナリルと一緒に、私も剣の練習をはじめる事にする。勿論、お前もしたいなら、参加すればよい」
「私も、剣の練習を? まあ、それはそれは……。そうね、やってみたいかも」
「そうか。では、家族の行事とするか」
王妃と王への歓声を聞きながら、私は決意した。
認めよう、ルイ―サ王妃。
あなたは特別な人間だ。
しかし、私も貴族のはしくれ。矜持がある。
このまま、ただ負けるわけにはいかない。
私だって、進化できる。
自分を改良して、革新して、刷新してやる!
そして、今以上に家族を幸せにし、国の為に役立つ人間になってやるぞ。
今回は負けた。
だが、勝負はこれからだ。
ルイ―サ王妃、待っていろ。
お読みいただき、おおきにです(^人^)
次話で完結です。
イラストはAIで生成したものを使っています。
いいなと思ったら応援しよう!