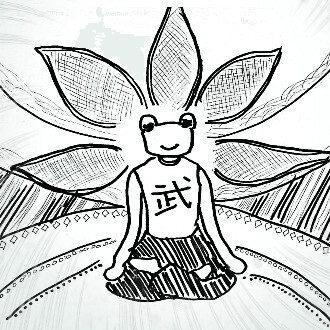再会した彼は予想外のポジションへ登りつめていた 外伝⑤
外伝⑤ アドラー王の告白 ◆
◆ 今回物語上、女性にとって不快な場面、辛さを連想させるような文章がでてきます。恐れ入りますが、苦手な方はとばしていただければと存じます。
「アドラー様、側妃を迎えられるという話を聞きましたが、本当ですか?」
「……誰がその話を……?」
「問題は誰が、ではありません。なぜ、私が知らないのか、だと思いますが?」
公務に追われるなか、久しぶりに二人でゆっくりできる時間を楽しもうというオレの浮かれた心は、突然のルイの言葉に瞬殺された。
彼女の顔が、表情のない作りものの仮面と化している。……まずいな。
「……すまない」
「……それで、側妃としてどのご令嬢がいらっしゃるのですか? いつから?」
「違う! 謝ったのは、その事についてではない! オレが相談を先延ばしにしたせいで、ルイにいらぬ心配をかけてしまった……。もっと早くにこのことについて話しておくべきだったのだ」
「……それは、つまり?」
「側妃を迎えるつもりはない」
ルイの瞳が、少し和らいだように見えた。
「しかし、アドラー様。結婚して丸5年が経ちますが、私はいまだに子を授かっておりません。周囲からはアドラー王の血をひく跡継ぎが必要だと言われています。もし、私が子を産めないのであれば、他の妃を立てるのも、慣例上は仕方のない事かと」
「ルイは、オレが他の女性を妃にして、子をなしても平気なのか?」
「……なぜそのような事を聞くのですか?」
「オレは嫌だからだ。義務の為に好きでもない女性を抱くのも、女性を子をつくる為の道具にするのも、その事によってルイとの関係が壊れるのも、どれもオレの望むところではない」
「……なるほど。わかりました。では、この件について腹を割って話をいたしましょう」
淡々と、しかし腹の底から響くルイの声に、オレは焦りを感じた。
「ルイ、まず先に、オレに話をさせてくれないか? 大事な話だ。……ずっと、話そうと思いながら、言えずにいた」
オレはテーブルの向う側に座るルイを、真正面から見つめる。
しばらくの間、互いに黙して見つめ合った後、ルイは目を閉じて小さく頷いた。
「うかがいましょう、アドラー様。その、大事なお話を」
オレは意を決して、話しはじめる。
ーーーー多分、あれはオレが王としてこの国を治めるようになって2、3年。ひと息ついた頃だ。
オレはダニエルとイザックに連れられて、初めて娼館の門をくぐった。
言い訳しておくと、ギルティアスにも閨教育の一環として勉強しておいた方がいいと言われた。色仕掛けにかからない耐久性を得る為に、そして将来、王妃を迎えて子を作る為に、と。
『絶対に子供ができず、信用でき、知識豊富で、他の男との接触がない、若様に相応しい女性を見つけ出したぜ。こちらは大人気の高級店、ハニーズの女将、アレキサンドリアさんだ』
『はじめまして、若様。アレキサンドリアです。ようこそハニーズへ。お二方にはいつもご贔屓にして頂いております。どうぞおかけになって』
少女のような無垢な笑顔と、ふっくらとした大人の身体をした上品な女性。アレキサンドリアは立ち居振る舞いも滑らかで、そこが娼館だと忘れる位、貴族然とした人だった。
「よろしく頼む」
「エル様とザック様からは、大事な貴族の若様の閨教育の為の女性を探してほしいと、難しい条件をだされましたの。絶対に子供ができず、口が固く、経験豊富で、なにより他のお客様をとらない専属の女性を、という事で私しか残らなかったのです。他の女の子は皆、お客様がついていますからね」
「あなたには、いないのか? ……その、他の客は……」
「私は5年前に、先代女将よりこのハニーズを引き継ぎました。それから、一切の個人的接触はございません」
「そうなのか」
「アレキサンドリアさんのファンは未だに多く、貴族からも後妻や愛妾としてきてほしいという依頼は常にある人気の方だ。若様は幸運だぜ。だが、このことは、他言無用だ」
「わかった」
「私はこの娼館を預かる者として、守秘義務は理解しております。館は一夜の甘い夢をみる場所、目が覚めれば消えてなくなる泡沫の空間。夢物語を他人に話すことはございません」
「頼もしいな。アレキサンドリアさん、では若様を宜しく頼みます」
「かしこまりました。では若様、まいりましょう」
オレはアレキサンドリアの部屋へと案内された。
「緊張されていますか? 初めてのお相手が、私のような年上の者で申し訳ありません」
「正直に言うと、緊張している。とても。そして……オレはあなたは美しいと思う」
オレがそう言うと、彼女は微笑んで、こう続けた。
「ありがとうございます。若様、最初に大切な事を2つお伝えしますね。ひとつめは、娼婦であれ、貴族のお嬢様であれ、閨を共にする相手には優しく対応して差し上げてほしい、という事です。裸で抱き合う場では、身分は関係ありません。自らの体と心を相手にさらけ出し、共に気持ち良くなる為に触れ合う。それが、閨の作法です」
「体と心をさらけ出す……。身分は関係ない……」
「ええ、身分が高かろうが、平民だろうが、裸になれば、みな一緒ですから。二つ目は、正式な奥様以外の相手との閨の際は、相手に勘違いをさせないよう気をつけてくださいませ」
「どういう事だ?」
「つまり、遊びの相手への優しさは礼儀であり、そこに愛情はないという事をはっきりさせておく必要があります。万が一にも、相手があなたに好意をもってしまえば、互いに不幸を招きます。相手があなたを本気で愛する事のないように、きちんと線を引くことを忘れないで下さい。よろしいですか?」
「……わかった。そのように努めると約束しよう」
そうして、オレのハニーズ通いがはじまった。
正直、オレは彼女とのその行為に夢中になった。
アレキサンドリアの事は、素敵な女性だと思った。しかし、ルイへの気持ちとは違うものだと確信している。
それでも、何度も会ううちに、オレのなかで彼女の存在が大きくなっていったのは確かだ。
最初の3ヶ月は、約束の通り月に一度だけという約束を守った。だが、貴族達との不協和音、法律の改正、国の組織改編、王城の人員不足等、民からの訴え、その他トラブルも多発した時期で、オレはすがるものが欲しかった。
月に一度の訪れが、二度になり、三度になり……。
ギルティアスや、ダニエルとイザックにも止められたが、オレはアレキサンドリアに溺れていった。
彼女との閨の間だけは、他の煩わしい事から解放されたのだ。
ハニーズはオレの、現実逃避の為の場所となった。
半年ほど過ぎた頃には、週に一度の頻度で通っていただろう。
それ以上の頻度で通う事を、アレキサンドリアは拒否した。彼女曰く、館の経営者として忙しいので、週に一度以上は来てもらうと迷惑だとの事だ。
そう言われて、オレは彼女がオレと同衾するのは、あくまでも仕事なのだと思い出した。
それから数ヶ月後のある晩、ハニーズで閨の前に出された軽食をつまみながら、オレは何気なしに聞いてしまった。
「前から思っていたが、アレキサンドリアは貴族の出ではないのか?」
「それを聞いてどうなさるの? 娼館にきた女は皆、過去を捨てますの。ですから、私にも過去はありません」
「……そうか、無粋な事を言った。すまない」
「いえ。でもそうですね。先代の女将から聞いた話を、かわりにお話しましょうか」
そして、彼女はこの話を聞かせてくれた。
ーーーーある貴族の女性がいた。かなりの上位貴族の娘だった彼女は高い教育を受け、聡明で意志も強く、本来であれば公爵家に嫁ぎ公爵夫人となる筈だった。しかし、突然の家門の取り潰しにあい、知らぬうちに娼館へ売りとばされてしまった。
何か起きたのか理解できず、ショックのあまり泣き崩れた。乱暴な男性からの無理やりの行為、殴る蹴るといった暴力、蔑みの言葉、同じ館の女性達からのやっかみ、嫌がらせ。
今まで彼女の人生になかった、人間の闇の部分をいきなり突き付けられた。
貴族にとって、平民は同じ人間ではない。別の生き物だ。しかも、下々のなかでも最下層の娼婦に自身が身を落とす事になるなど、一瞬たりとも考えた事もなかった。
2ヶ月後、彼女は館を逃げ出した。しかし、金銭も身分も頼る者もいない彼女を待っていたのは、更にひどい地獄だった。
彼女は思った。なぜ、自分がこんな辛い目にあわなくてはならないのか。死んだ方がマシだ。
自ら命を捨てようとしたところを、赤の他人に命を救われる。貧しくとも心の豊かな人々が存在する事を彼女は知った。そして、その他者を思いやる優しい人々に助けられ、生きぬく事を選択する。
彼女は気づく。かっての自分は何も理解していなかった。貴族令嬢としていかに幸せに暮らしてきたか。庶民の暮らしがどれだけ大変か。そして、動物のように売り買いされる女性の立場の弱さ。男性の言いなりになり、辛酸を舐めるのは女性や子供といった社会的に弱い立場の者。
彼女は決意する。このひどい世の中で、少しでも女性がましに暮らせる場所を自分の手でつくりたい、と。そして、血反吐を吐くような努力の末に手に入れたのが、ハニーズという館だった。
「この初代女将の話を、うちに入ってきた女の子達に必ず最初に話しますの。あなた達は、館が大金を払って買い取った大事な人材なのだと。あなた達が逃げたら、館は大きな損害を受ける。そして逃げても、あなた達が幸せになれる可能性は限りなく低い。だから、覚悟を決めて仕事をしてほしい。自分の価値を上げ、たくさん稼げるようになれば、自分で自分を身請けして自由になるという選択肢が増える。その為には、館の他のスタッフを敵視せず、仲間として互いに助け合う方が得策。ハニーズには、自分の得意な事、例えばダンスや貴族マナーや芸術等の知識を他の子にシェアする教育制度がある。それを利用して、自分を高めてほしい。そして、どんなに屈辱を受けても、これだけは忘れないでいて。裸になれば、貴族も商人も娼婦も一緒なの。同じ人間、ただの肉の塊よ。結局のところ、私達は人が決めたルールで身分がわけられているけれど、肉の塊としては同等だわ。その事を心に留めおいて仕事をなさい、とね」
貴族も平民もみな同じ人間、ただの肉の塊としては同等。
その言葉は、サラディナーサと重なり、オレの心を激しく揺さぶった。
国王という権利者に見初められたものの、平民出の側妃として周りから見下され、あげく命を狙われた母。父の庇護を受けれず、孤独に苛まれた母。
しかし、少なくとも、母には祖父や味方となる家族がいた。
もし、母が自らの運命と戦う勇気を持つことができていれば、あのように心を病み死ぬこともなかったのではないか。
「……あなたも、そして歴代の女将も、強い人なのだな」
「強くならざるをえなかった、という方が正解ですわ。私達自身が、こうなる事を望んだ訳ではありません。でも、最近こう思うのです。人には、それぞれ使命が与えられていているのではなか、と」
「使命?」
「はい、本人の希望は全く加味されない、一方的で非情な使命ですけれど。運命といってもよいかもしれません。その自分に課せられた使命を理解し受け入れ、そのなかでいかに快適にすごすか、自分を最大限に活かすか。それが肝要ではないかと思うのです。……私の使命は、このハニーズの女の子達を守る事だと認識しております」
そう言って、彼女は自嘲的に笑った。
「いらぬ話をお聞かせして申し訳ございません、若様。でも、今からお話する事は、どうか頭の片隅において頂ければと思います。将来、あなた様はこの国の重要な方になられると感じる私からの、お願い事です」
「……重要な人間になれるかどうかわからぬが、聞いておこう」
「ありがとうございます。若様、石女〈うまずめ〉という言葉をご存じですか?」
「知っている。子供ができない女性の蔑称だろう?」
「そのとおりです。この館にも、他の娼館にも、嫁ぎ先で子が出来ず、石女として離縁され、売られてくる女性は多いのです。しかし、妊娠する事だけが、女の価値でしょうか? この世界にいると様々な人間の話を聞きます。心と体の性別が違う人たち、女でも男でもない体を持つ人達。人間というものは全員が子をつくる能力を保持しているわけではありません。男性も同じです。子供ができない夫婦の問題は、常に女性側に問題があると言われますが、はたしてそうでしょうか? 男性が生殖能力を保持していない場合もあるでしょうが、その事は公にはされません。いつも、女性に非があると決めつけられる。……若様、私は女性の地位を上げたいと考えております。私達女にも、考える頭があります。きちんとした教育と、働く場所があれば、私達も結果を出す事ができます。どうか、身分制度、そして女性を下にみている現在の社会の在り方を、女性にとって少しでもましな環境へ変える為に、協力していただけませんか?」
オレにとってアレキサンドリアは、娼婦とはいえ知的で蠱惑的で落ち着いた、年上の婦人レディという印象だった。
それが、これほど性根の据わった革新的な考えを持つ、気骨のある人間だったとは。大きな衝撃を受けた。
つまり、オレは彼女を全く見ていなかった。軽んじていたのだ。
彼女の肉体には夢中になっていたが、彼女が自分の意思を持つ独立した人間だと気づいていなかった。いや、そもそも、興味もなかった。
オレは、彼女を人形扱いしていたのだ。
父に翻弄された母、そして身勝手な男に殺されたサラディナーサを見てきた。自分では女性を蔑視しない理解のある男だと考えていた。
なんのことはない、ただの自惚れだと気づかされた。軽蔑しているくだらない男達とオレは同類なのだと。
オレは、何のために兄や親族を手にかけてまで、王位を得たのだ?
みんなにとってより良い社会をつくる為ではなかったのか。
なのに、一番近しい場所にいる女性を、蔑ろにしている……。
「……すまない、アレクサンドリア。本当に申し訳……ない……ック……」
いきなり泣き出したオレを、彼女は優しく抱きしめてくれた。
「若様は、良い子ですね。私は若様にお会いできて、嬉しく思います」
「……ズッ……。良い子……では、ない……。……ッズッ……オレは、ただのバカだ……」
「バカな自分をちゃんと理解し反省できるのは、良い子ですよ。若様、ひとつ言い忘れていました」
「……なにを……?」
「閨教育の一番大切な事です。もし、愛する相手に出会ったら、出し惜しみせず全力で相手を愛してください。体も、心も、相手が気持ちよく嬉しい気持ちになるよう、そしてあなた自身も幸せになれるように。素直に、言葉で行動で、心からの愛を伝えるのです」
「……出し惜しみせず全力で愛する……。素直に、心からの愛を伝える」
「そうです。とても大切な事です。忘れないで、若様」
「……わかった。アレクサンドリアの助言、活かすように努める……」
「ありがとうございます。若様は、本当に良い子ですね」
彼女は、幼子をなだめるかのようにオレの髪を撫でた。オレは、母に抱かれているような感覚を味わった。
その夜、オレはハニーズに通いだして以来、初めて彼女と何もせず、ただ眠った。
そして、それが彼女と一緒に過ごした、最後の時間だった。
「最後とは、その女性はどうなったのですか?」
ルイは落ち着いた声でそう質問してきた。
他の女性の話をした事を、怒ってはないらしい。
「……アレクサンドリアは、その一月後に死んだ。オレは業務に忙しく、しばらくハニーズに行く時間がとれなかった。ダニエルが館から事件の報告を受け、オレに伝えてきた」
「……事件?」
「暴漢に殺されたのだ。館のスタッフを守る為に、護身用の短剣で抵抗そうだ。オレはその話を聞いて、彼女は戦士だと思った。何も戦場にいる剣を持った男だけが戦士ではない。あらゆる所で、名もなき女性の戦士達が、不条理に対し声を上げ闘っているのだと強く感じた」
オレは立ち上がり、ルイの前に跪き、彼女の手を握った。
「ルイ、オレはこれまでルイ以外に3人の女性に影響を受けた。一人目は母、二人目は前世のあなたサラディナーサ、そして三人目がアレキサンドリアだ。彼女の言葉が今も耳に残る。妊娠する事だけが、女の価値なのか、という問いが。それはまた、子種が無ければ、男として価値がないという話と同義だ。オレはその価値観を崩したいと思う。この5年間、オレ達に子は出来なかった。でもオレは、出来ないなら出来ないでいいと考えている。愛するルイと二人で、今、この国を育てている。オレはそれで満足だ。ルイはどう思う?」
ルイの顔を見つめる。
瞳が潤んでいるのがわかった。
「……アドラー様、本気なのですね? 本当に、側妃は娶られないと」
「二言はない。次の王には、なるべき者がなるだろう。ルイ、跡継ぎをつくらない無謀な王と王妃という非難に、共に耐えてくれるか?」
目に涙を溢れさせながら、ルイは最高の笑顔をみせてくれた。
「アドラー様、私は王をお護りする鷲の盾です。どんな時も、私はあなたと共に在ります。そして、アレクサンドリアさんを対等な人間として尊重されたあなたを、私は尊敬します。あなたを愛しています。これまで以上に」
オレは彼女を抱きしめる。
「愛している。オレもルイを心から愛している。ルイと出会えたこの人生に感謝している」
彼女の纏う爽やかなアロマの香りと、滑らかな手触りの髪に触れながら、アレキサンドリアを思い浮かべた。
今、彼女が生きていればこう言ってくれるだろう。
『若様。私の助言を忘れないで下さいませ。愛する方には、素直に、全力で愛を伝えること。お幸せにね』
オレはルイを愛しぬく。
そして、オレ達二人で、女性や弱者がより生きやすい国、己の価値を感じられる社会にかえていく。
約束しよう、アレクサンドリア。
私の初めての人であり、母のような存在であり、部下の為に戦って散った勇敢な戦士である、あなたに。
あなたが命をかけて使命を全うしたように、オレも己の使命を果たす事を、あらためてここに誓う。
アレクサンドリア、どうかみていてくれ。
お読みいただき、おおきにです(^人^)
イラストはAIで生成したものを使っています。
次話
いいなと思ったら応援しよう!