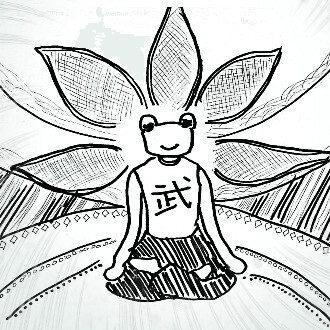再会した彼は予想外のポジションへ登りつめていた 外伝④
外伝④ それぞれの選択
「シルバー、準備は整ったのか?」
「ダニエル隊長、はい、最終点検も終えました。あとは、進行にそって順番に出すだけです」
「そうか。よろしく頼むぜ。なんせ、オレの可愛い部下達のめでたい祝いの席だ。最高にうまい料理でみなをもてなしたいからな」
「ダニエル、任せとけって。俺の部下の腕は確かだ。みんな、料理が旨すぎて泣いちまうかもしれねえぜ。な、シルバー副料理長」
「は……。皆様の御期待に添えるよう努めます」
「よし、任せたぞ! では、会場も確認しとくか」
そう言って、城外警防隊と食料隊隊長の両トップ、ダニエル隊長とイザック隊長は、楽しそうに厨房を出ていった。
ヤレヤレ、だ。
まさか、王城の野外の稽古場で、結婚披露宴を開催するなどと、誰が考えたんだか……。
しかも、鶏肉の串焼きをメニューに加えるなど。貴族の常識では考えられない。
串焼きは、兵士の野営時には定番の料理だ。肉をブツ切りにして塩コショウをまぶし、野菜と一緒に串にさして焼くだけの、なんの捻りもない調理法。平民の屋台では定番の人気料理ではあるが。
しかし、そのシンプルな料理だからこそ、料理人の腕次第でどうにでもかわる。
「うわっ、ヤバ……っ! シルバー、これめちゃめちゃ旨いぜ」
「信じられないほど、高級料理にばけてる!」
「本当にいつもと同じ鶏肉とは思えない旨みがあるな」
「さすが、シルバー副料理長。これはうめえわ!」
味見をした料理長や他の厨房の連中が、口々にそう褒めてくる。
悪い気はしない。
「味は合格のようでよかったです。この宴会料理は、料理長はじめ、みんなでつくった料理ですよ。今日は我々、食料隊の実力を見せつけてやりましょう」
「おう、そうだな。今日は食料隊の晴れ舞台でもあるな。よし、運ぶ準備をしようぜ」
「了解だ。向うの大皿からやるか?」
わいわいと笑顔で準備を進める仲間の声を聞きながら、今この瞬間、自分が厨房に立っているという事実を不思議に感じた。
私は下級貴族の家に生まれた。貧乏な男爵家だとはいえ、貴族は貴族だ。
貴族としての矜持を、両親は大切にしていた。
日常生活の為の用事、例えば掃除や雑務、そして料理をつくる行為は使用人がすべき仕事だ。決して、貴族自らが、その為に動くことはない。
使用人の数は少なかったが、両親は頑なにその貴族ルールを守っていた。
だから、ずっと言えなかった。
料理がしてみたい、とは。
私は幼少期から食べ物に対して、とても興味を持っていた。
肉、野菜、香辛料。作り方や一緒に添える食材により、味や食感がかわるのだ。
旨み、香り、のどごしが変化するのを感じて、料理は魔法ではないかとワクワクした。
だが両親の言葉で、私はそう考える事は貴族として恥ずべき事なのだと学んだ。
美しいと言われる容姿を磨き、剣と勉学に打ち込んだかいがあり、王城へ仕官する事ができた。
そして、私は出会ったのだ。
ルイ、いや、ルイ―サ王妃と。
初めて彼女を見た時、その眼力の強さに驚いた。
彼女は女性であるにもかかわらず、堂々と自分の意見を述べ、他の男性達の非難の声に負けることはなかった。
ルイは実際に強かった。剣の練習試合で、私は彼女に負けたのだ。
女性に剣で負けるなどと、この国の男性であれば、想像したこともないだろう。
貴族令嬢でありながらその型破りな生き方を貫く彼女に、私はいつしか憧れを抱くようになった。
ルイを、私の妻としたい。彼女を、独り占めしたい。
だが、私はしがない男爵家の三男。
今のままでは、身分が釣り合わない。彼女と結婚する為に、どうすればいいだろうか。
そんな思いはすぐに打ち砕かれた。
ルイは、アドラー王と結婚して、王妃となった。
しかも、ルイからのプロポーズで。
人生で一番の衝撃を受けた。
女性から男性へ、そして臣下から王への、婚姻の申し込み。
常識とは真逆の、あり得ない行為。
それを飄々と行い、自身の進む道を自分で掴み取っていくルイの姿をみて、心の痛みと共に、奥底に押し込めていた料理への情熱が再燃した。
彼女に、負けたくない。
私も、自分の道は自分で決めて生きたい。
私は勇気をだした。
食料隊への異動を希望し、厨房で修行し、そして嬉しい事に3か月前に最年少の副料理長の位を得た。
勿論、家族や親族には猛反対された。いまだに実家に帰った時には、家族の小言が聞こえてくるが、気にならない。
私は自分の望む道を選択し、行動を起こしたのだ。
今は王城の人々の胃袋を満たす為に、日々料理に明け暮れる日々だ。
自分の好きな事をするのが、こんなにも楽しいものだとは知らなかった。
勿論、それなりにもめ事や苦労もあるが、それでも。
料理への興味に蓋をして、全く興味等ないと振舞っていた頃に比べれば、幸せな毎日だ。
「料理長、シルバー、食料隊の皆、今日は世話になる。感謝する」
「おおー、今日の主役の登場だ! ゴドゥインさん、ご結婚おめでとうございます」
気がつくと、ゴドゥインが厨房に挨拶にきていた。
ルノワール侯爵家子息ゴドゥインと、平民であるローレライの結婚。
これも、今までならあり得ない話だ。
ましてや、貴族の見本のような考え立ち居振る舞いをしていたあのゴドウィンが、王妃に憧れて頭脳派の図書教育隊から街の治安を守る城外警防隊へと異動し、王妃に次ぐ女剣士と噂される腕前になった商家のローレライと結婚することになり、その披露宴の料理を私がつくる事になるなんて。
本当に、人生とは何がおこるかわからない。
人はかわる。
世の中の常識もかわる。
貴族ルールが、全くの悪習だとは思わない。
ただ、時代や状況の変化により、人間の考えや慣習も、おのずとかわっていくのだろう。
『流れる水は腐らず』
人も、国も、自然も、常に移り変わっていく。
ルイ―サ王妃は、その流れの大きな転換を担う、貴重な存在なのだろう。
そんな彼女を妻にしたいなどと、大それた望みを持ったものだ。
そう自嘲しながら、私は祝いの言葉を口にした。
「ゴドゥイン、結婚おめでとう。ローレライは剣の腕も、弁も立つし、判断力もある。安心して背中を預けられるパートナーだな。二人は似合いだと思う」
「感謝する、シルバー。だが、一点、訂正しておこう。多分ローレライは背後で大人しく待つような人間ではない。女性ながらに、私の前にでて戦おうとするだろう。男性である私が、彼女の背中を守る役目になりそうだ。困ったものだが、そんな希少な人間に出会えた事を幸運に思う」
そう照れながら言うゴドウィンの表情は柔らかく、幸福感に溢れていた。
「……そうだな。彼女は、希少な人間だ。出会えた幸運に感謝、だな」
ゴドウィンは、ローレライと出会えた。
そして、私もルイに出会う事ができた。
たとえ、彼女が王妃で、別の誰かを愛しているとしても。
たとえ、私のこの思いが、永遠に彼女に届かなくとも。
ルイの幸せそうな姿を見る事はできる。
彼女が懸命に取り組む国政に携わる事はできる。
彼女を知らなければ、私は自分が料理をつくるなど考えもしなかっただろう。
私が、今の私になるきっかけを、ルイは与えてくれたのだ。
彼女に出会えた幸運に、私は心の底から感謝した。
お読みいただき、おおきにです(^人^)
イラストはAIで生成したものを使っています。
次話
いいなと思ったら応援しよう!