
ノーベル経済学賞って何だろう?
本エントリは、「5つの「なぜ?」で分かるノーベル経済学賞」(『一橋ビジネスレビュー』65巻1号(2017年Summer)所収)の内容を約半分にまとめた縮約版です。明日発表される2017年度「ノーベル経済学賞」の理解の一助として頂ければ幸いです。
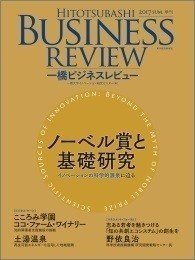
ご関心のある方は、スライド資料「2017年ノーベル経済学賞予想 --- 参考資料」も合わせてぜひご参照ください。
ノーベル経済学賞って何だろう?
大阪大学大学院経済学研究科
安田 洋祐
【要約】
ノーベル経済学賞は他の分野とかなり毛色の異なるノーベル賞である。本稿では、「経済学って本当にノーベル賞?」「受賞者はお年寄りばかり?」「受賞者はアメリカ人ばかり?」「経済学賞は権威に弱い?」「日本人は受賞できる?」という5つの疑問に答えながら、経済学賞の特徴を様々な角度から紹介する。さらに、ノーベル賞の選定に欠かせないであろう、新規性・無謬性・有用性という3つの基準が、どのように経済学賞の特徴に影響を与えているのかを分析する。また、期待の高まる日本人の初受賞に関しては、具体的な候補を挙げつつ近い将来の実現を予想する。
1. はじめに
ノーベル賞と聞いて、日本の読者の皆さんに最も馴染みが薄い分野が、おそらく経済学賞ではないだろうか。ノーベル賞が対象とする6分野の中で、いまだに日本人受賞者が誕生していない唯一の分野がこの経済学賞である。また、設立の経緯が他の5分野とは異なり、授賞の開始は他分野から半世紀以上も遅れている。この意味で、ノーベル経済学賞は、マイナーでオマケっぽい印象が拭えないかもしれない。しかし、自然科学ではなく社会科学の賞であることから、我々の生活やビジネスに最も距離が近い、というのも経済学賞の特徴である。そのため、経済学賞の歴史や動向を追うことで、人類が社会や経済をどのように理解してきたか、理解しようとしてきたか、という知的格闘の様子が掴み取れるに違いない。次節以降では、ノーベル経済学賞に関する5つの「なぜ?」という素朴な疑問に答えていきながら、こうした知的格闘の雰囲気を少しでもお伝えしていきたい。本稿を通じて、現実の社会や経済に対する見方をアップデートするきっかけとして頂けたら幸いである。
2. 経済学賞って本当にノーベル賞?
ご存知のように、ノーベル賞は世界で最も権威のある国際的学術賞である。ダイナマイトの発明によって巨万の富を得たアルフレッド・ノーベルの遺言にもとづいて、物理学・化学・生理学医学・文学・平和の五分野に対して、1901年から授賞が始まった。この時点で経済学はまだノーベル賞には含まれていなかったのである。それでは、いつから経済学賞はスタートしたのであろうか。
経済学賞は、1968年にスウェーデン国立銀行の設立300周年祝賀の一環として創設された。第1回目の受賞者は1969年に誕生しており、ノルウェー人のラグナル・フリッシュとオランダ人のヤン・ティバーゲンが「経済過程の分析に対する動学的モデルの発展と応用」への功績を理由に選ばれた。選考・授賞のプロセスは他の分野と同様である一方で、賞金はノーベル財団ではなくスウェーデン国立銀行によって(他分野と同額が)支払われている。こうした背景もあり、賞の正式名称は「ノーベル経済学賞」ではなく、「アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン銀行賞」となっている。ノーベルの遺言にもとづいていないことから、その正当性に対して彼の一族や他分野の受賞者、選考委員たちから疑義が投げかけられたこともあるが、一般のメディアなどではノーベル経済学賞と呼ばれることが多い。つまり、経済学賞は厳密にはノーベル賞ではないものの、実質的にノーベル賞として広く認められている学術賞と言うことができるだろう。
経済学賞は、正確には「経済科学(Economic Science)」に与えられる賞で、その選考対象は狭い意味での経済学にとどまらず「隣接する社会科学まで含む」ことが1995年に決定された。そのため、政治学・社会学・心理学・歴史学なども選考対象になり得る、という学際的な特徴を持っている。例えば、2002年の受賞者ダニエル・カーネマンは心理学者、2009年のエリノア・オストロムは政治学者としてキャリアを積んでおり、いわゆる経済学者ではない。選考範囲が明示的に広げられた1995年以前にも、1978年の計算機科学者ハーバード・サイモンや、1994年の数学者ジョン・ナッシュといった非経済学者も受賞している。今後も経済学界の外から、他の社会科学分野を専攻する受賞者の誕生が期待される。
3. 受賞者はお年寄りばかり?
ノーベル経済学賞の大きな特徴の一つとして、受賞者が高齢であることが挙げられる。ノーベル財団が公開しているデータによると、過去の経済学賞の受賞者の受賞時平均年齢は67歳である。これは6分野の中で最も高く、全分野の平均年齢59歳を8歳も上回っている。自然科学系の3分野が、物理学55歳、化学58歳、生理学医学58歳で、いずれも50代であるのと好対照と言えるだろう(【図1を参照】)。

【図1】ノーベル財団公式サイト(リンク)から引用。
平均だけでなく、最年長者および最年少者もそれぞれ、全分野を通じた最高齢を記録している。経済学賞の歴代最年長受賞者はレオニード・ハーヴィッツで、「メカニズムデザインの理論の基礎を確立した功績」によって、2007年になんと90歳で受賞している。ノーベル賞全分野を通じて、今のところ最高齢の受賞者であるハーヴィッツは、いったいどのような業績によって選ばれたのだろうか。彼の仕事を少し詳しく見てみよう。
インセンティブと制度設計
経済学は、市場を中心とした狭い意味での経済問題を越えて、今日では人々のインセンティブに関する様々な問題を扱っている。このインセンティブの重要性を、制度設計の文脈で初めてきちんと示したのがハーヴィッツなのである。彼はその先駆的な研究(Hurwicz, 1960)において、一見すると抽象的で捉えどころが無いように見える「制度」という対象を、参加者どうしの「コミュニケーション・システム」という具体的な形で定式化し、経済理論による制度分析の端緒を開いた。そして、1972年の論文(Hurwicz, 1972)で、与えられた制度や環境において、人々が(全体ではなく)個々のインセンティブに従って行動することを保証する条件として「誘因整合性」(Incentive Compatibility)という考え方を提示した。この概念は、直感的には次のように説明することができる。
社会にとって望ましい制度や仕組みの設計を検討する際に、ひとりひとりのメンバーのインセンティブを無視してはならない。なぜなら、彼らが自らのインセンティブに従って行動した上で、同時に社会にとっても望ましい結果が得られるのでなければ意味がないからだ。現実を見ても、旧東欧社会主義国家による計画経済の失敗が物語るように、人々の行動を強制できる、思った通りに動かせる、という想定のもとで制度をナイーブに設計するのは危険を伴う。参加者のインセンティブを無視した制度というのは、絵に描いた餅に過ぎないのだ。ハーヴィッツが生み出した誘因整合性は、制度設計者の思惑通りに各個人が意思決定を行うことが、当人にとっても最適となる、つまり社会の目的と個人のインセンティブが整合的であることを保証する条件である。これは社会におけるルール・仕組み作りを考える上で決定的に重要な概念であり、ハーヴィッツの貢献が土台となって、経済学における制度設計に関する研究が後に花開くことになった。制度設計に関する基礎理論を、経済学ではメカニズムデザインと呼んでいるが、彼こそがその生みの親なのである。
市場と社会選択の理論
さて、次に歴代最年少受賞者であるケネス・アローに目を向けてみたい。彼は「一般的経済均衡理論および厚生理論に対する先駆的貢献」を理由に、1972年に51歳で受賞している。経済学賞は、40代以下の若手受賞者が生まれていない唯一のノーベル賞なのだ。ちなみにアローは、数理計画法の応用、社会選択理論の確立、一般均衡理論における主要貢献、内生的成長理論と情報の経済学の開拓など、経済学分野全般において超一流の業績を残しており、20世紀最高の経済学者との呼び声も高い。2つ挙げられているノーベル賞の直接的な受賞理由のうち「一般的経済均衡理論に対する先駆的貢献」としては、後年に自身もノーベル経済学賞を受賞することになるジェラール・ドブルーとの共著論文(Arrow and Debreu, 1954)が最も重要なものである。市場メカニズムの振る舞いを数理的に描写する一般均衡理論は、20世紀半ばにおける最先端の経済理論であり、彼らが解決した「均衡解の存在問題」はその中で最も深刻な未解決問題だった。アローとドブルーは、当時の経済学者には馴染みのなかった位相数学のテクニックを用いて、理論予測として用いられる均衡解が非常に一般的な前提条件の下で存在することを数理的に示したのである。
もう一つの受賞理由である「厚生理論に対する先駆的貢献」は、何と言っても彼自身が確立した社会選択理論を挙げないわけにはいかない。1951年に出版した博士論文『社会的選択と個人的評価』(Social Choice and Individual Values)の中で、アローは社会における集合的な選択問題を扱う理論的な枠組みを構築し、この分野自体を事実上切り拓いた。さらに、その枠組みの下で、個人の選好(選択肢の相対的な好み)を集計して社会全体の選好を形成する難しさを厳密に証明した。この結果は、今日では「アローの不可能性定理」と呼ばれている。具体的には、アローは個人の選好を集計するルールが満たすべきだと考えられる4つのもっともらしい条件を定義して、それらを常に満たす集計ルールが独裁制、つまりある個人の選好を社会全体の選好と一致させるルールしかない、という結果を導いた。当然ながら、独裁制は民主的な選好の集計ルールとは言えないため、アローの定理は(直接)民主政による社会の合意形成が原理的に抱える困難を浮き彫りにしたと言えるだろう。
以上のように、受賞年齢を統計的な視点から眺めると、平均値、最大値、最小値のいずれをとっても経済学は最も高くなっており、データから、ノーベル経済学賞の受賞者が最も高齢であることが示唆される。ノーベル賞は存命中にしか受賞できないため、特に経済学賞では、長生きこそが受賞の秘訣なのかもしれない(もちろん、受賞に値する学術業績をあげていることが大前提ではあるが…)。
4. 受賞者はアメリカ人ばかり?
ノーベル経済学賞のもう一つの大きな特徴として、受賞者の国籍の偏在も挙げられる。経済学賞受賞者は、1969年から2016年までの間に総計78名誕生している。次の【表1】で示されるように、その中で3名以上の受賞者を輩出した国はわずか5ヵ国に過ぎない。二重国籍取得者については、両方の国でカウントしている。
<受賞者の国籍>
第1位:アメリカ 53名
第2位:イギリス 9名
第3位:カナダ 3名
第3位:フランス 3名
第3位:ノルウェー 3名
【表1】
過去の受賞者のほとんどが欧米の出身者で、中でもアメリカの出身者が突出して多く、全体の約7割を占めている。それに対して、非欧米出身者はわずかに3名しかおらず、しかもその内2名はイスラエルとアメリカの二重国籍取得者である。欧米諸国の国籍を持たない受賞者は、1998年に「所得分配の不平等にかかわる理論や、貧困と飢餓に関する研究」への貢献で単独で受賞した、インド人のアマルティア・センただ一人しかいない。彼は、前節で紹介した社会選択理論の大家としても高名である。特に、Sen (1970)が示した「自由主義のパラドックス」は、前述のアローの不可能性定理と並ぶ、社会選択理論における大定理として広く知られている。これは、個々のメンバーが、一部の社会的な帰結について自分一人でどれを選ぶかを決められる(個人に与えられたこの裁量をセンは「権利」もしくは「自由」と定義した)ときに、社会全体にとって望ましい結果を選ぶ選択ルールが存在しなくなる、という不可能性定理である。社会全体にとっての望ましさと、個人の自由あるいは権利を両立させることの難しさを、端的に表現した基礎理論と解釈することができる。
実はこのセンも、大学および大学院教育はイギリスのケンブリッジ大学で受けており、大学教員としてのキャリアもその大半をオックスフォード大学やハーバード大学といった欧米の大学で過ごしている。生まれこそインドではあるものの、アジア人初のノーベル経済学賞受賞者であるセンを卓越した研究者として育んだのは、英米の研究大学と言えるかもしれない。この点は他の受賞者にも共通している。博士号の取得大学や、受賞時の所属大学が英米の一部の大学に極度に集中しているのだ。その背景には、研究の中心地・発信地としてそれらの大学の影響力が強く、世界中から優秀な研究者や大学院生を引き寄せている、という経済学固有の事情がある。多くのノーベル経済学賞受賞者を輩出し、長らく経済学研究の一大拠点として君臨してきたシカゴ大学の研究グループが「シカゴ学派」と呼ばれるのも、そうした伝統の表れと言えるのではないだろうか。
次の【表2】は、分野ごとに世界の大学ランキングを発表しているQS世界ランキングの最新版から、経済学・計量経済学分野におけるトップ15大学を抜粋したものである。俗に「トップ5」(+1)と形容される上位5・6校はいずれもアメリカの大学が占め、上位15校のうち8割にあたる12校がアメリカの、残り2割にあたる3校がイギリスの大学となっている。第二次世界大戦以前は、経済学発祥の地であるイギリスが研究をけん引し、大戦後は大西洋をまたいで、世界一の経済大国であるアメリカに研究拠点が移った。これが、英米両国の研究面での優位性に大きく寄与していると考えられる。しかし、なぜ地理的な研究の中心地がここまで大きくシフトしたのか、なぜアメリカへの過剰な一極集中が進んだのか、といった問いに対するはっきりした答えは(少なくとも筆者には)不明である。いずれにしても、自然科学系であれば、トップ15の研究大学に、ドイツ・フランス・日本などの非英米大学が一校もランキング入りしない、という事態は考えにくいのではないだろうか。
<QS 世界大学ランキング―経済学・計量経済学:2016年度>
1位:マサチューセッツ工科大学
2位:ハーバード大学
3位:スタンフォード大学
4位:プリンストン大学
4位:カリフォルニア大学バークレー校
4位:シカゴ大学
7位:ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス
8位:オックスフォード大学
9位:イェール大学
10位:ケンブリッジ大学
11位:コロンビア大学
12位:カリフォルニア大学ロサンゼルス校
12位:ペンシルベニア大学
14位:ニューヨーク大学
15位:ノースウェスタン大学
【表2】QS World University Rankingの「経済学および計量経済学」のランキング(リンク)より作成。
5. 経済学賞は権威に弱い?
第3節と4節で、ノーベル経済学賞の受賞者が他分野と比べて高齢であること、彼らの出身国が欧米とりわけアメリカに大きく偏在していることを確認した。本節ではその理由について考察していきたい。アルフレッド・ノーベルの遺言「(賞金は)人類のために最大たる貢献をした人々に分配される」によって生まれたノーベル賞は、科学における世界最高の栄誉ある学術賞である。その認識は研究者だけでなく世間一般にまで幅広く共有されている。当然ながら、受賞業績や受賞者の選定は、慎重に慎重を重ねて行われなければならない。後述するように、この受賞に至るまでの道のりの長さ、ハードルの高さが、とりわけ経済学賞受賞者の高齢化や地域的な偏在をもたらしていると考えられる。
ノーベル賞を受賞するためには、ひとまず同業の研究者たちに推薦されて、候補者である250~300名に残らなければならない。では、どういった研究業績であれば、同業者たちからノーベル賞級であると認められやすいのであろうか。特に明示的な基準が設けられているわけではないため、これは筆者の推測に過ぎないが、少なくとも次の3つの条件を満たす必要があるだろう。
[条件1]新規性―新しい
[条件2]無謬性―正しい
[条件3]有用性―役に立つ
[条件1]新規性と[条件2]無謬性については、あまり解説の必要はないかもしれない。常識的に考えても、既存研究と大きな違いが無い、あるいは間違っている危険性のある発見に対して、ノーベル賞を与えるわけにはいかないだろう。[条件3]の有用性も、ノーベルの「人類のために最大たる貢献」という遺言を思い出すと、外すことができない条件だと考えられる。以下では、それぞれの条件が候補者の選び方を通じて、経済学賞の受賞傾向にどのような影響を及ぼすのかを占ってみたい。
[条件1]からは、新たな分野を切り拓くような革新的、独創的な研究が有利であることが予想される。既存研究の焼き直しや、ちょっとした拡張・変形、あるいは追試などでは候補にすら残れないに違いない。実際に、歴代の受賞者を振り返ると、ある分析手法や枠組みを広めた伝道者ではなく、最初にそのアイデアのひらめきを得て確立した先駆者ばかりが選ばれている傾向が確かに読み取れる。
[条件2]についてはどうだろうか。実は、この無謬性を立証することが、経済学のような社会科学では非常に難しい。なぜなら、自然科学のように制御された実験を行うことがほとんどできないからである。適切に実験環境を制御できるということは、観察された実験データを使って、理論や仮説が正しいかどうかを、誰の目にも分かる形でテストできるということを意味する。また、きちんと環境を制御することさえできれば、異なる時間や場所で誰が行っても、同じ結果を再現できることも保証される。
これに対して、経済学ではデータからその妥当性を立証する、つまり因果関係を導くことができない場合が多い。近年でこそ、被験者(学生の場合が多い)をモニターや仕切りなどの環境の整った教室に集めて行う実験室実験や、実際の社会環境に介入するフィールド実験などの実験研究が経済学でも増えてきている。しかしながら、未だにデータ分析の大半は、観察されたデータを統計的に分析する実証研究である。観察データを用いる場合、変数どうしがお互いに影響を及ぼしあっているため、どちらが原因でどちらが結果かを判定することは難しい。また、本来は分析に欠かせないデータが何らかの理由で手に入らないことによって、誤った因果関係や不正確な定量効果を導いてしまう危険性もある。もちろん、こうしたデータに関する制約を乗り越えて、因果関係を立証するための様々な手法が計量経済学によって生み出されていることから、実証研究の無謬性は高まっていると考えられる。ただ、多くの自然科学と同じレベルで仮説の正しさを保証するには至っていない、と評価するのが(少なくとも現時点では)フェアな見方だろう。
経済学において、データ分析が[条件2]無謬性を満たせないとしたら、いったいどのような研究がノーベル賞候補として残るのだろうか。それは、データと直接関係のない純粋理論の確立や、前述した因果関係を立証するための統計手法の開発といった基礎研究である。こうした研究成果の多くは数学の定理の形で表現されるため、(証明さえ間違っていなければ)無謬性は100%保証される。データ分析とは異なり、基礎研究を選んでいる限り「実は間違っていた!」と後から問題が発覚する恐れが無いのだ。ノーベル賞の選定においては、無謬性を高いレベルで要求せざるを得ないことから、結果的に経済学賞の大半は理論や手法への貢献に対して与えられてきたのである。
[条件3]の有用性は、経済学ではどのように判断されているのだろうか。ここまでの議論から、新規性の強い基礎研究は自動的に[条件1]と[条件2]を共に満たすことが分かる。有用性は、これらの中からノーベル賞級の研究をふるいにかけるための最も重要な基準、いわば最後の砦のような条件なのである。しかし、この有用性の判断が社会科学の場合には非常に難しい。理論研究では、ある前提から出発してその帰結を演繹的に導くが、その作業がどのくらい有用か、どの程度意味があるのか、というのを客観的に示すことは不可能に近い。なぜかと言うと、前述したように、データから理論と現実の当てはまりの良さを客観的に立証することが困難だからだ。例えば、マクロ経済政策の効果に関する理論研究について想像してみよう。扱う対象が社会全体に及ぶことから、その効果をフィールド実験によって直接確かめることはできないし、観察データから実証的に確認しようとしても、その無謬性を保証することも難しい。仮に、ある実証研究によって理論と整合的な結果が出たとしても、本当は現実を描写できていない理論がたまたま観察データに対してうまく当てはまった、という可能性が残ってしまうのだ。増税や金融政策の効果などについて、専門家同士でもしばしば意見が分かれる背景には、理論と現実の対応関係を立証する手段が無い・足りない、という社会科学固有の根深い問題が存在するのである。
では、何によって有用性を担保するのかというと、同業者からの主観的な評価と時の試練に頼らざるを得ない、というのが実情ではないだろうか。筋の良い研究は引用される機会が増えるため、論文の被引用件数は同業者たちの評価を“見える化”する、最重要の指標だと考えられる。他にも、経済学者として長年実績を積み重ねてきた研究者も高く評価されるだろう。[条件3]の有用性から、経済学賞においては、被引用件数が多く高齢の大御所学者が選ばれやすいことが予想されるのである。受賞者の地域的な偏在も、【表2】で掲げたトップスクールに大御所が集中していることを踏まえると自然な現象と言える。まとめると、以上の3つの条件から示唆されるノーベル経済学賞の受賞傾向は、次のようになる。
[傾向1]新規性 → 分野を切り拓いた先駆者
[傾向2]無謬性 → 数学的に常に正しい理論家
[傾向3]有用性 → 被引用件数の多い大御所
同業者からの評価の高さを示す証拠としては、影響力の大きい学会組織の要職、とりわけ会長職に就いているかどうかも優れた指標になると考えられる。経済学では、エコノメトリック・ソサエティ(ES)と全米経済学会(AEA)が二大国際学会であり、その歴代会長のうち、前者からは27名、後者からは26名もの経済学賞受賞者をそれぞれ輩出している。また、15名が両学会で会長を務めている。
6. 日本人は受賞できる?
冒頭で述べたように、経済学賞は日本人が受賞していない唯一の分野である。本節では、今後受賞する可能性が高いと考えられる日本人経済学者について、簡単に言及しておきたい。結論から言うと、近い将来の受賞可能性は十分に高いと筆者は考えている。
前節で明らかにした3つの傾向から、まず[傾向3]被引用件数の多さに注目してみよう。IDEASの被引用件数ランキングで、2017年4月末において上位1000本に入っている論文の中から、日本人(共)著者によるものを抜粋したのが【表4】である(ただし、チャールズ・ユウジ・ホリオカ氏は米国籍)。筆者が確認した限り、該当する論文は11本、合計9名の日本人経済学者が名を連ねていた。
<日本人著者による引用件数の多い論文>
(順位、著者名、出版年の順。日本人名は太字)
145 Kiyotaki, Nobuhiro & Moore, John, 1997.
170 Feldstein, Martin & Horioka, Charles, 1980.
188 James J. Heckman & Hidehiko Ichimura & Petra E. Todd, 1997.
247 Toda, Hiro Y. & Yamamoto, Taku, 1995.
297 James J. Heckman & Hidehiko Ichimura & Petra Todd, 1998
434 James Heckman & Hidehiko Ichimura & Jeffrey Smith & Petra Todd, 1998
498 Takeo Hoshi & Anil Kashyap & David Scharfstein, 1991.
501 Hayashi, Fumio, 1982.
536 Kandori, Michihiro & Mailath, George J & Rob, Rafael, 1993.
652 Chinn, Menzie D. & Ito, Hiro, 2006.
905 Kiyotaki, Nobuhiro & Wright, Randall, 1989.
【表4】IDEASのランキング(リンク)から作成。
この9名の中から、[傾向1]先駆者と[傾向2]理論家という2の条件を加えると、残る候補者は以下の4名になるだろう(五十音順。カッコ内は2017年4月時点での所属大学)。
・市村英彦(東京大学)
・神取道宏(東京大学)
・清滝信宏(プリンストン大学)
・林文夫(政策研究大学院大学)
彼らはいずれも1950年代生まれで、最も権威のある国際経済学会のひとつエコノメトリック・ソサエティの終身フェローでもある。博士号を米国トップ5大学(【表2】を参照)で取得し、英米の一流大学で教鞭をとっていた、という点も共通している。日本人経済学者で、前述の3つの傾向に合致し、かつ国際的に見ても大御所と言えるのはこの4名に絞られるのではないだろうか。さらに清滝氏は、ノーベル賞予想として注目されるトムソン・ロイター引用栄誉賞に、日本人経済学者としてただ一人選ばれている。Kiyotaki and Moore (1997)論文は、従来は別々に分析されてきた金融市場と実体経済を、担保を通じた投資という経路を通じて統合的に分析し、信用収縮が長期停滞を引き起こす可能性を指摘した。マクロ経済学に革新をもたらしたこの大研究の他にも、清滝氏は超一流の理論研究を複数行っている。「欲求の二重の一致」を解消する形で、どのように貨幣が生まれるのかを理論的に説明したKiyotaki and Wright (1989)論文や、独占的競争モデルを土台としたマクロ経済モデルを構築し、ニュー・ケインジアンと呼ばれる一学派の萌芽となったBlanchard and Kiyotaki (1987)論文などである。過去の経済学賞受賞者たちの研究業績と比較しても、清滝氏の一連の研究は遜色がない。少なくとも、彼の受賞に対して学界から異論が出ることはまず考えられないだろう。以上から判断すると、現段階で最もノーベル経済学賞に近い日本人経済学者は清滝氏で、その受賞可能性は十分に高いと言えるのではないだろうか。
ところで、過去に受賞していてもおかしくなかった日本人経済学者も複数存在する。エコノメトリック・ソサエティの会長職を務めた、森嶋通夫(1965年)、宇沢弘文(1976年)、根岸隆(1994年)の3名、国際経済学連合会長を務めた青木昌彦(2008~11年)などが代表的だろう。残念ながら根岸氏を除く3名は鬼籍に入られてしまった。他にも、計量経済学の雨宮健氏と空間経済学の藤田昌久氏は、自身の研究分野から経済学賞が選ばれた2000年と2008年に、それぞれ共同受賞の可能性があったと指摘する声がある。理由は割愛するが、筆者はこの中で宇沢氏が最もノーベル賞に近かったのではないかと感じている。
7. おわりに
本稿では、5つの素朴な疑問に答えるという形で、ノーベル経済学賞について様々な角度から紹介を試みた。ノーベル賞の中でも特に分かりにくいと悪評の高い(?)経済学賞を、少しでも身近なものと感じて頂けたら幸いである。日本人受賞者の一刻も早い誕生を祈念しつつ筆をおきたい。
【参考文献】
・Arrow, Kenneth J. (1951, 1963). Social Choice and Individual Values. Yale University Press.
・Arrow, Kenneth J. and Gerard Debreu (1954). Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Econometrica, 265-290.
・Blanchard, O. J. and Kiyotaki, N. (1987). Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand. American Economic Review, 647-666.
・Hurwicz, Leonid (1960). Optimality and Informational Efficiency in Resource Allocation Processes. Stanford University Press.
・Hurwicz, Leonid. (1972). On Informationally Decentralized Systems, in Radner and McGuire, Decision and Organization. North-Holland, Amsterdam.
・Kiyotaki, N. and Moore, J. (1997). Credit Cycles. Journal of Political Economy, 105(2), 211-248.
・Kiyotaki, N. and Wright, R. (1989). On Money as a Medium of Exchange. Journal of Political economy, 97(4), 927-954.
・Sen, Amartya. (1970). The Impossibility of a Paretian liberal. Journal of Political Economy, 78(1), 152-157.
