
完璧なオークションを求めて
本年度のノーベル経済学賞が12日夜(日本時間の18時45分頃)に公表され、
・Paul R. Milgrom(Stanford)
・Robert B. Wilson(Stanford)
の2名が(ついに)選ばれました!経済理論やゲーム理論を長年けん引してきた大御所コンビの受賞ということで、同分野を研究する自分にとっても非常に嬉しいニュースでした。本当におめでとうございます🎉
授賞理由は
”improvements to auction theory and inventions of new auction formats”
「オークション理論の改良と新しいオークション形式の発明」
に対してです。
【関連情報】
オークション理論の関連記事や文献については、経済セミナー編集部による以下のまとめ(note記事)が参考になりますので、ぜひご覧下さい。ちなみに、本ページの一番下で、私も【関連書籍】をコメント付きで紹介しています。そちらも合わせて参考にして頂ければ幸いです。
・2020年ノーベル経済学賞はオークション理論!
私がslideshareで公開しているオークションに関するスライド資料もご紹介します。文字情報が中心で少し読みにくいかもしれませんが、オークションの理論と実践の大まかな流れが追えると思います。ご活用下さい。
・オークションの仕組み

過去に早稲田大学オープンカレッジ「ゲーム理論とマーケットデザイン入門」(全8回)の中で行った関連講義の音声も公開しています。
・Lec7|オークションの理論と実践(2013年6月19日)
オークションの理論と実践について、過去に新聞や経済誌に寄稿した論考の一部をいくつかnoteに転載しております。
・オークション理論とビジネスへの実践
・周波数オークション設計の課題 正直な入札行動導く制度に
・注目集まる「マーケット・デザイン」 欧米の制度設計で適用
ノーベル経済学賞については、昨年も同様の解説/翻訳記事をnoteに投稿させて頂きました。
・貧困を減らす実験アプローチ
また、経済学賞自体に関する記事も公開しています。ご関心のある方はぜひこちらも眺めて頂けるとありがたいです。
・ノーベル経済学賞って何だろう?
以下では、公式ウェブサイトに掲載された資料のうち、今年度の受賞者たちの業績を非専門家でも理解できるように分かりやすくまとめた、全7ページ(本文は6ページ)にわたる
・Popular science background: The quest for the perfect auction
の日本語訳を掲載します。(訳出には、自動翻訳サービス「DeepL翻訳」を使用し、明らかな誤訳や不自然な箇所は安田が修正しました)
「完璧なオークションを求めて」
毎日、オークションは、買い手と売り手の間で天文学的な価値を分配しています。今年の受賞者であるポール・ミルグロムとロバート・ウィルソンは、オークションの理論を改良するとともに新しいオークション形式を発明し、世界中の売り手、買い手、納税者たちに利益をもたらしました。
オークションには長い歴史があります。古代ローマでは、お金の貸し手が、借金の支払いができない借り手から没収した資産を売るためにオークションを利用していました。世界最古のオークションハウスであるStockholms Auktionsverkは、1674年に設立されました。
オークションと聞くと、伝統的な農地競売や高級美術品のオークションを思い浮かべるかもしれませんが、インターネットで何かを売ったり、不動産業者を介して不動産を購入するような今日的な取引もオークションだと考えられます。オークションの結果は、納税者であり、また市民でもある私たちにとっても非常に重要です。家庭のごみ収集を管理している会社が、公共調達で最低価格をつけることで業務を落札している場合も少なくありません。地域の電力オークションで毎日決定される電気料金は、家庭の暖房費に影響を与えます。私たちの携帯電話の繋がりやすさは、通信事業者が電波オークションで取得した電波の周波数帯域に依存しています。現在では、どの国も国債を発行する際に競売にかけて財源調達するようになりました。欧州連合(EU)の排出権取引の目的は、地球温暖化の緩和です。
このように、オークションはあらゆるレベルで私たち全員に影響を与えています。しかも、ますます普遍的に使われるようになり、複雑化しています。今年の受賞者が大きな貢献をしたのは、まさにこの分野なのです。彼らは、オークションがどのように機能するのか、なぜ入札者が特定の方法で行動するのかを明らかにしただけでなく、彼らの理論的な発見を応用して、商品やサービスを販売するための全く新しいオークションの形式を発明しました。これらの新しいオークション形式は、世界中に広く普及しています。
オークション理論
受賞者の貢献を理解するためには、オークション理論についてもう少し知っておく必要があります。オークション(または調達)の結果は3つの要因に左右されます。第一は、オークションのルール、つまり形式です。入札はオープン(公開)なのかクローズド(封印)なのか? 参加者はオークションに何回入札することができるのか? 落札者はどのような価格を支払うのか ー 自分の入札額か、2番目に高い入札か? 2つ目の要素は、オークションで取引されるアイテムに関連しています。入札者ごとに異なる価値を持っているのか、それとも同じ様にアイテムを評価しているのか? 3番目の要因は、不確実性に関するものです。異なる入札者は、アイテムの価値についてどのような情報を持っているのか?
オークション理論を使うことで、これらの3つの要因がどのように入札者の戦略的行動を左右し、オークションの結果を導くのかを説明できます。この理論はまた、できる限り多くの価値を生み出すためにオークションを設計する方法を示すこともできます。どちらも、複数の相互に関連したアイテムが同時に競売にかけられるとき、特に難しくなります。今年の経済学賞受賞者は、オーダーメイドの新しいオークション形式を作成することで、オークション理論をより実践的に適用できるようにしました。
オークションの種類の違い
世界中のオークションハウスでは、通常、イギリス式オークション[English auction](競り上げ)を利用して個々の品物を販売しています。ここでは、競売人は低価格から始め、その後、徐々に高い価格を提案します。参加者はすべての入札を見ることができ、より高い入札をするかどうかを選択することができます。最高額の入札をした人が落札し、入札した金額を支払います。しかし、他のオークションでは全く異なるルールもあります。オランダ式オークション[Dutch auction](競り下げ)では、非常に高い価格からスタートし、落札されるまで徐々に金額を下げていきます。
イギリス式とオランダ式のオークションでは、入札はオープンになっており、参加者全員が他の人の入札を見ることができます。しかし、他のタイプのオークションでは、入札はクローズドです。例えば、公共調達では、入札者はしばしば封印された入札を行い、調達者は特定の品質要件が満たされていることを条件に、最低価格でサービスを提供することを約束するサプライヤーを選択します。いくつかのオークションでは、最終的な価格は最高入札(第一価格オークション[first-price auction])ですが、落札者が二番目に高い入札(第二価格オークション[second-price auction])を支払う他の形式もあります。
どのオークション形式がベストなのでしょうか? これは結果だけでなく、何をもって「ベスト」とするのかにもよります。民間の売り手は通常、売り上げの最大化に最も関心を持っています。公的な売り手は、社会全体に最も長期的な利益をもたらす入札者に商品を販売する、などのより広い目的を持っています。ベストなオークションの探究は、長い間経済学者を悩ませてきたトリッキーな問題なのです。
オークション分析の難しさは、各入札者の最適な入札戦略が、他の参加者がどのように入札すると考えているかに依存するという点です。入札者の中には、アイテムの価値が他の人よりも高いと考える人、低いと考える人がいるか? これらの異なる評価は、一部の入札者が商品の特性や価値についてより良い情報を持っていることを反映しているのか? 入札者が協力して入札行動を操作すること(入札談合)で、最終的な落札額を抑えることができるか?
私的価値
1996年に経済学賞を受賞したウィリアム・ヴィクリーは、1960年代初頭にオークション理論を確立しました。彼は、入札者が競売にかけられている商品やサービスに対して私的価値[private value]を持っている、という特別なケースを分析しました。これは、入札者の価値が互いに完全に独立していることを意味します。例えば、有名人(ノーベル賞受賞者など)との夕食のためのチャリティー・オークションなどが該当します。このような夕食会にいくら支払うかは主観的なものであり、あなた自身の価値は他の入札者が夕食会をどう評価するかによって影響を受けることはありません。では、このタイプのオークションではどのように入札すべきでしょうか? あなたは夕食会に対する自分自身の価値よりも高い金額を入札するべきではありません。では、低価格で落札できることを期待して、低い金額を入札をするべきでしょうか?
ヴィクリーは、すべての入札者が合理的でリスク中立であることを条件に、最もよく知られているオークション形式 ー イギリス式やオランダ式など ー は、売り手に同じ期待収益をもたらすことを示しました。
共通価値
完全な私的価値というのは極端なケースです。オークションで取引される多くのアイテム(有価証券、不動産、採掘権など)は、価値の一部がすべての潜在的な入札者にとって等しく、共通価値[common value]の側面が非常に強いです。実際に入札者は、アイテムの特徴に関して異なる量の私的情報[private information]を持っています。
具体的な例を挙げてみましょう。あなたがダイヤモンドのディーラーであり、あなたも他のディーラーと同様に、未加工ダイヤモンドの入札を考えていると想像してください。あなたがいくらまで支払うべきかは、数量と品質で決まるカットダイヤモンドの再販価格だけに依存します。この共通価値である再販価格について、専門知識や経験、ダイヤモンドを吟味した時間などによって、ディーラーたちは異なる意見を持っています。あなたが他のすべての入札者の見積もりを知ることができれば、より正確に評価をすることができるでしょうが、各入札者は自分の情報をライバルたちには秘密にしておきたいと考えています。
共通価値を持つオークションの入札者は、他の参加者が真の価値についてより正確な情報を持っているというリスクに直面します。これは、「勝者の呪い」[winner's curse]と呼ばれる、実際のオークションで勝者が払い過ぎてしまうという、よく知られた現象につながります。あなたがオークションでダイヤモンドを落札したとしましょう。これは、他の入札者があなたよりもダイヤモンドを低く評価していることを意味するため、最も楽観的であるあなたは損をしてしまうかもしれません。
ロバート・ウィルソンは、共通価値のオークションを分析するためのフレームワークを最初に生み出し、そのような状況下で入札者がどのように振る舞うかを説明しました。1960年代から1970年代にかけての3本の古典的な論文では、真の価値が不確実な場合における第一価格オークションの最適な入札戦略を分析しています。参加者は、払い過ぎを避け勝者の呪いに陥らないために、共通価値の最善な推定値よりも低い価格で入札します。彼の分析によると、不確実性が高いほど入札者はより慎重になり、最終的な落札価格も低くなります。最後にウィルソンは、勝者の呪いによって引き起こされる問題は、一部の入札者が他の入札者よりも優れた情報を持っている場合には、さらに大きくなることも示しました。情報面で不利な立場にある入札者が、より低い金額を入札したり、オークションへの参加自体を完全に断念したりすることになるからです。
私的価値と共通価値の混在
ほとんどのオークションでは、入札者はアイテムに対して私的価値と共通価値の両方を持っています。アパートや一軒家の競売への入札を考えているとしましょう。その場合、あなたの支払い意欲は、あなたの私的価値(その物件の状態や間取り、立地をどのくらい評価するか)と、あなたの見積もった共通価値(将来的にいくらで売れるか)によって決まります。天然ガスの採掘権を入札するエネルギー会社は、ガスの貯留層の大きさ(共通価値)と、ガスを採取するためのコスト(コストは各企業の技術力に依存するため、私的価値)の両方を気にしています。国債の入札に参加する銀行も、将来の市場金利(共通価値)と国債の購入を希望する顧客の数(私的価値)をともに考慮しています。私的価値と共通価値をどちらも含むようなオークションの入札行動を分析することは、ヴィックリーとウィルソンがそれぞれ扱った片方のみの特殊なケースよりもさらに厄介な問題であることが判明しました。最終的にこの問題を解決したのは、1980年頃に発表された数少ない関連論文の著者の一人であるポール・ミルグロムでした。
ミルグロムの分析 ー 一部はロバート・ウェーバーとの共同研究 ー には、オークションについての全く新しい重要な洞察が含まれています。その一つは、オークション形式の違いによって、勝者の呪いにどれだけうまく対処できるかという点です。イギリス式オークションでは、競売人は低い価格から始めて、それを徐々に上げていきます。このとき、他の入札者がどの価格で脱落するかを観察することで、各入札者は自分の評価に関する情報を間接的に得ることができます。競売からおりずに留まっている入札者たちは、オークション開始時よりも多くの情報を得ることができるため、見積価格を下回る入札をすることが少なくなります。一方、オランダ式オークションでは、競売人が高値からスタートして値下げを行っていき、誰かが買いたいと思った瞬間に入札が終了してしまうため、どの入札者も新たな情報は得られません。以上から、オランダ式オークションでは、勝者の呪いの問題がイギリス式オークションよりも深刻になり、(自分が“呪われる”ことを避けるべく、各人が入札額をより引き下げるため)最終的な落札価格も低くなります。
この結果は、次のような一般的な原理([linkage principle])を反映しています:オークション形式は、入札額と入札者たちの私的情報との間の連関が強いほど、より高い収益をもたらす。したがって、売り手は入札が始まる前に、参加者にアイテムの価値について可能な限り多くの情報を提供することに関心があります。例えば住宅の売主は、入札者が入札開始前に(独立した)専門家の評価にアクセスできるようにすることで、より高い販売価格を期待することができます。
より良いオークションの実践
ミルグロムとウィルソンは、オークションの基礎理論に貢献しただけではありません。彼らはまた、既存のオークション形式を使用できない複雑な状況にも対応できる、新しくてより良いオークションの形式を発明しました。最もよく知られている貢献は、米国当局が初めて通信事業者に無線周波数を販売したときに使われた、彼ら自身の設計によるオークションです。
携帯電話での通話、インターネットでの支払い、ビデオ会議など、無線通信を可能にする無線周波数は、消費者、企業、社会にとって大きな価値を持つ希少資源です。これらの周波数は政府が所有していますが、民間の事業者の方がより効率的に利用できることが少なくありません。そのため、当局は何らかの方法でこれらの事業者に周波数帯を使用する免許を割り当てる必要があります。これは当初、「美人コンテスト」と呼ばれるプロセスによって行われ、個々の企業はなぜライバル企業ではなく自分たちが免許を受けるべきなのかを論証しなければなりませんでした。この仕組みの下で、通信会社やメディア企業がロビー活動に巨額の資金を費やすことになります。しかしながら、政府が企業から得られる収益は限られていました。
1990年代、携帯電話市場の拡大に伴い、米国の監督官庁である連邦通信委員会(FCC)は、美人コンテストがもはや通用しないことに気付きました。携帯電話会社の数が急速に拡大し、FCCは事実上、無線周波数の免許申請を捌くことができなくなっていたのです。FCCからの圧力を受け、米国議会は周波数帯を割り当てるための抽選を許めることになります。このようにして、美人コンテストは抽選による免許のランダムな割り当てに取って代わられますが、こちらも同様に限られた収入しか政府にはもたらしませんでした。
携帯電話事業者も抽選方式には不満を持っていました。抽選は地方レベルで行われていたため、全国でサービス展開している携帯電話事業者が、地域ごとに異なる周波数帯を使う非連続なネットワークを手に入れる、という状況に陥ったからです。抽選の後でこうした事業者は、自分たちの間で周波数を売買しようとしたため、大規模な周波数帯免許の転売市場が出現することになりました。
他方で、米国の累積債務が増加の一途をたどっていたため、これ以上免許を実質的に無料で配布し続けることが政治的に困難になってきました。周波数帯免許の市場価値は数十億ドルにのぼりますが、その価値は米国財務省ではなく、免許の転売市場に現れた投機家たちの手に渡ったのです。(そして、この機会損失は最終的には納税者が負担することになります)最終的に、1993年に周波数帯をオークションで分配することが決定されました。
新しいオークション形式
ここで新たな問題が生まれます。それは、効率的な周波数帯の割り当てを実現しつつ、納税者に最大限の利益をもたらすオークションをどのように設計するかという問題です。周波数帯には、私的価値と共通価値の両方の要素があるため、この問題を解決するのは非常に困難であることが判明しました。さらに、ある地域における特定の周波数帯の価値は、その事業者が他にどの周波数帯を所有するかにも依存するのです。
全国的なモバイルネットワークを構築したいと考えている事業者がいるとしましょう。スウェーデンの規制当局が、北部のラップランドから始まり、南部のスコーネまで、国中の周波数帯を一つずつ競売にかけたとします。ここで、ラップランドの免許の価値は、事業者が後の入札でスコーネまでのライセンスを購入できるかどうか、及びその価格に依存します。事業者は今後の入札の結果を知らないため、ラップランドの免許にいくら支払うべきかを知ることはほぼ不可能です。さらに、中古市場で高値で転売することを目的に、投機的な買い手がこの事業者がスコーネで必要とする周波数帯を購入しようとするかもしれません。不確実性が大きいため、事業者は入札金額を低く抑えるか、オークションから完全に撤退して中古市場での取引を待つことになるでしょう。
上のスウェーデンの例は、一般的に生じる問題を示唆しています。この問題を回避するために、米国で最初に行われた周波数オークションでは、一度にすべての地域の電波周波数帯を割り当てなければなりませんでした。また、同時に多くの入札者を扱わなければなりませんでした。これらの問題に取り組むために、ミルグロムとウィルソンは、一部プレストン・マカフィーと共同で、全く新しいオークション形式である「同時複数ラウンド(競り上げ)オークション」[Simultaneous Multiple Round Auction: SMRA]を発明しました。このオークションでは、すべてのアイテム(地理的に異なる地域の周波数帯)を同時に出品します。低価格からはじめて、繰り返し入札を可能にすることで、このオークションは不確実性と勝者の呪いによって引き起こされる問題を軽減することができます。1994年7月にFCCが最初にSMRAを使用したときには、計47ラウンドの入札を経て、10個の免許が合計6億1700万ドルで落札されましたが、これはアメリカ政府がそれまで実質的に事業者に無料で割り当てていたものでした。
SMRAを使用した最初の周波数オークションは、大成功だと評価されました。そして、多くの国(フィンランド、インド、カナダ、ノルウェー、ポーランド、スペイン、英国、スウェーデン、ドイツを含む)が同じ方式を採用しました。この方式を用いたFCCの競売だけでも、1994年~2014年の20年間で 1200億ドル以上の収益をもたらし、世界的には、2000億ドル以上の収益を上げました。SMRAは、電気や天然ガスの販売など、他の事例でも活用されています。
その後も、計算機科学者、数学者、行動科学者と協力して、オークションの理論家たちは新しいオークション形式を改良してきました。彼らはまた、入札者たちによる価格の操作や談合の機会を減らすことにも挑みました。ミルグロムは、事業者が個々の免許ではなく、周波数の「パッケージ」に入札できるように改良したオークション(組み合わせクロック式オークション[Combinatorial Clock Auction])の設計者の一人です。このタイプのオークションでは、販売する周波数が増えるにつれて可能なパッケージの数が急速に増加するため、かなりの計算能力を必要とします。ミルグロムは、2つのラウンドからなる新しいオークション形式(インセンティブ・オークション[Incentive Auction])の開発も主導しています。第1ラウンドでは、現在の免許保有者から周波数帯を買い上げ、こうして集めた周波数帯を第2ラウンドで、より効率的に活用できる他の事業者に売却する仕組みです。
基礎研究が新発明につながった
ミルグロムとウィルソンによる初期の画期的なオークション研究は、基礎研究とみなされるべきです。彼らはゲーム理論を用いて、異なる参加者たちがそれぞれ異なる情報を入手しているときに、どのように戦略的に行動するかを分析したいと考えていました。戦略的行動を生み出す舞台となるオークションは、明確なルールによって記述することができるため、彼らの研究対象として自然な領域だったのです。ところが、オークションは次第に実用的な重要性を持つようになり、1990年代半ば以降は、周波数帯、電力、天然資源などの複雑な公共資産の割り当てにますます活用されるようになりました。オークション理論から得られた基礎的な知見は、現実の複雑な課題を克服する新しいオークション形式を構築するための土台を提供しました。
こうして生み出された様々な新しいオークション形式は、基礎研究が社会に利益をもたらす発明を生み出すことができる、という美しい例の一つです。今回の例が並外れているのは、理論と実践を発展させた人たちが同一人物であるという点です。このように、オークションに関する本年度の受賞者たちの画期的な研究は、買い手、売り手、そして社会全体に大きな利益をもたらしたのです。
【関連書籍】
オークションの理論と実践について概要が掴める入門書として、手前味噌ではありますが、私が監訳した『入門 オークション 市場をデザインする経済学』(ハバード&パーシュ)を挙げたいです。数式は全く登場しません!

本書に寄せた解説記事はnoteにも転載しました。一見すると地味な印象に映るかもしれないオークションというトピックが、なぜ経済学において大きな注目を集め、精力的に研究され続けてきたのか、という背景についてやや俯瞰的・理論的な視点から整理しています。オークション研究の学術的意義について関心のある方はぜひご覧下さい。
・入門オークション:監訳者「解説」
オークション分野で蓄積された研究知見のビジネスへの活用については、なんと言っても慶應大学の坂井さんによる新作『メカニズムデザインで勝つ ミクロ経済学のビジネス活用』が激しくおすすめです。ワークショップでの講演をもとにしていて、読み物としても抜群に面白いです。

オークションは情報科学の分野でも積極的に研究されています。主に複数のアイテムを割り当てる複数財オークションに関して、インセンティブ設計の難しさ(→経済学)と望ましい結果を計算する難しさ(→情報科学)をどちらも考慮するような、学際的な研究も進められてきました。情報科学分野の大御所である九州大学の横尾さんが書かれた『オークション理論の基礎 ゲーム理論と情報科学の先端領域』は、非経済学系(特に工学系)の読者でも非常に読みやすい優れた入門書としておすすめです。

受賞者たちが大きく貢献した電波オークションをはじめ、現実のオークション設計について関心がある方は、洋書にはなりますが、オックスフォード大学のPaul Klemperer教授による『Auctions: Theory and Practice』もぜひお薦めしたいです。著者はイギリスにおける電波オークションの設計を主導した超一流の経済学者です。本書は彼の研究論文を集めた論文集ですが、あまりテクニカルではなく英語自体もとても読みやすいです。

オークション理論は、2012年にノーベル経済学賞を受賞したマッチング理論と研究領域がかなりオーバーラップしており、近年では両者(の実践的な側面)を合わせて「マーケットデザイン」と呼ぶことも増えてきました。邦書の優れた入門書もすでに何冊か出版されており、坂井さんの『マーケットデザイン 最先端の実用的な経済学』は、シンプルな例を用いて直感的に様々なマーケットデザインの仕組みや応用事例を掴むことができます。

公立はこだて未来大学の川越さんによる『マーケット・デザイン オークションとマッチングの経済学』は、マーケットデザインの理論に関する経済思想・学説史的な背景や、オークション実験の豊富な解説など、類書ではあまり扱われていないトピックの記述も充実している希少な一冊です。この分野の学術的な意義・重要性をきちんと理解したい方に特に向いているように思います。

学部上級レベルの本格的なテキストとして、今年翻訳書が出た『マーケットデザイン オークションとマッチングの理論・実践』も非常に良い内容だと思います。英語にはなりますが、著者であるGuillaume Haeringer教授のウェブサイトから、各章の講義スライド(pdfだけでなく、なんとtexファイルまで公開されています!)をダウンロードできるのもありがたいです。

本格的にオークション理論を研究したい、という大学院生以上の方は、この分野の第一人者であるペンシルベニア州立大学のVijay Krishna教授による『Auction Theory (2nd edition)』を読みましょう。非常に簡潔かつエレガントに書かれた名著で、必読書です。おととし待望の翻訳書『オークション理論』も出版されましたが、後半の複数財パートについてはこの日本版では全くカバーされていないので注意が必要です。

受賞者であるミルグロム教授自身も、オークションをテーマにした上級レベルのテキスト『オークション 理論とデザイン』を執筆しています。ただ、内容がかなりテクニカルな上、前述のKrishna教授の定番テキストと違い分析手法も独特なので、好みが分かれる一冊かもしれません。とは言え、様々な現実のオークションの制度的背景について語られている「第1章 さあ、始めよう」は、この分野に関心があるならぜひ抑えておきたい内容です。

ミルグロム教授は、最近のオークション設計の話題について、3年前にコンパクトな書籍『Discovering Prices: Auction Design in Markets with Complex Constraints』も出版しています。今回の受賞を機に、ひょっとすると日本語訳が出たりするかもしれませんね。ぜひ期待したいです^^
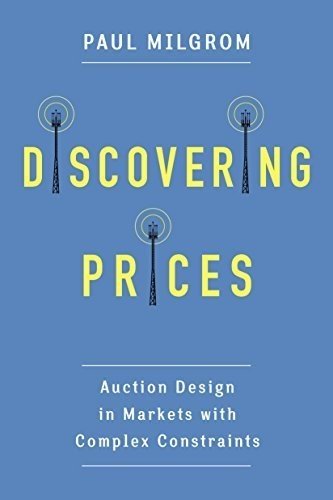
【おまけ】
受賞者のミルグロム、ウィルソン両教授に対して、教え子や共同研究者からも祝福の声が多数上がっています。特に印象的だった二人の記事を、その一部を引用しながらご紹介させて頂きます。
・Remarks on Paul Milgrom
ミルグロム教授の教え子であるJoshua Gans教授(トロント大学)が、2013年に開催されたミルグロム教授の65歳記念パーティーで自身が行ったスピーチを振り返りながら、応用理論家としての彼の偉大さを語っています。
Take a look here at his most highly cited works. With just a couple of exceptions, it is all applied theory. And moreover, when you look at where those citations are coming from it is not economics. It is management, strategy and finance. In other words, Paul is the most significant theorist in business and management, today, and possibly ever.
・David Kreps Lauds 2020 Nobel Laureate Robert Wilson
ウィルソン教授の同僚かつ共著者であり、自身もノーベル経済学賞の有力候補であるDavid Kreps教授(スタンフォード大学)が、「最も偉大な経済学者」[Greatest Economist]であるウィルソン教授の功績を称えています。記事内で引用されているSonnenschein教授の名言にもシビれました。
[T]his short appreciation is about Bob Wilson, whose own work is less wide-ranging than Paul’s but whose impact on the discipline of economics, in my opinion, puts him in the company of giants such as Ken Arrow and Paul Samuelson: Bob is, as much as anyone, the founder of the “School of Economic Theory as Engineering.”
