
【塾生インタビュー企画 私たちの軸足#10】~外交官としての幕開け~
このnoteは、薮中塾生の普段の活動や専門性を発信する企画の第10弾です。
インタビューアーは編集部の善波綾花(あーちゃん)が担当致します🌈🌈🌈
今回は、長谷川美佳(はせがわみか)さんにお話を伺いました!
議論のなかで鋭い指摘をするクールさと、おちゃめなかわいさを併せ持つスーパーウーマン美佳さん。
去年までは、大阪大学大学院国際公共政策研究科に所属し、国際法をテーマに研究していました。そして、今春からは薮中先生と同じ外交官として活躍するんだとか。
知れば知るほど魅力だらけな美佳さんの軸足を聞いていきたいと思います!
大学に入ってよかった!!
大学時代は法学部に所属し、外交史のゼミに所属していました。傍らでは国際法のゼミも聴講していました。
大学の4年間は広島で過ごしました。長崎と並び原爆の被害を受けたという土地柄から、平和シンポジウムや研修などが多く開催されました。自身も研修に参加する機会を得ましたし、企画・運営に携わらせていただくこともありました。
そうして語り部の方とお話したり、世界中から集まった参加者の方たちと議論したり、オバマ元大統領の訪問を見たりするなかで、平和について真剣に考えるようになりました。
大学院では国際公共政策を専攻し、国際法について研究を行いました。
学部時代に学んだ外交史を通じて歴史から学ぶことの意義を実感しました。今起こっている課題解決に関心をもち始めたとき、今の未熟な自分では、単に国際社会で起こった出来事にリアクションするだけになることになる!と無力感を覚えました。
ルールが分からないままスポーツの試合を見ても、「おっ、なんか今のプレーすごいっぽいなぁ」とか「なんで今の得点にならないの」とか、よくわからないまま振り回されちゃうだけですよね。
しかし、なぜアクターがその動きをするのかの見当がついていれば、予測や説明ができる。ルールが分かれば国際問題を本質的に学べて楽しくなるだろうなと。
また、そのインパクトの大きさに惹かれたのもあり、国際社会のルールである国際法を学ぼうと決めました。

バリでの学生会議にて

欧州における同伴者のいない未成年の庇護希望者の保護について研究しました。
ご周知のとおり、2016年の欧州難民危機によって、庇護希望者数がかなり増えたんですね。そのなかでも子どもで単独の庇護希望者となると、特にその保護が問題になります。子どもとしての権利もあるし、難民としての権利もあるのに、双方の権利の享受が危機にさらされている脆弱な状態にあるためです。
まず、庇護手続きを開始するに至るまでに、人身売買、暴力、精神的トラウマなどの被害を被りやすい。また、何とかして庇護申請を開始しようとしても、自分の意見を聞いてもらえなかったり、不法移民として拘留されてしまったりします。
教育へのアクセスも困難です。難民危機で庇護希望者の母数が増えると、このよう同伴者がない子どもの庇護希望者は、キャパシティー不足や国家による入国管理の強化などにより、さらに見過ごされてしまいやすくなりました。
入国管理は国際法の中でも国家に広い裁量が与えられている分野ですが、国際人権法は国家がどのように人を取り扱うかに一定の制限を課しています。そのなかの庇護申請という分野で、国際人権法が「同伴者のいない子どもの庇護希望者」という、特に脆弱な存在を守るためにどのような役割を果たしているかを研究しました。
「平和な世界」を目指して

子どもの権利委員会で、委員の先生のアシスタントのインターンをしていました。各種人権条約には履行確保制度として国家報告制度というものがあり、締約国は自身の条約の履行状況を報告し、委員会はそれに対し見解を出します。私は、その国家報告制度に関連して先生が必要なレポートをドラフトしたり、情報をまとめたりということで、お手伝いさせていただいていました。
その後もジュネーブに残り別のNGOでインターンをさせていただきました。そのNGOは、人権理事会や子どもの権利委員会のセッションに出席するNGOのサポートやサイドイベントの開催などをしていたのでそのお手伝いをしました。また、色んな会議やイベントに出席し、ひたすらメモを取って上司にあげていました。

ジュネーブのインターンにて
日本国内ではセーブザチルドレンにて、短期インターンとして中高生に子どもの権利条約についてのワークショップ開催をお手伝いさせていただきました。
子ども自身が子どもの権利を勉強する意義について聞かれることがあります。昨今、環境保全活動家のグレタさんのような子どもの活動家が増えていますよね。子どもが自身の権利を認識する、意見を聞いてもらう、権利を享受するというプロセスは人権保障において極めて重要です。
子どもは保護されるべき弱い存在であるという見方は古くなっており、子どもの意見表明権、子どもの主体性というものが注目されています。様々な方法で子どもの意見を政策なり意思決定に反映する仕組みが作られていると感じますし、そういった流れは今後もプッシュされていくと思いますね。
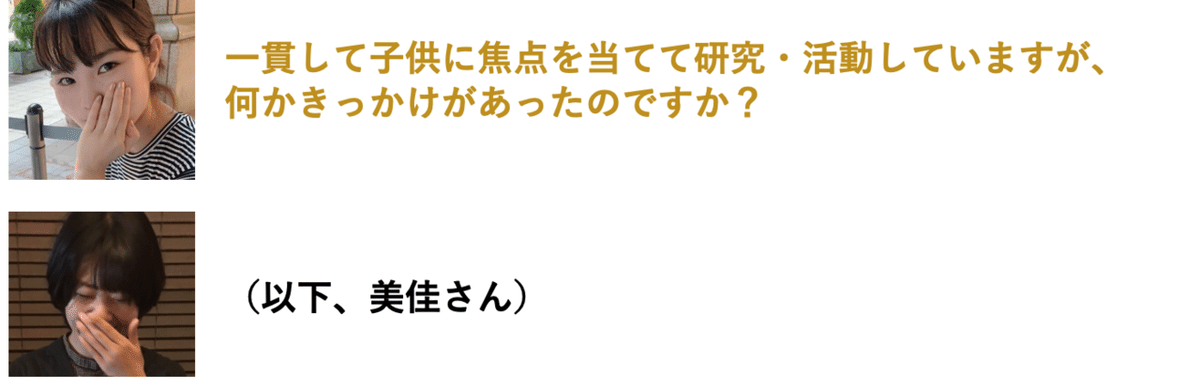
自分の関心が向く方向として弱い立場の人が気になるということと、
親が保育士で、私も元々同じ夢があったことが大きいですね。人格が形成されるなかで子ども時代の経験による部分は大きいと思うので、その時代を大切にしたいという思いがあります。
私が困難を抱える人全員に会って、ひとりひとり解決に取り組むことは残念ながら難しいですが、社会の仕組みを作る法なら広い範囲で影響を与える可能性があるのではないか、と考え、法の視点から勉強しました。

外交のあらゆる面で国際法の知識は必要だと思います。例えば、外交官として働けば携わるであろう条約の締結は国際法を扱う、もっと言えば作ることになると思うので、これまでの研究やインターンなどで得た学びを活かしたいと思います。
今後は、国際社会の平和と日本が国際社会で尊敬され名誉ある地位を占めるような国であること、この二つを目指し、逆算して、今ある課題解決に取り組んでいきたいです。


模擬国連ブラジル🇧🇷とエクアドルチーム🇪🇨
原体験があるわけではないのですが、国際法や外交を学び、インターンで様々な角度から物事を見る機会をいただき、最終的な決定をする国というアクターはやはり大きな存在だなと感じました。
海外で起こっていることに関心がありつつも日本が好きなので、日本のプレゼンスを示していくとともに、どうせやるなら日本単位で何かを残していきたいです。現実主義なところがある日本ですが、脆弱な人々や国を助けるなどもっと理想を追求してもいい、それが長期的には日本にとってもプラスになると思っています。
そのために、現場を大事にする、泥くさくて温かみのある外交官になりたいです。かっこよくやろうとせず、どんどん体当たりで挑戦し続けたいと思います!
【インタビュアー】長谷川美佳(はせがわみか)
【聞き手・ライター】善波綾花(ぜんばあやか)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回は、この春から外交官として働く長谷川美佳(はせがわみか)さんにお伺いしました。
日本の未来を背負った外交官としての美佳さん、過去と未来に一貫した軸があって素敵でした!✨
それでは、次回もお楽しみに!⭐️
