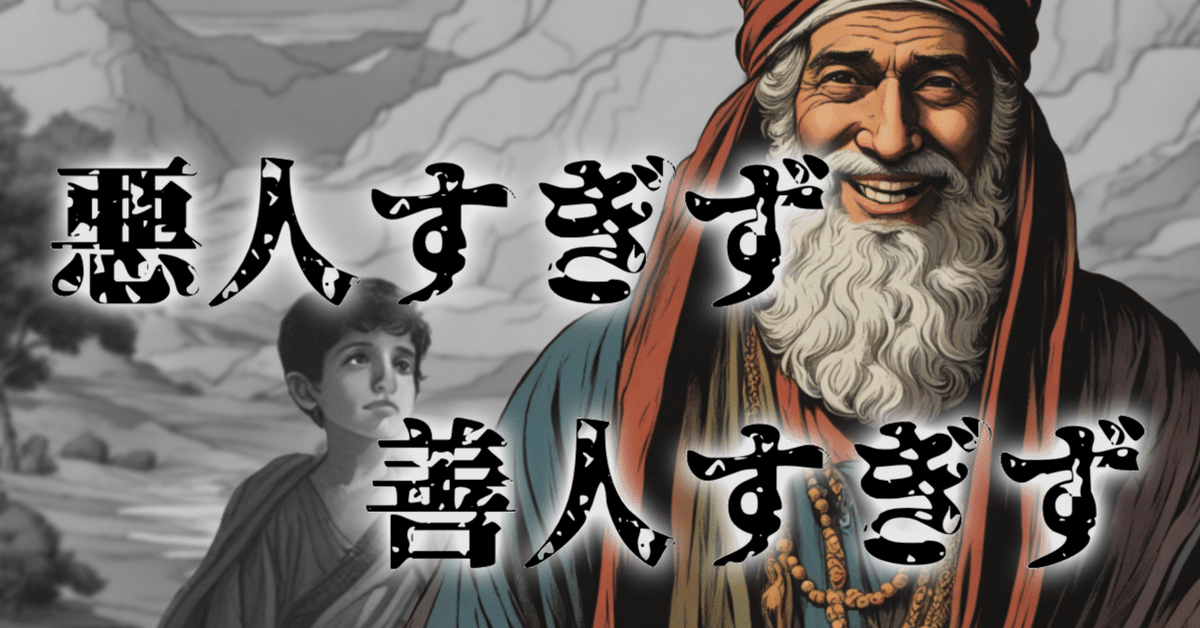
悪人すぎず 善人すぎず
音声データ
こちらからダウンロードしてお聴きください(最後5秒ほど切れてしまいました…)。
詩編・聖書日課・特祷
2024年2月25日(日)の詩編・聖書日課
旧 約 創世記22章1〜14節
詩 編 16編
使徒書 ローマの信徒への手紙8章31〜39節
福音書 マルコによる福音書8章31〜38節
特祷(大斎節第2主日)
全能の神よ、わたしたちには自らを助ける力のないことをあなたは知っておられます。どうか外は体を損なうすべての災いを防ぎ、内は魂を襲う悪念を除いてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン
下記のpdfファイルをダウンロードしていただくと、詩編・特祷・聖書日課の全文をお読みいただけます。なお、このファイルは「日本聖公会京都教区 ほっこり宣教プロジェクト資料編」さんが提供しているものをモデルに自作しています。
はじめに
どうも皆さん、「いつくしみ!」
2ヶ月ぶりのお話担当です。前回は、12月24日、アドヴェント最後の日曜日で担当させていただきました。「ヤギ」のお話でしたね。皆さん、覚えていらっしゃるでしょうか。
あの日は、礼拝ダブルヘッダーでした。午前中にこちらで礼拝をおささげした後、今度は18時から、尾張旭にある愛知聖ルカ教会でクリスマス礼拝を担当したのですけれども、実を言いますと、そっちのほうでもですね、全くおんなじ「ヤギ」の話をさせていただきました。まぁ、さすがに2回、同じ話でしたのでね。やっぱり2回目のほうが(ルカのほうが)、上手くいった感じがしました。そりゃそうですよね。1回こっちでやらせていただいているわけですからね。
というわけで、ルカのクリスマス礼拝は、まさしく一宮の皆さんのおかげで無事上手いこといきました!ということを、今日はまず、この場を借りて感謝申し上げたいと思います。どうもありがとうございました(笑)
神の子、救い主が……死んだ?
さて、それからちょうど2ヶ月が経ちまして、本日は2月25日。大斎節(レント)と呼ばれる期節の第2主日を迎えております。イエス・キリストが歩んだ、耐え難い痛みと苦しみを伴う十字架までの道――。その道のりを、聖書の御言葉に聴きながら辿りつつ、何より、“慎み”と“悔い改め”を大切にしながら過ごしていくのが、このレント(大斎節)という期節なのですよね。

これから読み進めていく、この大斎節の聖書日課の中で、イエス・キリストは、十字架につけられて殺されてしまうことになります。具体的には、3月24日、復活前主日の福音書の箇所が、イエスの十字架刑のシーンとなっているわけですけれども、彼は、ユダヤ教指導者たちが遣わした群衆によって捕えられ、そして敵対者たちが騒ぎ立てる中、無惨にも十字架刑によって殺されてしまうのですよね。
メシア、神の子、救い主として信じられていたあのイエスが、死んだ……? 実に衝撃的な場面です。まぁ、もちろん、イエスはその後復活することになりますので、その点に関しては“めでたし、めでたし”と言えるのかもしれませんけれども……、しかし、「イエスは死んだ」という、その出来事は、終わり良ければすべて良し――とはならず、彼の弟子たち、彼の信奉者たちに、ある一つの重要な問いを残すことになったのですね。すなわちそれは、「なぜイエスは死んだのか(なぜ、死ぬ必要があったのか)」ということです。
その疑問に関して、初期のキリスト者たちは、非常に早い段階で“ある一つの答え”を導き出しました。すなわちそれは「犠牲の死」。イエスは、すべての人を罪の呪縛から救い出すため、生贄の動物の如く死んでいった。しかも、それは人間の意思ではなく、神の意思として実行されたのだ、というように結論づけたのですね。
アブラハムのイサク奉献未遂
その「イエスの犠牲の死」を裏付ける一つのエビデンスとして、教会の歴史の中でずっと読まれてきたテクストがあります。それが、本日の旧約テクストの箇所として選ばれている、創世記22章の、いわゆる「イサク奉献」と呼ばれる物語です。今日はこの「イサク奉献」の物語をメインにお話ししてまいりたいと思います。

まず最初に、その内容を短く振り返ってみようと思うのですけれども……。イスラエルの父祖であるアブラハムは、ある時、不可解な行動をとろうとします。なんと、愛する一人息子であるイサクのことを“焼き尽くす献げ物”としてささげようとするのですね。いわゆる人身供犠(人身御供)といわれる儀式です。人間を神への生贄としてささげるという、非常におぞましい行為のことですけれども、アブラハムはそれを、あろうことか、自分の子どもを使って実行しようとしたわけです。しかも、さらに不可解なことに、その人身供犠は、彼自身が思いついたものではなくて、実は“神の命令”に基づくことだった――ということなんですね。そのアブラハムの行為は、結局、神のほうが制止したことで未遂に終わるのですけれども、その結果、神はアブラハムのことを「神を畏れる者」と認めて祝福を授与するという、そのようなストーリー展開になっているわけですね。
この「イサク奉献」の物語は、言わば、神に対して“たった一人の息子の命をささげようとした”、そのアブラハムの信仰、彼の忠誠心を称賛するエピソードとして、これまで、ユダヤ教・キリスト教の中で扱われてきました。しかし……。まぁ皆さん、これらの物語に関していろんな思いを抱いていらっしゃることと思いますけれども、少なくとも僕は、正直に言わせていただきますと、この物語に関する、そのような従来の理解については、否定的な意見を持っているのですね。具体的に言いますと、この物語の“読み方”というものに関して、僕は、神に対するアブラハムの忠誠心を称えているという伝統的な読み方ではなく、全く異なる読み方をしているわけです。すなわち、このお話というのは、実は、アブラハムと神との間で行われた“限界ギリギリの心理戦”を描いた物語だったのではないか、と考えているのですね。
アブラハムは、神から試されました。しかし、それと同時に、アブラハムのほうも神を試していた(神にチャレンジしていた)のだ……というのが、僕が今回、皆さんに提案させていただきたいと思っている読み方です。
限界ギリギリの“心理戦”
どうしてそのように言えるのか。あんまり長くなると良くないので、短く、ポイントを3つに絞ってご紹介させていただこうと思います(僕は大学時代、旧約聖書ゼミを専攻していたので、旧約の話になると、つい熱くなってしまうのです!)
まず一つ目は、22章の7〜8節のところ。アブラハムとイサクが一緒に山に登っている時、アブラハムはイサクから、「焼き尽くす献げ物の小羊はどこですか?」と尋ねられるわけですけれども、アブラハムは、そんな息子に対してこのように答えています。「焼き尽くす献げ物の小羊はきっと神が備えてくださる。」(8節)
この日本語訳では、「きっと神が備えてくださる」というような、非常に丁寧な翻訳になっているのですけれども、実は、この元々の文章は、もっとシンプルな文章なのです。すなわち、この箇所を直訳するとこうなります。「焼き尽くす献げ物の小羊(or 小山羊)は、神が自分で見出すだろう。」
「小羊はどこにいるの?」と息子に問いかけられたアブラハムは、動揺するわけでもなく、はたまた嘘をついたり誤魔化したりするわけでもなく、ただ一言、「神が自分で見出すだろう」と返答しているのです。「オレはイサクを殺す気は無い。神よ、これはあなたが始めたことだ。だから、あなたが自分で何とかしろ」という感じでしょうか。まぁ、およそ「信仰の父」と呼ばれている人物とは思えない、なかなか無礼な言葉のように聞こえますけれども、しかし僕は、このアブラハムのセリフの中に、“こんな無茶苦茶なことを命令してくるような神には絶対に屈しない”という、そういう強い意志というものを感じ取るのですね。
また、少しさかのぼって、今度は物語の中盤、5節のところをご覧いただけますでしょうか。この箇所で、アブラハムは、一緒に旅をしてきた従者たちに対して、次のように伝えています。「お前たちは、ろばと一緒にここで待っていなさい。わたしと息子はあそこへ行って、礼拝をして、また戻ってくる。」
この5節の最後に記されている「戻ってくる」という一言。実はこれは、「複数形」なのです。つまり、「“私たち”は戻ってくる」と語っているわけなんですね。「私たち」とは誰か。当然、アブラハムと息子イサクの二人ですよね。アブラハムはここで、二人の従者に対して、「まぁ本当は、一人で帰ってくることになるんだけどね……」と思いながら嘘をついたのではありません。そうではなくて、彼ははっきりと……、しかし他の三人には事情を悟られない程度に、「私たちは必ず“二人で”この場所に戻ってくるのだ」と言い残して(宣言をして)、山を登っていった――。この「“私たちは”戻ってくる」というさりげない一言からも、僕は、アブラハムの強い意思を読み取るわけです。
神に勝利したアブラハム
この“試し、試され”の、アブラハムと神の勝負は、結局、アブラハムが息子の首元に刃物を突きつける、その寸前までもつれ込むことになります。
最後のポイントはその9〜10節にかけての箇所です。ここの描写というのは、内容が具体的であるがゆえに、元々のヘブライ語のテクストでは、焦ったく感じるほどテンポがゆっくりなんですよね。
「彼らはその場所に着いた。アブラハムはそこに祭壇を築いた。薪を並べた。息子イサクを縛った。彼を祭壇の上、薪の上に置いた。アブラハムは手を伸ばした。彼は刃物を取った、自分の息子を屠るために。」
……という、まさにこんな感じで、その時のアブラハムの行動が一つずつ、丁寧に記されているわけなのですが、この“独特のテンポの悪さ"が、いかにも、「さぁ、神とアブラハム、どっちが先に音を上げるのか!」という緊張感のある演出を生み出しているように僕には感じられてならないのですね。「神よ、早く降参しろ!」というアブラハムの叫びが聞こえてきそうな印象を受けます。
そして、その声が届いたのか、ついに神が動きます。むしろ、ようやく「神を引き摺り出した」とも言えるのかもしれませんけれども、神は天から御使いを派遣して、アブラハムを制止。「もう止めよう!」と言って、神のほうがギブアップするのですね。息子への愛を守り抜いた父アブラハムの執念の勝利。そして、麓(ふもと)の従者たちに宣言したとおり、彼らは“二人で”山を降りることになった――、というような読み方が、従来の読み方とは全く異なる、僕なりの読み方です。皆さんは、どのようにお感じになられたでしょうか。これまでの、狂信的・妄信的なキャラクターとは違う、はっきりと自己を持っている、そういうアブラハムの姿を想像していただけたのではないかと思います。
真の「神を畏れる者」とはッ!
この読み方の中で、最も重要なのは、アブラハムが「神」よりも「愛する独り子イサク」のほうを選んだ、ということだと僕は思うのですね。そして、そんなアブラハムの“父親としての姿”を見て、神は、アブラハムの義(正しさ)を見出し、そうして、彼のことを「神を畏れる者」(12節)と認めるに至ったというわけです。
この「神を畏れる」という表現は、聖書の中に意外と出てこなくてですね、この箇所の他に、ヨブ記に3回(1:1、8、2:3)と、コヘレトの言葉に1回(7:18)に出てくるだけなのですけれども、そのコヘレトの言葉の箇所をちょっと読んでみようと思います。「善人すぎるな、賢すぎるな/どうして滅びてよかろう。悪事をすごすな、愚かすぎるな/どうして時も来ないのに死んでよかろう。一つのことをつかむのはよいが/ほかのことからも手を放してはいけない。神を畏れ敬えば/どちらをも成し遂げることができる。」
善とか悪とか、あるいは賢いとか愚かであるとか、そういうものに振り回されるのは良くないよね――。ひとつのことに一直線すぎて、ほかのことが疎かになるようじゃ良くないよね――というようなことを、この箇所は語っています。アブラハムに関して言えば、実は、“神の義(正しさ)”というものを求めすぎるあまり、この物語の直前で、もう一人の息子イシュマエルを失うという、大変ショックな出来事を経験しているのですね(21:9以下)。なので、二度とそのような過ちは繰り返したくない!と彼自身、考えていたはずなのです。
それで今回、この物語においては、自分がこれまで固執してきた“神の言葉は絶対だ”という考えを思い切って捨てて、あえて、神に反抗する態度をとった。その結果……、アブラハムは、意外にも、「神」と「イサク」、その両方との繋がりを守り切ることができたのかなと思います。善人すぎず、悪人すぎず、賢すぎず、愚かすぎずに「神を畏れ敬えば[一つのことも、ほかのことも]どちらをも成し遂げることができる。」
アブラハムという人物は、決して狂信的な人物などではなくて、むしろ実に人間味あふれる、人の命も、神への信仰も、どちらも大切にしようとした、まさに「信仰の父」、「神を畏れる者」と呼ばれるに相応しい人物だったと、そのように今回の物語から読み取ることができるのではないかと思います。
おわりに
この物語は、最後にもう一つ、我々に重要な示唆、信仰上の問いというものを与えてくれているように感じます。すなわち、「愛する独り子を犠牲にしなかったアブラハムが称えられているのであれば、『神が独り子イエスを贖いの犠牲にした』という従来のキリスト教理解の正当性が崩れてくるのではないか?」ということです。実際、ユダヤ教では、アブラハムの物語を契機に、古代世界で広く行われていた人身供犠(人身御供)という行為を、「忌むべき慣習」として徹底的に排除するようになります。そのユダヤ教の神理解をキリスト教は引き継いでいるはずなのに、「イエスの死」に関しては、例外として、「神はイエスという人間の命を犠牲とした」という信仰を確立してしまった。……おかしいですよね。しかも、さらに言いますと、福音書の著者が描くイエスは、弟子たちにこう命じているのです。「わたしの後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい。」(マルコ8:34) まるで、あなたたちも私に続いて“犠牲”となる覚悟をしなさい、と言っているかのようですよね。……なんか、おかしいなぁ。人間を“犠牲”にするという考えは、旧約聖書がすでに葬ったはずなのに、キリスト教はそれを蘇らせてしまったのではないか?本当にそれは正しいのか?
……というお話に関しては、また別の機会にじっくりさせていただこうと思います。それでは、礼拝を続けてまいりましょう。
