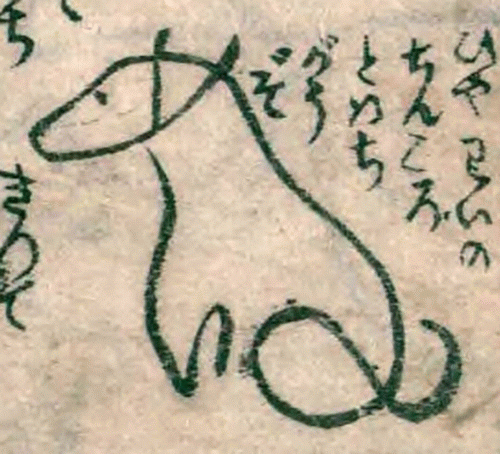江戸の犬は怒りっぽい
ここに、十辺舎一九著の『文字の知画』(文化四年・1807年序)がある。外題は「文字の知画」、序文の題は「文字之智画」、後の二文字はいずれも「ちゑ」との読みが振られる。「知恵を生かし、叡智を託した絵」といった抱負が隠されたと言えよう。国立国会図書館蔵は同デジタルコレクションで公開されている。
この作の前半は、一丁表の序を含めて十丁、「芸者」、「米屋」などの職人、「釣り」、「拳」などの趣味人、「侍」、「隠者」などの社会身分などあわせて三十九人の人物を描く。(丁の番号に乱れがあり、七が抜けて、八が二回現われる。なお一回目の八の表が脱落した。)それぞれはその人物の身分にあった口上を長く述べ、一部は歌まで詠みこまれている。
そのような鮮やかな人物の群像の中に、一匹の犬が混じり込んだ。人間以外の存在は、この犬のみである。ここにその犬の口上を読んでみよう。四丁裏の下半分である。つぎはそれを掲げる。

かな文字をそっくりそのまま書き出すと、およそつぎのような内容だ。二、三か所の読みには、十分通じなくて疑問が残る。
「いましい。うまくねているところを、さきへいくやろうめがおれのあしをふみやあがった。おれをだれだとおもふ。うちのまへのやせいぬやひゑいのやちんころとはちがうぞ。このおもててうからしんみちまつて、おれにたてづくいぬはいつひきもない。おぼうさんがせうべんすればとて、しろこいゝゝとおんばどのによばれて、しつぽをふりていゝやうなやすのじゃあないば。いまゝゝしい。」
この文章を漢字まじりに書き換えると、一通りつぎのようなものだろう。
「忌しい。うまく寝ているところを、先へ行く野郎目がおれの足を踏みやあがった。おれをだれだと思ふ。うちのまへの痩せ犬屋兵衛のやちんころとは違うぞ。この表町から新道まつて、おれに立てつく犬は一匹もない。お坊さんが小便すればとて、「しろ来い々々」とおんばどのに呼ばれて、尻尾を振りて良いやうなやすのじゃあないば。忌々しい!」
およそ説明も、現代語訳もいらない。江戸後期の、二百年もまえの言葉なのに、八割以上はそっくりそのままの現代日本語なのだ。試して声に出して読みあげてみれば、この犬の宣言がいかに堂々としたものかは簡単に伝わる。
犬とは、あくまでも人間の友であり、人間のペットなのだ。それにしても、飼い主以外の人を相手にして果敢に挑み、恐れを感じさせる江戸の犬、そして愛嬌を振り撒き、萌えと言わせる現代の犬、犬と人間との距離やそのあり方は、ここまで大きく変わったものだとつくづく見せつけられた一コマなのだ。
文字によって構成された絵は、明快にして分かりやすい。それでもあえてGIF動画に仕立てた。