
リンク取得のあれこれ
SNSでの発信や友人との交流などにおいて、特定のページへのリンクをめぐるやり取りが欠かせない。その中で、思わず戸惑いを感じることがすくなくない。
ここ二三日に経験した小さなひと時である。最近出したキンドル本『猫と鼠の世にも奇妙な大論争』へのアクセスを知らせようと、アマゾンでタイトルで検索したらすぐ出てきたが、アドレスバーに現われたのは、タイトルや作者名を漢字で記入したものであり、それをコピーしてメールに貼り付けると、つぎのような長大なものになってしまった。とても読めるものではなく、メールでこれを送信したらいかにも不親切に映る。続けて作者名などクリックしてもどれも結果が変わらなかった。
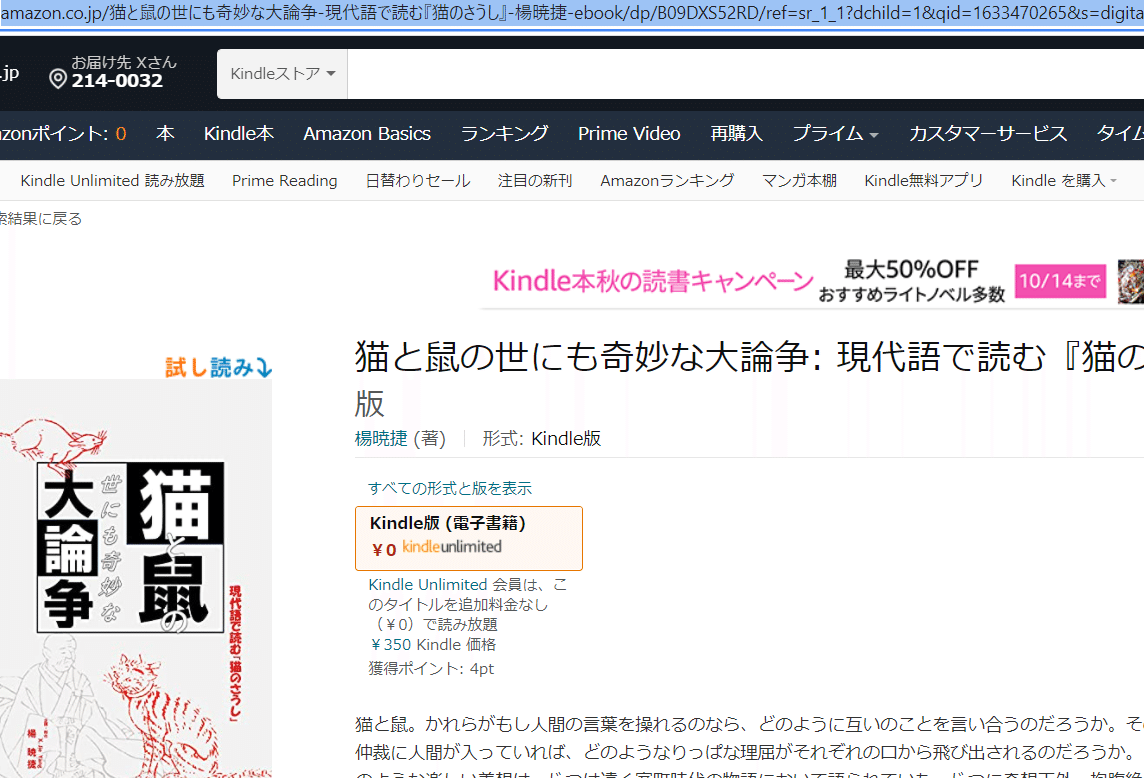
そこで作者ページのことを思い出した。あらためてKDPのサイトに入り、作品のページに記入した「View on Amazon」、それぞれの国や地域のアマゾンページに出るこの同じタイトルの情報の項目から、アマゾン日本を選択して、ようやくすっきりしたリンクがアドレスバーに現われた。つぎのようなものである。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09DXS52RD

このようなアドレスのことを定義、説明する専門的な用語がきっとあるに違いない。アマゾン書籍の巨大なデータベースにおいて、前者の長いものは、結局は検索でたどり着いた個別のデータの結果表示であり、後者はそのデータに対してデータベースが割りつけた固定リンクなのだろう。
このような特定のデータに対するサイトリンクの付け方は、いまのところじつに様々だ。個人的によく利用している図書館や研究機関でいうと、それこそ丁寧に勉強し、辛抱強く対応しなければならない基本的な事項の一つである。具体的に例をあげれば、国文学研究資料館が運営する「日本古典籍総合目録DB」は、個別の検索結果のリンクを提供せず、同じ作品でも再検索の場合はタイトルからやりなおさなければならない。それの「館蔵和古書目録DB」の部において、個別のタイトルを開けば、はじめて「書誌URL」とそのタイトルの固定リンクが提示される。

「国会図書館デジタルコレクション」では、作者名、作品名、シリーズ名など多様な検索経路が用意され、たどり着いたタイトル情報の一番に「永続的識別子」が表示され、しかもそれがアドレスバーにもすでに利用されている。

ちなみに、SNSの代表格であるFacebookもTwitterも、一つひとつの発信に対する固定リンクを提供している。ただし、その所在はあまり分かりやすいとは言い難い。発信の時間のところをクリックすればその内容が表示され、固定リンクがアドレスバーに現われるという形だ。このリンクさえ分かれば、たとえログインしていなくても内容が閲覧できるから、利用方法は一通り親切だと言わなければならないだろう。
これまでの議論は、いうまでもなく利用者立場のものに止まる。データ提供者側からすれば、検索の利便性、ユーザからの多様な要求への対応、資源の有効利用など、さまざまな要素を考えなければならないだろうから、ちょっとした利用上の不便を与えても、取り立てて文句を言われることでもなかろう。
