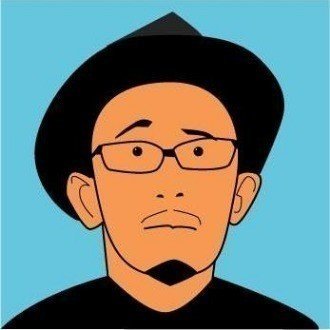Chat GPT は神か悪魔か
おはようございます 渡邉です。週末はとても天気が良かったですね。太陽が出ていると、洗濯物もすっきり乾いて、とても気持ちが良いです。
という訳で、週末は窓際で日向ぼっこしながら読んだ「Chat GPT は神か悪魔か」を紹介します。
この本は、落合陽一さん他6名の方による記事となっていて、発行は2023年10月なので、当時より大分世の中も進んできました。もはや、ビジネスのパートナーとして、生成AIと対話しない日はない位、日々の仕事に溶け込んできていますが、そんな生成AIについて改めて考えてみます。
Chat GPT は神か悪魔か
神とか悪魔といったレイヤーのものではなく、あくまでツール・道具です。
バカとAIは使いようだよね。無難な文章で書ける、どうでもいい書類などはChatGPTにつくらせればいい。
いきなり、結論から入りますが、神とか悪魔とかではなく、ツールであるということです。鋏と同様にそれが、使う人によるということです。美しい芸術を生み出したり、美味しい料理を作りだすこともあるし、使い方はを誤れば、何かを傷つけてしまったり、下手をすれば殺めてしまうこともあるかもしれません。使う人側のリテラシーであったり、場合によっては法整備によって非常に便利なツールとなり得るというのは、自動車が世の中に登場した時と同じなのかもしれないですね。
また、ハルシネーションと呼ばれる、事実と異なる内容や、文脈とは関係ない情報が出力されることについても触れられています。
これに関しても、生成AI以前に、インターネットで検索した(ググッた)結果に出てきた内容について、審議を確かめることなく鵜呑みにしてしまうのは危険ですし、人間同士のコミュニケーションにおいても、勘違いや思い違いなどで、嘘をついたり、間違えたことを伝えてしまうこともあるでしょう。これらより、AIだろうが、検索結果だろうが、誰かのアドバイスだろうが、参考の一つと捉え、最終判断は自らが下すという姿勢が必要とも言えますね。
Chat GPT とは何か?
Chat GPTとは、神でも悪魔でもなくだたのツールだとして、ではどんなものなのか?ということについて改めて考えてみます。
Chat GPT のGPTとは、Generative Pre-trained Transformer の略称ですが、このうち「T」が、まさにGoogleのTransformer にあたります。
一言に、AIと言っても大きく特化型AIと汎用型AIに分かれ、例えば2015年頃に話題になった、AlphaGo(アルファ碁)は、囲碁特化型のAIで、ChatGPTに代表されるような、現在我々が日々触れているAIは、汎用型AIです。2022年にGPT3.5が発表され、現在のChat GPTのように気軽に使えるようになりましたが、このバージョンからもわかるように、GPT-1は2018年にリリースされていたわけです。しかしながら、GPT-3までは、プログラミング技術がないと使えなかった為、一般的には話題になっていなかったという訳です。
どのように文章を生成しているかというと、根本原理が存在していて
手前の文に「確立的にありそうな続きの文字」をどんどんつなげていうAIだということです。
例として挙げられているのが、「昔々」とフレーズを入力すれば、確率が高い文として、「あるところに」が続き、さらにその後には、「おじいさんとおばあさんが」で「暮らしていました。」となるという訳です。
統計的な表現で言い換えるとすると、
ChatGPTは統計でいう正規分布グラフの山の一番高い部分、つまり両端から数えてちょうど真ん中のところ、「中央値」を答えとして出すということです。統計の中央値ですから、往々にして「それはわかるけど、まあ当たり前だよね」といった内容になりがちです。
言ってみれば、テッパンな答えを確認したい時には、非常に有効な話相手とも言えます。意外と、やった方がいいけど、出来ていないことっていうのが身の周りにはあふれていて、それを再確認することでも、一歩前に進みだせるということもあるかと思います。
一方で、向かないのは「外れ値」です。逆にいえば、今後、人間が担うべきはこの「外れ値」の部分で、単にトリッキーなものでなく、閃きと洞察力からくる、「この手があったか!」というものということです。
Chat GPT に何をしてもらうか?
文章の校正、翻訳・要約、そして雑談相手
校正
「中央値」を出すのが得意なChat GPTにとって、校正というのは、得意中の得意、正に朝飯前の作業とも言えますね。しかしながら、校正されたものをそのままコピペすると、なんか変な文章になる場合もあるので、提案をみながら、受け入れるものと無視するものを取捨選択していくことが、人間がやるべきことな気もします。
翻訳
翻訳だけでいえば、DeepLでも良い気がしますが、要約してくれるのは、助かりますね。要約を読んだうえで、詳細を読むかどうかを決める判断ができます。
雑談相手
3つ目の雑談相手というのが、僕にとっては一番強力です。現在、僕は週の4日リモートワークで自宅で仕事しているわけですが、アイデア出しの相手になってもらっています。特にフレームワークに応じて整理するのは、得意なのといくら掘り下げていっても不機嫌にならずに、なんか回答くれるのは助かりますね。
あと、先日試しに営業のロープレをしてみたのですが、こちらも中々良かったです。僕は、純粋な営業というのは、経験したことは無いですし、営業のロールプレイングというのもやったことが無いですが、世の中的にはやった方が良いと言われていますが、実際にどれくらいの人がやっているのでしょうか?なんか照れくさくてやっていないという人も多いかと思いますが、ChatGPTが相手なら、気軽に出来そうです。ちなみに、先日利用したスクリプトはこんな感じです。
以下の前提で、ロールプレイング相手になってください。あなたは、担当者役をお願いします。
私は、[サービス名] を手掛ける [会社名]社で営業担当を務めます。 [クライアント業界] 会社に対して提案の機会を獲得しました。
今、担当者と1対1の商談中(今回が3回目)で、ちょうど当社から提案と見積内容を出したところ(提案内容は、当社でも比較的ベーシックなものを出したと仮定)
ここで、「検討しますのでお待ちください」とシャットアウトされず、「受注確度が高い状態で次のコンタクト機会を約束する」をゴールとする
結構、対話が進むので、未経験の方はぜひ試してみてください。
また、高齢者の話相手にも良いですね。同じことをなんど聴いても、何度話しても嫌がらないだろうし、話を遮ることなく、聴いてくれると思います。オレオレ詐欺にひっかかるのを抑制してくれることとかもあり得ますね。
他にも、先日妻が仕事でクレーム電話があって大変だったという話をしていたのですが、クレーム対応はAIにして頂くとよいですね。結局は、話を聞いて貰いたいだけの人が多いと思いますので、適当に相槌を打って、適当に謝る仕事は人がやる必要はないですね。
ベーシックインカムとAI
世界中色々なところで、ベーシックインカム(BI)の実証実験が行われていますが、僕は割と賛成派です。なんていうか、嫌々働いているひとが作り出す余計な仕事により、日々神経すり減らすような仕事をして、、、という悪いループが回っているような気もします。
AI化・IT化によってどうしても不安定になる雇用状況に対して、究極的な政策はベーシックインカムを導入することだろうと考えています。
働かなくてもお金がもらえるようになったら何が起こるかというと、生活のために安い賃金で働く必要がないから、遊んでいてもいいし、好きなことに打ち込んでもいいしで、そうなると「嫌な仕事」というものが世の中から消えていく。それはとてもいいことだと思うね。
デヴィッド・グレーバー「ブルシットジョブ」によると、ブルシット・ジョブ(クソどうでもいい仕事)には、5つの類型があるということです。
1.取り巻き(flunkies):だれかを偉そうにみせたり、偉そうな気分を味わわせたりするためだけに存在している仕事
2.脅し屋(goons):雇用主のために他人を脅したり欺いたりする要素をもち、そのことに意味が感じられない仕事
3.尻ぬぐい(duct tapers):組織のなかの存在してはならない欠陥を取り繕うためだけに存在している仕事
4.書類穴埋め人(box tickers):組織が実際にはやっていないことを、やっていると主張するために存在している仕事
5.タスクマスター(taskmasters):他人に仕事を割り当てるためだけに存在し、ブルシット・ジョブをつくりだす仕事
実際に自分の仕事を振り返ってみると、こんな仕事に時間を取られているかもしれません。そんなことだと生産性は全然あがらないです。こんな仕事は、AIに代替してもらって人生における一番大切なリソースである時間を大切にした方が良いですね。
という訳で、今週は「ChatGPTは神か悪魔か」について考えてみました。何かの参考になれば幸いです。
2025.01.27-01.31
いいなと思ったら応援しよう!